| 会社名 | ヤマハ発動機株式会社 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 従業員数 | 連54206名 単10929名 |
| 従業員平均年齢 | 43.1歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 18.8年 |
| 平均年収 | 8175799円 |
| 1株当たりの純資産(連結) | 1230.38円 |
| 1株当たりの純利益(連結) | 110.12円 |
| 決算時期 | 12月 |
| 配当金 | 50円 |
| 配当性向 | 54.7% |
| 株価収益率(PER) | 11.6倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(連結) | 10.4% |
| 営業活動によるCF | 1768億円 |
| 投資活動によるCF | ▲1287億円 |
| 財務活動によるCF | ▲464億円 |
| 研究開発費※1 | 59億円 |
| 設備投資額※1 | 77億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 1276.13億円 |
| 株主資本比率※2 | 64.7% |
| 有利子負債残高(連結)※3※4 | 0円 |
経営方針
| 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2025年3月26日)現在において当社グループが判断したものです。 当面の優先的に対処すべき課題の内容等当社は、企業目的である「感動創造企業」のもと、2030年に向けた長期ビジョンとして「ART for Human Possibilities~人はもっと幸せになれる~」を2018年に発表しました。2025年からの新中期経営計画は、この長期ビジョンの後半6年間のスタートになります。新中期経営計画の基本方針は、「コア事業の競争力を高め、人の可能性を拡げる新技術を獲得し、人の悦びと環境が共存する社会をヤマハ発動機らしい挑戦で実現する」としています。 詳細は、当社ウェブサイト「中期経営計画」をご参照ください。(https://global.yamaha-motor.com/jp/profile/mtp/) ○事業ポートフォリオ当社は、前中期経営計画から、ポートフォリオ経営を実装しました。新中期経営計画では、ポートフォリオ戦略として、コア事業(二輪車事業、マリン事業)、戦略事業(ロボティクス事業、SPV事業、OLV事業)、新規事業の3つの領域に取り組みます。そして、将来的には、当社が保持する全ての事業がROIC 12.5%を上回る経営を目指します。 ■コア事業領域新中期経営計画では、コア事業の競争力を再強化していきます。二輪車事業とマリン事業へ重点的な投資を行い、魅力ある商品、サービスを提供することで、成長と収益性を両立させます。 [二輪車事業]「移動に喜びを、週末に楽しさを、人々と共に創る」ことを目指し、魅力的な商品ラインアップ、デジタル技術を活用したユーザーサービス強化に取り組みます。アセアン、新興国では、これまで注力してきたプレミアム戦略をさらに強化します。また、マーケティング力を強化することで、デジタル技術の活用とユーザーに寄り添った体験の提供により、顧客エンゲージメントを高めます。電動領域は、自社でのプラットフォーム開発と外部との連携の両輪で推進していきます。 [マリン事業]「信頼性と豊かなマリンライフ 海の価値を更に高める」ことを目指し、船外機大型モデルのラインアップ拡充、統合ボートビジネスの推進により、顧客価値の向上を追求していきます。統合ボートビジネスでは、これまで進めてきたマリン版CASE戦略を発展させ、次世代操船システムの導入、コネクテッド技術の活用、シェアリングシステムの提供、電動船外機の拡大など、多彩なボート体験を可能にしていきます。 ■戦略事業領域市場ポテンシャルの高い、ロボティクス事業、SPV事業、OLV事業(Outdoor Land Vehicle: RV事業とゴルフカー事業を統合)の3つを戦略事業領域とします。 [ロボティクス事業]加速するデジタル社会と変革するモビリティを、ワンストップスマートソリューションで支えていくことで、成長と収益性を両立させます。成長する領域に経営資源を集中し、当社の強みであるワンストップスマートソリューションを進化させることで、シェア向上と事業活動の効率化を実現します。 [SPV事業]地球環境に優しいモビリティである電動アシスト自転車を通じ、人々の挑戦を後押しすることで事業の成長を実現します。海外完成車ビジネス事業を見直し、中長期的な成長が見込めるe-Kitビジネスと国内完成車ビジネスに注力します。特にe-Kitビジネスでは、徹底したお客さま視点でOEM顧客の信頼を獲得するため、ダイレクトサービス機能の強化や供給リードタイムの短縮、開発スピードの迅速化に取り組みます。 [OLV事業]陸から海まで、お客さまが生涯にわたりワンブランドで楽しめるアウトドア商材を持つ、当社の強みが生きる北米市場でのシナジーを創出していきます。OLV事業の製品の市場規模は、付加価値化が進み、長期的に拡大すると見込んでいます。こうした市場成長を捉えるべく、新中期経営計画では、2030年に向けた次世代プラットフォームの開発に注力します。 ■新規事業領域これまで、モビリティサービス、低速自動走行、農業・医療省人化の領域で事業化に取り組んできましたが、今後は、事業拡大の可能性を見極めながら、モビリティサービス、低速自動走行、農業の3領域に注力していきます。 ■財務指標・株主還元方針資本コスト以上のリターンを継続的に創出することを目標とし、ROE14%水準、ROIC8%水準、ROA9%水準(いずれも3年平均)を目指します。株主還元については、「業績の見通しや将来の成長に向けた投資を勘案しつつ、安定的かつ継続的な配当を行う」ことを基本方針とし、キャッシュ・フローの規模に応じて機動的な株主還元を実施します。総還元性向は中期経営計画期間累計で40%以上です。 ■環境計画新中期経営計画における環境計画は、「気候変動」「資源循環」「生物多様性」の3つの柱で構成されています。気候変動では、企業活動における自社のCO2排出量は2010年比で74%の削減、2035年にカーボンニュートラルを目指します。また、お客さまや社員の製品使用からのCO2排出量はマルチパスウェイの方針で削減を進めます。資源循環では、2050年までにサステナブル原材料使用比率100%を目指し、新中期経営計画では、現状の14%から18%に引き上げます。生物多様性では、生態系と人間の双方に利益をもたらす課題解決方法を探求します。 ■人的資本経営グローバルエンゲージメント指標を導入し、人的資本経営の重要な指標として高いレベルを維持していきます。DE&Iの推進に加え、タレントマネジメントではグローバル人財プログラムを拡充します。多様な社員がチャレンジの機会を得ることで、個人と会社が成長し未来を切り開いていける組織を目指します。 ■リスク・コンプライアンス経営当リスク・コンプライアンス経営の強化を重要な方針として位置づけ、Global、Integrated、Agileの3つを柱に、当社の経営・事業に想定されるリスクを特定し、適切にコントロールしていきます。これらを通じて、環境の変化を素早く捉え、責任と権限のグローバル化を図る経営をさらに促進していきます。 なお、2024年6月3日公表の二輪車の型式指定申請における不適切事案につきまして、ステークホルダーの皆様に多大なご心配・ご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申しあげます。皆様からの信頼回復と再発防止に向けて、コンプライアンス及びガバナンスのさらなる強化を図ってまいります。 |
経営者による財政状態の説明
| 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】※当社グループは当連結会計年度(2024年1月1日から2024年12月31日まで)より、従来の日本基準に替えてIFRSを適用しており、前連結会計年度の数値をIFRSベースに組み替えて比較・分析を行っています。 当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 (1) 経営成績の概要及び分析当連結会計年度の当社グループを取り巻く環境について、米国はFRBが利下げに転じるなど、政府の景気刺激策が経済を下支えし、底堅い成長を維持しました。一方、欧州は中央銀行の利下げにより個人消費は回復基調にあるものの、ドイツやフランスの経済は停滞しています。加えて中東情勢をはじめとした地政学リスクや中国経済の低迷、資源価格高騰、金融資本市場の変動、米国新政権が及ぼす影響など、先行きの不透明な状況が続いています。当社においては、半導体の供給が改善し、二輪車のプレミアムモデルの供給が回復した一方、コロナ禍に高まったアウトドアレジャー需要は先進国を中心に落ち着き、マリン事業やRV事業、SPV事業については、需給の調整に取り組みました。このような経営環境の中、当社は中期経営計画に基づき各事業の戦略を推進するとともに、損益分岐点経営を念頭にコストダウンなどに取り組みました 当連結会計年度の売上収益は、コア事業の二輪車のうち、ブラジル、インドにおいて販売台数の増加及び台当たり単価が向上したことにより、2兆5,762億円と前連結会計年度に比べ1,614億円(6.7%)の増収となりました。営業利益は物価高騰に伴う人件費等販管費の増加、在庫評価減など事業構造の見直しに伴う費用やSPV事業やRV事業の一部固定資産の減損損失などを計上した結果、1,815億円と前連結会計年度に比べ624億円(25.6%)の減益となりました。親会社の所有者に帰属する当期利益は、営業利益の減少に伴い、1,081億円と前連結会計年度に比べ504億円(31.8%)の減益となりました。なお、当連結会計年度の為替換算レートは、米ドル152円(前期比11円の円安)、ユーロ164円(同12円の円安)でした。財務体質については、ROEは9.7%(前期比5.9ポイント減少)、ROICは5.4%(同3.7ポイント減少)、ROAは6.8%(同3.5ポイント減少)となりましたが、中期経営計画期間累計目標はいずれも達成しました。親会社の所有者に帰属する持分は1兆1,616億円(前期末比858億円増加)、親会社所有者帰属持分比率は41.7%(同0.2ポイント減少)となりました。また、フリー・キャッシュ・フロー(販売金融含む)は481億円のプラス(前期比782億円増加)となりました。 セグメント別の概況〔ランドモビリティ〕売上収益1兆7,154億円(前期比1,301億円・8.2%増加)、営業利益855億円(同420億円・33.0%減少)となりました。部門別の経営成績の概要は、次の通りです。二輪車事業では、売上収益1兆5,711億円(前期比1,577億円・11.2%増加)、営業利益1,265億円(同10億円・0.8%増加)となりました。先進国では、欧州主要国の需要が増加し、欧米の販売台数が増加した結果、売上収益3,993億円(前期比420億円・11.8%増加)となりました。新興国では、需要が増加しているブラジル、インドにおける販売台数の増加及び台当たり単価の向上により、売上収益1兆1,718億円(前期比1,157億円・11.0%増加)となりました。二輪車事業全体の営業利益は、新興国でのプレミアムモデルの供給改善により販売台数は増加した一方、物価高騰に伴う人件費や製品保証引当金繰入額等の販管費の増加により前年並みとなりました。二輪車全体の販売台数は、ブラジル、インドを中心に多くの地域で需要が堅調に推移し、496万台(前期比2.8%増加)となりました。RV事業(四輪バギー、レクリエーショナル・オフハイウェイ・ビークル(ROV))では、売上収益1,058億円(前期比241億円・18.5%減少)、営業損失183億円(前期:営業利益72億円)となりました。需要が前年を下回り、当社の出荷も下回った結果、減収となりました。営業利益は、販売減少ならびにモデルミックスの悪化、競争環境の激化に伴う販促費の増加、また固定資産の減損損失などを計上した結果、減益となりました。SPV事業(電動アシスト自転車、e-Kit、電動車いす)では、売上収益385億円(前期比36億円・8.6%減少)、営業損失227億円(前期:営業損失52億円)となりました。国内向け電動アシスト自転車は、販売台数が前年を上回りました。一方、e-Kitは、メイン市場である欧州の需要停滞に伴い在庫調整局面が継続し、販売台数が減少した結果、減収となりました。営業利益は、e-Kitの販売減少や海外完成車の販促費の増加、固定資産の減損損失など、事業構造の見直しに伴う費用を計上した結果、減益となりました。 [マリン]売上収益5,377億円(前期比98億円・1.8%減少)、営業利益878億円(同164億円・15.7%減少)となりました。船外機の需要は、主要な市場である米国において、9月に政策金利の引き下げがあったものの、高い金利水準が続いていたことや物価上昇の影響により減少しました。当社販売のうち、新モデルは好調だったものの、船外機全体では減少となりました。ウォータービークルは、金利上昇を懸念した買い控えにより需要が減少した一方、当社の販売台数は、昨年の部品不足やサプライチェーン混乱による供給制約が改善されたことにより増加しました。この結果、マリン事業全体では減収・減益となりました。なお、当連結会計年度の業績には、ドイツのマリン電動推進機メーカーTorqeedo GmbHの2024年4月~12月の業績を含んでいます。 [ロボティクス]売上収益1,133億円(前期比115億円・11.4%増加)、営業損失30億円(前期:営業利益7億円)となりました。サーフェスマウンターは、先進国の販売台数は減少したものの、中国などアジアにおける販売台数が増加した結果、当社の販売は増加しました。産業用ロボットの販売台数は増加したものの、モデルミックスは悪化しました。また、半導体製造後工程装置は生成AIや先端パッケージ向けの需要が増加し、販売が増加しました。これらの結果、ロボティクス事業全体では増収となりました。営業利益は、製造経費や開発費などの販管費の増加により、減少しました。 [金融サービス]売上収益1,122億円(前期比257億円・29.7%増加)、営業利益227億円(同56億円・32.6%増加)となりました。当社の売上収益は、販売金融債権の増加により増収となりました。営業利益は、金利収入の増加に加えて、前期に発生した金利スワップ評価損が当期は評価益に転じたことで増益となりました。 [その他]売上収益976億円(前期比39億円・4.1%増加)、営業損失115億円(前期:営業損失56億円)となりました。当社の売上収益は、ゴルフカーの北米での需要増加を背景に販売台数が増加した結果、増収となりました。営業利益は、パワープロダクツ事業関連商品の在庫評価減の影響などにより減益となりました。 なお、各セグメントの主要な製品及びサービスは以下のとおりです。セグメント主要な製品及びサービスランドモビリティ二輪車、中間部品、海外生産用部品、四輪バギー、レクリエーショナル・オフハイウェイ・ビークル、電動アシスト自転車、電動アシスト自転車ドライブユニット(e-Kit)、電動車いす、自動車用エンジン、自動車用コンポーネントマリン船外機、ウォータービークル、ボート、漁船・和船ロボティクスサーフェスマウンター、半導体製造後工程装置、産業用ロボット、産業用無人ヘリコプター金融サービス当社製品に関わる販売金融及びリースその他ゴルフカー、発電機、汎用エンジン、除雪機 (2) 生産、受注及び販売の実績① 生産実績当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。セグメントの名称製品台数(台)前期比(%)ランドモビリティ二輪車4,971,871102.6四輪バギー、レクリエーショナル・オフハイウェイ・ビークル48,040123.1電動アシスト自転車、電動アシスト自転車ドライブユニット(e-Kit)291,61044.5マリン船外機225,96068.9ウォータービークル53,912101.2ボート、漁船・和船6,49975.7ロボティクスサーフェスマウンター、産業用ロボット33,315111.1その他ゴルフカー72,373103.3 (注) 主要製品について記載しています。 ② 受注実績当社グループは主に見込み生産をしています。 ③ 販売実績(a)当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。セグメントの名称金額(百万円)前期比(%)ランドモビリティ1,715,384108.2マリン537,73998.2ロボティクス113,262111.4金融サービス112,172129.7報告セグメント計2,478,558106.8その他97,620104.1合計2,576,179106.7 (注) セグメント間取引については相殺消去しています。 (b)ランドモビリティの主要製品である二輪車の当連結会計年度における当社グループの販売実績は、次のとおりです。地域台数(台)前期比(%)日本72,00495.1海外4,888,768102.9地域別内訳北米82,275107.8欧州225,666108.1アジア3,862,85899.5その他717,969123.2合計4,960,772102.8 (3) 財政状態の概要及び分析当連結会計年度末の総資産は、前期末比2,199億円増加し、2兆7,835億円となりました。流動資産は、販売金融債権の増加や現金及び現金同等物の増加などにより同951億円増加しました。非流動資産は、販売金融債権の増加や固定資産の増加などにより同1,248億円の増加となりました。負債合計は、社債及び借入金の増加や引当金の増加などにより同1,277億円増加し、1兆5,569億円となりました。資本合計は、配当金の支払484億円、自己株式の取得200億円、当期利益1,246億円などにより同922億円増加し、1兆2,266億円となりました。これらの結果、親会社所有者帰属持分比率は41.7%(前期末:42.0%)、D/Eレシオ(ネット)は0.50倍(同:0.47倍)となりました。 (4) キャッシュ・フローの状況〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕税引前当期利益1,832億円(前期:2,361億円)や減価償却費831億円(同:710億円)、棚卸資産の減少313億円(同:383億円の増加)などの収入に対して、法人所得税の支払額966億円(同:792億円)や販売金融債権の増加622億円(同:1,230億円の増加)などの支出により、全体では1,768億円の収入(同:860億円の収入)となりました。 〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕有形固定資産及び無形資産の取得による支出1,159億円(前期:1,090億円の支出)やTorqeedo GmbHの支配獲得による支出123億円などにより、1,287億円の支出(同:1,161億円の支出)となりました。 〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕短期借入金の増加や社債の発行などがありましたが、配当金の支払、自己株式の増加などにより464億円の支出(前期:885億円の収入)となりました。 これらの結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは481億円のプラス(前期:301億円のマイナス)、現金及び現金同等物の残高は3,730億円(前期末比:260億円の増加)となりました。当連結会計年度末の有利子負債(リース負債を除く)は9,520億円(同:1,082億円の増加)となりました。 (5) 金融サービス事業を区分した経営成績情報以下の表は金融サービス事業と金融サービス事業以外の事業を区分した要約連結財政状態計算書、要約連結損益計算書及び要約連結キャッシュ・フロー計算書です。これらの要約連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準においては要求されていませんが、金融サービス事業はそれ以外の事業とは性質が異なるため、このような表示が連結財務諸表の理解と分析に役立つものと考えています。なお、以下の「金融サービス事業以外の事業及び消去」は連結計から金融サービス事業の数値を差し引いたものとしています。 要約連結財政状態計算書 (単位:百万円) 金融サービス事業金融サービス事業以外の事業及び消去連結計 2023年12月期2024年12月期2023年12月期2024年12月期2023年12月期2024年12月期資産 現金及び現金同等物22,13433,461324,882339,537347,016372,999 営業債権及びその他の債権1,044251178,663177,934179,707178,186 販売金融債権324,098372,582–324,098372,582 棚卸資産–568,596574,105568,596574,105 その他32,72516,12061,09494,37393,819110,493 流動資産合計380,001422,4161,133,2371,185,9511,513,2381,608,368 有形固定資産、のれん及び無形資産21,69627,969476,934536,343498,630564,313 販売金融債権316,676367,709–316,676367,709 その他8,92128,898226,093214,212235,015243,110 非流動資産合計347,295424,577703,027750,5551,050,3221,175,133 資産合計727,296846,9941,836,2651,936,5072,563,5612,783,501負債 営業債務及びその他の債務2,6422,365151,476147,557154,118149,922 社債及び借入金179,368380,913259,505299,417438,873680,330 その他39,86616,457259,332301,151299,199317,608 流動負債合計221,877399,735670,314748,126892,1921,147,861 社債及び借入金316,960211,75887,97359,884404,934271,643 その他3,68419,311128,390118,097132,075137,409 非流動負債合計320,645231,070216,364177,982537,009409,053 負債合計542,523630,806886,678926,1081,429,2021,556,915資本 資本金49,68653,15336,41432,94786,10086,100 資本剰余金1431264,00363,36364,14663,375 利益剰余金106,878120,827839,228858,360946,106979,188 自己株式–△61,389△54,064△61,389△54,064 その他の資本の構成要素28,06542,19412,74444,77440,81086,969 非支配持分–58,58565,01758,58565,017 資本合計184,773216,187949,5861,010,3981,134,3591,226,586 負債及び資本合計727,296846,9941,836,2651,936,5072,563,5612,783,501 要約連結損益計算書 (単位:百万円) 金融サービス事業金融サービス事業以外の事業及び消去連結計 2023年12月期2024年12月期2023年12月期2024年12月期2023年12月期2024年12月期売上収益86,471112,1722,328,2882,464,0062,414,7592,576,179売上原価△51,668△66,156△1,550,846△1,688,058△1,602,515△1,754,214売上総利益34,80246,016777,441775,948812,244821,964販売費及び一般管理費△18,961△24,077△554,345△618,447△573,307△642,525その他の収益費用(純額)1,284766△1,450△5,752△166△4,985持分法による投資損益–5,1497,0625,1497,062営業利益17,12622,705226,794158,810243,920181,515金融収益652349,86615,4459,93215,679金融費用△1,883△34△15,896△13,984△17,779△14,019税引前当期利益15,30822,904220,765160,271236,073183,175法人所得税費用△3,407△6,363△59,786△52,241△63,194△58,605当期利益11,90016,540160,978108,029172,879124,570親会社の所有者11,90016,540146,52091,528158,421108,069非支配持分–14,45816,50014,45816,500 要約連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円) 金融サービス事業金融サービス事業以外の事業及び消去 連結計 2023年12月期2024年12月期2023年12月期2024年12月期2023年12月期2024年12月期営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期利益15,30822,904220,765160,271236,073183,175 減価償却費及び償却費3,6132,70567,42780,36271,04183,067 販売金融債権の増減額(△は増加)△122,979△62,199–△122,979△62,199 その他9,709△4,924△107,813△22,271△98,103△27,196 営業活動によるキャッシュ・フロー△94,348△41,513180,380218,36186,031176,847投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産及び無形資産の取得による支出△9,582△7,424△99,447△108,458△109,029△115,882 その他79,9541,343△87,051△14,209△7,096△12,865 投資活動によるキャッシュ・フロー70,372△6,080△186,498△122,667△116,126△128,748財務活動によるキャッシュ・フロー 借入金の増減額(△は減少)21,09671,271142,734△28,649163,83142,622 社債の増減額(△は減少)8,809△11,60019,91519,91528,7248,314 その他14,062960△118,086△98,323△104,023△97,363 財務活動によるキャッシュ・フロー43,96960,63144,563△107,05888,532△46,426現金及び現金同等物に係る換算差額△11,180△2,9122,61321,693△8,56718,781現金及び現金同等物の増減額(△は減少)8,81210,12441,05810,33049,87120,454現金及び現金同等物の期首残高12,99522,134283,823324,882296,819347,016新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額3251,203-4,3253255,528現金及び現金同等物の期末残高22,13433,461324,882339,537347,016372,999 (6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析当社グループにおける主な資金需要は、製品製造のための材料・部品等の購入費、製造費用、製品・商品の仕入、販売費及び一般管理費、運転資金、設備投資資金、投融資及び当社製品に関わる販売金融です。運転資金については返済期限が一年以内の短期借入金で、通常各々の会社が運転資金として使用する現地の通貨で調達しています。設備投資資金については主に資本金、内部留保といった自己資金でまかなうこととしています。資金の流動性管理にあたっては、適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性を適度に維持することで、必要な流動性を確保しています。当連結会計年度においては、設備投資やTorqeedo GmbHの支配獲得などの活発な投資活動による支出があったものの、船外機やSPVの在庫適正化に伴う棚卸資産の減少による運転資金の減少などにより、フリー・キャッシュ・フローを確保しました。また、株主還元と資本効率の向上を図るために自己株式の取得を行いました。当社は株主の皆様の利益向上を重要な経営課題と位置付け、企業価値の向上に努めています。株主配当については期末配当1株当たり25円(2025年3月25日開催の第90期定時株主総会にて決議)、2025年は年間配当1株当たり50円、加えて100億円の自己株式の取得を予定しています。また、2025年の設備投資は1,400億円、研究開発支出は1,550億円を計画しています。 (7) 重要な会計方針及び見積り当社グループの連結財務諸表は、IFRSに準拠して作成しています。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者はこれらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断していますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は、これらの見積りと異なる場合があります。当社の連結財務諸表で採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 3.重要性がある会計方針」に記載していますが、特に次の重要な会計方針が連結財務諸表作成における重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼすと考えています。なお、当連結会計年度における重要な会計上の見積りについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載しています。 ① 棚卸資産当社グループは、棚卸資産の、推定される将来需要及び市場状況に基づく時価の見積額と総平均法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しています。)による評価額との差額に相当する陳腐化の見積額について、評価減を計上しています。実際の将来需要又は市場状況が、当社グループ経営者による見積りより悪化した場合、追加の評価減が必要となる可能性があります。 ② 損失評価引当金当社グループは、売掛金、販売金融債権及び貸付金その他これらに準ずる債権を適正に評価するため、営業債権及びその他の債権については常に損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しています。金融サービス事業に係る債権については、報告日ごとに予想信用損失を見積り、予想信用損失に対して損失評価引当金を計上しています。なお、米国内のインフレの急激な進行等の外部環境の変化により債権の信用リスクが増加した場合には、必要に応じて見積りに対し補正を加えています。将来、債権の相手先の財務状況がさらに悪化して支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上又は追加の損失が発生する可能性があります。 ③ 非金融資産の減損当社グループは、減損の兆候のある資産または資産グループごとに将来キャッシュ・フローの見積りを行い、当該資産の減損要否の判定を行っています。資産または資産グループの減損が必要であると判断した場合、帳簿価額が回収可能価額を超える部分について減損損失を認識します。将来、回収可能価額が減少した場合、減損損失の計上が必要となる可能性があります。 ④ 繰延税金資産当社グループは、将来の一定期間における課税所得の見積りやタックスプランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を検討しています。これらの将来に係る見積りは、市場の動向や経済環境、また、当社グループの事業計画等の変動の影響を受けるため、回収可能性が大きく変動した場合、税金費用が大きく変動する可能性があります。 ⑤ 製品保証引当金当社グループは、販売済製品の保証期間中のアフターサービス費用、その他販売済製品の品質問題に対処する費用の見積額を計上しています。当該見積りは、過去の実績若しくは個別の発生予想額に基づいていますが、実際の製品不良率又は修理コストが見積りと異なる場合、アフターサービス費用の見積額の修正が必要となる可能性があります。 ⑥ 退職給付に係る負債従業員の退職給付費用及び退職給付債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されています。これらの前提条件には、割引率、長期期待運用収益率、将来の給与水準、退職率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率などが含まれます。当社及び一部の国内連結子会社が加入する年金制度においては、割引率は優良社債を基礎とした複数の割引率を退職給付の支払見込期間ごとに設定しています。長期期待運用収益率は、年金資産が投資されている資産の種類毎の期待収益率の加重平均に基づいて計算されます。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、その影響は累積され、将来にわたって規則的に計上されるため、一般的には将来期間において認識される収益・費用、計上される資産・負債及び純資産に影響を及ぼします。確定給付制度の当期勤務費用及び確定給付負債(資産)の純額に係る利息の純額は純損益として認識しています。確定給付制度の再測定額は、発生した期に一括してその他の包括利益で認識し、直ちに利益剰余金に振り替えています。制度の改訂による従業員の過去の勤務に係る確定給付制度債務の増減は、純損益として認識しています。 (8) 並行開示情報「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年(1976年)大蔵省令第28号。第3編から第6編を除く。以下「日本基準」という。)により作成した要約連結財務諸表、要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更は、次のとおりです。なお、日本基準により作成した要約連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けていません。また、日本基準により作成した要約連結財務諸表については、百万円未満を切り捨てして表示しています。 ① 要約連結貸借対照表 (単位:百万円) 前連結会計年度(2023年12月31日)当連結会計年度(2024年12月31日)資産の部 流動資産1,517,1581,628,790 固定資産 有形固定資産433,886473,906 無形固定資産51,13270,619 投資その他の資産547,437621,261 固定資産合計1,032,4571,165,787 資産合計2,549,6152,794,577負債の部 流動負債865,1651,128,383 固定負債524,125397,671 負債合計1,389,2911,526,054純資産の部 株主資本1,073,0611,122,368 その他の包括利益累計額28,05280,402 非支配株主持分59,21065,752 純資産合計1,160,3231,268,523負債純資産合計2,549,6152,794,577 ② 要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書要約連結損益計算書 (単位:百万円) 前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)売上高2,414,7592,576,179売上原価1,602,5751,754,444売上総利益812,183821,734販売費及び一般管理費567,706641,054営業利益244,477180,680営業外収益21,41833,103営業外費用30,09224,945経常利益235,803188,839特別利益4,2123,201特別損失4,5128,712税金等調整前当期純利益235,503183,328法人税等合計60,98847,487当期純利益174,515135,840非支配株主に帰属する当期純利益14,35016,556親会社株主に帰属する当期純利益160,164119,284 要約連結包括利益計算書 (単位:百万円) 前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)当期純利益174,515135,840 その他の包括利益合計47,31155,204包括利益221,826191,045(内訳) 親会社株主に係る包括利益202,206171,635 非支配株主に係る包括利益19,62019,410 ③ 要約連結株主資本等変動計算書前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) (単位:百万円) 株主資本その他の包括利益累計額非支配株主持分純資産合計当期首残高1,016,475△13,40151,2251,054,298会計方針の変更による累積的影響額△23,025--△23,025会計方針の変更を反映した当期首残高993,449△13,40151,2251,031,272当期変動額79,61141,4537,984129,050当期末残高1,073,06128,05259,2101,160,323 当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) (単位:百万円) 株主資本その他の包括利益累計額非支配株主持分純資産合計当期首残高1,073,06128,05259,2101,160,323当期変動額49,30752,3506,542108,200当期末残高1,122,36880,40265,7521,268,523 ④ 要約連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円) 前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)営業活動によるキャッシュ・フロー80,150165,941投資活動によるキャッシュ・フロー△116,972△125,261財務活動によるキャッシュ・フロー95,260△39,006現金及び現金同等物に係る換算差額△8,56718,781現金及び現金同等物の増減額(△は減少)49,87120,454現金及び現金同等物の期首残高296,819347,016新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額3255,528現金及び現金同等物の期末残高347,016372,999 ⑤ 要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)(連結の範囲の変更)新たに設立した4社、及び重要性が高まった非連結子会社1社を連結の範囲に含めました。また、清算結了により2社を連結の範囲から除いています。 (持分法適用の範囲の変更)新たに出資した関係会社1社を持分法適用の範囲に含めました。また、清算結了により2社、株式売却により1社を持分法適用の範囲から除いています。 (会計方針の変更)(米国財務会計基準審議会会計基準編纂書(ASC)第326号「金融商品-信用損失」の適用)米国基準を採用する北米子会社において、ASC第326号「金融商品-信用損失」を当連結会計年度の期首から適用しています。これにより、金融商品の測定方法を見直し、また金融資産について予想信用損失モデルによる減損を認識することが求められます。本会計基準の適用にあたっては、その経過的な取扱いとして認められている会計方針の変更による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しています。この結果、流動資産が368百万円、投資その他の資産が4,265百万円、株主資本が4,634百万円減少しています。 (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)日本基準を採用する当社及び国内子会社において、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。 当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)(連結の範囲の変更)新たに設立した3社、新たに取得した3社、及び重要性が高まった非連結子会社5社を連結の範囲に含めました。また、吸収合併により3社を連結の範囲から除いています。 (持分法適用の範囲の変更)清算結了により1社、株式売却により3社を持分法適用の範囲から除いています。 (会計方針の変更)(費用計上区分の変更)当社グループは、当連結会計年度より、従来、売上原価に計上していた研究開発費を販売費及び一般管理費に計上する方法に変更しています。詳細は、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (会計方針の変更)」に記載しています。当該会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度の要約連結貸借対照表は、流動資産が31,396百万円、株主資本が22,346百万円減少し、投資その他の資産が9,049百万円増加しています。また前連結会計年度の要約連結損益計算書は、売上原価が96,833百万円減少し、売上総利益が96,833百万円、販売費及び一般管理費が103,011百万円増加しています。これにより、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益がそれぞれ6,178百万円、法人税等合計が2,223百万円、当期純利益が3,955百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が3,955百万円減少しています。前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本の期首残高は、18,391百万円減少しています。 なお、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額が22.54円、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益がそれぞれ3.94円減少しています。 (9) 経営成績等の状況の概要に係る主要な項目における差異に関する情報前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 40.初度適用」をご参照ください。 当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)(リース)日本基準では借手としてのリースについてファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類し、オペレーティング・リースについては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っていました。IFRSでは借手としてのリースについて当該分類を行わず、基本的にすべてのリースについて使用権資産及びリース負債を認識しています。この影響により、IFRSでは、日本基準に比べ使用権資産が23,609百万円増加し、リース負債が17,852百万円増加しています。また、営業活動によるキャッシュ・フローが7,335百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローが同額減少しています。 (開発費の資産化)日本基準では費用処理していた一部の開発費用について、IFRSでは一定の要件を満たした部分について資産計上しています。この影響により、IFRSでは、日本基準に比べ無形資産が9,005百万円増加しています。 (のれんの償却)日本基準ではのれんを一定期間にわたり償却していますが、IFRSでは移行日以降償却は行わず、毎年減損テストを実施しています。この影響により、IFRSでは、日本基準に比べ販売費及び一般管理費が666百万円減少しています。 |
※本記事は「ヤマハ発動機株式会社」の令和6年12期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
※4. この企業は、連結財務諸表ベースで見ると有利子負債がゼロ。つまり、グループ全体としては外部借入に頼らず資金運営していることがうかがえます。なお、個別財務諸表では親会社に借入が存在しているため、連結上のゼロはグループ内での相殺消去の影響とも考えられます。
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

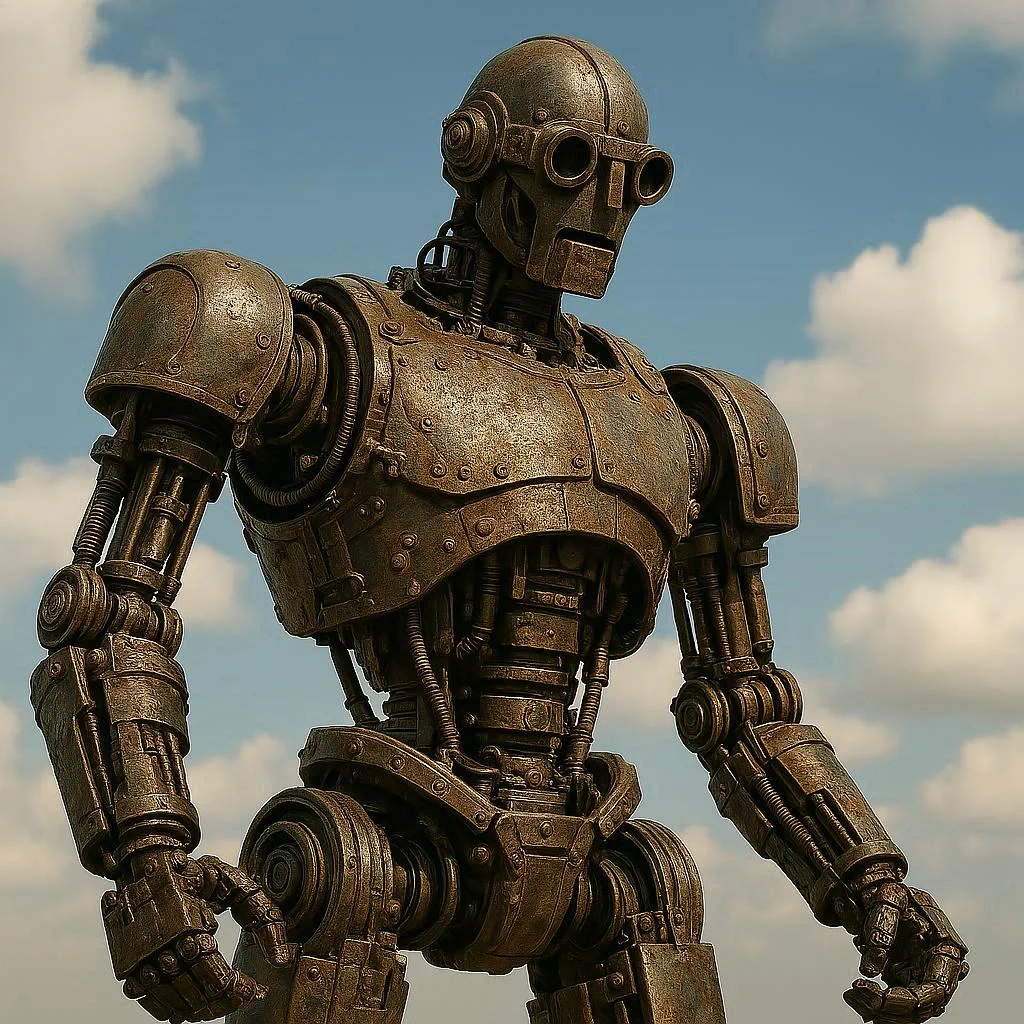


コメント