| 会社名 | 株式会社SUBARU |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 従業員数 | 連37866名 単17885名 |
| 従業員平均年齢 | 39.8歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 15.9年 |
| 平均年収 | 7307644円 |
| 1株当たりの純資産(連結) | 2105.71円 |
| 1株当たりの純利益(連結) | 458.03円 |
| 決算時期 | 3月 |
| 配当金 | 115円 |
| 配当性向 | 26.1% |
| 株価収益率(PER) | 6.01倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(連結) | 8.5% |
| 営業活動によるCF | 4921億円 |
| 投資活動によるCF | ▲4040億円 |
| 財務活動によるCF | ▲1873億円 |
| 研究開発費※1 | 7億円 |
| 設備投資額※1 | 1761.44億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 611.1億円 |
| 株主資本比率※2 | 46.5% |
| 有利子負債残高(連結)※3※4 | 0円 |
経営方針
| 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において、当社グループ(当社、連結子会社および持分法適用会社)が判断したものです。 当社グループは、『“お客様第一”を基軸に「存在感と魅力ある企業」を目指す』という経営理念のもと、ありたい姿である「笑顔をつくる会社」の実現に向け、提供価値である「安心と愉しさ」を進化させていきます。そして、SUBARUを自動車事業と航空宇宙事業における魅力あるグローバルブランドへ持続的に成長させるとともに、すべてのステークホルダーの皆様に事業活動へ共感いただくことを通じてSUBARUグループの持続的な成長と愉しく持続可能な社会の実現を目指しています。 (1) ありたい姿、提供価値、経営理念<ありたい姿> 笑顔をつくる会社 <提供価値> 安心と愉しさ <経営理念> “お客様第一”を基軸に「存在感と魅力ある企業」を目指す (2) 基本方針<品質方針> 私たちは何より品質を大切にしてお客様の信頼に応えます 1.お客様に安心して長くお使いいただける商品をお届けします 2.お客様の声に常に耳を傾け、商品とサービスに活かします 3.法令・社会規範・社内規則を遵守し、お客様に信頼される仕事をします <SUBARUグローバルサステナビリティ方針> 私たちSUBARUグループ*は、人・社会・環境の調和を目指し、 1.事業を通じて、地球環境の保護を含む様々な社会課題の解決と、持続可能な社会の実現に貢献します。 2.高品質と個性を大切にし、先進の技術で、SUBARUならではの価値を提供し続け、SUBARUグループに関わるすべての人々の人生を豊かにしていきます。 3.国際社会における良き企業市民として、人権および多様な価値観・個性を尊重し、すべてのステークホルダーに誠実に向き合います。 4.従業員一人ひとりが、安全に安心して働くことができ、かつ働きがいを感じられるよう職場環境を向上させます。 5.国際ルールや各国・地域の法令を遵守するとともに、その文化・慣習等を尊重し、公正で透明な企業統治を行います。 6.ステークホルダーとの対話を経営に活かすとともに、適時かつ適切に企業情報を開示します。 *SUBARUグループ:株式会社SUBARUおよびすべての子会社 (3) 新経営体制における方針当社グループは、2023年の新経営体制への移行に伴い、同年8月2日に公表した「新経営体制における方針(以降、「新体制の方針」)」※1において、2030年に向けた電動化計画をアップデートし、2023年から2028年までの5年間を大変重要な期間と位置づけ、「モノづくり」と「価値づくり」で世界最先端を目指した取り組みを進めています。100年に一度の大変革期を勝ち残っていくために、これらの取り組みを強力に推進し「安心と愉しさ」を追求し続けていきます。さらに近年の自動車産業を取り巻く非連続かつ従来以上にスピード感のある変化に対しては「柔軟性と拡張性」の観点を念頭に置き、よりタイムリーに対応していきます。 ※1:詳細は2023年8月に公表した「新体制の方針」と2024年5月および2024年11月に公表したアップデートをご参照ください。https://www.subaru.co.jp/outline/about/policy/ (4) 対処すべき課題<経営環境の変化の下での収益確保に向けた取り組み>自動車メーカーとしては決して規模の大きくない当社グループが、厳しい競争環境のなかで稼ぐ力を維持し持続的に成長していくためには、お客様にSUBARUならではの価値を認めていただくことが何より大事であり、また徹底した差別化戦略・付加価値戦略が不可欠です。これまで、当社グループの強みを発揮できる分野や市場にターゲットを絞り、限られた経営資源を投入する「選択と集中」を推し進めることで「付加価値」を高めて、競争力を強化してきました。市場については米国を最重要市場と設定し、商品は日常からアクティブライフまで使い勝手が良く、米国市場を中心にお客様との親和性が高いSUV領域に、開発においては当社グループの技術の強みを活かすことができる「安心と愉しさ」を追求する領域に経営資源を集中してきました。また、当社グループにとって大事なパートナーである販売店と共に、より良い社会の実現に向けて各地域に寄り添った支援活動「Love Promise」を米国において継続的に進めています。これらビジネスモデルや取り組みに対し、販売店・お客様・地域コミュニティからの共感をいただいており、共にSUBARUブランドを磨き、成長を遂げてきました。その結果、2008年からコロナ禍前の2019年にかけて12年連続で小売販売が前年実績を超え、販売台数は約3.7倍と急成長しました。コロナ禍後も米国市場での堅調さは維持し、2025年3月には米国で販売する自動車ブランドの中で唯一、32か月連続で前年同月超えを記録しました。2025年3月期の当社グループの全世界の売上台数93.6万台のうち、米国における売上台数は66.2万台を占めました。米国売上台数のうち50%強は米国現地生産車となりますが、日本で生産され輸入する車両も半数程度あります。日本から輸入する完成車のほか、米国現地生産車においては一部の国から輸入する部品などが米国の関税政策の影響を受けます。しかしながら、当社グループがこれまで育んできたSUBARUブランドの強さおよびお客様との関係の深さに鑑みると、今後も米国市場を最重要市場と位置付けることが、当社グループにとって最善の選択であると考えています。今後、米国市場で最量販車種である「フォレスター」の生産地を米国に移管することを予定し、米国市場で需要が伸びているストロングハイブリッド車両も生産いたします。また、売上台数の増加・売上構成の改善・販売奨励金の抑制・原価低減・費用圧縮などあらゆる収益機会の創出を行うことにより、収益の確保に努めます。 <大変革期の勝ち残りに向けて>①「柔軟性と拡張性」の考え方のもと「モノづくり革新」と「価値づくり」を推進当社グループは、BEV※2はカーボンニュートラルの実現に向けた有力な選択肢ではあるものの、その移行スピードは不透明であり、ICE※3系商品の需要も一定程度継続すると考えています。先行きの見えない変化に柔軟に対応していくためには、従来の考え方・手法を革新的に変えていく必要があり、2023年8月2日に発表した「新体制の方針」の中で、BEVを切り口に大変革に突き進むことを発信しました。一方で、最終的にどのパワーユニットの商品を選択するかを決めるのはお客様です。そのための選択肢として、BEVだけではなく、ICE系商品も幅広く用意することこそが「柔軟性」であり、それを実現するために「モノづくり」と「価値づくり」で世界最先端を狙うという考え方は、方針発表当初から何ら変わるものではありません。その一つの手段として、更地にゼロから生産の構えを構築し、開発の手法・プロセスもゼロからスタートできるBEVに一旦舵を切り、「モノづくり革新」と「価値づくり」を実現し、その成果をICE系商品にも展開します。このようにして市場の変化に対応できる「柔軟性」を身に付けていきます。 ※2:Battery Electric Vehicle(電気自動車)※3:Internal Combustion Engine(内燃機関) (商品ラインアップ)BEVの市場導入については、2026年末までにSUVを4車種、2028年末までにはさらに4車種と合計8車種のラインアップを予定しています。2026年末までに導入を予定する4車種のうち、2022年に市場に導入した「ソルテラ」はトヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」という。)と共に両社の強みを持ち寄りつくりあげ、その改良モデルを2025年4月に公開しました。また同時にBEVラインナップの第2弾となる新型「トレイルシーカー」を公開しました。新型「トレイルシーカー」は2026年以降に米国市場への導入を予定しており、当社の矢島工場で生産し、トヨタへの供給も予定しています。また2024年度は、トヨタハイブリッドシステムをベースとし水平対向エンジンと機械式AWDを組み合わせたSUBARUらしい独自のストロングハイブリッドシステムである次世代e-BOXERを開発・公表しました。搭載する国内向け「クロストレック」、国内および米国向けの新型「フォレスター」を発表し、すでに多くの受注をいただいています。今後も市場の動向を見据えながら展開拡大を計画します。 新型「トレイルシーカー」(米国仕様車) ストロングハイブリッドシステム さらに、SUBARUのフラッグシップクロスオーバーSUVとして歴史を積み重ねてきた「アウトバック」をフルモデルチェンジいたします。パワーユニットは、改良された水平対向2.5L直噴NAエンジンと2.4L直噴ターボエンジンを採用し、2026年以降に米国市場への導入を予定しています。このように、市場のニーズに合わせたBEV/HEV※4/ICEそれぞれのラインアップを充実させ、電動化移行期における商品の柔軟性を確保していきます。※4:Hybrid Electric Vehicle(ハイブリッド自動車) (生産体制の再編計画)電動車の生産に向け、当社グループは2022年5月より生産体制の再編計画を段階的にアップデートしてきました。国内では2024年秋に北本工場において、ストロングハイブリッドシステムの基幹ユニットとなるトランスアクスルの生産を当初予定通りに開始しました。また、新型「トレイルシーカー」およびトヨタへ供給予定の新型BEVならびにガソリンエンジン車の混流生産を矢島工場にて計画しており、2025年度はその準備が本格化します。矢島工場にある2本のラインのうち、1本のラインを約半年にわたり生産を止めて工事を行うため、一定数の生産台数の減少を想定していますが、その影響を最小限に抑えられるように進めていきます。大泉新工場は現在、環境規制およびお客様の受容などの動向を踏まえながら、「段階的」な立ち上げ準備をしています。またバッテリーの生産工場は、パナソニックエナジー株式会社とともに大泉新工場の近接地への建設を予定しています。群馬県太田市を中心に近距離圏内に工場が位置するメリットを活かし、お取引先様および部品物流まで含めたサプライチェーンのさらなる「高効率化」を図ります。段階的な立ち上げおよびロケーションメリットの活用などにより、「合理的な生産」の実現を目指すというこれまでの方針に変わりはありませんが、昨今の経営環境を踏まえ、投資の実行のタイミングはこれまで以上に精緻かつ柔軟に判断いたします。 (モノづくり革新)モノづくり革新を通じて、小回りの利く「SUBARUの規模だからこそできる」製造・開発・お取引先様領域まで含めたサプライチェーンが一体となった“ひとつのSUBARU化”を進めることで、高密度なモノづくりを推進する―この考え方を軸に、「開発手番半減」、「部品点数半減」、「生産工程半減」を実現し、世界最先端のモノづくりを成し遂げます。開発を含むこれまでの「モノづくり」は、お客様ニーズの多様化やクルマの複雑化などにより対応領域が多岐にわたり、個々の領域の専門化およびお取引先様も含めた分業が一気に進みました。結果として、前工程の手離れを待つリレー式のモノづくりを定着させてきました。この形は、時代の変化に適応しながら成長する過程において発生した制約に対し、でき得る範囲で効率的かつ効果的に対応してきた結果であると評価しています。一方で、従来とは大きく車両構造の異なるBEVという「新しい商品」を企画・開発し、更地にゼロから建設する「新しい工場」で生産を始めるということは、「モノづくり」のアプローチやプロセスを大きく変えるチャンスであると捉えており、これらを起点に合理的で高密度なモノづくりを推進し、徹底的に極めていきます。お取引先様と共に集い、開発・生産など様々な検討を行う「大部屋活動」では、「ひとつのSUBARU化」を推し進め、モノの流れである「サプライチェーン」と開発の流れである「エンジニアリングチェーン」を一体化した「アジャイル」なモノづくりの検討を進めています。高密度な工場ロケーションやサプライチェーン網、それらを基盤とした物流システム確立などの「高効率なパッケージ」と合わせて「開発手番半減」、「部品点数半減」、「生産工程半減」を実現します。「新しい工場」では「生産ラインのモジュール化」および「柔軟なサブラインの構築」、そして当社が長年突き詰めてきた「変種変量短生産」の考えに基づく「高効率」な混流生産手法をさらに進化させていきます。更地にゼロから建設する「自由度」を十分に活かしながら、敷地および建屋空間の最大活用も視野に入れて効率化を図っていきます。同時に、ラインで流れるBEVを始めとした「新しい商品」に関しても開発初期段階での「車両構造」および「仕様」のシンプル化による部品点数の大幅な削減を進め、「生産工程半減」へつなげます。これらの取り組みに加え、ストロングハイブリッドシステムの基幹ユニットとなるトランスアクスルを製造する埼玉県の北本工場を含めた各工場のロケーションメリットを最大活用し物流効率を極限まで高めることにより、リードタイムの大幅な短縮につなげていき、従来以上にお客様のニーズにお応えする商品をより早くお届けすることを目指します。 (価値づくり)米国では販売子会社であるスバル オブ アメリカ インク(SOA)と全米の販売店が一体となった「Love Promise」という活動が実を結んでいます。SUBARUの商品を核として、販売店・お客様・地域社会の人と人そしてSUBARUを強固につなげるこの取り組みこそが、SUBARUの「社会と未来への価値貢献」であり、これを守りさらに取り組みの輪を拡げていくという想いは、この先の大変革期や電動化時代においても決して変わるものではありません。そしてSUBARUは、フォーブス誌の「社会へ良い影響をもたらす企業ランキング」において、米国内3,000を超えるブランドの中で、2023年と2024年は2年連続で2位に、2025年には3位に選ばれました。これは、商品だけでなく、SUBARUの理念や取り組みに対する総合的な評価ですが、その根幹は「安心と愉しさ」という不変の提供価値を具現化するために追求し続けてきた「テクノロジー」にあると考えています。例えば、運転支援システム「アイサイト」は、30年以上にわたる開発の過程で「安心」という「価値」を磨いてきました。今後も究極の安全を目指し、お客様にあらゆる運転環境下においても絶対的な安心を感じていただくために、SUBARUの強み領域におけるテクノロジーの進化を加速させていきます。商品や機能を核とし、お客様には「安心」、「挑戦」、「いつでも新しい」というような「SUBARUと共に過ごすことでの色褪せない情緒的な価値」を感じていただけると考えています。電動化が進むことにより、「今まで以上にお客様の人生に寄り添うSUBARU」を目指していきます。テクノロジーの進化に向けた取り組みのポイントは、2つあります。1つ目のポイントは「協業の深化」です。特にBEVでは新たな領域の「価値づくり」が必要であり、従来のお取引先様との関係を越えて、いかに協業のカタチをより深化させるかが大切です。2つ目のポイントは、「知能化」です。SUBARUらしい「安心と愉しさ」の強化はもちろん、BEVならではの「シームレスでストレスフリー」といった新たな価値を加え、そしてそれらをICE系商品にも展開していきます。 協業の深化2024年1月に稼働を開始した群馬県太田市の開発拠点「イノベーション・ハブ」では、当社従業員とお取引先様が垣根なく集い、開発・生産など様々な検討を行う「大部屋活動」を推し進めています。軽量・コンパクトな次世代電動車両用e-Axleは株式会社アイシンと共同で開発しています。単なる共同開発の枠に留まらず、調達・生産の領域まで踏み込むことにより両社の強みを活かした競争力のあるe-Axleを実現するために、共に歩みを進めています。 互いに100年を超える歴史を持つパナソニック エナジー株式会社とは、「次の100年をつくり上げるために、互いの技術と知見を持ち寄り、世界最先端の性能とコストを実現する」という大義のもとで、バッテリー供給に関する協業を進めています。新設するバッテリー工場のロケーションメリットやコスト視点も踏まえた両社の様々な知見の活用など、競争力を高める取り組みを進めています。世界的な半導体メーカーであるAMDとは、「2030年死亡交通事故ゼロ」の実現に向けて、アイサイトとAI推論の融合に関わる協業を行っています。その協業により実現する最適化されたSoC※5は、「ADAS※6」のみならず「車両運動」領域などを制御する「統合ECU」の重要な構成要素を担います。これらの「協業の深化」により、世界最先端の「安心と愉しさ」の実現を目指していきます。 ※5:System on a Chip ※6:Advanced Driver-Assistance Systems(先進運転支援システム) 知能化「統合ECU」はSUBARUの強みである安全や走りの領域に絞り込んだ「内製開発」により、コスト競争力を保ちつつ、車両の「頭脳」として、SUBARUらしい高度な「知能化」を実現します。「統合ECU」を活用した制御ノウハウやBEVをつくりあげる過程で得た知見を蓄積するとともに、当社が得意とする内製化のスピードをさらに高め、ICE系商品への活用および実装も踏まえて検討を深めます。当社グループは、この100年に一度と言われる大変革期の中、「モノづくり革新」と「価値づくり」を推し進めます。開発・生産の工程はもちろん、事業活動全体の効率化・生産性を突き詰め、商品競争力を磨き、SUBARUらしいアフォーダブルな商品として提供することで「お客様に感じていただける価値の最大化」に取り組みます。2030年以降に向けてそれらを実現することにより、「業界高位の収益力」を維持し、勝ち残っていきます。 ②脱炭素社会に向けた取り組み当社グループは脱炭素社会に貢献するため、商品(スコープ3)および工場・オフィスなど(スコープ1および2)に関する長期目標(長期ビジョン)を2050年とし、それを補完する中期目標(マイルストーン)を設定しています。これらの目標は非連続かつ急速に変化する事業環境に応じて随時見直されており、2023年には、工場・オフィスなどの中期目標を「2035年度に2016年度比60%削減」に引き上げました。当社グループのバリューチェーン全体のCO2排出量は販売した商品の使用によるものが大部分を占めるため、前述の通り自動車の電動化に向けた取り組みを着実に進めていくことが重要です。また、当社グループが直接排出するCO2(スコープ1および2)の削減に当社自らが率先して取り組むことは、バリューチェーン全体での削減活動をより充実させていくものと考え、再生可能エネルギーの利用や高効率な設備への更新などに取り組んでいきます。なお、商品および工場・オフィスに「素材部品」、「輸送」、「廃棄」を加えたバリューチェーン全体の脱炭素社会に向けた取り組みは、各領域でのCO2削減を目的とした会議体にて管理され、最終的には環境委員会にて全体統括されています。 <人財づくり>当社が目指す世界最先端の「モノづくり」「価値づくり」は「真の競争力をもった人・組織」により実現されると認識しており、その強化に取り組んでいます。当社では「真の競争力をもった人・組織」とは、「人財それぞれの異なる能力が最大発揮されている」、「本質業務に注力し成果創出までのスピードが速い」、「全体最適の意識を持ち、組織の壁を容易に越えながら動ける」、「挑戦・応援できる風土がある」状態と捉えており、その実現に向けた各種施策を実施しています。「個の成長」に向けた人財育成では、自律的なキャリアプランの形成を職場や上司がサポートする仕組みをベースに、さらにチャレンジを加速する施策として「公募型ジョブローテーション」や従業員が学びの機会を自ら探し出し会社から全面支援を受けることができる制度などを導入し、推進しています。ほかにも全従業員が自身のレベルや目的に応じて選択できる多様な研修プログラムを整備し、個々に応じたキャリア開発が実現できうる仕組みづくりを進めています。「個の成長」を後押しする仕組みの整備や様々な施策の継続により、自律的な人財の育成が着実に実を結びつつあります。「組織の成長」に向けて、直接部門では全員参加の現場主権による現場力強化活動を、間接部門ではDX推進による業務の効率化・機械化の推進を基軸として生産性向上を図り、成長につなげていきます。IT・AI活用の領域においては技術部門で構築済の「ソフトウエア人財育成プロジェクト」に加え、すべてのSUBARU社員を対象とした「ITアカデミー」を設立しました。また、さらなる成長を目指す観点では、「つながりの強化」を最重要項目に位置付け注力していきます。経営として目指す姿と従業員一人ひとりの取り組みのつながりの深化、部署間の連携や協働の強化、全社のチャレンジを支援・応援できる仕組みづくり、従業員同士の接点増加などを通じて、個々のチャレンジをより大きな成果につなげるとともに、挑戦に向かう人財創出スピードを向上させていきます。一例として全役職者約4,000名を対象に「組織の壁を越え、組織の力を強化する」手法を学ぶ大規模研修を進めています。自律した人財一人ひとりが持つ熱意や個性を最大限に活かし、「ひとつのSUBARU」として持続的に最大限の成果を創出できるよう、「真の競争力をもった人・組織」の実現に向けた取り組みを強力に推し進めていきます。 <資本コストや株価を意識した経営>当社は持続的な成長に向けて「資本コストや株価を意識した経営の実現」が不可欠だと考えています。当社の直近の資本コスト(WACC ※CAPMベース)は7%半ばですが、ROEは12.8%と資本コストを上回る数値で推移しております。自動車業界の大変革期においても、世界最先端の「モノづくり」「価値づくり」を着実に実行し、競争力のあるSUBARUらしい商品を市場へ導入することで2030年を見据えた長期的目標として、「業界高位の収益力」「ROE10%以上」を追求していきます。2025年3月期は、足許のキャッシュの状況および株価の水準などを踏まえ、より一層、株主の皆様に報いる趣旨から安定的・累進的な配当を目指し、DOE(親会社所有者帰属持分配当率)の考え方を取り入れた株主還元方針に変更いたしました。一方、PERについては、現状6倍前後とプライム市場平均PERに対し低位で推移し、また、PBRは1倍を下回っています。米国における関税政策など自動車産業の不確実性を背景に期待が醸成されづらい状況であることが要因と捉えており、今後より一層のIR活動の強化に取り組み、「モノづくり革新」「価値づくり」の着実な実行の進捗開示などを通して、当社グループへの期待値向上へつなげていきます。 |
経営者による財政状態の説明
| 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要ならびに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は次の通りです。文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものです。 (1) 経営成績 当連結会計年度の世界経済は、地政学リスクの高まりや主要国でのインフレーションなどにより、先行き不透明な状況が継続しました。国内では、物価上昇が続くなかで緩やかな景気回復が見られました。また米国も底堅い雇用環境を背景に景気は堅調に推移しましたが、政権交代を受けて先行きの不透明感が増大しました。このような経営環境のなか、当社は、自動車業界の100年に一度と言われる大変革期においても、「安心と愉しさ」という不変の提供価値を具現化するために、「柔軟性と拡張性」の考え方のもとで、「モノづくり」と「価値づくり」で世界最先端を狙う取り組みを強力に推進してきました。 (売上収益)新型「フォレスター」およびストロングハイブリッドシステムを搭載した「クロストレック」が価格面で貢献したことならびに為替変動による増収効果などがあったものの、販売奨励金の増加および自動車売上台数の減少などにより、売上収益は4兆6,858億円と前連結会計年度に比べ172億円(0.4%)の減収となりました。 (営業利益)上記の理由に加え、研究開発費の増加および航空宇宙事業における引当金の計上などにより、営業利益は4,053億円と前連結会計年度に比べ629億円(13.4%)の減益となりました。 (税引前利益)4,485億円と前連結会計年度に比べ841億円(15.8%)の減益となりました。 (親会社の所有者に帰属する当期利益)3,381億円と前連結会計年度に比べ470億円(12.2%)の減益となりました。 (単位 金額:百万円、比率:%) 売上収益 親会社の所有者に為替レート営業利益税引前利益帰属する(利益率)(利益率)当期利益 (利益率) 2025年3月期4,685,763405,308448,507338,062152円/米ドル (8.6)(9.6)(7.2)162円/ユーロ2024年3月期4,702,947468,198532,574385,084144円/米ドル (10.0)(11.3)(8.2)154円/ユーロ増減△17,184△62,890△84,067△47,022 増減率△0.4△13.4△15.8△12.2 セグメントごとの経営成績は次の通りです。(単位 金額:百万円、比率:%) 売上収益セグメント利益(△損失)2024年3月期2025年3月期増減増減率2024年3月期2025年3月期増減増減率自動車4,593,6394,569,035△24,604△0.5461,524420,410△41,114△8.9航空宇宙104,317111,5847,2677.02,667△19,642△22,309-その他4,9915,1441533.13,6333,687541.5調整額----374853479128.1合計4,702,9474,685,763△17,184△0.4468,198405,308△62,890△13.4(注)1.売上収益は、外部顧客への売上収益です。 2.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去です。 (自動車事業)当社の重点市場である米国の自動車全体需要は約1,620万台と前連結会計年度を約3%上回りました。また、国内の自動車全体需要は約458万台と前連結会計年度を約1%上回る結果となりました。このような事業環境のなか、当連結会計年度の国内の生産台数は、前連結会計年度並みの60.2万台となりました。また、海外市場における販売状況および在庫台数などを踏まえた生産を行ったことにより、海外の生産台数は34.5万台と前連結会計年度に比べ2.3万台(6.3%)の減少となりました。以上の結果、国内と海外の生産台数の合計は94.6万台と前連結会計年度に比べ2.3万台(2.4%)の減少となりました。国内は、「フォレスター」などの登録車を中心に堅調に推移し、売上台数は10.4万台と前連結会計年度に比べ0.5万台(5.4%)の増加となりました。海外の卸売に相当する売上台数は、上記の販売状況などに呼応した生産を行ったことにより、83.2万台と前連結会計年度に比べ4.5万台(5.2%)の減少となりました。以上の結果、海外と国内の売上台数の合計は93.6万台と前連結会計年度に比べ4.0万台(4.1%)の減少となりました。なお、重点市場の米国におけるお客様への小売販売は32か月連続で前年同月超えを達成し堅調さを維持しています。新型「フォレスター」およびストロングハイブリッドシステムを搭載した「クロストレック」が価格面で貢献したことならびに為替変動などによる増収効果などがあったものの、販売奨励金の増加および自動車売上台数の減少などにより、売上収益は、4兆5,690億円と前連結会計年度に比べ246億円(0.5%)の減収となりました。またセグメント利益は、4,204億円と前連結会計年度に比べ411億円(8.9%)の減益となりました。 なお、当連結会計年度の連結売上台数は次の通りです。 (単位 台数:万台、比率:%) 2024年3月期2025年3月期増減増減率国内合計9.910.40.55.4 登録車8.79.10.55.2 軽自動車1.21.30.16.6海外合計87.883.2△4.5△5.2 北米76.373.2△3.2△4.1 欧州2.72.3△0.4△16.5 豪州4.74.4△0.4△7.8 中国0.60.3△0.3△52.9 その他地域3.43.1△0.2△6.6総合計97.693.6△4.0△4.1 (航空宇宙事業)防衛事業における生産の増加およびヘリコプター事業における納入機数の増加などにより、売上収益は1,116億円と前連結会計年度に比べ73億円(7.0%)の増収となりました。また、セグメント損失は、工事損失引当金を計上したことおよび民間機事業において納入機数が減少したことなどにより、196億円と前連結会計年度に比べ223億円の減益となりました。 (その他事業)売上収益は51億円と前連結会計年度に比べ2億円(3.1%)の増収となりました。また、セグメント利益は37億円と前連結会計年度に比べ1億円(1.5%)の増益となりました。 生産、受注および販売の実績は、次の通りです。 ① 生産実績当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次の通りです。なお、自動車の生産台数は、海外市場における販売状況および在庫台数などを踏まえた生産を行ったことにより、前連結会計年度を下回りました。 セグメントの名称当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)前年同期比(%)自動車 普通自動車(万台)94.6△2.4航空宇宙(百万円)141,698△14.6 (注)金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しています。 ② 受注状況当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次の通りです。 なお、自動車事業については見込生産を行っています。セグメントの名称受注高(百万円)前年同期比(%)受注残高(百万円)前年同期比(%)航空宇宙187,062△47.6643,944+13.6 (注)セグメント間の取引については相殺消去しています。 ③ 販売実績当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りです。セグメントの名称当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)前年同期比(%)自動車(百万円)4,569,035△0.5航空宇宙(百万円)111,584+7.0その他(百万円)5,144+3.1合計(百万円)4,685,763△0.4 (注)金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しています。 (2) 財政状態 ① 資産の状況当連結会計年度末の資産は、5兆882億円と前連結会計年度末に比べ2,741億円の増加となりました。主な要因は、外貨建定期預金の増加などにより「その他の金融資産(流動)」が1,448億円増加したこと、設備投資などで「有形固定資産」が928億円増加したこと、新車在庫の増加などに伴い「棚卸資産」が789億円増加したこと、法人税等および配当金支払いなどにより「現金及び現金同等物」が1,065億円減少したことです。 ② 負債の状況負債は、2兆3,725億円と前連結会計年度末に比べ1,238億円の増加となりました。主な要因は、未払費用の増加などにより「その他の流動負債」が495億円増加したこと、買掛金の増加などで「営業債務及びその他の債務」が413億円増加したこと、自動車環境規制関連引当金の増加などに伴い「引当金(流動・非流動)」が412億円増加したこと、「未払法人所得税」が413億円減少したことです。 ③ 資本の状況資本は、2兆7,157億円と前連結会計年度末に比べ1,503億円の増加となりました。主な要因は、当期利益の計上、配当金の支払いおよび取得した自己株式の消却により「利益剰余金」が1,995億円増加したこと、有価証券評価差額金および為替換算の影響により「その他の資本の構成要素」が486億円減少したことです。 (単位:百万円) 前連結会計年度(2024年3月31日)当連結会計年度(2025年3月31日)増減資産合計4,814,1495,088,246274,097負債合計2,248,7552,372,538123,783資本合計2,565,3942,715,708150,314 (3) キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、9,415億円となりました。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)営業活動による資金の増加は4,921億円(前連結会計年度は7,677億円の増加)となりました。主な要因は、税引前利益4,485億円、減価償却費及び償却費2,325億円、法人所得税の支払額1,732億円などです。 (投資活動によるキャッシュ・フロー)投資活動による資金の減少は4,041億円(前連結会計年度は7,037億円の減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出(売却による収入との純額)1,687億円、定期預金の増加1,243億円、無形資産の取得及び内部開発に関わる支出944億円などです。 (財務活動によるキャッシュ・フロー)財務活動による資金の減少は1,873億円(前連結会計年度は665億円の減少)となりました。主な要因は、親会社の所有者への配当金の支払額786億円、自己株式の取得による支出600億円、リース負債の返済による支出479億円などです。 (単位:百万円) 前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)増減営業活動によるキャッシュ・フロー767,665492,136△275,529投資活動によるキャッシュ・フロー△703,699△404,077299,622財務活動によるキャッシュ・フロー△66,469△187,320△120,851現金及び現金同等物の期末残高1,048,000941,460△106,540 (4) 資本政策の方針当社では資本政策の考え方として“「財務健全性と安定性の実現」「成長投資」「株主還元」の三位一体での実行”を掲げています。事業、市場、商品等の領域において「選択と集中」を進める当社にとって、経営基盤となる「財務健全性と財務安定性」の確保は不可欠であると考えます。そのうえで自動車業界の大変革期における世界最先端の「モノづくり」と「価値づくり」を実現し、SUBARUらしい商品の実現を支える「成長投資」と持続的な企業経営における重要要素と位置付ける「株主還元」のバランスを持った実行を目指しています。資本政策の実行にあたっては、資本コストや株価を意識した経営視点での取り組み実行が重要であると認識しております。2025年3月末時点において、資本コスト(WACC※CAPMベース)は国内金利の上昇傾向を受け7%半ば程度に上昇しましたが、資本収益性(ROE)は12.8%と資本コストを上回る数値で推移しております。加えて2024年8月の株式市場急落、その後の米国における関税政策を主とする自動車産業の不確実性の高まりを受け、PBRは0.7倍、PERは5.8倍となり、特にPERはプライム市場平均に対して低位の水準にあり改善課題と認識しています。この状況を踏まえ、当社では「ROE向上」「最適資金配分/1株あたり価値向上」「PER向上」「実効性の向上」という4つの取り組みテーマの実行により、2030年を見据えた長期目標として「業界高位の収益力」と「ROE10%以上」を追求しています。これらに関しては、経営会議および取締役会等において定期的に報告され、取り組みのアップデートを実施しています。 ①経営資源の配分に関する考え方当社は、財務健全性と安定性の担保に必要となる手元資金水準を考慮しつつ、設備投資や研究開発投資をはじめとする成長投資や株主還元等へ経営資源の適切かつ安定的な配分を目指しています。成長投資に関しては、2030年頃までに最大で約1.5兆円を電動化関連の投資金額として見込み、その内訳として「国内における電池・電動車生産」「電動車開発」「米国における電池・電動車生産」を計画しています。一方で、変化の激しい足元の経営環境を鑑み電動化投資に関する大きな方向性は維持しつつも投資時期を含めた計画見直しを実施しています。株主還元については、不確実性が高い経営環境下において資本効率向上をより意識するとともに、引き続き株主還元を持続的な企業経営の重要な要素と位置づけて取り組むべく、2025年2月に株主還元方針の見直しを公表しました。毎期の業績、投資計画、経営環境などを総合的に勘案したうえで、目標還元水準を総還元性向40%以上とし、配当を株主還元の基本と位置づけ、累進的な配当実現を目指すべくDOE3.5%を設定しています。また、配当額が総還元性向40%を下回る場合は自己株式取得を主として対応していきます。なお、2025年3月期業績に基づく株主還元については、米国における関税政策を主とする不確実性を鑑み、自己株式取得の実施判断を保留としております。 ②資金調達及び資金の流動性に係る分析当社は、当社グループの中期的な資金需要を念頭に置いた資金調達計画を策定し経営会議および取締役会の審議を経て意思決定しています。成長投資およびその他の事業資金については、事業活動により獲得した内部資金に加えて、市場環境に応じた適切な手段により外部から調達することとしており、銀行からの借入及び国内普通社債発行による資金調達を実施しています。手元資金は、2025年3月末時点において3か月超の定期預金を含む現金及び現金同等物の残高として1兆5,897億円となっています。これに加え、未使用のコミットメントライン約2,000億円を有しており、成長投資および変化の激しい事業環境を考慮しても十分な流動性を確保していると考えています。これらは安全性並びに流動性の極めて高い短期金融商品で運用しています。中長期的な資金の確保については、引き続き営業キャッシュ・フローに加え、外部からの調達により行っていきます。安定的な外部資金調達能力の維持向上を重視し、国内の格付機関である格付投資情報センター(R&I)から格付を取得しており、格付は「シングルAマイナス(安定的)」となっています。強固な財務体質を維持し、取引金融機関と良好な関係を構築していることからも、今後の資金調達に関して問題はないと認識しています。なお、連結子会社は原則として銀行などの外部から資金調達を行わず、当社及び関係会社を通じたキャッシュ・マネジメント・サービスやグループ・ファイナンスの活用により、資金調達の集約と資金効率化、流動性の確保を図っています。 (5) 重要性がある会計方針及び見積り当社グループの連結財務諸表は、IFRSに基づき作成されています。この連結財務諸表の作成にあたっては、様々な見積りによる判断が行なわれていますが、見積りに内在する不確実性により、実際の結果は異なることがあります。 連結財務諸表で採用する重要性がある会計方針は、「第5 経理の状況 連結財務諸表注記 3.重要性がある会計方針、4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載しており、特に重要な見積りを伴う会計方針は以下の通りです。 ① 損失評価引当金当社グループは、各報告日において、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大したかどうかを評価 しており、当該信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、当該金融商品に係る損失評価引当金を12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で測定しています。また、当該金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融資産に係る損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しています。ただし、営業債権、リース債権および契約資産については、常に損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しています。 将来、取引先などの財務状況が悪化するなどにより支払能力が低下した場合、引当金の追加計上または貸倒損失が発生する可能性があるため、連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があると考えています。 ② 製品保証引当金当社グループは、製品販売時に付与した保証約款に基づく製品保証とともに、主務官庁への届出等に基づいて個別に無償の補修を行っています。 保証約款に基づく製品保証の対象は、各国における保証約款に基づき、期間および走行距離や不具合の原因などにより決定しています。 保証約款に基づく製品保証の保証修理費用は、製品を販売した時点で引当金を認識しており、保証期間内に不具合が発生して部品を修理または交換する際に発生する費用の総額について、過去の補修実績、過去の売上台数を基礎として将来の発生見込みに基づく最善の見積りにより引当計上しています。 主務官庁への届出などに基づく個別の保証修理費用は、経済的便益を有する資源の流出が生じる可能性が高く、その債務の金額について信頼性をもって見積ることができる場合に引当金を認識しており、製品の不具合に関する過去の経験を基礎として算定した1台当たり将来保証修理費用などおよび対象台数に基づく最善の見積りにより引当計上しています。 当社グループは、発生が見込まれる保証修理費用について、現在入手可能な情報に基づき必要十分な金額を引当計上していると考えていますが、製品保証引当金の計算では将来複数年にわたり生じる保証修理費用を予測しているため、実際の保証修理費用が見積りと乖離することにより、製品保証引当金を追加計上する必要が生じる可能性があることから、連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があると考えています。③ 従業員給付当社グループは、従業員給付のうち退職給付について、将来の退職給付の支払いに備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、退職給付を計上していますが、この計算は主として数理計算上で算定される前提条件に基づいて行われています。この前提条件には、割引率、将来の給与水準、退職率、死亡率などが含まれており、それぞれの条件は現時点で十分に合理的と考えられる方法で計算されています。当社は、実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合には、将来期間において認識される費用および債務に影響を与える可能性があるため、連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があると考えています。割引率が変動した場合の確定給付制度債務に与える影響額については、連結財務諸表注記の「19 従業員給付(4)数理計算の仮定」を参照ください。 ④ 金融資産当社グループは、価格変動性の高い公開会社の株式、株価の決定が困難である非公開会社の株式、国債、社債および投資信託などを保有しています。 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産については、投資価値の変動により損失が発生することがあるため、連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があると考えています。 ⑤ 繰延税金資産繰延税金資産は将来減算一時差異などを使用できるだけの課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で認識し、繰延税金負債は原則としてすべての将来加算一時差異について認識しています。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期および金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の有価証券報告書において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。 |
※本記事は「株式会社SUBARU」の令和7年3月期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
※4. この企業は、連結財務諸表ベースで見ると有利子負債がゼロ。つまり、グループ全体としては外部借入に頼らず資金運営していることがうかがえます。なお、個別財務諸表では親会社に借入が存在しているため、連結上のゼロはグループ内での相殺消去の影響とも考えられます。
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

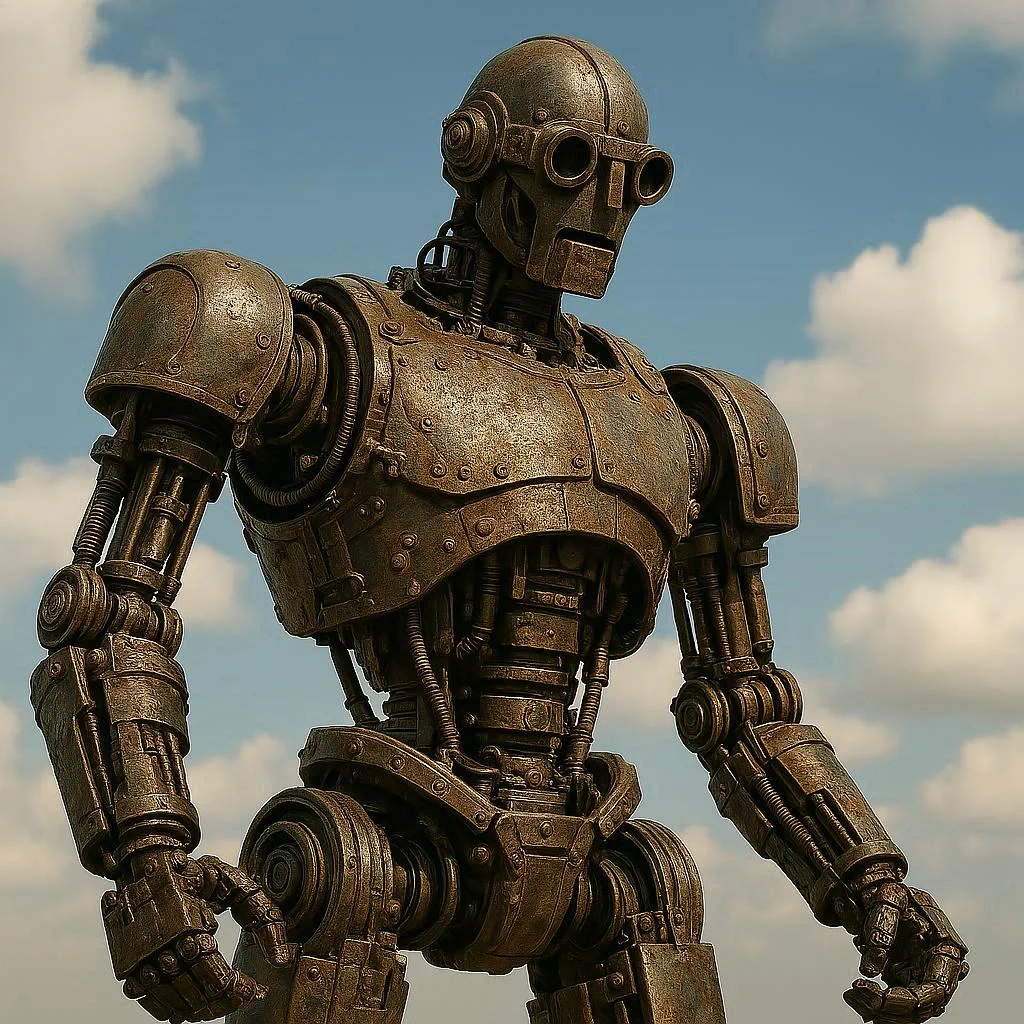

コメント