| 会社名 | 株式会社ジェイテクト |
| 業種 | 機械 |
| 従業員数 | 連45018名 単11153名 |
| 従業員平均年齢 | 41.3歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 17.3年 |
| 平均年収 | 7533357円 |
| 1株当たりの純資産(連結) | 1415.45円 |
| 1株当たりの純利益(連結) | 40.36円 |
| 決算時期 | 3月 |
| 配当金 | 50円 |
| 配当性向 | 32% |
| 株価収益率(PER) | 7.22倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(連結) | -1.3% |
| 営業活動によるCF | 802億円 |
| 投資活動によるCF | ▲759億円 |
| 財務活動によるCF | ▲520億円 |
| 研究開発費※1 | 558.65億円 |
| 設備投資額※1 | 122.29億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 611.1億円 |
| 株主資本比率※2 | 45.1% |
| 有利子負債残高(連結)※3※4 | 0円 |
経営方針
| 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。(1) 経営方針当社グループは、培った技術で社会課題の解決に貢献することを企業としての存在意義と考え、「技術をつなぎ地球と働くすべての人を笑顔にする」ことを企業経営と事業運営の軸としております。これに基づき、持てるモノづくり技術によって人とモノの自由な移動を可能にするソリューションプロバイダーとなることを2030年までの目指す姿として掲げ、一人ひとりが目標実現のために協力し合い、新たな価値を共創することを目指しております。 これからもMVV(Mission, Vision, Value)を企業経営の軸とし、モノづくりとモノづくり設備で培ってきた強みを結集して、グループの総力を最大限発揮する「全員参加」により、社会に最適なソリューションを提供し続けてまいります。 (2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標当社グループは、効率性と収益性を重視した経営を実現するため、ROE、PBR、事業利益率を経営上の目標の達成状況を判断するための重要指標と位置づけております。また、経営状況を把握する指標として、売上収益、事業利益、損益分岐点売上比率、棚卸資産回転数、NET DEレシオ、ROA、ROIC等の実績を用いております。 (3) 長期的な会社の経営戦略社会を取り巻く環境は、温暖化等に代表される環境問題やエネルギー資源の枯渇、新興国の経済発展・人口増加に伴う水・食料の不足、先進国での高齢化等、様々な課題が顕在化しております。各産業分野で社会の持続的な成長に向けてテクノロジーにより社会的課題の解決が図られている中で、当社グループの売上収益の約8割を占める自動車産業においても、100年に一度の大変革期と言われているとおり、自動運転や電動化等CASEに代表される技術革新が急速に進んでおります。環境規制は更に強化され、カーボンニュートラルに向けた再生エネルギーの活用や水素社会の実現に向けた取組みも着実に進んでおります。これらの取り巻く環境の変化に対応し、社会課題の解決を通して企業を成長させるため、2024年に第二期中期経営計画をスタートさせるとともに、2030年の目指す姿として「JTEKT Group 2030 Vision」を策定いたしました。 <中期経営計画>2021年から2030年までの10か年を、3年、3年、4年の三期に分け、第二期中期経営計画期間に当たる2024~2026年度は、「既存事業の成長と新規事業の育成」をテーマに各施策を進めております。既存製品の高付加価値化により成長への原資を生み出し、その原資をもとに新領域へチャレンジするという両輪で、企業価値向上を実現いたします。そのための重点施策と位置付けた「ソリューションの創出力強化」、「競争力の強化」、「グローバル体制の再構築」により、成長への足場固めを図ります。加えて、経営基盤を強化するために、「人と現場中心の経営」、「カーボンニュートラルの推進」、「キャッシュアロケーション・株主還元」にも注力してまいります。当社は、2030年に目指す姿を実現するためのメインドライバーは「ソリューションプロバイダーへの変革」であると捉えております。ソリューションを創出できる仕組みづくりを着実に進め、グループ全体が持つ技術や社員一人ひとりの強みを掛け合わせたジェイテクトならではのソリューションで社会に貢献してまいります。 (4) 経営環境当連結会計年度の世界経済には底堅い成長が認められましたが、当社の事業領域においては、自動車生産台数の伸び悩みや農建機を中心とした産機市場の冷え込み等、次第に不透明感が強まってまいりました。地域別には、特に欧州や中国で想定以上に景気停滞が深刻化し、成長を下押しする要因となりました。 (5) 優先的に対処すべき課題当社は、中長期的な目標であるJTEKT Group 2030 Visionで「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」を目指すことを掲げました。自動車部品や軸受のモノづくり技術と、工作機械というモノづくり設備に強みをもつ当社だからこそ実現できる、画期的なソリューションで社会に貢献していきたいと考えております。そのためには、コア技術やコンピタンスを掛け合わせることで、既存製品の付加価値を高めていくとともに、新たな領域へチャレンジし成長事業へと育てていくことが不可欠となります。その先進的な事例として、主力製品の電動パワーステアリングの補助電源装置として開発された高耐熱リチウムイオンキャパシタ「LibuddyR」が、当社の持つ様々なコンピタンスと掛け合わさり、多方面へ新たなソリューションを提供しつつあります。例えば、電動パワーステアリングで培ったモーター制御技術や安全設計技術等のコンピタンスとLibuddyRを融合させ、ドローンの姿勢制御システムの開発に着手しております。更なる開発・検証を重ね、次世代のモビリティであるドローンの性能向上への貢献を目指します。このように当社がこれまで積み重ねてきた多岐にわたる技術や強みを活用し、積極的に新領域開拓に挑んでまいります。人やモノが自由に移動できるモビリティ社会のなかで、当社が存在価値を発揮していくためには、これまでの受動型のビジネスからソリューション型ビジネスに大きく転換しなければなりません。その第一歩として、コアコンピタンスプラットフォーム(以下「ココプラ」)と呼ばれる、グループのコア技術やスキルを持つ人財を集約したプラットフォームの構築に注力しております。また、新たに設置したソリューション共創センター(以下「ソリセン」)では、お客様や社内が抱える課題を受け付け、ココプラをつなぎ合わせた最適なソリューションの創出を目指します。まずはココプラやソリセンの活用事例を社内で蓄積し、ソリューション型ビジネスの土台を築いてまいります。この仕組みをブラッシュアップしていくことで、全てのビジネスをソリューション型へと転換させ、ソリューションプロバイダーへと変革してまいります。加えて、ソリューションプロバイダーへの飛躍を支える経営基盤の強化のため、不要なコストや固定費の徹底的な削減、構造改革や業務の見直し・効率化にも覚悟を持って取り組んでまいります。特に足元では北米において、Covid19蔓延以降の熟練技能者の離職増加や人員不足の顕在化による生産性悪化や不要なコスト増加が課題となっております。生産体制の正常化、コストの最小化のため、タスクフォースチームを現地に派遣して収益性改善に努めております。北米地域に限らず会社全体で不要なコストを極小化させ、健全に収益を生み出すことができる体制を固めてまいります。また、「安全第一・品質第二」を旨とする当社は、「Yes for All, by All! ~みんなのためにみんなでやろう~」という価値観のもと、安全の確保や不正を起こさない職場風土の醸成といったガバナンスの強化を一層推し進め、社会から信頼される会社であり続けるよう、絶え間ない改善を続けてまいります。 |
経営者による財政状態の説明
| 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (経営成績等の状況の概要)(1) 財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度の世界経済には底堅い成長が認められましたが、当社の事業領域においては、日本での自動車生産台数の伸び悩みや、欧州や中国の景気停滞継続等、次第に不透明感が強まってまいりました。外部環境の厳しさが増すなかではありましたが、2030年までに目指す姿として掲げた「JTEKT Group 2030 Vision」を指針として、「ソリューションプロバイダーへの変革」を実現するための体制づくりに注力いたしました。2030年に向け、既存製品の高付加価値化により成長への原資を生み出し、その原資をもとに新領域へチャレンジするという両輪で、ソリューションプロバイダーへの飛躍を目指します。 当社は、第二期中期経営計画(2024?2026年度)に基づき、当連結会計年度はその初年度として、本計画に沿った戦略を着実に実行してまいりました。特に、重点施策として位置づけた「ソリューションの創出力強化」、「競争力の強化」、「グローバル体制の再構築」により、成長への足場固めを図りました。加えて、経営基盤を強化するために、「人と現場中心の経営」、「カーボンニュートラルの推進」、戦略的な「キャッシュアロケーション・株主還元」にも注力いたしました。 「ソリューションの創出力強化」につきましては、2025年1月にソリューション共創センター(ソリセン)を開設いたしました。全社を挙げてジェイテクトグループの持つ技術や知見(コアコンピタンス)をプラットフォーム化し、ソリセンは、それらをつなぎながら、社内外から寄せられた課題をともに解決へと導く役割を担います。ソリセンには、すでに100件を超える相談が集まり、中にはお客様満足度向上につながったソリューション創出事例も出始め、着実に成果が現れております。ソリセンの仕組みを活用し、社会や社内の課題解決策の創出を積み重ねることにより、会社全体でソリューションプロバイダーへの変革を実現してまいります。「競争力の強化」の取組みとして、「自動車事業」においては、お客様のニーズに応えるために「軽量・コンパクト」をコンセプトにしたC-EPSの開発、「良質廉価」なモノづくりをコンセプトにした第2世代のRP-EPSの開発を実施してまいりました。また、将来のビジネスを見据えて、我々のコア技術をベースとしたステアバイワイヤ(自動運転に親和性の高い新ステアリングシステム)の開発に注力しているほか、PairdriverR(人とシステムがシームレスに調和した自動運転を実現するシステム)をさらに進化させるため、高付加価値化に努めております。「産機・軸受事業」では、デジタルを活用した開発リードタイムの短縮等、競争優位性の確立に努めてまいりました。軸受設計プロセスにおいては、設計データの管理一元化や、設計者による計算等の作業を自動化するシステムの開発・導入により、設計検討時間を従来比1/4に短縮することを実現いたしました。「工作機械・システム事業」では、幅広い顧客ニーズにお応えするための研削盤大型モデル、BEV用電池の進化を支える設備の開発を進めました。また、労働力不足や環境対応等の課題解決に貢献するために、自動化・工程集約のご提案や保全業務を効率化するデジタルサービスも強化しております。「アフターマーケット事業」では、海外新興市場の開拓やお客様の新たなニーズにお応えする商品の開発に注力いたしました。気候変動等により多発する水害の未然防止に貢献するために、耐環境性に優れ、海水域や寒冷地等の悪環境下でも長寿命を実現した水位計「STD series」を発表しております。また、当社はこれら事業を支えるデジタル基盤強化のため、全社を挙げてITリテラシーの向上や、生産現場でのAI導入・自動化による生産性改善等、デジタルモノづくり改革を推進しております。「デジタル祭り」と銘打った全社活動では、ITデジタルツールを整備するとともに、デジタル活用事例を共有できるサイトの公開やイベントを実施いたしました。これらの活動を通じ、各人が業務内で自発的にデジタル化を進める機運が高まりました。また、生産現場においても、検査工程等においてプログラミング不要で容易に使用できるAI活用プラットフォームを内製する等、着実にデジタルモノづくり改革を進めております。「グローバル体制の再構築」としては主要地域ごとに戦略を明確化し、グローバルでの企業価値最大化に向けた取組みを実行してまいりました。成長市場と位置付けているインドにつきましては、2024年10月に新工場の設立を決定いたしました。一方、市場低迷が続き収益体質改善が急務である欧州では、構造改革を加速させました。拠点ごとに生産体制の在り方を精査し、油圧ポンプ製造拠点及びニードルローラーベアリング事業の売却を実行しております。欧州では、今後もう一段の構造改革を実行し、早期黒字化を目指してまいります。 人的資本戦略としては「人と現場中心の経営」を掲げ、「チャレンジが人を育て、人が新たなソリューションを生み出す」という考えのもとチャレンジできる風土の醸成を進めてまいりました。また、従業員エンゲージメントの向上がソリューションプロバイダーへの変革の重要ファクターと位置付け、「おもいやりコミュニケーション研修」や「おたがいを尊重しよう月間」等の新たな試みを実施いたしました。環境に配慮した取組みとしては、「カーボンニュートラルの推進」の一環として刈谷工場内にCNラボを開設いたしました。CNラボは、太陽光発電により水素を生成し、貯めることができるモデルプラントであります。当社では、2035年にグローバルでカーボンニュートラル達成を目指しており、その実現に向けた当社グループの2030年度の温室効果ガス排出削減目標(2021年度比)は、SBT※認定を取得しております。このような気候変動への取組みは、国際環境非営利団体CDPによる最新の気候変動分野の評価で最上位のAを獲得する等、外部からも高く評価されております。また、サーキュラーエコノミーの実現にも一層注力し、資源の再利用や廃棄物の削減等の取組みを進めてまいります。「キャッシュアロケーション・株主還元」につきましては、第二期中期経営計画期間中に1,000億円の株主還元を計画し、着実に施策を実行してまいりました。配当につきましては、安定的な配当を継続する姿勢を明確にするべく還元方針をDOE(親会社所有者帰属持分配当率)2-3%目安に改定し、増配いたしました。加えて、当社としては初の自己株式取得として280億円超の買付けを実施いたしました。今後も企業価値を高めるとともに株主のみなさまへの還元の充実を図ってまいります。また、政策保有株式につきましてもゼロ化に向けて縮減を着実に進めております。それにより創出された資金は、持続的な成長実現のため人財や研究開発等に積極投資する等、資本効率の最適化に努めてまいります。 ※SBT:パリ協定が求める水準と整合した、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標 当連結会計年度の連結業績につきましては、次のとおりであります。前連結会計年度に比べ、売上収益は71億7百万円(0.4%)減収の1兆8,843億97百万円、事業利益は79億60百万円(10.9%)減益の649億38百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益は265億44百万円(65.9%)減益の137億13百万円となりました。なお、売上収益事業利益率は3.4%と前連結会計年度より0.4ポイント低下しております。 セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。「自動車」におきましては、為替影響はあるものの、欧州や中国での減収が大きく、売上収益は前連結会計年度に比べ112億87百万円(0.8%)減収の1兆3,331億50百万円となりました。事業利益は、為替影響や原価改善の効果はあるものの、減収や北米における生産性悪化の影響等により、66億95百万円(14.9%)減益の383億44百万円となりました。「産機・軸受」におきましては、為替影響はあるものの、日本や欧州での減収が大きく、売上収益は前連結会計年度に比べ58億8百万円(1.6%)減収の3,522億68百万円となりました。事業利益は、為替影響や原価改善の効果はあるものの、減収の影響が大きく、40億36百万円(31.8%)減益の86億49百万円となりました。「工作機械」におきましては、為替影響もあり北米や中国を中心に増収となり、前連結会計年度に比べ売上収益は99億89百万円(5.3%)増収の1,989億78百万円となり、事業利益は、為替影響や原価改善の効果等により、26億74百万円(18.1%)増益の174億10百万円となりました。 財政状態につきましては、次のとおりであります。当連結会計年度末における資産は、現金及び現金同等物や棚卸資産の減少等により、1兆5,653億91百万円と前連結会計年度末に比べ631億22百万円の減少となりました。負債につきましては、繰延税金負債や退職給付に係る負債の減少等により、7,879億22百万円と前連結会計年度末に比べ178億21百万円の減少となりました。また、資本につきましては、配当や自己株式の消却による利益剰余金の減少等により、7,774億69百万円と前連結会計年度末に比べ453億1百万円の減少となりました。なお、1株当たり親会社所有者帰属持分は前連結会計年度の2,300円32銭から2,340円55銭に増加いたしました。また、社債及び借入金につきましては、2,404億75百万円と前連結会計年度末に比べて14億72百万円減少しました。当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の「(3) 長期的な会社の経営戦略」や「(5) 優先的に対処すべき課題」に記載しております様々な取組みにより、第二期中期経営計画の目標達成につなげてまいります。 (2) キャッシュ・フローの状況連結キャッシュ・フローにつきましては、次のとおりであります。営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益の計上等により、当連結会計年度は802億38百万円の資金の増加となりました。(前連結会計年度は1,544億61百万円の資金の増加)投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入があったものの、有形固定資産の取得による支出等により、当連結会計年度は759億36百万円の資金の減少となりました。(前連結会計年度は713億52百万円の資金の減少)財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や自己株式の取得、配当金の支払等により、当連結会計年度は520億76百万円の資金の減少となりました。(前連結会計年度は472億24百万円の資金の減少)これらに換算差額を減算した結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,190億60百万円となりました。 (生産、受注及び販売の実績) (1) 生産実績 セグメントの名称当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)生産高(百万円)前年同期比(%)自動車1,091,40995.0産機・軸受346,216103.6工作機械97,506110.5合計1,535,13297.7 (注) 1 金額は平均販売価格によっております。2 上記の金額には、外注加工費及び購入部品費が含まれております。 (2) 受注実績当社グループの販売高の大部分を占める、自動車業界向け部品については、納入先から提示される生産計画を基に、当社グループの生産能力等を勘案して生産を行っております。なお、工作機械の受注実績は以下のとおりであります。 セグメントの名称当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)受注高(百万円)前年同期比(%)受注残高(百万円)前年同期比(%)工作機械117,025119.460,144104.2 (3) 販売実績 セグメントの名称当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)販売高(百万円)前年同期比(%)自動車1,333,15099.2産機・軸受352,26898.4工作機械198,978105.3合計1,884,39799.6 (注) 主要な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。 相手先前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)販売高(百万円)割合(%)販売高(百万円)割合(%)トヨタ自動車㈱369,22419.5382,12420.3 (経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。(1) 重要性がある会計方針及び見積り当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条の規定によりIFRSに準拠して作成しております。この連結財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基づいて実施しております。なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要性がある会計方針及び、将来に関する仮定及び報告期間末における見積りの不確実性の要因となる事項は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 連結財務諸表注記」の「2.作成の基礎 (4)重要な会計上の判断、見積り及び仮定」及び「3.重要性がある会計方針」に記載しております。 (2) 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容① 売上収益当連結会計年度の売上収益は、前連結会計年度に比べ71億7百万円(0.4%)減収の1兆8,843億97百万円となりました。セグメント別に見ると次のとおりであります。「自動車」は前連結会計年度に比べ112億87百万円(0.8%)減収の1兆3,331億50百万円となりました。地域別の主な内訳は、日本5,121億33百万円(62億50百万円、1.2%の増収)、アジア・オセアニア3,296億38百万円(136億28百万円、4.0%の減収)、北米2,945億13百万円(153億67百万円、5.5%の増収)であります。「産機・軸受」は前連結会計年度に比べ58億8百万円(1.6%)減収の3,522億68百万円となりました。地域別の主な内訳は、日本1,495億78百万円(31億94百万円、2.1%の減収)、北米913億1百万円(11億81百万円、1.3%の減収)、アジア・オセアニア568億58百万円(25億28百万円、4.7%の増収)であります。「工作機械」は前連結会計年度に比べ99億89百万円(5.3%)増収の1,989億78百万円となりました。地域別の主な内訳は、北米995億64百万円(46億77百万円、4.9%の増収)、日本773億40百万円(2億76百万円、0.4%の増収)、アジア・オセアニア206億80百万円(51億8百万円、32.8%の増収)であります。 ② 事業利益当連結会計年度の事業利益は、前連結会計年度に比べ79億60百万円(10.9%)減益の649億38百万円となりました。セグメント別に見ると次のとおりであります。「自動車」は、為替影響や原価改善の効果はあるものの、減収や北米における生産性悪化の影響等により、前連結会計年度に比べ66億95百万円(14.9%)減益の383億44百万円となりました。「産機・軸受」は、為替影響や原価改善の効果はあるものの、減収の影響が大きく、前連結会計年度に比べ40億36百万円(31.8%)減益の86億49百万円となりました。「工作機械」は、為替影響や原価改善の効果等により、前連結会計年度に比べ26億74百万円(18.1%)増益の174億10百万円となりました。 ③ その他の収益・その他の費用その他の収益は、受取保険料等が増加しましたが、前連結会計年度に製品保証引当金戻入を計上していたこと等により、前連結会計年度に比べ34億41百万円(30.1%)減少の79億96百万円となりました。その他の費用は、事業構造改善費用の増加等により、前連結会計年度に比べ123億42百万円(55.7%)増加の344億82百万円となりました。 ④ 金融収益・金融費用主に為替影響により、金融収益は、前連結会計年度に比べ106億91百万円(55.6%)減少の85億47百万円となり、金融費用は、前連結会計年度に比べ73億84百万円(75.7%)増加の171億39百万円となりました。 ⑤ 親会社の所有者に帰属する当期利益上記の要因等により、親会社の所有者に帰属する当期利益は、前連結会計年度に比べ265億44百万円(65.9%)減益の137億13百万円となりました。 当社グループは、2030年の目指す姿を達成するための第二期中期経営計画期間の目標を以下のとおりとしております。 第二期中期経営計画(期間:2024~2026年度)の目標及び実績 実績(2024年度)目標(2026年度)ROE1.8%7-8%PBR0.48倍1倍事業利益率3.4%5-6% なお、これらの目標につきましては、達成を保証するものではありません。 (3) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりであります。当社グループの資金需要の主なものは、設備投資、投融資、研究開発費等の長期資金需要と、当社製品製造のための材料及び部品購入等の運転資金需要であります。当社グループは、事業活動のための適切な資金確保、適切な流動性の維持及び健全な財政状態の維持を財務方針としております。 現金及び現金同等物等の流動性資産に加え、営業活動によるキャッシュ・フロー、市場あるいは金融機関からの資金調達を通じ、現行事業の推進と事業拡大に必要となる資金を確保できる状況と考えております。 また、グループ各社に偏在する余剰資金の相互融通を図る等、資金効率の向上に努めております。 |
※本記事は「株式会社ジェイテクト」の令和7年3月期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
※4. この企業は、連結財務諸表ベースで見ると有利子負債がゼロ。つまり、グループ全体としては外部借入に頼らず資金運営していることがうかがえます。なお、個別財務諸表では親会社に借入が存在しているため、連結上のゼロはグループ内での相殺消去の影響とも考えられます。
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

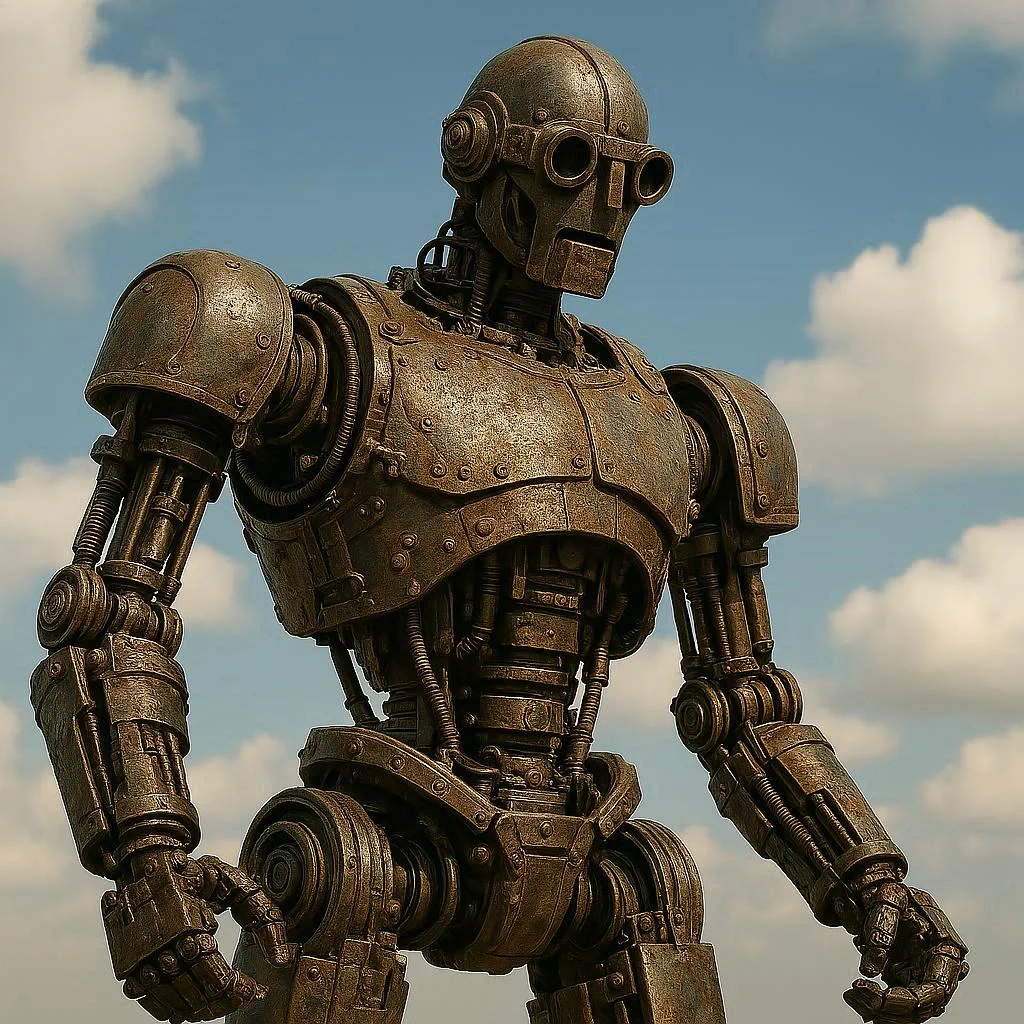


コメント