| 会社名 | トヨタ自動車株式会社 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 従業員数 | 連383853名 単71515名 |
| 従業員平均年齢 | 40.7歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 15.6年 |
| 平均年収 | 9825635円 |
| 1株当たりの純資産(単体) | 1648.01円 |
| 1株当たりの純利益(連結) | 359.56円 |
| 決算時期 | 年3 |
| 配当金 | 90円 |
| 配当性向 | 31% |
| 株価収益率(PER) | 9倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(単体) | 18.3% |
| 営業活動によるCF | 36969億円 |
| 投資活動によるCF | ▲41897億円 |
| 財務活動によるCF | 1972億円 |
| 研究開発費※1 | 157.42億円 |
| 設備投資額※1 | 21348.9億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 611.1億円 |
| 株主資本比率※2 | 72.3% |
| 有利子負債残高(連結)※3※4 | 0円 |
経営方針
| 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】本項においては、将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は2025年3月31日現在において判断したものです。 (1)会社の経営の基本方針 トヨタは経営の基本方針を「トヨタ基本理念」として掲げており、その実現に向けた努力が、企業価値の増大につながるものと考えています。その内容は次のとおりです。1. 内外の法およびその精神を遵守し、オープンでフェアな企業活動を通じて、国際社会から信頼される企業市民をめざす2. 各国、各地域の文化、慣習を尊重し、地域に根ざした企業活動を通じて、経済・社会の発展に貢献する3. クリーンで安全な商品の提供を使命とし、あらゆる企業活動を通じて、住みよい地球と豊かな社会づくりに取り組む4. 様々な分野での最先端技術の研究と開発に努め、世界中のお客様のご要望にお応えする魅力あふれる商品・サービスを提供する5. 労使相互信頼・責任を基本に、個人の創造力とチームワークの強みを最大限に高める企業風土をつくる6. グローバルで革新的な経営により、社会との調和ある成長をめざす7. 開かれた取引関係を基本に、互いに研究と創造に努め、長期安定的な成長と共存共栄を実現する (2)トヨタフィロソフィートヨタはモビリティカンパニーへの変革を進めるために、改めて歩んできた道を振り返り、未来への道標となる「トヨタフィロソフィー」をまとめました。トヨタはモビリティカンパニーとして移動にまつわる課題に取り組むことで、人や企業、コミュニティの可能性を広げ、「幸せを量産」することを使命としています。そのために、モノづくりへの徹底したこだわりに加えて、人と社会に対するイマジネーションを大切にし、様々なパートナーと共に、唯一無二の価値を生み出していきます。 「トヨタフィロソフィー」 MISSIONわたしたちは、幸せを量産する。技術でつかみとった未来の便利と幸福を手の届く形であらゆる人に還元する。VISION可動性(モビリティ)を社会の可能性に変える。人、企業、自治体、コミュニティができることをふやし、人類と地球の持続可能な共生を実現する。VALUEトヨタウェイソフト、ハード、パートナーの3つの強みを融合し、唯一無二の価値を生み出す。 (3)会社の対処すべき課題 グループビジョン「次の道を発明しよう」グループビジョンは、トヨタグループ*1の目指すべき方向、トヨタグループ全員が立ち戻ることができるビジョン・価値観です。 「次の道を発明しよう」。 グループの創始者・豊田佐吉は「苦労する母親を少しでも楽にしたい」という想いで、「豊田式木製人力織機」を発明しました。そして、豊田喜一郎は「日本人の頭と腕で自動車工業を興さねばならない」との想いで「国産乗用車」を発明しました。誰かを想い、学び、技を磨き、ものをつくり、人を笑顔にする。発明への情熱と姿勢こそ、トヨタグループの原点です。正解のない時代に、互いに「ありがとう」と言い合える風土を築き、多様な人財が活躍し、未来に必要とされるトヨタグループを目指していきます 。*1 ㈱豊田自動織機、トヨタ自動車㈱、愛知製鋼㈱、㈱ジェイテクト、トヨタ車体㈱、豊田通商㈱、㈱アイシン、㈱デンソー、トヨタ紡織㈱、トヨタ不動産㈱、㈱豊田中央研究所、トヨタ自動車東日本㈱、豊田合成㈱、日野自動車㈱、ダイハツ工業㈱、トヨタホーム㈱、トヨタ自動車九州㈱、ウーブン・バイ・トヨタ㈱の18社(2025年3月31日時点) 足場固めと認証問題への対応[足場固め]この1年は、持続的成長の基盤として「1,000万台のクルマづくりの競争力」と「多様な挑戦の実行力」を発揮できる環境をつくること、すなわち「足場固め」の取り組みを着実に進めてきました。全社を挙げて、余力をつくり、人材育成や安全・品質の徹底に取り組んできました。特に注力してきたのが、生産現場の基盤整備です。モノづくりを取り巻く環境は、厳しさを増しています。日本の生産年齢人口は、今後15年で2割減少する見込みです。建屋・設備の老朽化が進み、稼働に影響を与えることも増えています。「生産性」と「働きやすさ」を向上させなければ、モノづくりの基盤を守り抜けないという問題意識のもと、各工場で暑熱対策をはじめとする環境改善や、多様なメンバーの全員が働きやすい生産ラインづくりなどに取り組んできました。さらに、将来に向けて、モノづくりの変革を目指す「未来工場」のプロジェクトも立ち上げました。自動化の大幅な拡充や多様な働き方の導入など、10年先、50年先を見据えて、生産性向上とやりがいにつながる踏み込んだ取り組みを検討していきます。 開発においても、「1,000万台のクルマづくりの競争力」の向上に取り組んできました。そのひとつが、TNGAプラットフォームの素性の良さを活かして、多様なお客様ニーズに柔軟に応えながら、お客様のニーズを正しく把握して仕様や部品の種類を適正化する「AREA35」の活動です。国内10工場でのトライアルを通じて、フルモデルチェンジ3プロジェクト相当の開発効率化につなげることができました。今後はグローバルに活動を展開して、さらなる開発・生産効率の向上を目指します。 また、基幹システムが分散していることで、人が介在してつないでいる車両仕様情報をDXにより開発から販売まで一気通貫でつなぐ仕組みなど、将来を見据えたクルマづくりの基盤整備も進めてきました。 [認証問題への対応]認証問題については、全社を挙げて、再発防止に取り組んできました。国土交通省には四半期報告としてこれまで2回、その進捗を報告し、ご指導をいただきながら改善を進めています。短期の取り組みは、再発防止で定めた14項目の着実な実行です。認証問題を通じて分かった経営と現場の乖離という反省を踏まえ、多くの経営メンバーが現場を回る活動に取り組みました。 これらの取り組みにより、認証業務は「現場の頑張り」に支えられているということ、また、現場では設備や備品の老朽化が業務に大きな影響を与えていることなど、様々な課題が明らかになりました。こうした実態を踏まえて、現場の負担や不安を解消できるよう、負荷が高い部署の人員の拡充や、正しい仕事に必要な設備250件以上の投資を即決するなど、対策を進めました。監査体制についても、2線監査を強化するために「法規主監」のメンバーを約40名まで増員し、認証現場の実態をくまなく把握できる体制を整えました。そして、開発の節目管理も強化するために、認証準備や開発完了などの節目で、責任者を明確にしたうえで次のフェーズへの移行可否を判断する仕組みへ見直しました。実際のプロジェクトで、計画に無理が認められるものは移行を止めるという運用が既に始まっています。引き続き、現場を楽にする改善を積み重ねて、正しい仕事ができる環境を整えています。中期の取り組みでは、一人ひとりの意識、風土を変えることを目指しています。その軸となるのが、会長の豊田のリードで進めている法規認証をテーマにしたTPS自主研の取り組みです。TPS自主研では、余力を生み出し正しい仕事を実践するために部署を超えたメンバーが集まって、仕事のプロセス全体で、停滞やムダを減らす改善を進めています。例えば、エンジンECUの開発プロセスや車両仕様書をつくるプロセスのリードタイムの短縮をテーマに掲げて、改善活動が進んでいます。長期の取り組みは、認証制度の改革です。2025年3月には、国土交通省と自動車メーカーの間で、未来志向の認証制度を検討する「官民協議会」がキックオフしました。認証現場の声を国土交通省に届け、日本の競争力に資する制度改革につなげていきます。認証問題への対応を通じ、この取り組みは、会社全体の風土・体制・仕組みを改善することそのものであると感じています。引き続き、取り組みの実効性を高めて、トヨタらしいガバナンスの向上につなげていきます。 連結ガバナンスの進捗連結ガバナンスについても、昨年取りまとめた施策を着実に実行しました。 風土面では、グループ6社*2が一体となったTPS自主研の活動において、グループ各社のトップが集まり、現場に軸足を置いた改善を進めています。トップおよび実務で重層的なコミュニケーションを拡充し、各社の悩みや本音を双方向で共有しています。特に、認証問題の再発防止に取り組むダイハツ工業㈱、日野自動車㈱、㈱豊田自動織機との連携を強化しました。ダイハツ工業㈱と㈱豊田自動織機とは、再発防止の進捗や、事業連携のあり方など、お互いの困りごとや経営課題について、トップ間で頻度高く、話し合いを続けてきました。日野自動車㈱に対しては、ダイムラートラック社とともに、三菱ふそうトラック・バス㈱との経営統合の準備をサポートしています。今後とも、トップ同士、実務間で、再発防止を踏まえたグループ連携を深めていきます。体制面では、取締役会の実効性の向上に取り組むとともに、昨年6月に立ち上げた「ガバナンス・リスク・コンプライアンス会議」では、認証問題や大規模災害のBCPをはじめとする足元の重要経営課題について、また、「サステナビリティ会議」では、未来工場やダイバーシティ人財の活躍など、サステナビリティ経営の重点5テーマについて、社外役員の知見を取り入れて、施策の方向づけを行ってきました。仕組みの面では、内部統制の強化に向けて、重点対象の子会社17社に対して、従来の2倍以上の時間をかけて、多面的な監査を実施してきました。さらに、子会社の役員向けの内部統制に関する研修会の実施、他社事例の共有など、実践的かつ具体的な研修プログラムも展開しています。なお、認証問題の責任については、会長・副会長・社長の評価に反映し、報酬を減額しています。詳細は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(4)役員の報酬等」を参照ください。引き続き、グループ・連結の視点で、ガバナンスの向上に取り組んでいきます。*2 ㈱豊田自動織機、トヨタ自動車㈱、トヨタ車体㈱、トヨタ自動車東日本㈱、日野自動車㈱、ダイハツ工業㈱ モビリティカンパニーへの変革の実践トヨタは、すべての人に移動の自由と楽しさをお届けし、安心・安全で、持続可能なモビリティ社会を実現するために、モビリティカンパニーへの変革を目指しています。 将来にわたって、クルマが世の中の人々を笑顔にするモビリティであり続けるためには、交通事故や環境負荷の増大、渋滞など、クルマが生み出すネガティブな影響を最小化し、同時に、利便性や快適性、運転の楽しさなど、ポジティブな面を最大化していくことが必要であると考えています。そのステップを「モビリティ1.0:クルマの価値の拡張」「モビリティ2.0:モビリティの拡張」「モビリティ3.0:社会システムとの融合」の3つに整理したToyota Mobility Conceptのもと、「カーボンニュートラル」「移動価値の拡張」という重点テーマに基づき、様々な挑戦を進めています。クルマの未来を変えていくうえでは、エネルギーの未来に向き合うことが大切です。将来的には、再生可能エネルギーの普及を通じて、社会を支えるエネルギーは電気と水素に収れんしていくと考えられます。一方で、足元では国・地域ごとに様々なエネルギー事情があり、トランジションのペースは異なります。こうした背景認識のもと、電気と水素の未来を見据えながら、短期的にはエネルギーの実情や多様なお客様ニーズに応える選択肢を提供し、現実に即したトランジションを進めていくのが、トヨタのマルチパスウェイの考え方です。当期も、実践的なCO2削減に貢献するハイブリッド車の多様なラインアップを基盤に、マルチパスウェイの取り組みの解像度を上げるべく、選択肢の具体化を着実に進めてきました。内燃機関においては、レースを通じて鍛えている水素エンジンの技術をはじめ、長年培ってきた燃焼技術を磨いて、環境性能の高い小型・高効率な新エンジンを開発しています。次世代BEVの小型電動ユニットも活用し、電気リッチなハイブリッド車・プラグインハイブリッド車を生み出すことをめざしています。次世代BEVでは、原理原則に立ち返って、クルマの構造・設計とモノづくりの合理化に取り組み、デザインはもちろん、空力をはじめとするBEVの最適な性能にこだわって開発を進めています。小型電動ユニットなど、磨いた技術をその他のパワートレーンの進化にも活かしていきます。水素で走るFCEVは、まずは商用車を軸に事業・市場の基盤づくりを進めています。エネルギー事業者をはじめとする仲間とともに、「つくる」「はこぶ」「つかう」のバリューチェーン全体での連携を強化しています。 そして、多様な移動ニーズにお応えしていくために、社会とつながるクルマの新たな価値づくりをめざしています。そのカギは、ソフトウエアプラットフォームのAreneの実装を通じて、データとエネルギーの可動性を高めていくことです。次世代BEVで挑戦するソフトウエア・ディファインド・ビークル(SDV)がこの取り組みをリードしていきます。トヨタが考えるSDVの最も重要な提供価値は、安全・安心です。交通事故ゼロに貢献する自動運転など、安全・安心を軸にしたクルマの価値を広げるために、日本電信電話㈱をはじめとするパートナーの皆様とともに、切れ目のない通信・AI基盤の構築を進めています。さらに、クルマを多様なサービスやアプリとつなげて、お客様に寄り添った移動の価値を生み出していきたいと考えています。 また、クルマの価値を広げながら、パーソナルモビリティから車いすモビリティ、e-Paletteなどの商用モビリティ、ボート、フライングモビリティまで、新しい領域へのモビリティの拡張に取り組んでいます。多くのパートナーと共に、今の事業範囲を越えて、世界中のお客様の移動を支えていきたいと考えています。モビリティ3.0の領域では、社会システムと融合したモビリティの価値づくりをめざしています。タイでパートナーと取り組んでいるデータ・エネルギー・モビリティの社会実装や、中国における自動運転・水素社会の実装など、地域ごとにプロジェクトを進めています。蓄電事業では、再生可能エネルギーの普及に向けた持続可能な社会システムの構築をめざしています。電池のエコシステムづくりをはじめ、「より少ない資源でつくる」「より長く使う」「回収時に廃棄物を出さない」という考え方のもと、サーキュラーエコノミーの実現を目指した取り組みも進めています。これらの挑戦を支えるのが、2025年秋以降に実証をスタートするモビリティのテストコース「Woven City」です。Woven Cityは「自分以外の誰かのために」という思いをもつInventors(発明家)が「モビリティの拡張」を目指し、自らのプロダクトやサービスを生み出し、実証を行う場です。Woven Cityにおける価値を共創するWeavers(住民やビジター)からリアルなフィードバックを受けながら、様々なInventorsとのコラボレーションを通じて、未来につながるイノベーションを生み出していきます。様々な新しい技術・サービスをWoven Cityで実証し、社会実装で育てるサイクルを回して、社会システムと融合したモビリティの価値をスピーディに具現化していきたいと考えています。Toyota Mobility Conceptのもと、クルマの新たな価値を追求し続けていくことで、モビリティカンパニーへの変革を着実に進めていきます。 今後とも、各地域のお客様に笑顔になっていただけるいいクルマをお届けできるよう、全社を挙げて努力を重ねていきます。そして、「クルマの未来を変えていこう」という想いのもと、安全・安心で豊かなモビリティ社会をつくることを目指して、多くの仲間とともに挑戦を加速していきます。 |
経営者による財政状態の説明
| 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1)経営成績等の状況の概要①経営成績の状況当連結会計年度の世界経済は、中国において、住宅価格の下落が継続し、消費マインドの停滞が見られた一方、米国において、個人消費を中心とした景気拡大が継続したことを受け、堅調に推移しました。このような経営環境の中、トヨタは、「もっといいクルマをつくろうよ」という軸のもと、長年の「商品と地域を軸にした経営」を通じて、フルラインアップの商品とグローバルな事業基盤を構築してきました。それからの基盤を活かして、当期も、安全・品質の徹底をはじめとする「足場固め」の取り組みを進めながら、世界各地のお客様にいいクルマをお届けする努力を重ねてきました。 そして、多様なモビリティのご提供を通じて「幸せを量産する」という当社の使命を果たすべく、Toyota Mobility Conceptのもと、モビリティカンパニーへの変革に向けた様々な技術開発や基盤づくりに取り組んできました。当連結会計年度における日本、海外を合わせた自動車の連結販売台数は、936万2千台と、前連結会計年度に比べて8万台(0.9%)の減少となりました。日本での販売台数については、199万1千台と、前連結会計年度に比べて2千台(0.1%)減少しました。海外においても、737万2千台と、前連結会計年度に比べて7万8千台(1.0%)の減少となりました。当連結会計年度の業績については、次のとおりです。 営業収益48兆367億円(前期比増減2兆9,413億円(6.5%))営業利益4兆7,955億円(前期比増減△5,573億円(△10.4%))税引前利益6兆4,145億円(前期比増減△5,504億円(△7.9%))親会社の所有者に帰属する当期利益4兆7,650億円(前期比増減△1,798億円(△3.6%)) なお、営業利益の主な増減要因は、次のとおりです。 営業面の努力1,450億円原価改善の努力±0億円 為替変動の影響5,900億円諸経費の増減・低減努力△9,900億円その他△3,023億円 事業別セグメントの業績は、次のとおりです。a.自動車事業営業収益は43兆1,998億円と、前連結会計年度に比べて1兆9,336億円(4.7%)の増収となりましたが、営業利益は3兆9,402億円と、前連結会計年度に比べて6,811億円(14.7%)の減益となりました。営業利益の減益は、諸経費の増加などによるものです。 b.金融事業営業収益は4兆4,811億円と、前連結会計年度に比べて9,969億円(28.6%)の増収となり、営業利益は6,835億円と、前連結会計年度に比べて1,134億円(19.9%)の増益となりました。営業利益の増益は、融資残高の増加および金利スワップ取引などの時価評価による評価損が減少したことなどによるものです。 c.その他の事業営業収益は1兆4,471億円と、前連結会計年度に比べて789億円(5.8%)の増収となり、営業利益は1,811億円と、前連結会計年度に比べて59億円(3.4%)の増益となりました。 所在地別の業績は、次のとおりです。a.日本営業収益は21兆8,590億円と、前連結会計年度に比べて8,383億円(4.0%)の増収となりましたが、営業利益は3兆1,511億円と、前連結会計年度に比べて3,331億円(9.6%)の減益となりました。営業利益の減益は、諸経費の増加および日野自動車㈱による認証不正問題の影響などによるものです。 b.北米営業収益は19兆3,003億円と、前連結会計年度に比べて1兆3,572億円(7.6%)の増収となりましたが、営業利益は1,088億円と、前連結会計年度に比べて3,975億円(78.5%)の減益となりました。営業利益の減益は、諸経費の増加などによるものです。 c.欧州営業収益は6兆3,134億円と、前連結会計年度に比べて6,317億円(11.1%)の増収となり、営業利益は4,155億円と、前連結会計年度に比べて274億円(7.1%)の増益となりました。営業利益の増益は、原価改善の努力などによるものです。 d.アジア営業収益は8兆9,880億円と、前連結会計年度に比べて2,573億円(2.9%)の増収となり、営業利益は8,965億円と、前連結会計年度に比べて309億円(3.6%)の増益となりました。営業利益の増益は、為替変動の影響および諸経費の減少・低減努力などによるものです。 e.その他の地域 (中南米、オセアニア、アフリカ、中東) 営業収益は4兆5,212億円と、前連結会計年度に比べて1,314億円(3.0%)の増収となり、営業利益は2,526億円と、前連結会計年度に比べて542億円(27.4%)の増益となりました。営業利益の増益は、営業面の努力などによるものです。 ②財政状態の状況 当連結会計年度末における財政状態については、次のとおりです。 資産合計は93兆6,013億円と、前連結会計年度末に比べて3兆4,870億円 (3.9%)の増加となりました。負債合計は56兆7,224億円と、前連結会計年度末に比べて1兆8,474億円 (3.4%)の増加となりました。資本合計は36兆8,789億円と、前連結会計年度末に比べて1兆6,395億円 (4.7%)の増加となりました。 ③キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は8兆9,824億円と、前連結会計年度末に比べて4,296億円(4.6%)の減少となりました。 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前連結会計年度に対するキャッシュ・フローの増減は、次のとおりです。 営業活動によるキャッシュ・フロー当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、3兆6,969億円の資金の増加となり、前連結会計年度が4兆2,063億円の増加であったことに比べて、5,094億円の減少となりました。 投資活動によるキャッシュ・フロー当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、4兆1,897億円の資金の減少となり、前連結会計年度が4兆9,987億円の減少であったことに比べて、8,090億円の減少幅の縮小となりました。 財務活動によるキャッシュ・フロー当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、1,972億円の資金の増加となり、前連結会計年度が2兆4,975億円の増加であったことに比べて、2兆3,003億円の減少となりました。 ④生産、受注及び販売の実績a.生産実績当連結会計年度における生産実績を事業別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 事業別セグメントの名称当連結会計年度(2025年3月31日に終了した1年間)前期比(%)自動車事業日本4,000,448台△1.0北米1,957,568 △0.9欧州810,741 △4.1アジア1,789,573 △4.6その他490,733 △6.2計9,049,063 △2.3 (注)1「自動車事業」における生産実績は、車両(新車)生産台数を示しています。 2「自動車事業」における「その他」は、中南米、アフリカからなります。 b.受注実績当社および連結製造子会社は、国内販売店、海外販売店等からの受注状況、最近の販売実績および販売見込等の情報を基礎として、見込生産を行っています。 c.販売実績当連結会計年度における販売実績を事業別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 事業別セグメントの名称当連結会計年度(2025年3月31日に終了した1年間)前期比(%)数量金額(百万円)数量金額自動車事業車両9,362,410台36,892,232△0.9+4.7生産用部品- 1,606,173-+0.6部品- 3,423,389-+8.1その他- 1,074,505-+0.6計― 42,996,299―+4.7金融事業―――――――- 4,437,827-+28.7その他の事業―――――――- 602,578-+6.2合計― 48,036,704―+6.5 (注)1主要な相手先別の販売実績については、当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため、主要な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合の記載を省略しています。 2「自動車事業」における「車両」の数量は、車両(新車)販売台数を示しています。 3金額は外部顧客への営業収益を示しています。 前述の当連結会計年度における「自動車事業」の販売数量を、仕向先別に示すと、次のとおりです。 事業別セグメントの名称当連結会計年度(2025年3月31日に終了した1年間)前期比(%)自動車事業日本1,990,846台△0.1北米2,702,759 △4.0欧州1,171,942 △1.6アジア1,838,050 +1.9その他1,658,813 +1.3計9,362,410 △0.9 (注)1上記仕向先別販売数量は、車両(新車)販売台数を示しています。 2「自動車事業」における「その他」は、中南米、オセアニア、アフリカ、中東ほかからなります。 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容本項においては、将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は有価証券報告書提出日(2025年6月18日)現在において判断したものです。 ①概観トヨタの事業セグメントは、自動車事業、金融事業およびその他の事業で構成されています。自動車事業は最も重要な事業セグメントで、当連結会計年度においてトヨタの営業収益合計(セグメント間の営業収益控除前)の88%を占めています。当連結会計年度における車両販売台数ベースによるトヨタの主要な市場は、日本(21.3%)、北米(28.9%)、欧州(12.5%)およびアジア(19.6%)となっています。 a.自動車市場環境世界の自動車市場は、非常に競争が激しく、また予測が困難な状況にあります。さらに、自動車業界の需要は、社会、政治および経済の状況、新車および新技術の導入ならびにお客様が自動車を購入または利用される際に負担いただく費用といった様々な要素の影響を受けます。これらの要素により、各市場および各タイプの自動車に対するお客様の需要は、大きく変化します。当連結会計年度の世界経済は、中国において、住宅価格の下落が継続し、消費マインドの停滞が見られたものの、米国において、個人消費を中心とした景気拡大が継続したことを受け、堅調に推移しました。 次の表は、過去2連結会計年度における各仕向地域別の連結販売台数を示しています。 千台 3月31日に終了した1年間 2024年 2025年日本1,993 1,991 北米2,816 2,703 欧州1,192 1,172 アジア1,804 1,838 その他1,638 1,659 海外計7,450 7,372 合計9,443 9,362 (注)「その他」は、中南米、オセアニア、アフリカ、中東ほかからなります。 トヨタの日本における当連結会計年度の連結販売台数は、市場が前連結会計年度を上回るものの、減少しました。トヨタの海外における連結販売台数は、中国を除くアジアや中近東などの地域で販売台数が増加したものの、北米で販売台数が減少したことにより、全体としては減少となりました。 各市場における全車両販売台数に占めるトヨタのシェアは、製品の品質、安全性、信頼性、価格、デザイン、性能、経済性および実用性についての他社との比較により左右されます。また、時機を得た新車の導入やモデルチェンジの実施も、お客様のニーズを満たす重要な要因です。変化し続けるお客様の嗜好を満たす能力も、売上および利益に大きな影響をもたらします。 自動車事業の収益性は様々な要因により左右されます。これらには次のような要因が含まれます。 車両販売台数 販売された車両モデルとオプションの組み合わせ 部品・サービス売上 価格割引およびその他のインセンティブのレベルならびにマーケティング費用 顧客からの製品保証に関する請求およびその他の顧客満足のための修理等にかかる費用 研究開発費等の固定費 原材料価格 コストの管理能力 生産資源の効率的な利用 特定の仕入先への部品供給の依存による生産への影響 気候変動による物理的リスクや低炭素経済への移行リスクを含む、気候変動リスク 自然災害および感染症の発生・蔓延や社会インフラの障害による市場・販売・生産への影響 日本円およびトヨタが事業を行っている地域におけるその他通貨の為替相場の変動 法律、規制、政策の変更およびその他の政府による措置も自動車事業の収益性に著しい影響を及ぼすことがあります。これらの法律、規制および政策には、車両の製造コストを大幅に増加させる環境問題、車両の安全性、燃費および排ガスに影響を及ぼすものが含まれます。 多くの国の政府が、現地調達率を規定し、関税およびその他の貿易障壁を課し、あるいは自動車メーカーの事業を制限したり本国への利益の移転を困難にするような価格管理あるいは為替管理を行っています。このような法律、規制、政策その他の行政措置における変更は、製品の生産、ライセンス、流通もしくは販売、原価、あるいは適用される税率に影響を及ぼすことがあります。トヨタは、トヨタ車の安全性について潜在的問題がある場合に適宜リコール等の市場処置(セーフティ・キャンペーンを含む)を発表しています。前述のリコール等の市場処置をめぐり、トヨタに対する申し立ておよび訴訟が提起されています。これらの申し立ておよび訴訟に関しては、連結財務諸表注記24ならびに30を参照ください。 世界の自動車産業は、グローバルな競争の時期にあり、この傾向は予見可能な将来まで続く可能性があります。また、トヨタが事業を展開する競争的な環境は、さらに激化する様相を呈しています。トヨタは一独立企業として自動車産業で効率的に競争するための資源、戦略および技術を予見可能な将来において有していると考えています。 b.金融事業自動車金融の市場は、大変競争が激しくなっています。自動車金融の競争激化は、利益率の減少を引き起こす可能性があり、また、顧客がトヨタ車を購入する際にトヨタ以外の金融サービスを利用するようになる場合、マーケット・シェアが低下することも考えられます。 トヨタの金融サービス事業は、主として、顧客および販売店に対する融資プログラムおよびリース・プログラムの提供を行っています。トヨタは、顧客に対して資金を提供する能力は、顧客に対しての重要な付加価値サービスであると考え、金融子会社のネットワークを各国へ展開しています。 小売融資およびリースにおけるトヨタの主な競争相手には、商業銀行、消費者信用組合、その他のファイナンス会社が含まれます。一方、卸売融資における主な競争相手には、商業銀行および自動車メーカー系のファイナンス会社が含まれます。 トヨタの金融事業に係る債権は、主に融資残高の増加により、当連結会計年度において増加しました。また、賃貸用車両及び器具は、主に北米の金融子会社でのオペレーティング・リース件数の増加により、当連結会計年度において増加しました。 金融事業に係る債権および賃貸用車両及び器具の詳細については、連結財務諸表注記8および12を参照ください。 トヨタの金融債権は、回収可能性リスクを負っています。これは顧客もしくは販売店の支払不能や、担保価値(売却費用控除後)が債権の帳簿価額を下回った場合に発生する可能性があります。詳細については、連結財務諸表注記3および19を参照ください。 トヨタは、車両リースを継続的に提供してきました。当該リース事業によりトヨタは残存価額のリスクを負っています。これは車両リース契約の借手が、リース終了時に車両を購入するオプションを行使しない場合に発生する可能性があります。詳細については、連結財務諸表注記3(8)を参照ください。 トヨタは、主に固定金利借入債務を機能通貨建ての変動金利借入債務へ転換するために、金利スワップおよび金利通貨スワップ契約を結んでいます。特定のデリバティブ金融商品は、経済的企業行動の見地からは金利リスクをヘッジするために契約されていますが、トヨタの連結財政状態計算書における特定の資産および負債をヘッジするものとしては指定されていないため、それらの指定されなかったデリバティブから生じる未実現評価損益は、その期間の損益として計上されます。詳細については、連結財務諸表注記20および21を参照ください。 資金調達コストの変動は、金融事業の収益性に影響を及ぼす可能性があります。資金調達コストは、数多くの要因の影響を受けますが、その中にはトヨタがコントロールできないものもあります。これには、全般的な景気、金利およびトヨタの財務力などが含まれます。当連結会計年度の資金調達コストは主に市場金利の上昇により増加しました。 トヨタは、2001年4月に日本でクレジットカード事業を立上げました。カード会員数は、2025年3月31日現在16.0百万人と、2024年3月31日から0.12百万人の減少となりました。カード債権は、2025年3月31日現在5,745億円と、2024年3月31日から157億円の増加となりました。 c.その他の事業トヨタのその他の事業には、情報通信事業等が含まれます。 トヨタは、その他の事業は連結業績に大きな影響を及ぼすものではないと考えています。 d.為替の変動トヨタは、為替変動による影響を受けやすいといえます。トヨタは日本円の他に主に米ドルおよびユーロの価格変動の影響を受けており、また、米ドルやユーロに加え、豪ドル、加ドルおよび英国ポンドなどについても影響を受けることがあります。日本円で表示されたトヨタの連結財務諸表は、換算リスクおよび取引リスクによる為替変動の影響を受けています。 換算リスクとは、特定期間もしくは特定日の財務諸表が、事業を展開する国々の通貨の日本円に対する為替の変動による影響を受けるリスクです。たとえ日本円に対する通貨の変動が大きく、前連結会計年度との比較において、また地域ごとの比較においてかなりの影響を及ぼすとしても、換算リスクは報告上の考慮事項に過ぎず、その基礎となる業績を左右するものではありません。トヨタは換算リスクに対してヘッジを行っていません。 取引リスクとは、収益と費用および資産と負債の通貨が異なることによるリスクです。取引リスクは主にトヨタの日本製車両の海外売上に関係しています。 トヨタは、生産施設が世界中に所在しているため、取引リスクは大幅に軽減されていると考えています。グローバル化戦略の一環として、車両販売を行う主要市場において生産施設を建設することにより、生産を現地化してきました。前連結会計年度および当連結会計年度において、トヨタの海外における車両販売台数のそれぞれ75.9%および73.5%が海外で生産されています。北米では前連結会計年度および当連結会計年度の車両販売台数のそれぞれ75.9%および76.0%が現地で生産されています。欧州では前連結会計年度および当連結会計年度の車両販売台数のそれぞれ73.1%および69.6%が現地で生産されています。アジアでは前連結会計年度および当連結会計年度の車両販売台数のそれぞれ97.4%および94.6%が現地で生産されています。生産の現地化により、トヨタは生産過程に使用される供給品および原材料の多くを現地調達することができ、現地での収益と費用の通貨のマッチングをはかることが可能です。 トヨタは、取引リスクの一部に対処するために為替の取引およびヘッジを行っています。これにより為替変動による影響は軽減されますが、すべて排除されるまでには至っておらず、年によってその影響が大きい場合もあり得ます。為替変動リスクをヘッジするためにトヨタで利用されるデリバティブ金融商品に関する追加的な情報については、連結財務諸表注記20および21を参照ください。 一般的に、円安は営業収益、営業利益および親会社の所有者に帰属する当期利益に好影響を及ぼし、円高は悪影響を及ぼします。日本円の米ドルに対する期中平均相場は、前会計年度に比べて円安に推移しました。また、 日本円の米ドルに対する決算日の為替相場は、前会計年度末に比べて円高となりました。日本円のユーロに対する期中平均相場は、前会計年度に比べて円安に推移しました。また、 日本円のユーロに対する決算日の為替相場は、前会計年度末に比べて円高となりました。詳細については、連結財務諸表注記19を参照ください。 e.セグメンテーショントヨタの最も重要な事業セグメントは、自動車事業セグメントです。トヨタは、世界の自動車市場においてグローバル・コンペティターとして自動車事業を展開しています。マネジメントは世界全体の自動車事業を一つの事業セグメントとして資源の配分やその実績の評価を行っており、自動車事業セグメント内で資源を配分するために、販売台数、生産台数、マーケット・シェア、車両モデルの計画および工場のコストといった財務およびそれ以外に関するデータの評価を行っています。トヨタは国内・海外または部品等のような自動車事業の一分野を個別のセグメントとして管理していません。 ②地域別内訳次の表は、過去2連結会計年度のトヨタの地域別外部顧客向け営業収益を示しており、当社または連結子会社の所在国の位置を基礎として集計しています。 金額:百万円 3月31日に終了した1年間 2024年 2025年日本10,193,556 10,719,120 北米17,624,268 18,930,253 欧州5,503,738 6,110,052 アジア7,604,269 7,903,360 その他4,169,494 4,373,919 (注)「その他」 は、中南米、オセアニア、アフリカ、中東からなります。 ③業績―当連結会計年度と前連結会計年度の比較 金額:百万円 3月31日に終了した1年間 増減および増減率 2024年 2025年 増減 増減率営業収益 日本 21,020,721 21,859,094 838,373 4.0% 北米 17,943,072 19,300,327 1,357,254 7.6% 欧州 5,681,764 6,313,489 631,725 11.1% アジア 8,730,749 8,988,062 257,314 2.9% その他 4,389,785 4,521,257 131,472 3.0% 消去又は全社 △12,670,767 △12,945,525 △274,758 - 計 45,095,325 48,036,704 2,941,380 6.5%営業利益 日本 3,484,270 3,151,123 △333,147 △9.6% 北米 506,319 108,808 △397,512 △78.5% 欧州 388,096 415,553 27,457 7.1% アジア 865,591 896,510 30,919 3.6% その他 198,345 252,626 54,281 27.4% 消去又は全社 △89,687 △29,033 60,655 - 計 5,352,934 4,795,586 △557,348 △10.4%営業利益率 11.9% 10.0% △1.9% 税引前利益 6,965,085 6,414,590 △550,495 △7.9%税引前利益率 15.4% 13.4% △2.0% 親会社の所有者に帰属する当期利益 4,944,933 4,765,086 △179,847 △3.6%親会社の所有者に帰属する当期利益率 11.0% 9.9% △1.1% (注)「その他」は、中南米、オセアニア、アフリカ、中東からなります。 a.営業収益当連結会計年度の営業収益は48兆367億円と、前連結会計年度に比べて2兆9,413億円(6.5%)の増収となりました。この増収は、主に為替変動の影響1兆7,700億円によるものです。 トヨタの事業別外部顧客向け営業収益の商品別内訳は次のとおりです。 金額:百万円 3月31日に終了した1年間 増減および増減率 2024年 2025年 増減 増減率車両 35,249,865 36,892,232 1,642,368 4.7%生産用部品 1,596,111 1,606,173 10,062 0.6%部品 3,166,586 3,423,389 256,803 8.1%その他 1,068,169 1,074,505 6,336 0.6% 自動車事業合計 41,080,731 42,996,299 1,915,568 4.7%その他の事業 567,399 602,578 35,179 6.2%商品・製品売上収益合計 41,648,130 43,598,877 1,950,747 4.7%金融事業に係る金融収益 3,447,195 4,437,827 990,632 28.7% 営業収益合計 45,095,325 48,036,704 2,941,380 6.5% 営業収益は自動車事業およびその他の事業の合計である商品・製品売上収益ならびに金融事業に係る金融収益で構成されており、当連結会計年度の商品・製品売上収益は43兆5,988億円と、前連結会計年度に比べて4.7%の増収となり、金融事業に係る金融収益は4兆4,378億円と、前連結会計年度に比べて28.7%の増収となりました。商品・製品売上収益の増収は、為替変動の影響や価格改定によるものです。金融事業に係る金融収益の増収については、「(1)経営成績等の状況の概要 ①経営成績の状況 b.金融事業」を参照ください。前連結会計年度末および当連結会計年度末の各地域における融資件数(残高)の状況は次のとおりです。 ・金融事業における融資件数残高 千件 3月31日 増減および増減率 2024年 2025年 増減 増減率日本 2,781 2,740 △41 △1.5%北米 5,589 5,647 58 1.0%欧州 1,784 1,944 160 9.0%アジア 2,133 2,245 112 5.3%その他 981 1,054 73 7.4% 合計 13,268 13,630 362 2.7% (注)「その他」は、中南米、オセアニア、アフリカからなります。 当連結会計年度の営業収益(セグメント間の営業収益控除前)は前連結会計年度に比べて、日本では4.0%、北米では7.6%、欧州では11.1%、アジアでは2.9%、その他の地域では3.0%の増収となりました。為替変動の影響1兆7,700億円を除いた場合、当連結会計年度の営業収益は前連結会計年度に比べて、日本では3.0%、北米では2.4%、欧州では5.7%、その他の地域では30.0%の増収、アジアでは1.5%の減収であったと考えられます。各地域における営業収益(セグメント間の営業収益控除前)の状況は次のとおりです。 ・日本 千台 3月31日に終了した1年間 増減および増減率 2024年 2025年 増減 増減率連結販売台数 4,014 3,932 △82 △2.0%(日本は輸出台数を含む) 金額:百万円 3月31日に終了した1年間 増減および増減率 2024年 2025年 増減 増減率営業収益 商品・製品売上収益 20,679,979 21,468,488 788,509 3.8% 金融事業に係る金融収益 340,742 390,606 49,864 14.6% 営業収益計 21,020,721 21,859,094 838,373 4.0% 日本においては、トヨタの販売台数が前連結会計年度に比べて82千台減少したものの、輸出取引に係る為替変動の影響や価格改定などにより、増収となりました。前連結会計年度および当連結会計年度における輸出台数はそれぞれ2,021千台および1,941千台となりました。 ・北米 千台 3月31日に終了した1年間 増減および増減率 2024年 2025年 増減 増減率連結販売台数 2,816 2,703 △113 △4.0% 金額:百万円 3月31日に終了した1年間 増減および増減率 2024年 2025年 増減 増減率営業収益 商品・製品売上収益 15,705,804 16,606,446 900,642 5.7% 金融事業に係る金融収益 2,237,268 2,693,881 456,613 20.4% 営業収益計 17,943,072 19,300,327 1,357,254 7.6% 北米においては、インディアナ工場の生産停止の影響はあったものの、為替変動の影響や価格改定により、増収となりました。 ・欧州 千台 3月31日に終了した1年間 増減および増減率 2024年 2025年 増減 増減率連結販売台数 1,192 1,172 △20 △1.6% 金額:百万円 3月31日に終了した1年間 増減および増減率 2024年 2025年 増減 増減率営業収益 商品・製品売上収益 5,255,395 5,577,646 322,252 6.1% 金融事業に係る金融収益 426,369 735,843 309,473 72.6% 営業収益計 5,681,764 6,313,489 631,725 11.1% 欧州においては、トヨタの販売台数が前連結会計年度に比べて20千台減少したものの、為替変動の影響や価格改定により、増収となりました。 ・アジア 千台 3月31日に終了した1年間 増減および増減率 2024年 2025年 増減 増減率連結販売台数 1,804 1,838 34 1.9% 金額:百万円 3月31日に終了した1年間 増減および増減率 2024年 2025年 増減 増減率営業収益 商品・製品売上収益 8,485,219 8,701,501 216,282 2.5% 金融事業に係る金融収益 245,529 286,561 41,031 16.7% 営業収益計 8,730,749 8,988,062 257,314 2.9% アジアにおいては、主にインドでの販売が好調だったため、トヨタの販売台数が前連結会計年度に比べて34千台増加したことや、為替変動の影響や価格改定により、増収となりました。 ・その他の地域 千台 3月31日に終了した1年間 増減および増減率 2024年 2025年 増減 増減率連結販売台数 1,638 1,659 21 1.3% 金額:百万円 3月31日に終了した1年間 増減および増減率 2024年 2025年 増減 増減率営業収益 商品・製品売上収益 4,037,260 4,023,077 △14,183 △0.4% 金融事業に係る金融収益 352,525 498,180 145,655 41.3% 営業収益計 4,389,785 4,521,257 131,472 3.0% その他の地域においては、主に中東での販売が好調だったため、トヨタの販売台数が前連結会計年度に比べて21千台増加したことや、融資残高の増加や為替変動の影響により、増収となりました。 b.営業費用 金額:百万円 3月31日に終了した1年間 増減および増減率 2024年 2025年 増減 増減率営業費用 売上原価 33,600,612 35,510,157 1,909,545 5.7% 金融事業に係る金融費用 2,126,395 2,948,509 822,114 38.7% 販売費及び一般管理費 4,015,383 4,782,452 767,069 19.1% 営業費用合計 39,742,390 43,241,118 3,498,728 8.8% 金額:百万円 営業費用の対前期比増減車両販売台数および販売構成の変化による影響30,000為替変動の影響1,180,000金融事業に係る金融費用の増加680,000原価改善の努力±0諸経費の増減・低減努力990,000その他618,728 合計3,498,728 当連結会計年度における営業費用は43兆2,411億円と、前連結会計年度に比べて3兆4,987億円(8.8%)の増加となりました。 ・原価改善の努力当連結会計年度は、±0億円の営業費用の増減となりました。この増減には、仕入先と一体となった原価改善活動に引き続き精力的に取り組んだ結果、VE(Value Engineering)活動を中心とした設計面での原価改善など2,400億円および工場・物流部門などにおける原価改善450億円が含まれますが、仕入先基盤強化および資材高騰の影響2,850億円の営業費用の増加により相殺されています。 原価改善の努力は、継続的に実施されているVE・VA(Value Analysis)活動、部品の種類の絞込みにつながる部品共通化、ならびに車両生産コストの低減を目的としたその他の製造活動に関連しています。なお、資材高騰の影響には、鉄鋼、貴金属、非鉄金属(アルミ等)、樹脂関連部品などの資材・部品価格の変動による影響が含まれています。 ・売上原価当連結会計年度における売上原価は35兆5,101億円と、前連結会計年度に比べて1兆9,095億円(5.7%)の増加となりました。この増加は、主に為替変動の影響9,050億円、品質関連費用2,750億円および労務費1,700億円の増加によるものです。 ・金融事業に係る金融費用当連結会計年度における金融事業に係る金融費用は2兆9,485億円と、前連結会計年度に比べて8,221億円(38.7%)の増加となりました。この増加は、主に市場金利の上昇等による資金調達コストの増加によるものです。 ・販売費及び一般管理費当連結会計年度の販売費及び一般管理費は4兆7,824億円と、前連結会計年度に比べて7,670億円(19.1%)の増加となりました。この増加は、主に経費2,350億円の増加および日野自動車㈱による認証不正問題の影響1,750億円の増加によるものです。 c.営業利益 金額:百万円 営業利益の対前期比増減営業面の努力145,000原価改善の努力±0 為替変動の影響590,000諸経費の増減・低減努力△990,000その他△302,348 合計△557,348 当連結会計年度における営業利益は4兆7,955億円と、前連結会計年度に比べて5,573億円(10.4%)の減益となりました。この減益は、諸経費の増減・低減努力9,900億円およびその他3,023億円によるものですが、為替変動の影響5,900億円および営業面の努力1,450億円により一部相殺されています。 上記の諸経費の増減・低減努力は、経費ほか6,200億円、労務費2,350億円および研究開発費1,300億円の増加によるものです。その他の減益要因は、日野自動車㈱による認証不正問題の影響2,805億円などを含んでいます。 また、為替変動の影響の増益要因は、主に輸出入等の外貨取引による影響4,150億円によるものです。営業面の努力は、バリューチェーン収益の拡大1,900億円などを含んでいます。 当連結会計年度における営業利益(セグメント間の利益控除前)は前連結会計年度に比べて、北米では3,975億円(78.5%)、日本では3,331億円(9.6%)の減益、その他の地域では542億円(27.4%)、アジアでは309億円(3.6%)、欧州では274億円(7.1%)の増益となりました。各地域における営業利益の状況は次のとおりです。 ・日本 金額:百万円 営業利益の対前期比増減営業面の努力55,000原価改善の努力△160,000為替変動の影響645,000諸経費の増減・低減努力△525,000その他△348,147 合計△333,147 ・北米 金額:百万円 営業利益の対前期比増減営業面の努力5,000原価改善の努力125,000為替変動の影響△55,000諸経費の増減・低減努力△430,000その他△42,512 合計△397,512 ・欧州 金額:百万円 営業利益の対前期比増減販売面での影響△55,000原価改善の努力60,000為替変動の影響10,000諸経費の増減・低減努力△5,000その他17,457 合計27,457 ・アジア 金額:百万円 営業利益の対前期比増減販売面での影響△15,000原価改善の努力10,000為替変動の影響15,000諸経費の増減・低減努力10,000その他10,919 合計30,919 ・その他 金額:百万円 営業利益の対前期比増減営業面の努力80,000原価改善の努力△35,000為替変動の影響△25,000諸経費の増減・低減努力△25,000その他59,281 合計54,281 d.その他の収益・費用当連結会計年度における持分法による投資損益は5,912億円と、前連結会計年度に比べて1,719億円(22.5%)の減益となりました。この減益は、主に持分法適用会社の親会社の所有者に帰属する当期利益の減益によるものです。 当連結会計年度におけるその他の金融収益は5,567億円と、前連結会計年度に比べて1,905億円(25.5%)の減少となりました。この減少は、主に有価証券売却益および受取利息の減少によるものです。 当連結会計年度におけるその他の金融費用は1,907億円と、前連結会計年度に比べて870億円(83.9%)の増加となりました。この増加は、主に有価証券評価損の増加によるものです。 当連結会計年度における為替差損益<純額>は7,052億円と、前連結会計年度に比べて5,177億円の増益となりました。為替差損益は、外国通貨建て取引によって生じた外貨建ての資産および負債を、取引時の為替相場で換算した価額と、先物為替契約を利用して行う決済を含め、同会計年度における決済金額または決算時の為替相場で換算した価額との差額を示すものです。為替差損益<純額>の増益5,177億円は、主に当連結会計年度において、一部の連結子会社の支配の喪失から生じた利得を、連結包括利益計算書の「在外営業活動体の為替換算差額」から連結損益計算書の「為替差損益<純額>」に振り替えたことによるものです。 当連結会計年度におけるその他<純額>は434億円の損失と、前連結会計年度に比べて614億円の減益となりました。 e.法人所得税費用当連結会計年度における法人所得税費用は1兆6,248億円と、前連結会計年度に比べて2,688億円(14.2%)の減少となりました。これは、主に税引前利益の減少などの影響によるもので、当連結会計年度における平均実際負担税率は25.3%となりました。 f.非支配持分に帰属する当期利益当連結会計年度における非支配持分に帰属する当期利益は246億円と、前連結会計年度に比べて1,018億円(80.5%)の減益となりました。この減益は、主に連結子会社の当期利益の減益によるものです。 g.親会社の所有者に帰属する当期利益当連結会計年度の親会社の所有者に帰属する当期利益は4兆7,650億円と、前連結会計年度に比べて1,798億円(3.6%)の減益となりました。 h.その他の包括利益(税効果考慮後)当連結会計年度におけるその他の包括利益(税効果考慮後)は7,460億円の損失と、前連結会計年度に比べて2兆8,631億円利益が減少しました。これは、主に米ドルやユーロに対する為替レートの変動により、在外営業活動体の為替換算差額が前連結会計年度の1兆1,788億円の利益に対し、当連結会計年度は8,278億円の損失となったこと、および主に株価が変動したことにより、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値変動が前連結会計年度の5,697億円の利益に対し、当連結会計年度は1,332億円の利益となったことによるものです。 i.事業別セグメントの状況以下は、トヨタの事業別セグメントの状況に関する説明です。記載された数値は、セグメント間の営業収益控除前です。 金額:百万円 3月31日に終了した1年間 増減および増減率 2024年 2025年 増減 増減率自動車 営業収益 41,266,204 43,199,865 1,933,661 4.7%営業利益 4,621,475 3,940,278 △681,197 △14.7%金融 営業収益 3,484,198 4,481,180 996,982 28.6%営業利益 570,023 683,519 113,495 19.9%その他 営業収益 1,368,164 1,447,114 78,949 5.8%営業利益 175,241 181,194 5,953 3.4%消去又は全社 営業収益 △1,023,242 △1,091,455 △68,213 -営業利益 △13,805 △9,405 4,401 -合計 営業収益 45,095,325 48,036,704 2,941,380 6.5% 営業利益 5,352,934 4,795,586 △557,348 △10.4% ・自動車事業セグメント自動車事業の営業収益は、トヨタの営業収益のうち最も高い割合を占めます。当連結会計年度における自動車事業セグメントの営業収益は43兆1,998億円と、前連結会計年度に比べて1兆9,336億円(4.7%)の増収となりました。この増収は、主に為替変動の影響1兆5,900億円によるものです。 当連結会計年度における自動車事業セグメントの営業利益は3兆9,402億円と、前連結会計年度に比べて6,811億円(14.7%)の減益となりました。この営業利益の減益は、主に諸経費の増減・低減努力9,900億円によるものですが、為替変動の影響5,800億円などにより一部相殺されています。 ・金融事業セグメント当連結会計年度における金融事業セグメントの営業収益は4兆4,811億円と、前連結会計年度に比べて9,969億円(28.6%)の増収となりました。この増収は、主に融資残高の増加および為替変動の影響によるものです。当連結会計年度における金融事業セグメントの営業利益は6,835億円と、前連結会計年度に比べて1,134億円(19.9%)の増益となりました。この営業利益の増益は、主に融資残高の増加および金利スワップ取引などの時価評価による評価損が減少したことなどによるものです。 ・その他の事業セグメント当連結会計年度におけるその他の事業セグメントの営業収益は1兆4,471億円と、前連結会計年度に比べて789億円(5.8%)の増収となりました。当連結会計年度におけるその他の事業セグメントの営業利益は1,811億円と、前連結会計年度に比べて59億円(3.4%)の増益となりました。 ④流動性と資金の源泉トヨタは従来、設備投資および研究開発活動のための資金を、主に営業活動から得た現金により調達してきました。 2026年3月31日に終了する連結会計年度については、トヨタは設備投資および研究開発活動のための十分な資金を、主に手元の現金及び現金同等物、営業活動から得た現金、および社債・借入金等の資金調達で充当する予定です。トヨタはこれらの資金を、従来の設備の維持更新・新製品導入へ効率的に投資しつつ、モビリティ・カンパニーへの変革に向け、競争力強化・将来の成長に資する分野に重点を置いて投資する予定です。2024年4月1日から2025年3月31日までに行われた重要な設備投資および処分に関する情報ならびに現在進行中の重要な設備投資および処分に関する情報は、「第3 設備の状況」を参照ください。 顧客や販売店に対する融資プログラムおよびリース・プログラムで必要となる資金について、トヨタは販売金融子会社の営業活動から得た現金と社債・借入金等の資金調達によりまかなっています。トヨタは金融子会社のネットワークを通じて、世界中の現地市場で資金を調達する能力を向上させるよう努めています。 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の4兆2,063億円の資金の増加に対し、3兆6,969億円の資金の増加となり、5,094億円減少しました。この減少は、当連結会計年度(2025年3月31日に終了した12ヶ月間)における法人所得税の支払額が増加した結果、資金が1兆3,770億円減少したことなどによるものです。 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の4兆9,987億円の資金の減少に対し、4兆1,897億円の資金の減少となり、8,090億円減少幅が縮小しました。この減少幅の縮小は、主に定期預金の預入の金額が前連結会計年度と比較して、7,293億円減少したことによる影響です。 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の2兆4,975億円の資金の増加に対し、1,972億円の資金の増加となり、2兆3,003億円減少しました。この減少は、主に長期有利子負債の返済が2兆1,199億円増加したことによるものです。 当連結会計年度における資本的支出(賃貸資産を含む)は、前連結会計年度の4兆8,480億円から5兆9,912億円となり、1兆1,432億円増加しました。この増加は、主に金融事業におけるリース資産購入による資本的支出が9,317億円増加したことによるものです。 2026年3月31日に終了する連結会計年度において、賃貸および賃借資産を除く設備投資額は約2兆3,000億円となる予定です。 現金及び現金同等物は、2025年3月31日現在で8兆9,824億円でした。現金及び現金同等物の大部分は円建てまたは米ドル建てです。 トヨタは、現金及び現金同等物、定期預金、公社債および信託ファンドへの投資を総資金量と定義しており、当連結会計年度において総資金量は、21兆1,777億円となりました。 当連結会計年度における営業債権及びその他の債権は、1,097億円(2.9%)減少し、3兆6,797億円となりました。これは主に、為替変動の影響によるものです。 当連結会計年度における棚卸資産は、71億円(0.2%)減少し、4兆5,982億円となりました。 当連結会計年度における金融事業に係る債権合計は、1兆9,306億円(6.1%)増加し、33兆6,250億円となりました。これは主に、顧客や販売店に対する融資残高の増加によるものです。2025年3月31日現在における金融債権の地域別内訳は、北米53.9%、欧州15.0%、アジア11.7%、日本8.9%、その他の地域10.5%でした。 当連結会計年度におけるその他の金融資産合計は、7,258億円(4.5%)増加しました。これは主に、公社債の増加によるものです。 当連結会計年度における有形固定資産は、1兆759億円(7.5%)増加しました。これは主に、設備投資によるものです。 当連結会計年度における営業債務及びその他の債務は、2,759億円(5.3%)増加しました。これは主に、部品調達に伴う買掛金の増加によるものです。 当連結会計年度における未払法人所得税は、7,190億円(58.7%)減少しました。これは主に、税引前利益の減少に伴う法人所得税費用の減少などによるものです。 当連結会計年度における有利子負債合計は、2兆2,310億円(6.1%)増加しました。トヨタの短期借入債務は、加重平均利率2.26%の借入金と、加重平均利率3.82%のコマーシャル・ペーパーにより構成されています。当連結会計年度における短期借入債務は、前連結会計年度に比べて234億円(0.4%)減少し、5兆4,644億円となりました。トヨタの長期借入債務は、加重平均利率が1.93%から8.12%、返済期限が2025年から2048年の無担保の借入金、担保付きの借入金、無担保普通社債およびミディアム・ターム・ノート、担保付普通社債などにより構成されています。当連結会計年度の1年以内に返済予定の長期借入債務は4,280億円(4.3%)増加し、10兆2,729億円となり、返済期限が1年超の長期借入債務は1兆7,557億円(8.5%)増加し、22兆5,221億円となりました。借入債務合計の増加は、主に金融子会社における融資残高の伸びに伴う資金需要の高まりによるものです。2025年3月31日現在で、長期借入債務の約50%は米ドル建て、約14%はユーロ建て、約12%は円建て、約5%は豪ドル建て、約4%は加ドル建て、約15%はその他の通貨によるものです。トヨタは、金利スワップを利用することにより固定金利のエクスポージャーをヘッジしています。トヨタの借入必要額に重要な季節的変動はありません。 2024年3月31日現在におけるトヨタの親会社の所有者に帰属する持分合計に対する有利子負債比率は、106.8%でしたが、2025年3月31日現在では108.0%となりました。 トヨタの短期および長期借入債務は、2025年5月31日現在、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)、ムーディーズ(Moody’s)および格付投資情報センター(R&I)により、次のとおり格付けされています。なお、信用格付けは株式の購入、売却もしくは保有を推奨するものではなく、何時においても撤回もしくは修正され得ます。各格付けはその他の格付けとは個別に評価されるべきです。 S&P Moody’s R&I短期借入債務 A-1+ P-1 ―長期借入債務 A+ A1 AAA 当連結会計年度における確定給付負債(資産)の純額は、国内および海外で、それぞれ2,206億円および3,508億円と、前連結会計年度に比べて、国内は1,825億円(479.3%)増加し、海外は152億円(4.2%)の減少となりました。確定給付負債(資産)の純額は、トヨタによる将来の現金拠出または対象従業員に対するそれぞれの退職日における支払いにより解消されます。国内においては、主に株価の下落に伴う制度資産の減少により、確定給付負債(資産)の純額は増加しました。詳細については、連結財務諸表注記23を参照ください。 トヨタの財務方針は、すべてのエクスポージャーの管理体制を維持し、相手先に対する厳格な信用基準を厳守し、市場のエクスポージャーを積極的にモニターすることです。トヨタは、トヨタファイナンシャルサービス㈱に金融ビジネスを集中させ、同社を通じて金融ビジネスのグローバルな効率化を目指しています。 財務戦略の主な要素は、短期的な収益の変動に左右されることなく事業を継続し、研究開発活動、設備投資および金融事業に対して戦略的に投資できるような、安定した財務基盤を維持することです。トヨタは、現在必要とされる資金水準を十分満たす流動性を保持していると考えており、また、高い信用格付けを維持することにより、引き続き多額の資金を比較的安いコストで外部から調達することができると考えています。高い格付けを維持するためには、数多くの条件が求められ、その中にはトヨタがコントロールできないものも含まれています。これらの条件には、日本およびトヨタが事業を行うその他の主要な市場の全体的な景気などが含まれています。 トヨタは金融事業のための資金調達の一つの方法として特別目的事業体を通じた証券化プログラムを利用しています。これらの証券化取引は、トヨタが第一受益者であるものとして連結しており、当連結会計年度におけるオフバランス化される取引に重要なものはありません。 トヨタの非デリバティブ金融負債およびデリバティブ金融負債の残存契約満期期間ごとの金額に関しては、連結財務諸表注記19を参照ください。また、トヨタはその通常業務の一環として、一定の原材料、部品およびサービスの購入に関して、仕入先と長期契約を結ぶ場合があります。これらの契約は、一定数量または最低数量の購入を規定している場合があります。トヨタはかかる原材料またはサービスの安定供給を確保するためにこれらの契約を締結しています。 次の表は、2025年3月31日現在のトヨタの契約上の債務および商業上の契約債務を要約したものです。 金額:百万円 返済期限 合計 1年未満 1年以上3年未満 3年以上5年未満 5年以上契約上の債務: 短期借入債務5,464,469 5,464,469 - - - 長期借入債務33,328,410 10,365,047 12,714,587 7,634,239 2,614,537有形固定資産およびその他の資産ならびにサービスの購入に係る契約上のコミットメント(注記30)3,807,743 429,884 354,869 683,305 2,339,685合計42,600,622 16,259,400 13,069,456 8,317,544 4,954,222 商業上の契約債務: 通常の事業から生じる最大見込保証債務(注記30)2,314,927 727,105 1,101,358 410,501 75,963合計2,314,927 727,105 1,101,358 410,501 75,963 * 長期借入債務の金額は、将来の支払元本を表しています。 また、トヨタは2026年3月31日に終了する連結会計年度において、退職後給付制度に対し、国内および海外で、それぞれ33,651百万円および16,454百万円を拠出する予定です。 ⑤貸出コミットメントa.クレジットカード会員に対する貸出コミットメントトヨタは金融事業の一環としてクレジットカードを発行しています。トヨタは、クレジットカード事業の慣習に従い、カード会員に対する貸付の制度を有しています。貸出はお客様ごとに信用状態の調査を実施した結果設定した限度額の範囲内で、お客様の要求により実行されます。カード会員に対する貸付金には保証は付されませんが、貸倒損失の発生を最小にするため、また適切な貸出限度額を設定するために、トヨタは、提携関係にある金融機関からの財務情報の分析を含むリスク管理方針により与信管理を実施するとともに、定期的に貸出限度額の見直しを行っています。2025年3月31日現在のカード会員に対する貸出未実行残高は1,577億円です。 b.販売店に対する貸出コミットメントトヨタは金融事業の一環として販売店に対する融資の制度を有しています。貸付は買収、設備の改装、不動産の購入、運転資金の確保のために行われます。これらの貸付金については、通常担保権が設定されており、販売店の不動産、車両在庫、その他販売店の資産等、場合に応じて適切と考えられる物件に対して設定しています。さらに慎重な対応が必要な場合には販売店が指名した個人による保証または販売店グループが指名した法人による保証を付しています。貸付金は通常担保または保証が付されていますが、担保または保証の価値がトヨタのエクスポージャーを十分に補うことができていない可能性があります。トヨタは融資制度契約を締結することによって生じるリスクに従って融資制度を評価しています。トヨタの金融事業は、販売店グループと呼ばれる複数のフランチャイズ系列に対しても融資を行っており、しばしば貸出組合に参加することでも融資を行っています。こうした融資は、融資先の卸売車両の購入、買収、設備の改装、不動産の購入、運転資金の確保等を目的とするものです。2025年3月31日現在の販売店に対する貸出未実行残高は3兆347億円です。 ⑥保証詳細については、連結財務諸表注記30を参照ください。 ⑦関連当事者との取引詳細については、連結財務諸表注記32を参照ください。 ⑧会計基準の選択に関する基本的な考え方当社は、資本市場における財務情報の国際的な比較可能性の向上等を目的として、2021年3月期第1四半期よりIFRSを任意適用しています。 ⑨重要な会計上の見積りIFRSに準拠した連結財務諸表を作成するにあたり、会計方針の適用、資産・負債およびトヨタの連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の見積りおよび仮定に関する情報は、次のとおりです。 ・品質保証に係る負債 ・金融事業に係る金融損失引当金 ・非金融資産の減損 ・退職給付に係る負債 ・公正価値測定 ・繰延税金資産の回収可能性 詳細については、連結財務諸表注記4を参照ください。 |
※本記事は「トヨタ自動車株式会社」の令和7年年3期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
※4. この企業は、連結財務諸表ベースで見ると有利子負債がゼロ。つまり、グループ全体としては外部借入に頼らず資金運営していることがうかがえます。なお、個別財務諸表では親会社に借入が存在しているため、連結上のゼロはグループ内での相殺消去の影響とも考えられます。
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

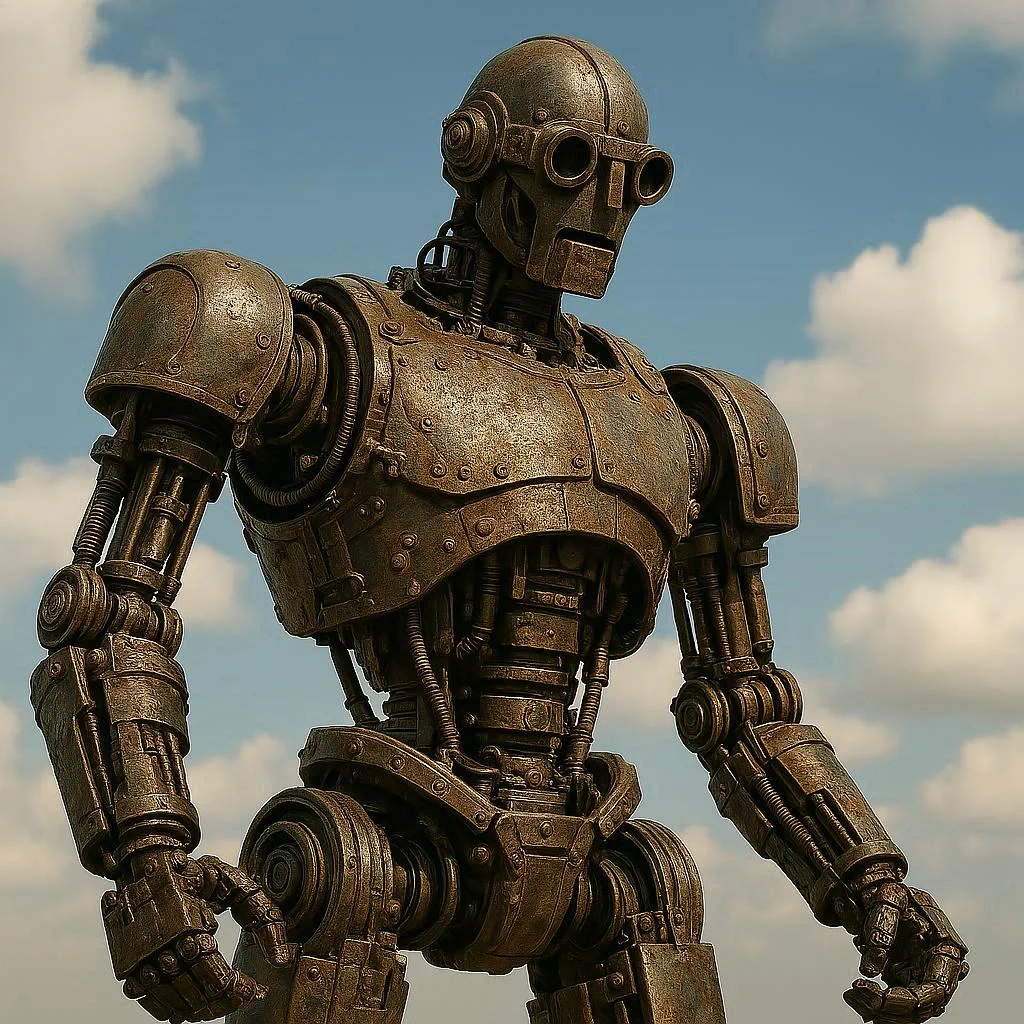

コメント