| 会社名 | スズキ株式会社 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 従業員数 | 連74077名 単17414名 |
| 従業員平均年齢 | 41歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 18年 |
| 平均年収 | 7849435円 |
| 1株当たりの純資産(連結) | 1404.09円 |
| 1株当たりの純利益(連結) | 215.66円 |
| 決算時期 | 3月 |
| 配当金 | 41円 |
| 配当性向 | 34.2% |
| 株価収益率(PER) | 8.9倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(連結) | 15% |
| 営業活動によるCF | 6697億円 |
| 投資活動によるCF | ▲4756億円 |
| 財務活動によるCF | ▲1859億円 |
| 研究開発費※1 | 4億円 |
| 設備投資額※1 | 9.61億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 368000円 |
| 株主資本比率※2 | 45.9% |
| 有利子負債残高(連結)※3※4 | 0円 |
経営方針
| 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末時点において当社グループが判断したものです。また、当該事項については、取締役会等の社内会議体で合理的な根拠に基づき適切な検討を行ったものです。これらの記載は実際の結果と異なる可能性があり、その達成を保証するものではありません。 2030年度に向けた主な取組み<連結売上収益目標>2030年度の経営目標を売上収益8兆円、営業利益8,000億円、営業利益率10%、ROE13%としました。BEV比率の増加や労務費の上昇、原材料費が高騰する中でもしっかりと収益体質を改善させ、2030年代前半にはROE15%を達成することを見据えながら、必要な投資を進めていきます。 <各事業>○四輪事業各国の規制に対応すべく、適切なBEVモデルを投入していきます。それぞれの国、地域のエネルギー事情等に応じて、お客様がご自身に合った商品を選んでいただけるよう、CNG(CBG)車・エタノール混合燃料対応車(FFV、E20)などの商品も投入していきます。 (注)CNG:圧縮天然ガス、CBG:圧縮バイオメタンガス、FFV:フレックス燃料車、E20:エタノール20%混合 日本スズキにとって成長市場と捉えています。登録車販売を伸ばし、収益を高めていきます。お客様と社会に必要とされる会社となることを目指し、日常の足として軽自動車をお使いのお客様の生活を守っていきます。商品に込めた想い、こだわりを丁寧に発信し、お客様が感じるスズキの価値を向上させ、商品価値に見合う、適正な価格で商品を販売していきます。また、お客様に寄り添った営業活動により、新たなお客様の獲得、代替の増加、サービス売上の増加により利益を増やし、お客様とともに成長していきます。 インド今後も成長が続くスズキにとっての最重要市場です。自動車のリーディングカンパニーとしてシェア50%、BEVの生産・販売・輸出1位を目指します。SUVやMPVセグメントでの商品力を強化しつつ、中間層のお客様が初めて購入する車として、エントリーモデルの開発にも注力します。インド各地の事情に合わせて、BEV・HEV・CNG(CBG)車・FFVなど選択肢を示していきます。そのためにも、お客様との物理的な距離が近いマルチ・スズキの商品企画・開発能力を向上させ、インドのお客様の嗜好に合った商品をタイムリーに提供する体制にしていきます。販売については、NEXA店を上級志向、ARENA店を幅広いお客様向けとして、役割を明確化し2つのチャネルをさらに磨きあげていきます。 欧州要求性能が極めて高く、先進的な環境・安全規制が導入される市場です。欧州のお客様が必要とする商品を供給することで、スズキの技術・製品を磨いていきます。インド生産のモデルも活用し、必要な商品ラインアップを揃え、販売・サービス網を維持していきます。また、デジタルを活用した営業活動強化も進めていきます。 中東・アフリカ大きな成長可能性を秘めた市場です。インドと地理的な距離が近く、道路事情などお客様のニーズがインドと似ているため、インド製モデルを活用して開拓し、販売・利益を増やすことを目指します。スズキの得意とする小型車の需要が見込める国で、お客様満足度の向上を図りながら、販売増を目指します。 アジア(インドを除く)ASEAN市場については、インドネシアを中心に事業を再構築し販売台数を伸ばすことを目指します。インドネシアの生産・販売のボリュームを増やし、競争力の高い商品をインドネシアからASEAN各国に供給できる体制を構築していきます。45%のシェアを持つパキスタンでは、さらなる事業規模拡大を進めることに取り組みます。パキスタンでは、日本の軽自動車が受け入れられていますので、軽自動車のグローバル化の一拠点として、商品ラインアップを充実させ、スズキの強みである販売網も駆使して、拡販していきます。 中南米・大洋州中南米では、小型SUVのさらなる拡販をしていきます。インド製商品を拡充し、より市場における競争力を高めていきます。大洋州では、低燃費商品の拡充をしていきます。各国で進む燃費規制の動向を踏まえ、スズキらしい“小型で低燃費”の機種を売り込むことで、スズキの存在感を高めていきます。 ○二輪事業妥協しない商品づくりを通じてお客様が求める「価値ある製品」を提供し、作り手の想いを伝え、お客様の信頼獲得を推進していきます。欧米を中心とした趣味嗜好で使用する商品とインド等の市場で生活の足、業務に使用する商品に層別し、商品づくりや販売・サービス活動を強化していきます。 ○マリン事業世界中のお客様に耐久性と信頼性に優れた製品を提供し、お客様にとって、水上の「楽しむ」と「働く」を支える頼れるパートナーとなれるよう取り組みます。「楽しむ」お客様と、「働く」お客様とで層別し、商品づくりや販売・サービス活動を行います。マイクロプラスチック回収装置などマリンのお客様の大切な場所である水辺の環境を整備する活動にも力を入れていきます。技術について、カーボンニュートラルに取り組むのはもちろんのこと、船体の統合制御、操作支援の技術開発、商品化も進め、お客様が求める、より高い価値を提供していきます。 ○新事業既存事業の強みを活かし、サービスモビリティやエネルギー分野で新規事業を立ち上げ、事業規模の拡大と収益化を目指します。スズキに足りない技術やノウハウは、他社との積極的な協業により実現していきます。スズキの強みを生かし、インドの社会課題を解決することでともに成長する取組みであるバイオガス事業では、牛糞からバイオメタン、CBGを精製し、エネルギーが乏しいルーラルエリアの方の生活・炊事に、また、CNG(CBG)車の燃料として使っていただき、移動の自由を提供する取組みを推進していきます。 <技術戦略>製造からリサイクルまで「エネルギーを極少化させる技術」を実現し、世界中の人々に移動する喜びをご提供しつつ、カーボンニュートラルな世界を目指します。上記実現のため、全ての基本として全体を支える「軽くて安全な車体」、お客様の用途に合わせた適所適材な「バッテリーリーンなBEVとHEV」、「効率良いICEとCNF技術の組み合わせ」、アフォーダブルな仕組みでクルマの価値を創造する「SDVライト」、サーキュラーエコノミーに向けた「リサイクルしやすい易分解設計」、これらを5つの柱として技術開発を進めます。(注)ICE:ガソリン等を燃料としたエンジン(内燃機関) CNF技術:バイオエタノールやCBGなどカーボンニュートラル燃料を少量で上手く燃やす技術 SDV:ソフトウエアの追加・更新により販売後にも機能を拡張・変更できる自動車 <カーボンニュートラル>事業活動からのCO2排出[Scope1,2]について、グローバル(インド含む)で2050年までのカーボンニュートラル達成を目標に取り組みます。パリ協定の1.5℃水準に沿った目標に移行し、中間目標として、総量で2030年度に2022年度比42%削減を目指します。 <研究開発・設備投資>収益性・効率性を改善させ投資資金を最大限確保し、積極的に成長投資を実行していきます。企業価値を最大化できるように、外部状況に応じて柔軟に経営資源を適所適材に振り分けていきます。成長投資は主にインドの需要拡大に応える生産能力増強とエネルギー極少化に向けた技術開発に取り組みます。具体的には、成長投資として、2030年度までに、設備投資に2兆円、研究開発費に2兆円、あわせて4兆円を計画しており、設備投資のうちインド関連で1兆2,000億円、研究開発費のうちエネルギー極少化に向けたもので1兆3,500億円を計画しています。 |
経営者による財政状態の説明
| 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。これらの記載は実際の結果とは異なる可能性があり、その達成を保証するものではありません。※当社グループは当連結会計年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)より、従来の日本基準に替えてIFRSを適用しており、前連結会計年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)の数値をIFRSに組み替えて比較分析を行っています。 (1) 経営成績当連結会計年度の業績は、売上収益は5兆8,252億円となり前期に比べ4,676億円(8.7%)増加しました。営業利益は6,429億円となり前期に比べ1,490億円(30.2%)増加しました。税引前利益は7,302億円となり前期に比べ1,385億円(23.4%)増加しました。親会社の所有者に帰属する当期利益は、4,161億円となり前期に比べ990億円(31.2%)増加しました。売上収益は販売台数の増加、価格改定、及び為替影響等により増収となりました。営業利益は、研究開発費や労務費等の固定費の増加、及び取引先基盤強化の取組みによる影響等を、増収効果や原価低減等によりカバーし、増益となりました。収益性に関して、当期の営業利益率は11.0%となり前期9.2%から改善、また、ROEは14.6%となり前期12.6%から改善し、稼ぐ力の向上に取り組んできた成果が出たと認識しています。 事業別セグメントの業績は、次のとおりです。 ① 四輪事業 売上収益は5兆3,052億円と前期に比べ4,356億円(8.9%)増加しました。営業利益は5,676億円と前期に比べ1,437億円(33.9%)増加しました。 ② 二輪事業 売上収益は3,981億円と前期に比べ331億円(9.1%)増加しました。営業利益は408億円と前期に比べ17億円(4.4%)増加しました。主にインドでの販売拡大が増収増益に寄与しました。 ③ マリン事業 売上収益は1,097億円と前期に比べ20億円(1.8%)減少しました。営業利益は306億円と前期に比べ31億円(11.4%)増加しました。 ④ その他事業 売上収益は121億円と前期に比べ9億円(7.9%)増加しました。営業利益は38億円と前期に比べ5億円(13.5%)増加しました。 生産、受注及び販売の状況は、次のとおりです。 ① 生産実績セグメントの名称当連結会計年度(千台)前年比(%)四輪事業3,296+0.9二輪事業1,530+12.6マリン事業110△1.8 ② 受注実績当社グループは主に見込み生産を行っているため、受注生産について該当事項はありません。 ③ 販売実績セグメントの名称当連結会計年度(億円)前年比(%)四輪事業53,052+8.9二輪事業3,981+9.1マリン事業1,097△1.8その他事業121+7.9合計58,252+8.7 (注) 販売実績は外部顧客への売上高を示しています。 (2) 財政状態当連結会計年度末の財政状態につきましては、資産は、5兆9,937億円(前期末比2,360億円増加)となりました。負債は、2兆3,056億円(前期末比676億円減少)となりました。借入金につきましては、世界情勢の不安定さを踏まえ、現在の借入水準を当面維持していく考えです。資本は、3兆6,881億円(前期末比3,036億円増加)となりました。その内、親会社の所有者に帰属する持分は、主に当期利益の計上等により利益剰余金が3,779億円増加したこと、及び為替換算調整勘定の減少等によりその他の資本の構成要素が1,182億円減少したことに伴い、2兆9,707億円(前期末比2,509億円増加)となりました。これらの結果、親会社所有者帰属持分比率は49.6%(前期末:47.2%)となりました。 (3) キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報① キャッシュフローの状況当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は8,427億円となり、前連結会計年度末に比べ27億円増加しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 (ⅰ)営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動による資金の増加は、6,698億円(前年同期は5,018億円の増加)となりました。主な要因は、税引前利益7,302億円等です。 (ⅱ)投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動による資金の減少は、4,756億円(前年同期は4,774億円の減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出3,447億円等です。 (ⅲ)財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動による資金の減少は、1,860億円(前年同期は929億円の減少)となりました。主な要因は、親会社の所有者への配当金の支払額709億円、及び非支配持分への配当金の支払額299億円等です。 ② 資本の財源及び資金の流動性当社グループは、2025年2月に発表した中期経営計画のなかで、2026年3月期から2031年3月期の6年間のキャピタル・アロケーションを示しました(下図参照)。資金使途に関しては、主に設備投資と研究開発費の成長投資に計4兆円を配分し、中期経営計画の実現を通して企業価値を向上させていく考えです。財源に関しては、主に営業活動から得る現金により調達していく考えです。外部調達に関しては、資金調達の多様化の観点から様々な手法を検討しており、そのひとつとして社債発行枠2,000億円を設定しています。当社グループの資金の流動性管理にあたっては、急激な外部環境変化に対応できるよう、一定水準の手元流動性を確保する方針としています。また、国内及び欧州においてはキャッシュプールシステムを通してグループ内で機動的に対応できる体制を構築しています。加えて、当社は取引銀行6行と総額3,000億円のコミットメントライン契約を締結しています。なお、当連結会計年度末においてコミットメントラインは未使用となっています。 当社の当連結会計年度末の現金及び現金同等物は5,743億円(単独ベース)で、これは月商2.6ヶ月に相当し十分な流動性を確保しています。流動性向上の取組みのひとつとして、子会社から受け取る配当金について一定のルールにて本社への還元を図っており、当連結会計年度では464億円のキャッシュインがありました。当社グループの当連結会計年度末の現金及び現金同等物は8,427億円(連結ベース)です。更にこれとは別に、インドの子会社マルチ・スズキ・インディア社では営業活動から得た現金を主にオープンエンドの投資信託にて運用しており、その残高は約1兆円規模であり、十分な流動性を確保しています。今後の主な設備投資としてインドでの四輪車の生産能力増強投資がありますが、マルチ・スズキ・インディア社の資金にて実施していく考えです。また、当社グループは国内格付機関である格付投資情報センターから格付を取得しており、当報告書提出日現在における格付は「シングルAプラス(安定的)」となっています。2024年9月実施の格付にて、前回の格付「シングルA(ポジティブ)」から1ランクアップとなりました。 (ご参考)中期経営計画スライド資料 37ページ「キャピタル・アロケーション」 (4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定当社グループの連結財務諸表は、IFRSに準拠して作成しています。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断していますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものの内容及び金額は「第5 経理の状況 連結財務諸表注記 4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載しています。 (5) 並行開示情報「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(第3編から第6編までを除く。以下、「日本基準」という。)により作成した要約連結財務諸表、要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更は、次のとおりです。なお、日本基準により作成した要約連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けていません。また、日本基準により作成した要約連結財務諸表については、百万円未満を切り捨てして表示しています。 ① 要約連結貸借対照表 (単位:百万円) 前連結会計年度(2024年3月31日)当連結会計年度(2025年3月31日)資産の部 流動資産2,437,6382,557,593 固定資産 有形固定資産1,329,8401,461,109 無形固定資産7,80412,936 投資その他の資産1,610,3341,554,042 固定資産合計2,947,9803,028,089 資産合計5,385,6185,585,683負債の部 流動負債1,741,0461,560,319 固定負債506,174618,216 負債合計2,247,2202,178,536純資産の部 株主資本2,198,2452,508,657 その他の包括利益累計額292,768200,221 新株予約権4141 非支配株主持分647,342698,226 純資産合計3,138,3973,407,147負債純資産合計5,385,6185,585,683 ② 要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書要約連結損益計算書 (単位:百万円) 前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)売上高5,374,2555,843,087売上原価3,959,8184,253,829売上総利益1,414,4371,589,257販売費及び一般管理費948,874995,967営業利益465,563593,289営業外収益58,11165,574営業外費用35,14936,775経常利益488,525622,089特別利益3,48644,896特別損失2,7342,186税金等調整前当期純利益489,276664,799法人税等合計145,049190,592当期純利益344,227474,206非支配株主に帰属する当期純利益76,50984,040親会社株主に帰属する当期純利益267,717390,166 要約連結包括利益計算書 (単位:百万円) 前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)当期純利益344,227474,206 その他の包括利益合計377,835△92,281包括利益722,062381,925(内訳) 親会社株主に係る包括利益552,832297,619 非支配株主に係る包括利益169,23084,306 ③ 要約連結株主資本等変動計算書前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) (単位:百万円) 株主資本その他の包括利益累計額新株予約権非支配株主持分純資産合計当期首残高2,070,3637,65341430,5612,508,620当期変動額127,881285,114-216,781629,777当期末残高2,198,245292,76841647,3423,138,397 当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) (単位:百万円) 株主資本その他の包括利益累計額新株予約権非支配株主持分純資産合計当期首残高2,198,245292,76841647,3423,138,397当期変動額310,412△92,546-50,883268,749当期末残高2,508,657200,22141698,2263,407,147 ④ 要約連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円) 前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)営業活動によるキャッシュ・フロー446,045596,949投資活動によるキャッシュ・フロー△433,855△419,630財務活動によるキャッシュ・フロー△81,225△171,108現金及び現金同等物に係る換算差額40,526△4,707現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△28,5081,502現金及び現金同等物の期首残高882,146853,637現金及び現金同等物の期末残高853,637855,140 ⑤ 要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(連結の範囲の変更)新たに設立した1社を連結の範囲に含めました。また、清算結了により2社を連結の範囲から除きました。 (持分法適用範囲の変更)株式の追加取得により1社を持分法適用の範囲に含めました。また、清算結了等により2社を持分法適用の範囲から除きました。 当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(連結の範囲の変更)新たに設立した2社を連結の範囲に含めました。 (持分法適用範囲の変更)新たに出資した関係会社等2社を持分法適用の範囲に含めました。 (6)経営成績等の状況の概要に係る主要な項目における差異に関する情報前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記」の「39.初度適用」をご参照ください。 当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(有形固定資産)日本基準では有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、主として定率法を採用していましたが、IFRSでは定額法を採用しています。また、IFRSの適用に伴い、見積耐用年数を見直しています。この処理により従来の方法によった場合に比べて、税引前利益は90億円増加しています。 (無形資産)日本基準では、発生時費用処理していた研究開発費について、IFRSでは資産化の要件を満たす支出額を資産計上しています。この処理により従来の方法によった場合に比べて、税引前利益は246億円増加しています。 (負債性金融商品)日本基準では投資有価証券に含まれる一部の負債性金融商品について、公正価値の変動をその他の包括利益で認識していましたが、IFRSでは「金融収益」及び「金融費用」として認識しています。この処理により従来の方法によった場合に比べて、税引前利益は239億円増加しています。 |
※本記事は「スズキ株式会社」の令和7年3月期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
※4. この企業は、連結財務諸表ベースで見ると有利子負債がゼロ。つまり、グループ全体としては外部借入に頼らず資金運営していることがうかがえます。なお、個別財務諸表では親会社に借入が存在しているため、連結上のゼロはグループ内での相殺消去の影響とも考えられます。
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

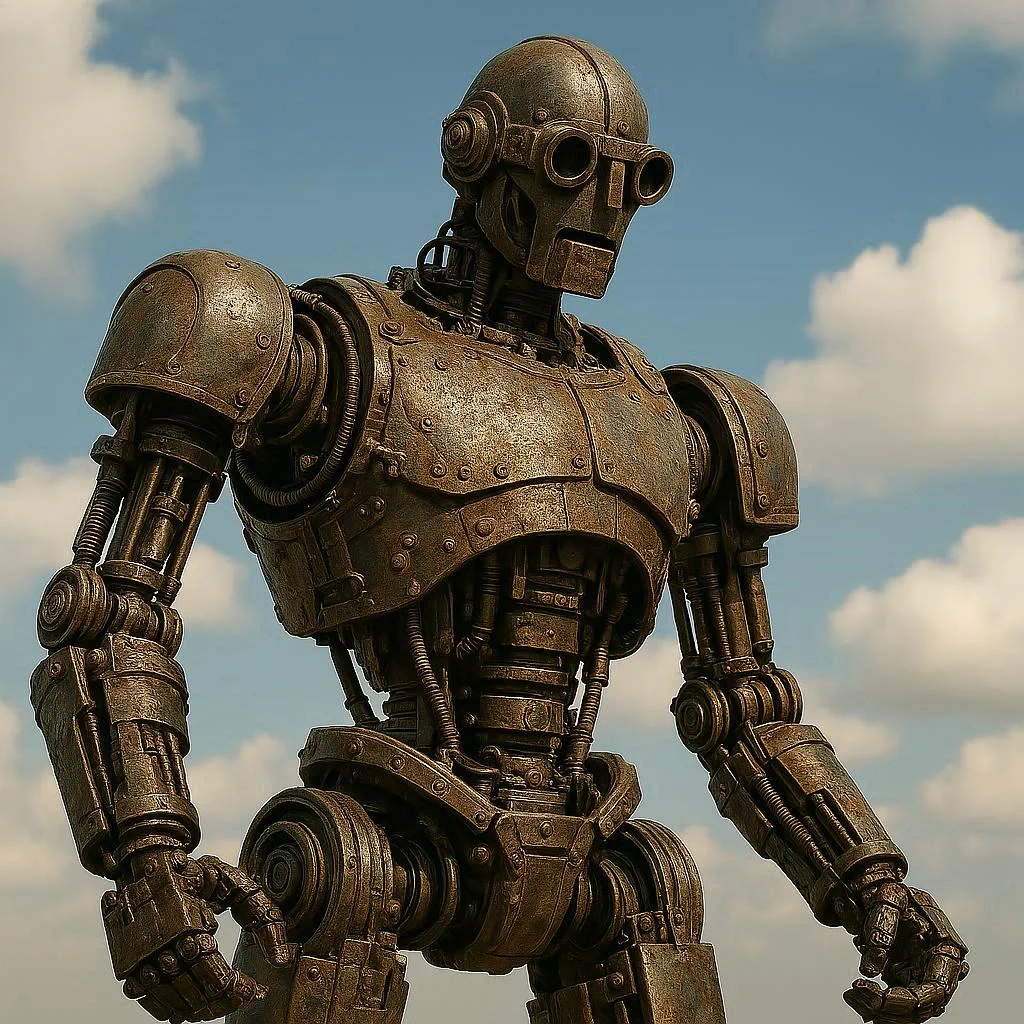

コメント