| 会社名 | 住友ファーマ株式会社 |
| 業種 | 医薬品 |
| 従業員数 | 連3832名 単1799名 |
| 従業員平均年齢 | 43.7歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 18.4年 |
| 平均年収 | 7132006円 |
| 1株当たりの純資産(連結) | 1215.84円 |
| 1株当たりの純利益(連結) | 59.49円 |
| 決算時期 | 3月 |
| 配当金 | 0円 |
| 配当性向 | 0% |
| 株価収益率(PER) | 2.7倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(連結) | 8% |
| 営業活動によるCF | 165億円 |
| 投資活動によるCF | 997億円 |
| 財務活動によるCF | ▲1088億円 |
| 研究開発費※1 | 499億円 |
| 設備投資額※1 | 121億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 4276.14億円 |
| 株主資本比率※2 | 29.3% |
| 有利子負債残高(連結)※3※4 | 0円 |
経営方針
| 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 当社は、「人々の健康で豊かな生活のために、研究開発を基盤とした新たな価値の創造により、広く社会に貢献する」を企業理念として掲げ、事業活動を進めています。少子高齢化社会の進展、パンデミックなどの社会課題を背景に、精神神経領域およびがん領域の医療ニーズは拡大していくことが予想されます。また、医療ニーズはますます高度化しており、多様なモダリティを駆使し、デジタルとリアルが融合した生活と人々の価値観に寄り添うヘルスケア課題の解決が社会から期待されています。かかる環境において、当社グループは、変わりゆくヘルスケア課題の解決に貢献するため、2019年4月に策定したビジョン「もっと、ずっと、健やかに。最先端の技術と英知で、未来を切り拓く企業」に基づき、精神神経領域およびがん領域を重点疾患領域とし、医薬品、再生・細胞医薬等による多様なアプローチで人々の健康で豊かな生活に貢献してまいります。また、その他領域においても、保有アセットを生かし、確かな価値を患者さんに届けてまいります。これにより、2033年に「グローバル・スペシャライズド・プレーヤー(GSP)」の地位を確立することを目指します。当社は、このビジョンのもと、2023年度を起点とする5か年の「中期経営計画2027」を2023年4月に策定しましたが、当社グループが目標として掲げる、「グローバル・スペシャライズド・プレーヤー(GSP)」の地位確立の方針に変更はないものの、当社グループが直面する経営環境を受け、「中期経営計画2027」については取り下げることとしました。そして、改めて「グローバル・スペシャライズド・プレイヤー(GSP)」の地位確立に向かい全社一丸となって取り組むべく、2025年5月に、2027年度までの活動計画である「Reboot 2027 ~力強い住友ファーマへの再始動~」を発表しました。 なお、当社は、グループ一体経営を推進するため、米国グループ会社の再編を契機に、2023年7月1日付けで理念体系を再構成し、理念、バリューおよび行動宣言をグループ全体で共有するフィロソフィとして、グループ内への浸透を進めています。併せて、当社の理念の実践により、持続可能な社会実現に貢献し持続的な企業価値向上につなげることを「サステナビリティ経営」と定義しています。 理念(当社の存在意義、社会に対する約束・使命)人々の健康で豊かな生活のために、研究開発を基盤とした新たな価値の創造により、広く社会に貢献する バリュー(全役員・従業員が共有すべき価値観)Patient FirstAlways with IntegrityOne Diverse Team 行動宣言(日々の業務において守るべき行動規範)1.”Innovation today, healthier tomorrows” の実現に取り組みます2.誠実な企業活動を行います3.積極的な情報開示と適正な情報管理を行います4.自らの能力を高め、協働します5.人権を尊重します6.地球環境問題に積極的に取り組みます7.社会との調和を図ります 活動方針当社は、2023年度において多額の損失を計上し、厳しい経営状況に陥りました。この状況に対し、2024年度は、大幅な人員削減を含むグループをあげた抜本的構造改革を断行しました。事業面では、再生・細胞医薬事業の再編を行うことで住友化学、RACTHERAおよびS-RACMOとの連携体制を構築したことに加え、選択と集中の一環として、アジア事業およびフロンティア事業を再編しました。これらの取組の結果、必達目標として掲げたコア営業利益および最終損益の黒字化を達成しました。また、既存借入金のリファイナンスを行うことで財務環境の安定化を図りました。しかしながら、2024年度の業績には一過性の収益が含まれており、実態としては依然厳しい経営状況が続いています。当社は今後、大規模な構造改革後の新しい組織体制のもと、効率的な組織運営を行い、研究開発の成功確度向上に取り組んでまいります。これにより、研究開発型ファーマとしての「価値創造サイクル」を循環させることで「力強い会社」へと再始動し、改めてグローバル・スペシャライズド・プレイヤー(GSP)の地位確立を目指してまいります。 価値創造サイクル(「Reboot2027」より) (注)当社は、特定の領域・技術において「価値創造サイクル」を力強く循環させ、継続的にイノベーションを創出・社会実装します。これにより、人々の健康で豊かな生活に貢献しグローバルに「住友ファーマ」ブランドを確立することでGSPの地位確立を目指します。 当社グループは、再成長への道筋を定めるうえで、2025年度を研究開発型ファーマとしての真価を示す年と位置付け、以下の方針に従って事業を運営してまいります。 ① 売上収益の拡大北米においては、引き続き進行性前立腺がん治療剤「オルゴビクス」、子宮筋腫・子宮内膜症治療剤「マイフェンブリー」および過活動膀胱治療剤「ジェムテサ」(以下「基幹3製品」)の早期価値最大化に最注力してまいります。「オルゴビクス」については、強い成長トレンドを維持し、本剤の進行性前立腺がん治療におけるアンドロゲン除去療法の標準治療薬としての位置付け獲得を目指します。また、薬剤給付制度の変更により2025年1月から患者自己負担額の上限が引き下げられたことを周知徹底するなどのプロモーション活動を行うことで、さらなるシェアの拡大に努めてまいります。「マイフェンブリー」については、2024年12月末をもってPfizer Inc.(以下「Pfizer社」)との共同開発・共同販売を終了しましたが、引き続きプロモーション活動に注力し、子宮内膜症におけるシェア拡大を推進するとともに患者さんおよび医療関係者への認知度向上を通じて、経口GnRH(ゴナドトロピン放出ホルモン)市場の拡大および同市場内での製品シェア拡大に注力してまいります。「ジェムテサ」については、競合品に対するジェネリック参入による販売量の減少が見込まれますが、2024年度に前立腺肥大症を伴う過活動膀胱に対する適応追加承認を取得したことを契機とし、さらなる販売拡大に取り組んでまいります。日本においては、2025年度に2型糖尿病治療剤「エクメット」の独占販売期間が終了する一方、2025年2月からヤンセンファーマ株式会社(以下「ヤンセンファーマ」)との持効性抗精神病剤「ゼプリオン」および「ゼプリオンTRI」の販売提携を開始しました。非定型抗精神病薬「ラツーダ」および2型糖尿病治療剤「ツイミーグ」とともに注力製品の価値最大化を図ってまいります。 ②将来の成長シーズの確保2025年度も徹底的なコスト管理を継続し、がん領域のenzomenibおよびnuvisertibに資源を集中させるとともに、他社との提携機会を追求することにより、両剤の開発を最優先で推進し早期の承認取得と価値最大化を目指します。enzomenibについては、急性骨髄性白血病の単剤療法の承認申請に向けたフェーズ2試験および併用療法のフェーズ1/2試験を引き続き推進してまいります。nuvisertibについては、骨髄線維症を対象とした単剤療法および併用療法のフェーズ1/2試験を引き続き推進いたします。なお、「Reboot 2027」の期間において、enzomenibは日本および米国での承認取得・上市を目指し、nuvisertibは両国での承認申請を目指します。精神神経領域では、RACTHERAと連携し、世界初のiPS細胞由来製品の実用化とゲームチェンジャーとなる治療の実現に向け、日本においては他家iPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞のパーキンソン病を適応症とした条件および期限付き承認取得を目指し、米国においてもフェーズ1/2試験を着実に推進してまいります。また、他家iPS細胞由来網膜色素上皮細胞については、網膜色素上皮裂孔を対象とした日本でのフェーズ1/2試験を、他家iPS細胞由来網膜シートについては、網膜色素変性治療に関する米国でのフェーズ1/2試験を着実に推進してまいります。特長ある低分子の初期臨床開発品目群については、2030年代のグループ収益を支える優先品目を選抜し、次のフェーズへの移行に向けた取組を推進してまいります。その他領域では、ユニバーサルインフルエンザワクチンについて、ベルギーでのフェーズ1試験の中間解析を実施し、KSP-1007については、アジア地域への展開を見据えた日本および中国でのフェーズ1試験を継続し、開発を着実に推進してまいります。なお、ユニバーサルインフルエンザワクチンおよびKSP-1007の研究開発は、日本医療研究開発機構(AMED)からの委託研究開発費を活用しています。 当社グループは、今後も全社一丸となって事業活動を推進し、患者さん、ご家族および介護者の皆さんへも貢献できる新しい価値を一日も早く提供するために、スピード感をもって取り組んでまいります。 株主還元当社は、業績に裏付けられた成果を適切に配分することを重視しており、安定的な配当に加えて、業績向上に連動した増配を行うことを配当の基本方針としています。当連結会計年度の業績は、基幹3製品の伸長に加え、北米および日本における事業構造改善等によるコスト削減効果の発現もあり、コア営業損益は432億円、親会社の所有者に帰属する当期損益は236億円と大きく改善しました。しかしながら、前連結会計年度末に発生したシンジケートローン契約に付されている財務制限条項への抵触については、当連結会計年度末に実施したリファイナンスにより解消したものの、当連結会計年度末の有利子負債残高は3,054億円と財務面では依然として厳しい状況が続いており、2025年3月期の期末配当については、期初の予想のとおり無配といたします。また、2026年3月期はコア営業利益560億円を見込みますが、当面は財務体質の改善を優先する必要があることから、2026年3月期の配当についても、誠に遺憾ながら無配の予想とさせていただきます。株主の皆様に深くお詫び申しあげますとともに、早期の業績回復および財務体質改善に努めてまいりますので、何卒ご理解のうえ、引き続きご支援を賜りますようお願い申しあげます。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 |
経営者による財政状態の説明
| 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。また、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものです。 (1) 重要な会計方針および見積り当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準(以下「IFRS」)に準拠して作成しています。連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記3.重要性がある会計方針」に記載しています。連結財務諸表の作成にあたっては、過去の実績や状況に応じ合理的であると考えられる様々な要因に基づき、見積り及び判断を行っていますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるために、これらの見積りと異なる場合があります。当社グループの財政状態又は経営成績に重要な影響を及ぼす会計上の見積りおよび判断は、以下のとおりです。 ・のれん及び無形資産のれん及び無形資産の減損テストにおける処分コスト控除後の公正価値は、将来キャッシュ・フローの見積額を資金生成単位ごとに設定した加重平均資本コスト等を割引率として用いて現在価値に割り引いて算定しています。上市後の無形資産の将来キャッシュ・フローの見積りには、対象となる製品の販売価格、関連する疾患領域における患者数及び当該製品のシェア等に基づく製品の収益予測及び固定費の予測等の多くの前提条件が含まれています。また、のれんを含む資金生成単位の将来キャッシュ・フローの見積りは、上述の前提条件に加え、開発品に係る研究開発活動の成功確率等を勘案した開発品の収益予測等の前提条件が含まれています。これらの前提条件や割引率は、将来発生する事象によっては影響を受ける可能性があり、翌連結会計年度の連結財務諸表において、のれん及び無形資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。 ・引当金引当金は、期末日における将来の債務の決済時期及び決済に必要と予想されるキャッシュ・フロー等に関する最善の見積りに基づいて算定しています。特に、米国で販売している製品に適用される売上割戻引当金の見積りに用いられる将来の販売数量や割戻率等は、将来発生する事象によっては影響を受ける可能性があり、翌連結会計年度の連結財務諸表において、引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。 ・繰延税金資産の回収可能性繰延税金資産は、将来減算一時差異等を利用できる将来課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識しています。当該回収可能性の判断は、当社グループの事業計画に基づいて見積もった将来の各事業年度の課税所得を前提としています。当該将来の課税所得の見積りは、将来発生する事象によっては影響を受ける可能性があり、翌連結会計年度の連結財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を生じさせる可能性があります。 ・条件付対価契約に関する金融資産、および条件付対価契約に関する金融負債子会社売却に伴い生じた条件付対価契約に関する金融資産および企業結合の結果生じる条件付対価契約に関する金融負債の公正価値は、特定の開発品の開発進捗に応じて発生する開発マイルストンや販売後の売上収益に応じて発生する販売マイルストンを考慮して、それらが達成される可能性や貨幣の時間的価値を考慮して算定しています。これらの見積りは、将来発生する事象によっては影響を受ける可能性があり、翌連結会計年度の連結財務諸表において、条件付対価契約に関する金融資産および金融負債の金額に重要な影響を与える可能性があります。 (2) 経営成績当連結会計年度の世界経済は、中国など一部の地域で足踏みが見られましたが、米国では個人消費の増加を背景に景気は堅調に推移し、総じて持ち直しが見られました。一方、地政学リスクや金融市場の不確実性の高まり、米国の関税措置の動向などによる先行きの不透明感が継続しました。わが国経済については、緩やかな回復基調を維持しつつも、内需の弱さが懸念される状況が続きました。医薬品業界では、医療費抑制の取組と並行してデジタル技術の活用や薬価制度改革などによる事業環境の改善は見られたものの、新薬開発の難化、研究開発費の高騰などを背景に事業の選択と集中が進みました。当社グループは、ピーク時の売上が2,000億円を超えていた「ラツーダ」の米国での独占販売期間が2023年に終了したことによる売上収益の減少と、北米における基幹3製品の売上収益の伸びが想定を下回ったことにより、前連結会計年度に多額の損失を計上し非常に厳しい状況に置かれています。 このような状況のもと、当社グループは、基幹3製品をはじめとした既存製品の事業拡大を図るとともにグループ全体で抜本的構造改革を断行することによって、早期の業績回復と再成長を目指して事業活動を進めてまいりました。日本においては、精神神経領域では、パーキンソン病治療剤「トレリーフ」の独占販売期間が2024年6月に終了しましたが、「ラツーダ」および非定型抗精神病薬「ロナセンテープ」を中心に情報提供活動に注力しました。また、ヤンセンファーマと「ゼプリオン」および「ゼプリオンTRI」の販売提携を行い、2025年2月より共同プロモーション活動を開始しました。糖尿病領域では、「ツイミーグ」、2型糖尿病治療剤「エクア」(2024年12月に独占販売期間終了)および「エクメット」の販売に引き続き注力しました。北米においては、基幹3製品および小児先天性無胸腺症向け培養ヒト胸腺組織「リサイミック」の販売拡大に注力しました。また、「マイフェンブリー」については、2024年12月にPfizer社との共同開発・共同販売を終了し、自社単独による事業に移行しました。アジアにおいては、主力製品であるカルバペネム系抗生物質製剤「メロペン」の販売に引き続き注力しました。抜本的構造改革については、前連結会計年度に北米グループ会社の再編を実施したことに続き、国内事業における黒字体質確立に向けて、当社従業員を対象とした早期退職者の募集を行いました。また、再生・細胞医薬事業において、同事業の推進および研究開発を担うRACTHERAならびに製法開発や製造を受託するS-RACMOの2社について、当社が保有する株式の一部を親会社である住友化学に譲渡しました。住友化学グループにおけるシナジーを最大化することにより、同事業の早期育成およびグローバル展開の加速に努めてまいります。これらに加え、2024年5月にフロンティア事業を新設子会社であるFrontAct株式会社に承継させ、2025年3月に同社の全株式をサワイグループホールディングス株式会社に譲渡するための契約を締結しました。これらの事業活動により業績改善に取り組むとともに、既存の借入金について、Roivant Sciences Ltd.(以下「Roivant社」)株式の売却資金を返済に充当したうえで、新たなシンジケートローン契約締結によるリファイナンスを行い、財務基盤の強化を図りました。なお、注力領域に経営資源を集中し、当社の持続的な成長につなげることを目指して、当社の子会社である住友制葯投資(中国)有限公司およびSumitomo Pharma Asia Pacific Pte. Ltd.ならびにそれらの子会社を通じて運営するアジア事業を丸紅グローバルファーマ株式会社に譲渡する旨の契約を2025年4月に締結しました。 (業績管理指標として「コア営業利益」を採用)当社グループでは、IFRSの適用にあたり、会社の収益性を示す利益指標として、「コア営業利益」を設定し、これを当社独自の業績管理指標として採用しています。「コア営業利益」は、営業利益から一部の項目を除外したものとなります。除外する主なものは、減損損失、事業構造改善費用、条件付対価公正価値の変動額等です。 当連結会計年度の当社グループの連結業績は、以下のとおりです。(単位:億円) 前連結会計年度(2024年3月期)当連結会計年度(2025年3月期)増減増減率(%)売上収益3,1463,98884326.8コア営業利益△1,3304321,761-営業利益△3,5492883,837-税引前当期利益△3,2311763,407-当期利益△3,1492363,386-親会社の所有者に帰属する当期利益△3,1502363,386- ■ 売上収益は、3,988億円(前連結会計年度比26.8%増)となりました。北米において基幹3製品の売上が拡大したことに加え、「マイフェンブリー」の自社単独による事業への移行に伴い、契約一時金等に係る繰延収益について売上収益として一括計上したことや期中の平均為替レートが円安となったことによる為替換算の影響等により増収となりました。 ■ コア営業損益は、432億円の利益(前連結会計年度は1,330億円の損失)となりました。売上収益の増加に加え、北米グループ会社の再編等による事業構造改善効果の発現や研究開発投資の選択と集中による削減等、グループをあげて合理化を進めたことにより、販売費及び一般管理費ならびに研究開発費が大きく減少しました。また、RACTHERAの株式の一部を譲渡したこと等に伴う収益を計上したことから、コア営業損益は大幅に改善し、黒字化を達成しました。 ■ 営業損益は、288億円の利益(前連結会計年度は3,549億円の損失)となりました。コア営業損益の改善に加え、減損損失や事業構造改善費用が減少したこと等により、営業損益は大幅に改善しました。 ■ 税引前当期損益は、176億円の利益(前連結会計年度は3,231億円の損失)となりました。為替が円高に振れたため為替差損を計上したこと等により金融収益と金融費用をあわせた金融損益は減益となりましたが、営業損益が大きく改善したことから、税引前当期損益は大幅に改善しました。 ■ 当期損益は、236億円の利益(前連結会計年度は3,149億円の損失)となりました。税引前当期損益が改善したことにより、当期損益は大幅に改善しました。 ■ 親会社の所有者に帰属する当期損益は、236億円の利益(前連結会計年度は3,150億円の損失)となりました。非支配持分に帰属する利益を控除した親会社の所有者に帰属する当期損益は大幅に改善し、黒字化を達成しました。 (セグメント業績指標として「コアセグメント利益」を採用)セグメント別の業績では、各セグメントの経常的な収益性を示す利益指標として、「コアセグメント利益」を設定し、当社独自のセグメント業績指標として採用しています。「コアセグメント利益」は、「コア営業利益」から、グローバルに管理しているため各セグメントに配分できない研究開発費、事業譲渡損益などを除外したセグメント別の利益となります。 セグメント別の経営成績は次のとおりです。 <日本>■ 売上収益は、998億円(前連結会計年度比12.9%減)となりました。「ツイミーグ」や「ラツーダ」、オーソライズド・ジェネリック品などの売上が伸長しましたが、「トレリーフ」および「エクア」の独占販売期間が終了したこと等による売上減少に加え、薬価改定の影響により、減収となりました。■ コアセグメント損益は、114億円の利益(前連結会計年度比14.6%減)となりました。コスト削減により販売費及び一般管理費は減少しましたが、減収による売上総利益の減少の影響が大きく、減益となりました。 <北米>■ 売上収益は、2,518億円(前連結会計年度比58.3%増)となりました。基幹3製品および抗てんかん剤「アプティオム」の売上が伸長したことに加え、「マイフェンブリー」の自社単独による事業への移行に伴い、契約一時金等に係る繰延収益について売上収益として一括計上したことや為替換算の影響により、増収となりました。■ コアセグメント損益は、426億円の利益(前連結会計年度は802億円の損失)となりました。増収による売上総利益の増加に加え、北米グループ会社の再編等に伴う事業構造改善効果等による販売費及び一般管理費の減少が大きく寄与し、コアセグメント利益となりました。 <アジア>■ 売上収益は、472億円(前連結会計年度比15.5%増)となりました。中国において、「メロペン」の売上が増加したこと等により、増収となりました。■ コアセグメント損益は、239億円の利益(前連結会計年度比30.0%増)となりました。増収による売上総利益の増加により、増益となりました。 (3) 生産、受注及び販売の実績① 生産実績当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。セグメントの名称金額 (百万円)前期比 (%)日本62,597△24.6北米153,816△3.6アジア44,94910.7合計261,362△7.7 (注) 1 金額は販売価格により換算したものです。2 セグメント間取引については相殺消去しています。 ② 仕入実績当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。セグメントの名称金額 (百万円)前期比 (%)日本23,471△22.5北米6,609△49.8アジア--合計30,080△30.8 (注) 金額は仕入価格によっています。 ③ 受注状況当社グループの生産は見込生産で、受注生産は行っていません。 ④ 販売実績当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。 セグメントの名称金額 (百万円)前期比 (%)日本99,838△12.9北米251,81458.3アジア47,18015.5合計398,83226.8 (注) 1 セグメント間取引については相殺消去しています。2 当連結会計年度において、北米セグメントにおける販売実績が著しく増加しました。これは、基幹3製品および「アプティオム」の売上が伸長したことに加え、「マイフェンブリー」の自社単独による事業への移行に伴い、契約一時金等に係る繰延収益について売上収益として一括計上したことや為替換算の影響によるものです。3 主な相手先別の販売実績および総販売実績に対する割合は、次のとおりです。相手先前連結会計年度当連結会計年度金額 (百万円)割合 (%)金額 (百万円)割合 (%)Cencora, Inc.(米国)(注)38,63712.373,30418.4McKesson Corporation(米国)44,79314.271,28717.9Cardinal Health, Inc.(米国)33,87410.853,69713.5 (注)前連結会計年度においてAmerisourceBergen Corporationから社名変更されました。 (4) 財政状態資産については、前連結会計年度末に比べ1,649億円減少し、7,426億円となりました。非流動資産では、Roivant社株式等の当社が保有する投資有価証券の売却によりその他の金融資産が大きく減少したため、前連結会計年度末に比べ1,485億円減少しました。流動資産では、売却目的で保有する資産が増加しましたが、棚卸資産や未収法人所得税等が減少し、前連結会計年度末に比べ164億円減少しました。負債については、投資有価証券売却資金を返済に充当し、借入金が減少しました。また、「マイフェンブリー」の自社単独による事業への移行に伴い、契約一時金等に係る繰延収益を一括計上したことなどにより、その他の負債が減少しました。この結果、前連結会計年度末に比べ1,782億円減少し、5,731億円となりました。なお、社債及び借入金は合計で3,054億円となり、前連結会計年度末に比べ1,135億円減少しました。資本合計は、投資有価証券の売却等により、その他の資本の構成要素が減少しましたが、利益剰余金が増加した結果、前連結会計年度末に比べ133億円増加し、1,695億円となりました。なお、当連結会計年度末の親会社所有者帰属持分比率は22.8%となりました。また、アジア事業およびフロンティア事業を譲渡する契約を締結したことに伴い、関連する資産については売却目的で保有する資産、負債については売却目的で保有する資産に直接関連する負債、資本については売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益にそれぞれ分類しています。 (5) キャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フローは、減損損失などの非資金損益項目を除いた当期損益が大幅に改善したことに加え、事業構造改善に伴う支出が減少したこと、法人所得税が前連結会計年度において支払となったのに対し当連結会計年度においては還付となったこと等により、前連結会計年度に比べ2,584億円改善し、165億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、Roivant社株式等の投資有価証券の売却により、前連結会計年度に比べ667億円収入が増加し、998億円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は多額の借入がありましたが、当連結会計年度は借入返済となったこと等により、前連結会計年度に比べ1,867億円収入が減少し、1,088億円の支出となりました。上記のキャッシュ・フローに、現金及び現金同等物に係る換算差額および売却目的で保有する資産への振替に伴う増減額を加味した結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は231億円となり、前連結会計年度末に比べ59億円減少しました。 |
※本記事は「住友ファーマ株式会社」の令和7年3月期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
※4. この企業は、連結財務諸表ベースで見ると有利子負債がゼロ。つまり、グループ全体としては外部借入に頼らず資金運営していることがうかがえます。なお、個別財務諸表では親会社に借入が存在しているため、連結上のゼロはグループ内での相殺消去の影響とも考えられます。
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

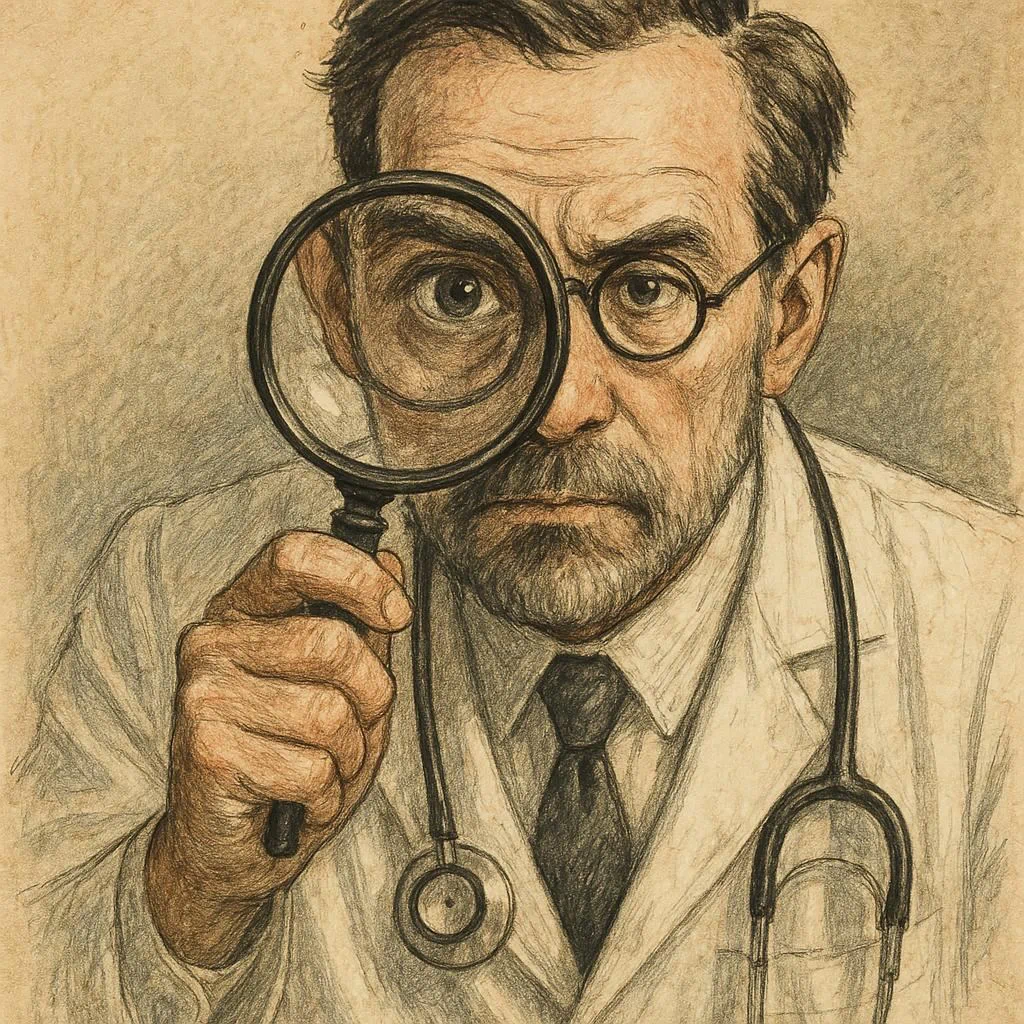

コメント