| 会社名 | 住友重機械工業株式会社 |
| 業種 | 機械 |
| 従業員数 | 連25337名 単4410名 |
| 従業員平均年齢 | 43.2歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 13.5年 |
| 平均年収 | 8353000円 |
| 1株当たりの純資産(連結) | 5059.88円 |
| 1株当たりの純利益(連結) | 63.86円 |
| 決算時期 | 12月 |
| 配当金 | 125円 |
| 配当性向 | 176.1% |
| 株価収益率(PER) | 13.3倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(連結) | 1.2% |
| 営業活動によるCF | 127億円 |
| 投資活動によるCF | ▲372億円 |
| 財務活動によるCF | 419億円 |
| 研究開発費※1 | 83億円 |
| 設備投資額※1 | 44億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 1276.13億円 |
| 株主資本比率※2 | 23.5% |
| 有利子負債残高(連結)※3 | 2139.72億円 |
経営方針
| 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】事業を取り巻く経済環境は依然として複雑に変化しており、厳しさが継続しております。国内は業種により景気動向の差が大きく、製造業においても同様の状況です。自動車産業では、EV化の波が一時的に減速しております。産業のインフラともいえる半導体産業では、生成AIに関係する企業のみが恩恵を受けている状況から、回復局面を経て再び成長局面に入っていくと想定しております。海外においては、米国のみが堅調に推移し、積極的なインフラ整備投資が期待されておりますが、新政権による不確実性が残る状況であります。欧州はドイツにおいて製造業の低迷が長期化しており、利下げにより緩やかに持ち直す見込みも出てきていますが、依然低下傾向が続いております。また、中国は米中貿易戦争の影響を受け、成長の鈍化が続くなど、不透明な状況が続いております。 (1) 会社の経営の基本方針住友重機械グループは、1888年(明治21年)、住友グループの祖業である別子銅山の工作方として創業以来、社会と産業の発展とともに歩んできました。住友グループ各社に共通の理念と位置付けられる「住友の事業精神」は、社会性が重要視される現在の環境との親和性も高く、当社グループにとっても経営の基本であり、この精神に則り企業活動を実践していきます。また当社グループは、住友の事業精神のもと、従来の経営理念(企業使命+私たちの価値観)に加え、このたび企業の存在意義となるパーパスを次のとおり制定し、理念体系を整備いたしました。 パーパスこだわりの心と、共に先を見据える力で、人と社会を優しさで満たしますEnhance society and those within it with compassion through our ownership and vision 当社グループはこれら理念に則り、製品及びサービスのさらなる深化を図り、顧客の声に応え続けるとともに、持続可能な社会実現に向けて、イノベーションにより社会課題解決へのソリューションとなる製品及びサービスを提供していくことで、社会価値及び企業価値の拡大に引き続き取り組んでいきます。 (2) 中長期的な経営戦略、目標とする経営指標及び会社の対処すべき課題「中期経営計画2026」の概要と進捗、今後の施策等 「中期経営計画2026」は、「あるべき姿」からバックキャストして社会課題を導き、「製品・サービスによる社会課題解決を通じて持続的に企業価値を拡大する」という方針を継続しつつ、新たにパーパスを策定し、当社グループとして何を目指していくのかを共通認識として持つ、大事な道標といたしました。2030年の「あるべき姿」を「コア技術で豊かな社会を支え、CSV*を実現する企業」とし、成長力、収益力、信用力といった「企業価値」と、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の観点で示される「社会価値」をバランスさせ、環境に左右されない、変化に強い、「強靭な事業体の構築」を基本方針としております。本基本方針のもと、「収益力の改善」、「資本効率の向上」、「新事業探索の強化」を重点課題と位置付け、コーポレートとセグメントの両面から遂行する基本戦略とし、「深化による稼ぐ力の強化、利益にこだわる経営」、「ROIC経営の徹底」及び「探索による事業機会の発掘」を推進しております。〔図1〕 「中期経営計画2026」では、2026年度に売上高12,500億円、営業利益1,000億円、ROIC8.0%を達成することを財務目標としてスタートしましたが、欧州市況の低迷長期化など、当社グループを取りまく外部環境の変化に起因した2024年度の受注、営業利益の低迷を受け、2026年目標値を売上高11,730億円、営業利益800億円、ROIC7.0%へ修正いたしました。「中期経営計画2026」では「強靭な事業体の構築」を基本方針としており、重点課題の「収益力の改善」に注力して取り組み「稼ぐ力」の強化を図ってまいります。 また、非財務目標としてESGの各項目に分類したサステナビリティ重要課題(E:環境負荷の低減、S:よりよい暮らし・働き方の実現、従業員の安全・健康・育成、地域との共存・共栄、持続可能なサプライチェーンの構築、G:ガバナンスの強化、製品品質の確保)の各目標値を設定しており、当初の計画どおり進捗しております。 図1「中期経営計画2026」基本方針及び骨子 コーポレート戦略a.事業ポートフォリオ改革の推進〔図2〕 成長を見込む重点領域事業へ経営資源を集中し事業の拡大を図り、事業ポートフォリオ改革を推進してまいります。当社グループ製品を支える技術が多岐にわたるなかで、外部環境や当社グループの強みを踏まえて、コア技術をベースに、「ロボティクス・自動化」分野、「半導体」分野、「先端医療機器」分野及び「環境・エネルギー」分野の4つの「重点投資領域」を設けております。これらの「重点投資領域」へ「中期経営計画2023」を上回る積極的な投資を行うことで、事業を伸長し新たな価値創造と企業価値向上を目指してまいります。 また、今後、収益低迷事業については収益力強化のための施策を実行してまいります。また、低成長・低収益事業の戦略再構築を行い、成長を見込む4つの「重点投資領域」事業へ経営資源を集中し事業の拡大を図ってまいります。図2 コーポレート戦略:事業ポートフォリオ改革の推進 b.資本政策「中期経営計画2026」ではROIC向上施策の推進によりキャッシュ・フロー創出力を強化するとともに、財務の健全性を損なわない範囲で有利子負債も活用し、重点投資領域を中心に投資へ1,900億円、研究開発費へ900億円、株主の皆様へ800億円の還元を計画しておりましたが、2024年度業績を受けて見直しを検討させていただいております。2024年度は100億円の自社株買いを実施し、1株当たり配当を5円増配の125円としました。今後の還元は中長期的にDOE**3.5%以上、最低配当125円、自社株買いを含めた総還元性向40%以上を基本方針とし、安定的かつ継続的な配当の実現と柔軟な自己株式の取得により、株主還元の充実を図ってまいります。 c.新事業探索の強化2023年に設置した新事業探索室を中心に、4つのセグメント及び本社部門と連携をとりながら、セグメントをまたぐ横断的な探索テーマの調整と推進、コーポレート視点でのテーマ発掘と事業化推進を行ってまいります。新事業探索室では先進技術の調査、及び新規事業の探索・創出を目的に、マサチューセッツ工科大学(MIT)の近隣にボストンオフィスを設立し、鋭意活動を展開中です。また、新事業テーマを創出する社内ピッチコンテストを実施しました。また、社内企業家人材の育成と事業化へ向けた活動プログラムなども実施し、計画に沿って実行している状況であります。 d.経営基盤強化「中期経営計画2026」では、上記の取組みを支える経営基盤(サステナビリティ、人的資本、DX***)の強化を進めております。サステナビリティでは、SDGs、当社グループの2050年カーボンニュートラル目標達成に向けた対応を強化し、社会環境変化のリスクをチャンスへ変えて、企業価値向上を目指しております。具体的には、機械メーカーに対応が求められるサステナビリティ課題を抽出し、7つの重要課題を特定して、事業を通じた社会課題解決への貢献や、気候変動リスクをはじめとする中長期的なリスクへの対応に取り組んでおります。特定した7つのサステナビリティ重要課題及び関連する主な指標・目標の詳細は、表1のとおりです。また2024年度の実績については、2025年7月発表の統合報告書にて公表予定としております。人的資本では、「人材育成基盤の強化」と「組織能力の強化」が事業の持続的成長を支えるとの人的資本経営の考え方のもと、人材確保、人材育成基盤の強化、グローバル人材マネジメントの基盤整備、組織能力強化、ダイバーシティ推進を重点課題と位置付け、人材戦略を遂行しております。DXでは、デジタライゼーションを継続し、強靭な事業体実現を支えるDX推進基盤を構築してまいります。同時に、新たな顧客価値を創出する、一流の商品・サービスづくり及び設計・製造バリューチェーンなどの業務プロセスの変革を加速させ、DXを用いたサービス事業の強化も行ってまいります。また、SDGs実現に向けて、環境・安全対策に取り組み、社会課題の解決を推進しております。表1 特定した7つのサステナビリティ重要課題及び関連する主な指標・目標 セグメント戦略「中期経営計画2026」では、メカトロニクスセグメント、インダストリアル マシナリーセグメント、ロジスティックス&コンストラクションセグメント及びエネルギー&ライフラインセグメントのそれぞれの役割を以下のように位置付け、セグメントごとにROIC目標を設定し、成長戦略を遂行する計画としております。 メカトロニクス : 高収益で成長牽引セグメントインダストリアル マシナリー : 高収益で成長牽引セグメントロジスティックス&コンストラクション : 安定収益を確保する基盤セグメントエネルギー&ライフライン : 将来成長のための育成セグメント 各セグメントは、コーポレート戦略で設定された「重点投資領域」の4つの分野を踏まえ、深化による稼ぐ力の強化、探索による事業機会の発掘を行ってまいります。メカトロニクスセグメントは「ロボティクス・自動化」と「半導体」分野、インダストリアル マシナリーセグメントは「半導体」と「先端医療機器」分野、ロジスティックス&コンストラクションセグメントは「ロボティクス・自動化」分野、エネルギー&ライフラインセグメントは「環境・エネルギー」分野を軸に実行してまいります。2024年度には、セグメント運営の効率化とシナジー推進を目的として、2025年度にセグメント間の事業の組替えを実施することとしました。具体的には、本年1月にメカトロニクスセグメントのレーザ関連装置についてインダストリアル マシナリーセグメントへ、またインダストリアル マシナリーセグメントの極低温冷凍機についてメカトロニクスセグメントへの組替えを実施しました。 4つのセグメントは、2024年度業績を受けて、「重点投資領域」の課題のみならず、「基盤事業領域」の課題へ、より注力し、「収益力の改善」を行ってまいります。 表2 「中期経営計画2026」セグメント別 基本戦略それぞれのセグメントは、セグメント内だけにとどまらず、セグメント間でシナジーを追求しつつ、同時にセグメント組織の効率化を図り、強靭な事業体の構築を目指し、目標達成へ向けて取り組んでまいります。「中期経営計画2026」の最終年度となる2026年12月期の数値目標について、直近の業績動向を踏まえ、見直すことを決議いたしました。2024年度決算概要・中期経営計画の見直しは当社ウェブサイトに掲載しております。https://www.shi.co.jp/ir/library/presentation/pdf/zaimu_kessan24_12.pdf *CSV(共有価値の創造 Creating Shared Value)とは、事業活動を通じて社会課題の解決に貢献することで自社の持続的成長につなげるという考え方です。**DOE(株主資本配当率 Dividend on Equity Ratio)とは、年間の配当総額を株主資本で割って算出する財務指標を指します。 ***DX(デジタルトランスフォーメーション Digital Transformation)とは、ITの活用により、あらゆる活動をより良い方向に変化させることを指します。 |
経営者による財政状態の説明
| 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 (1)経営成績等の状況の概況① 経営成績の状況 当期における当社グループを取り巻く経営環境は、国内においては、製造業を中心に設備投資は緩やかな回復に向かう中、半導体市況の持ち直しの動きに足踏みが見られるなど、一部に弱さが見られました。海外においては、米国では設備投資が底堅く推移する一方、油圧ショベル市場では需要の減少が見られました。欧州では金融引き締めによる景気悪化の影響で弱含みが続き、中国においても不動産市況の悪化に端を発した需要の低迷が続きました。 このような経営環境のもと、当社グループは「中期経営計画2026」に基づき、製品・サービスによる社会課題解決を通じて持続的に企業価値を拡大することを目指し、強靭な事業体の構築に向け、収益力の改善、資本効率の向上、新事業探索の強化を遂行するとともに、SDGsへの貢献拡大及び環境負荷低減への取組み強化などの施策を推進してまいりました。 この結果、当社グループの受注高は9,361億円(前期比7%減)、売上高は1兆711億円(前期比1%減)となりました。損益面につきましては、営業利益は551億円(前期比26%減)、経常利益は492億円(前期比30%減)となりましたが、特別損失275億円を計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は77億円(前期比76%減)となりました。特別損失は主に、当社の連結子会社であるLafert S.p.A.において、欧州の市況低迷の影響を受けて事業環境の不透明感が継続しており、同社の買収時に想定していた収益の実現が困難であるとの判断に至ったことから、のれんを含む固定資産の減損損失を計上したことによるものであります。 また、ROICは4.8%となりました。 当社の子会社である住友重機械ハイマテックス株式会社は、2024年11月21日に、公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告を受けました。本勧告は、同社が、製品の一部部品の製造を委託していた下請事業者に対し、当該部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、部品の製造に使用する同社所有の金型等を無償で保管させていた行為が、同法第4条第2項第3号の規定に違反すると判断されたものです。なお、同社は、対象下請事業者との間で補償に関する協議を実施し、同事業者に対し、既に保管等にかかる費用に相当する金額を支払っております。 当社は、この事実を真摯に受け止め、下請代金支払遅延等防止法の遵守の徹底を図るとともに、当社グループのコンプライアンス体制の一層の整備と強化に努めてまいります。 また、当社の子会社である住友重機械搬送システム株式会社は、機械式駐車装置の取引に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2023年9月12日に公正取引委員会の立入検査を受け、以後、同委員会の実施する調査に対し、全面的かつ真摯に協力してまいりました。2025年3月24日、同社は、同委員会から、水平循環方式分離式の機械式駐車装置の取引に関連し、独占禁止法違反行為があったとして、同法違反行為を既に取りやめていることの確認及び今後同様の行為が行われることのないよう必要な措置を講じることなどを内容とする排除措置命令並びに1億9,995万円の課徴金納付命令を受けました。なお、課徴金に関しましては、課徴金減免制度の適用を申請した結果、課徴金の30%の減額が認められております。 ② セグメント別の状況各部門の経営成績は次のとおりであります。a.メカトロニクス 中小型の減・変速機が国内で堅調に推移した一方、半導体関連の需要が減少したことから、受注は減少しました。また、欧州や中国において減・変速機やモータの需要が回復せず、売上、営業利益も減少しました。 この結果、受注高は1,944億円(前期比2%減)、売上高は2,061億円(前期比6%減)、営業利益は38億円(前期比69%減)となりました。 b.インダストリアル マシナリープラスチック加工機械事業は、中国において電気電子関連の需要が底入れするも、欧州では投資の冷え込みが継続したことから、受注は前期並みとなりました。一方、欧州を中心に受注残が減少したことから売上、営業利益は減少しました。その他の事業では、半導体市況停滞に伴う顧客の在庫調整や投資先送りの影響が続き、受注は減少しました。売上は受注残が高い水準であったことから増加した一方、営業利益は機種構成の変化により微減となりました。この結果、受注高は2,536億円(前期比4%減)、売上高は2,843億円(前期比2%増)、営業利益は203億円(前期比21%減)となりました。 c.ロジスティックス&コンストラクション油圧ショベル事業は、国内や米国においてレンタルを中心とした需要が減少したことなどにより、受注、売上、営業利益ともに減少しました。その他の事業では、建設用クレーン事業は、国内での需要が弱含んだことから受注は減少した一方、北米にて高水準の受注残があったことから、売上、営業利益は増加しました。また、運搬機械事業では、製鉄や造船向けの大型案件があったことから受注、売上は増加しましたが、高採算案件の減少により営業利益は前期並みとなりました。この結果、受注高は3,397億円(前期比14%減)、売上高は前期並みの3,925億円、営業利益は253億円(前期比10%減)となりました。 d.エネルギー&ライフライン エネルギープラント事業は、バイオマス発電設備の案件増加により受注は増加しましたが、受注残が少なかったことから売上は減少し、液化空気エネルギー貯蔵システム(LAES)事業化に向けた開発費増加などにより営業利益も減少しました。 その他の事業では、受注は新造船事業の撤退などにより減少しましたが、当期売上対象となる案件の増加により、売上、営業利益は増加しました。 この結果、受注高は1,418億円(前期比3%減)、売上高は前期並みの1,820億円、営業利益は38億円(前期比41%減)となりました。 e.その他受注高は65億円(前期比9%増)、売上高は62億円(前期比2%増)、営業利益は20億円(前期比3%増)となりました。 ③ 財政状態の状況総資産は、前連結会計年度末と比べて、無形固定資産が174億円減少しましたが、受取手形、売掛金及び契約資産が176億円、有形固定資産が180億円それぞれ増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて594億円増の1兆2,602億円となりました。負債合計は、支払手形及び買掛金が277億円減少した一方、有利子負債が764億円増加したことなどにより、前連結会計年度末比404億円増の6,138億円となりました。純資産は、自己株式の取得により100億円減少した一方、為替換算調整勘定が248億円増加したことなどにより、前連結会計年度末比190億円増の6,464億円となりました。以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末比0.8ポイント減少し、50.8%となりました。 ④ キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ73億円増加し、1,075億円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、128億円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べて526億円の減少となりました。これは、棚卸資産が減少した一方で、売掛債権及び契約資産が増加したこと、仕入債務の減少幅が拡大したこと、税金等調整前当期純利益が減少したこと及び法人税等の支払額が増加したことなどによるものであります。 (投資活動によるキャッシュ・フロー)当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、495億円の資金の減少となり、前連結会計年度に比べて62億円支出の増加となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したことなどによるものであります。 (財務活動によるキャッシュ・フロー)当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、419億円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べて591億円収入の増加となりました。これは、重点投資領域を中心に設備投資を継続した一方で、営業活動によるキャッシュ・フローが減少したことなどにより有利子負債が増加したことによるものであります。 (2)生産、受注及び販売の状況① 生産実績当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。セグメントの名称生産高(百万円)前年同期比(%)メカトロニクス206,826△8.1インダストリアル マシナリー287,513△2.3ロジスティックス&コンストラクション400,825△8.3エネルギー&ライフライン185,9403.7その他6,5199.3合計1,087,623△4.7 (注)金額は販売価格によっており、セグメント間の取引につきましては、相殺消去しております。 ② 受注実績当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。セグメントの名称受注高(百万円)前年同期比(%)受注残高(百万円)前年同期比(%)メカトロニクス194,426△1.782,011△12.5インダストリアル マシナリー253,630△4.3152,460△16.7ロジスティックス&コンストラクション339,744△13.7207,153△20.3エネルギー&ライフライン141,821△3.1188,555△17.6その他6,5269.21,92618.2合計936,147△7.2632,106△17.6 (注)セグメント間の取引につきましては、相殺消去しております。 ③ 販売実績当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。セグメントの名称販売高(百万円)前年同期比(%)メカトロニクス206,095△6.3インダストリアル マシナリー284,2771.6ロジスティックス&コンストラクション392,549△0.2エネルギー&ライフライン181,976△0.1その他6,2302.4合計1,071,126△1.0 (注)セグメント間の取引につきましては、相殺消去しております。 (3)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討結果は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況に関する分析・検討内容当社グループの連結会計年度の経営成績等の分析につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概況」に記載のとおりであります。 ② 資本の財源及び資金の流動性に係る情報 当社は事業活動に必要な手元流動性について、現金及び現金同等物及びコミットメントラインの未使用額を合わせた金額を流動性として位置づけています。当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は1,075億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメントラインも保持しており、当連結会計年度末の未使用のコミットメントラインの総額は900億円であります。現預金、未使用のコミットメントライン額の合計で1,975億円を確保しており、当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。 当社グループの資金需要の主なものは、設備投資、M&Aなどの長期資金需要と当社グループの製品製造のための材料及び部品の購入などの運転資金需要であります。 資金の調達については、調達コストの低減と資金の安定調達の観点から、社債、コマーシャル・ペーパー等の直接金融と銀行借入等の間接金融の比率や、調達期間の分散を図りながら、その時々のマーケットの状況から有利な調達手段を機動的に選択・活用しております。その結果、有利子負債残高は前連結会計年度末より764億円増加し2,386億円となりました。 ③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成されており、連結財務諸表の作成にあたっての重要な会計方針については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」及び、「第5 経理の状況 2 財務諸表等(重要な会計方針)」に記載しております。また、連結財務諸表を作成する際には、当連結会計年度末日時点の資産・負債及び当連結会計年度の収益・費用を認識・測定するため、合理的な見積り及び仮定を使用する必要があります。会計上の見積りが必要となる項目のうち、特に当社グループの財政状態又は経営成績に対して重要な影響を与える可能性があると認識している主な項目は以下のとおりであります。 a.一定の期間にわたり充足される履行義務に係る工事原価総額当社グループは、一定の期間にわたり充足される履行義務につきましては、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。進捗度の見積りは主に原価比例法を用いており、原価比例法においては、実施した工事に関して発生した工事原価が見積工事原価総額に占める割合をもって工事の進捗度としております。当初想定できなかった経済情勢の変動やプロジェクトごとの進捗状況等によって当初の見積りが変更された場合、認識された損益に影響を与える可能性があります。 b.受注工事損失引当金当社グループは、未引渡工事のうち、期末時点で大幅な損失の発生する可能性が高いと見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能な工事について、翌期以降の損失見積額を受注工事損失引当として計上しております。受注工事損失引当金の見積りを行っていますが、当初想定できなかった経済情勢の変動やプロジェクトごとの進捗状況等により、受注工事損失引当金の金額に影響を与える可能性があります。 c.有形固定資産、のれん及びその他無形固定資産の減損当社グループは、減損損失の認識の判定及び測定を行う単位として資産のグルーピングを行い、減損損失を認識する必要のある資産又は資産グループについて、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。将来の当該資産又は資産グループを取り巻く経営環境の変化による収益性の変動や市況の変動により、回収可能価額を著しく低下させる変化が見込まれた場合、減損損失の金額に影響を与える可能性があります。 d.繰延税金資産当社グループの繰延税金資産の回収可能性は、将来の収益力やタックスプランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の発生状況等に基づき判断しております。当該見積り及び当該仮定において、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する繰延税金資産の金額に影響を与える可能性があります。 e.貸倒引当金当社グループは、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては、貸倒実績率により貸倒引当金を計上しております。また、貸倒懸念債権及び破産更生債権につきましては、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。将来、債務者の財政状況の悪化等の事情によってその支払能力が低下した場合には、貸倒引当金又は貸倒損失の金額に影響を与える可能性があります。 ④ 経営者視点による経営成績等の状況に関する分析・検討当社グループは、2024年度を初年度とする3か年の中期経営計画「中期経営計画2026」に基づき、あらゆるステークホルダーの期待に応え、企業価値を持続的に高めるため、ROIC経営を継続してまいります。「中期経営計画2026」では、2026年度に売上高12,500億円、営業利益1,000億円、ROIC8.0%を達成することを財務目標としてスタートしましたが、欧州市況の低迷長期化など、当社グループを取りまく外部環境の変化に起因した2024年度の受注、営業利益の低迷を受け、2026年目標値を売上高11,730億円、営業利益800億円、ROIC7.0%へ修正いたしました。「中期経営計画2026」の詳細については、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)中長期的な経営戦略、目標とする経営指標及び会社の対処すべき課題」を参照ください。「中期経営計画2026」財務目標及び、現時点での2025年12月期の業績予想は以下のとおりであります。「中期経営計画2026」2024年度実績2025年度予想2026年度目標受注高9,361億円11,300億円12,000億円売上高10,711億円10,900億円11,730億円営業利益率(営業利益)5.1%(551億円)5.5%(600億円)6.8%(800億円)ROIC4.8%5.0%7.0% |
※本記事は「住友重機械工業株式会社」の令和6年12期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

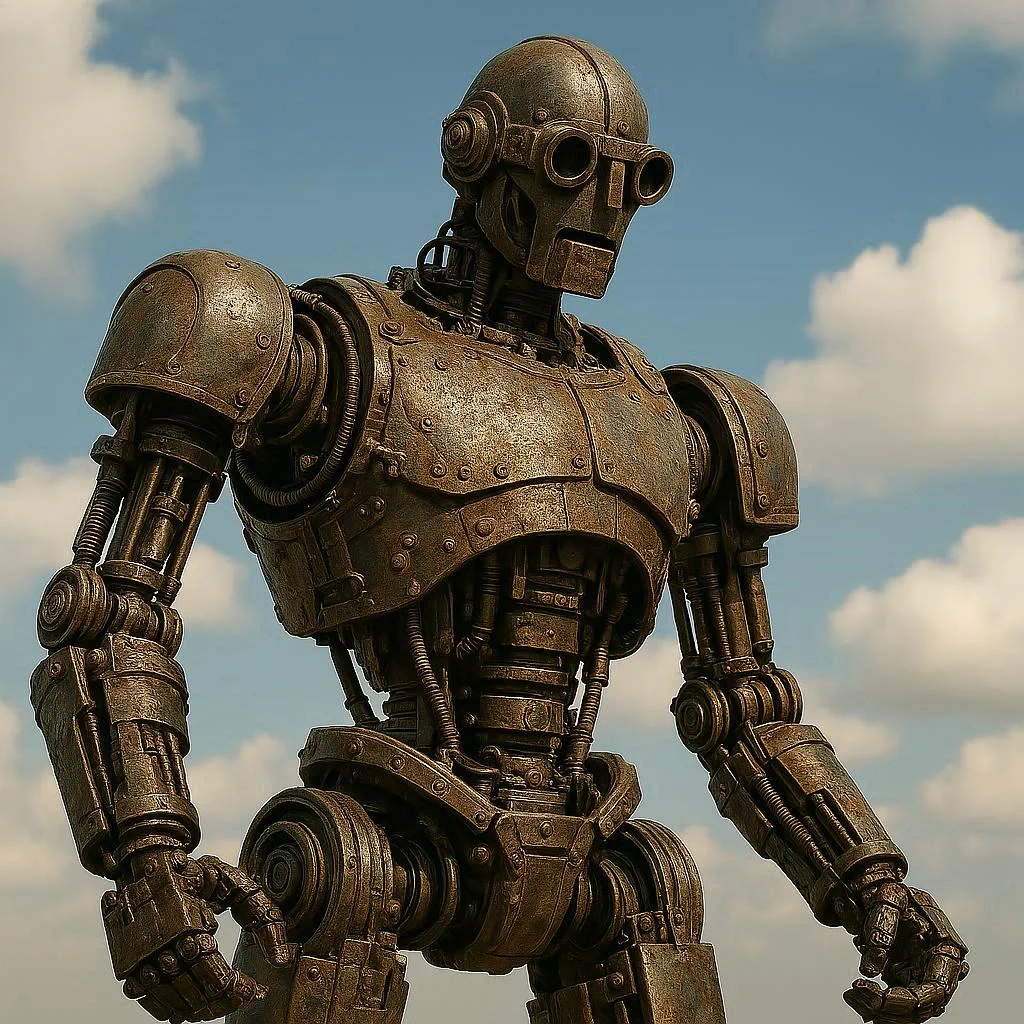

コメント