| 会社名 | 日産自動車株式会社 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 従業員数 | 連132790名 単24413名 |
| 従業員平均年齢 | 41歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 14.7年 |
| 平均年収 | 8956336円 |
| 1株当たりの純資産(連結) | 1419.78円 |
| 1株当たりの純利益(単体) | -187.08円 |
| 決算時期 | 3月 |
| 配当金 | 0円 |
| 配当性向 | 0% |
| 株価収益率(PER) | 5.51倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(連結) | -12.3% |
| 営業活動によるCF | 7536億円 |
| 投資活動によるCF | ▲9712億円 |
| 財務活動によるCF | 2632億円 |
| 研究開発費※1 | 6190億円 |
| 設備投資額※1 | 5773億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 611.1億円 |
| 株主資本比率※2 | 38.2% |
| 有利子負債残高(連結)※3 | 53327.35億円 |
経営方針
| 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】(1) 経営方針及び経営戦略等当社グループは、「人々の生活を豊かに。イノベーションをドライブし続ける。」というコーポレートパーパスを定めた。これは長年にわたり掲げてきた企業ビジョン「人々の生活を豊かに」を踏まえ、創業以来大切にしてきた“他がやらぬことをやる”という精神を引き継ぎながら、日産は何のために存在するか、どのように役割を果たすのか、企業としての存在意義を明確化したものである。そして、サプライヤーや販売会社の皆様との関係をさらに強化し、共にビジネスモデルを発展させていく。グローバルなあらゆる事業活動を通じて企業として成長し、経済的に貢献すると同時に、世界をリードする自動車メーカーとして、社会が直面する課題の解決に貢献することも私たちの使命である。日産は、お客さま、株主、従業員、地域社会などすべてのステークホルダーを大切に思い、将来にわたって価値ある持続可能なモビリティの提供に努める。さらに、持続可能な社会の発展に貢献し、「ゼロ・エミッション」「ゼロ・フェイタリティ」社会を目指し、2050年までに事業活動を含むクルマのライフサイクル全体におけるカーボンニュートラルを実現することを目標としている。この目標に向け、2021年11月には、長期ビジョン「Nissan Ambition 2030」を発表し、2030年度に向けて、当社が進むべき道を示した。2023年度には、第5次中期環境行動計画「ニッサン・グリーンプログラム2030(NGP2030)」、及び2030年度までの社会性の取り組みを包括的に推進する「ニッサン・ソーシャルプログラム2030(NSP2030)」を策定した。日産は事業を通じてサステナビリティ課題の解決に取り組むことで、社会に価値を提供していく。2024年度の当社の状況は、(2) 2024年度の経営環境及び主要な経営指標に記載のとおり、厳しい市場環境に加え、コスト競争力やブランド力などの当社固有の課題によっても厳しいものとなった。このような状況下で、2024年11月以降、今後のビジネス環境の変化にも柔軟かつ機敏に対応できる「スリムで強靭な事業構造」に再構築するための緊急対策として「ターンアラウンド」の取り組みを計画し、進めてきた。そして、2025年4月から新たなマネジメント体制に移行し、当社の新しい経営陣は、「ターンアラウンド」を含む主要な取り組みを慎重に再検討し、2025年5月には、確実に業績を回復させるためのさらなる取り組みである日産経営再建計画「Re:Nissan」を発表した。「Re:Nissan」は、コスト削減、戦略の再定義、パートナーシップの強化を柱とした現実的な実行計画で、2024年度の実績比で、固定費と変動費を計5,000億円削減し、2026年度までに自動車事業における営業利益とフリーキャッシュフローの黒字化を目指す。 <変動費の削減>2026年度までに2,500億円の変動費の削減を目指す(2024年度実績比)・エンジニアリングとコスト効率の向上TdC (Total delivered Cost) トランスフォーメーションチーフの下に各部門から集められた約300人のエキスパートで構成するTdC改革オフィスを設置し、コストに関する意思決定を行う。先行開発や2026年度以降の商品開発に、開発期間を短縮するプロセスを迅速に適用することで、商品の投入を遅らせることなく、開発に関わる3,000人の従業員を一時的に配置転換し、コスト削減活動に集中的に取り組む。<固定費の削減>2026年度までに2,500億円の固定費の削減を目指す(2024年度実績比)・生産の再編と効率化車両生産工場を2027年度までに17から10の工場に統合し、パワートレイン工場についても見直しを行う。これにより、配置転換や生産シフトの調整に加え、設備投資も削減することで、固定費を削減する。北九州市におけるLFP(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー新工場の建設中止も本取り組みの一部である。・人員の削減2024年度から2027年度にかけて計20,000人の人員削減を行う(生産部門、一般管理部門、契約社員も含むR&D部門の直接員と間接員)。販売費と一般管理費においても、シェアードサービスの範囲を拡大し、マーケティングの効率向上を推進する。・開発の刷新エンジニアリングコストの削減や開発スピードの向上を図るため、開発のプロセスを刷新する。グローバルでR&Dのリソースの合理化を通じて、平均の労務費単価を20%削減することを目指す。部品種類を70%削減するとともに、プラットフォームの統合と最適化を進め、プラットフォームの数を2035年度までに現在の13から7に減少させる。また、リードモデルの開発期間を37ヶ月、後続モデルの開発期間を30ヶ月へと大幅に短縮する取り組みを進めている。 <市場戦略と商品戦略の再定義>商品戦略は市場とブランドに焦点を当てて再構築する。革新的な取り組みを加速し、お客さまにより魅力的な商品を届ける。強化される商品ポートフォリオは、HEARTBEATモデルを中心とした3つのカテゴリーで構成される。HEARTBEATモデルは日産のDNAを体現し、コアモデルは台数と収益を重視し、成長モデルは将来の成長に貢献する。これに加えて、パートナーシップモデルが補完する。市場戦略では米国、日本、中国、欧州、中東、メキシコを主要市場として位置付け、他の市場についてはそれぞれの市場要件にあわせたアプローチを行う。その中で、中国・メキシコを輸出拠点として活用する。また、アライアンスパートナーや中国でのパートナーシップを活用してラインアップの拡充を進める。<パートナーシップの強化>当社はパートナーと協働して商品ポートフォリオを補完し、各市場で固有のニーズに応えるモデルを提供する。アライアンスパートナーであるルノー及び三菱自動車工業株式会社とOEM供給等のプロジェクトを継続する。また、本田技研工業株式会社とは、三菱自動車工業株式会社とともに、自動車の知能化・電動化における戦略的パートナーシップの枠組みにおける連携を継続する。 (2) 2024年度の経営環境及び主要な経営指標2024年度は、グローバル自動車市場において、販売競争の激化、急激な為替変動及びインフレーションの影響を受ける厳しい環境が続いた。特に、米国市場では、メキシコからの輸入に対する25%の関税に対する懸念から業界全体の在庫及び販売奨励金が増加傾向であった。米国の現在の政権の関税政策は、日々状況が変わり先行きを見通すことが非常に困難である上に、それに対する各国の対抗措置も重なり、当社にも大きな影響を与えている。中国市場では、バッテリーEV、プラグインハイブリッド車などの新エネルギー車への長期にわたる急激なシフトと、販売競争激化の状況が続いた。さらに、当社固有の課題によっても厳しい状況となった。販売計画が達成できない状況が続き、一般管理費を中心に固定費が増加しているほか、インフレーション、取引先に対する補償費用の発生などにより変動費も増加した。また、モデルミックスの悪化、在庫削減や競争環境に対応するためのインセンティブの増加も収益を圧迫している。また、米国のように、変化するお客さまのニーズに対応した電動車をタイムリーに提供できないことも大きな課題である。その結果、当社グループの当期の経営成績は下記のとおりとなった。当社グループのグローバル小売台数は前年度比2.8%減の334万6千台となり、売上高は12兆6,332億円と前連結会計年度に比べ525億円(0.4%)の減収となった。営業利益は698億円と前連結会計年度に比べ4,989億円(87.7%)の減益となった。また、2025年3月末時点の当社株価は、前年比37.7%減の378円70銭、PBRは0.27倍であった。当社は、2024年4月に発行済株式総数(自己株式を除く)の2.5%の自己株式を取得し、同月にその全株式を消却、また2024年10月に発行済株式総数(自己株式を除く)の5%の自己株式を取得し、同月にその全株式を消却することで、1,393億円の株主還元を実施した。当社は、株主還元と資本効率の向上、財務パフォーマンスの継続的改善、将来の成長のための財務柔軟性の維持に取り組んでいる。 (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題当連結会計年度における事業上及び財務上の対処すべき課題は、次のとおりである。 ・元会長らの不正行為に関連した事項当社の元代表取締役が金融商品取引法違反(虚偽有価証券報告書提出罪)で起訴されるとともに、元代表取締役会長においては会社法違反(特別背任罪)でも起訴された。併せて当社自身も金融商品取引法違反により起訴された。当社はこの事態を重く受け止め、独立第三者及び独立社外取締役で構成されるガバナンス改善特別委員会を設置し、2019年3月27日に同委員会からガバナンスの改善策及び、将来にわたり事業活動を行っていくための基盤となる健全なガバナンス体制の在り方についての提言をまとめた報告書を受領した。これを受け、当社は指名委員会等設置会社へ移行した。当社は、2019年9月9日の取締役会において、監査委員会よりゴーン氏らの不正行為に関する社内調査の報告を受けた。2019年9月9日付の「元会長らによる不正行為に関する社内調査報告について」と題する適時開示に記載したとおり、本報告では、ゴーン氏らによる不正行為を認定している。そのうち、ゴーン氏の会社資産の私的流用等及び販売代理店に対する奨励金支払いに関する不適切な行為は、以下のとおりである。2019年9月9日以降、当有価証券報告書提出日時点において、下記の内容に特段の変更は生じていない。今後、下記の内容に重要な進展が生じた場合には、法令等に基づき開示する。 A) ゴーン氏の会社資産の私的流用等ゴーン氏は、以下を含む様々な方法で当社の資産を私的に流用した。・将来性のある技術に投資するとの名目で子会社Zi-A Capital社を設立させ、同社の投資資金のうち約2,700万米ドルを、ブラジル(リオデジャネイロ)及びレバノン(ベイルート)所在のゴーン元会長個人のための住宅の購入に流用したほか、会社資金で秘密裏に購入又は賃借した住宅を私的に利用した。・2003年から10年以上にわたり、実体のないコンサルティング契約に基づくコンサルタント報酬名目で実姉に合計75万米ドルを超える金銭を支払った。・コーポレートジェットを自身及び家族の私的用途に使用した。・会社の資金を家族の旅費支払いや、個人的な贈答品支払いなどに充てた。・業務上の必要性がないにもかかわらず自身の出身国の大学への200万米ドルを超える寄付を会社資金で行わせた。・2008年、ゴーン氏は個人的に締結した為替スワップ契約のもと約18億5,000万円の含み損を抱え、事実と異なる取引内容を取締役会に説明したうえ為替スワップ契約を当社に承継させて、かかる含み損を当社に承継させた(金融当局の指摘を受け、2009年、当該為替スワップ契約は秘密裏にゴーン氏の関連企業に再承継された)。・2018年4月以降、三菱自動車工業株式会社との間で設立した合弁会社であるNissan-Mitsubishi B.V.(以下「NMBV」)から、給与・契約金名目での取締役会決議を欠く支払い合計780万ユーロを受領した。 B) 販売代理店に対する奨励金支払いに関する不適切な行為ゴーン氏は、国外の知人から私的な資金援助を得ていることを当社取締役会及び関係部署に秘したまま、当社子会社から当該知人の経営する企業に対し、自身とその直属の特定少数の部下が承認すれば金銭支出が可能となる予備費予算(CEOリザーブ)を使用して、特別ビジネスプロジェクト費用などの名目で合計1,470万米ドルの支払いを行わせた。また、国外の販売代理店の関係者からゴーン氏自身又はその関係企業に対して数千万米ドルの支払いがなされていることを当社取締役会及び関係部署に秘したまま、当社子会社から当該販売代理店に対し、CEOリザーブを使用して、販売奨励金名目で合計3,200万米ドルの支払いを行わせた。 金融庁長官から、2019年12月13日付で審判手続開始決定通知書を受領した。これにつき、当社は、課徴金に係る事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を2019年12月23日に提出した。その後、2020年2月27日付で金融庁長官から24億2,489万5,000円の課徴金納付命令の決定の送達を受けた。 2022年3月3日、当社は東京地方裁判所から金融商品取引法違反(虚偽有価証券報告書提出罪)により、罰金2億円に処するとの有罪判決を受けた。当社は、当社に対する当該判決を厳粛に受け止め、判決の主文並びに理由として述べられた事項を慎重に検討した結果、当該判決に対する控訴を行わないことを決定した。その後、当社及び検察官のいずれも刑事訴訟法が定める控訴期間内に控訴しなかったため、当該判決は確定した。上記課徴金に関して、金融商品取引法第185条の8第6項の規定に基づき、当該刑事裁判の判決による罰金額である2億円を控除し、課徴金の総額を22億2,489万5,000円に変更する処分が2022年4月26日付で行われた。当該課徴金については、すでに全額納付済である。 また、ゴーン氏がNMBV及び他の当社の子会社に対してアムステルダム地方裁判所に提起した不当解雇訴訟において、NMBVは、ゴーン氏がNMBVから不正に着服した資金の返還を求めゴーン氏に対し反対請求を提起した。アムステルダム地方裁判所は、2021年5月20日に出された判決においてゴーン氏の請求を棄却し、ゴーン氏に対し約500万ユーロの返還を命じたが、ゴーン氏は2021年8月20日に控訴状をアムステルダム高等裁判所に提出した。その後NMBVが提出した交差控訴及び防御の結果、2022年8月23日にアムステルダム高等裁判所による判決が出され、ゴーン氏の請求は大部分が棄却されるとともに、ゴーン氏に対し約420万ユーロの返還が命じられた。上告期限の経過により判決は確定した。 ゴーン氏による会社資金の不正使用により購入された住居の一部については、売却が完了している。 当社は、既に英領バージン諸島においてゴーン氏及びその関係者を相手に、豪華ヨットに対する仮処分命令を申立て、同命令を得た上で、損害賠償等を求めて訴訟を提起し、また日本国内においても、2020年2月12日にゴーン氏に対し、2022年1月19日に当社元代表取締役ケリー氏に対し、損害賠償請求訴訟を提起しているが、本社内調査結果を踏まえ、今後も、ゴーン氏らの責任を明確にすべく、ゴーン氏らの法令違反や不正行為によって被った損害の回復のため法的措置を含めた必要な対応をとっていく方針である。 指名委員会の選出による経営層の新体制が2019年12月に発足、内部監査による監督機能を強化したこと、などに見られるように、種々の再発防止策に取り組んでいる。当社は、2020年1月16日に東京証券取引所に提出した改善状況報告書に記載した改善措置の継続的実施を含め、これからも必要な改善を随時検討するなど、引き続きガバナンスの向上に努めるとともに、企業風土の改革、企業倫理の再構築、企業情報の適切な開示、コンプライアンスを遵守した経営に努めていく所存であることを表明している。 ・公正取引委員会からの勧告に関連した事項2024年3月7日、当社は公正取引委員会から、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」という。)の適用対象となる事業者との取引に関して、下請法に基づく勧告を受けた。これは、当社が、下請法の適用対象となる事業者36社との取引において、当該事業者から割戻金を受け取った行為の一部が、下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の違反と判断されたものである。本勧告において下請代金の減額に該当すると判断された割戻金の総額は、2021年1月から2023年4月までの約30億円である。当社は、本勧告の対象下請事業者に対して、下請代金の減額に該当すると判断された金額を返金するとともに、割戻金の運用自体も廃止した。当社は、本勧告を大変重く受け止めている。サプライヤーの皆様との強固な信頼関係なくして双方の事業の発展は成し得ない。法令の遵守状況についての定期的な点検、並びに役員や下請取引に関わる従業員への教育の徹底及び定期的な研修の実施などを通じて、法令遵守体制を強化するとともに、再発防止策の徹底に取り組み、取引適正化を図っており、2025年3月5日に改善報告書を公正取引委員会に提出した。取引先との関係を強化し、双方に価値を創造し、法令遵守の徹底のための更なる取り組みの一環として、法令違反の疑いなどがある場合に、取引先から匿名で意見を集約するホットラインを外部に設置している。さらに、モノづくり部門、並びに、関連部署の担当者からなる社長直轄の「パートナーシップ改革推進室」を新設した。このチームは、積極的に取引先のもとに足を運び、懸念事項を正しく理解し、頂いた声を速やかに社内にフィードバックして、必要な対応を迅速に講じることができるようにしている。各部署の通常窓口に加え、2つのルートを設けることで、取引先の状況把握、法令遵守の徹底を図っている。 |
経営者による財政状態の説明
| 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1) 経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概況は次のとおりである。 ① 財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度のグローバル全体需要は前連結会計年度に比べ3.3%増の8,730万台となった。当社グループのグローバル小売台数は前連結会計年度に比べ2.8%減の334万6千台となった。売上高は12兆6,332億円となり、前連結会計年度に比べ525億円(0.4%)の減収となった。営業利益は698億円となり、前連結会計年度に比べ4,989億円(87.7%)の減益となった。営業外損益は1,404億円の利益となり、前連結会計年度に比べ69億円の増益となった。経常利益は2,102億円となり、前連結会計年度に比べ4,920億円(70.1%)の減益となった。特別損益は6,238億円の損失となり、前連結会計年度に比べ5,209億円の悪化となった。税金等調整前当期純損失は4,136億円となり、前連結会計年度に比べ1兆128億円の悪化となった。親会社株主に帰属する当期純損失は6,709億円となり、前連結会計年度に比べ1兆975億円の悪化となった。 ② キャッシュ・フローの状況当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により7,537億円増加、投資活動により9,712億円減少、財務活動により2,633億円増加した。また、現金及び現金同等物に係る換算差額により256億円増加した結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末残高に対し713億円(3.4%)増加の2兆1,975億円となった。 ③ 生産、受注及び販売の状況a.生産実績会社所在地生産台数(台)増減前年同期比前連結会計年度当連結会計年度(台)(%) 日 本724,838641,348△83,490△11.5% 米 国605,652500,434△105,218△17.4% メキシコ607,089664,56157,4729.5% 英 国325,458276,336△49,122△15.1% タ イ93,60563,435△30,170△32.2% インド124,627152,01727,39022.0% 南アフリカ25,13610,425△14,711△58.5% ブラジル58,76161,1712,4104.1% アルゼンチン29,64617,698△11,948△40.3% エジプト12,08421,1549,07075.1%合計2,606,8962,408,579△198,317△7.6% (注) 台数集約期間は2024年4月から2025年3月までである。 b.受注状況当社グループの受注生産は僅少なので受注状況の記載を省略する。 c.販売実績(小売り)仕向地販売台数(小売台数:台)増減前年同期比前連結会計年度当連結会計年度(台)(%) 日本 484,195460,868△23,327△4.8% 北米 1,262,1101,303,23641,1263.3% 内、米国915,712938,35822,6462.5% 欧州 361,372350,957△10,415△2.9% アジア910,055793,425△116,630△12.8% 内、中国793,768696,631△97,137△12.2% その他 424,525437,76213,2373.1%合計 3,442,2573,346,248△96,009△2.8% (注) 1 台数集約期間は、アジアに含まれる中国、台湾は2024年1月から2024年12月まで、日本、北米、欧州、その他、並びに中国、台湾を除くアジアは2024年4月から2025年3月までである。2 中国には合弁会社である東風汽車有限公司の販売台数が含まれる。 d.販売実績(連結売上)仕向地販売台数(連結売上台数:台)増減前年同期比前連結会計年度当連結会計年度(台)(%) 日 本 473,517438,659△34,858△7.4% 北 米 1,340,5871,302,898△37,689△2.8% 内、米国977,028911,819△65,209△6.7% 欧 州 363,926336,862△27,064△7.4% アジア153,669132,262△21,407△13.9% 内、中国8210△821△100.0% その他 453,915445,911△8,004△1.8%合計 2,785,6142,656,592△129,022△4.6% (注) 1 台数集約期間は、アジアに含まれる中国、台湾は2024年1月から2024年12月まで、日本、北米、欧州、その他、並びに中国、台湾を除くアジアは2024年4月から2025年3月までである。2 中国には合弁会社である東風汽車有限公司の販売台数が含まれない。 (2) 経営者の視点による経営成績の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであり、原則として連結財務諸表に基づいて分析したものである。なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在において当社グループが判断したものである。 ① 重要な会計方針及び見積り当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成している。この連結財務諸表の作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とする。経営者は、これらの見積りについて過去の実績や現状等を勘案し合理的に判断しているが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合がある。連結財務諸表を作成するにあたって、重要な見積りは以下のとおりである。なお、「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴い、翌連結会計年度に重要な影響を及ぼす可能性のある一部の項目については、第5[経理の状況]の1[連結財務諸表等]の(重要な会計上の見積り)に記載している。 a.製品保証引当金当社グループは、製品のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、保証書の約款に従い、類似の費用特性を有する製品グループごとに保証経過期間における発生費用総額に対して、過去実績に基づく保証期間内の費用発生パターンを見積もり、引当金を算定している。当社グループは、製品の安全を最優先課題として、研究開発・製造から販売サービスまで最善の努力を傾けているが、実際の製品の不具合等により発生した保証費用の発生パターンの実績が見積りと乖離した場合、引当金の追加計上が必要となる可能性がある。b.退職給付費用当社グループの従業員の退職給付に備えるための退職給付費用及び債務は、割引率、退職率及び死亡率などの年金数理計算上の基礎率及び年金資産の長期期待運用収益率に基づき算出されている。ただし、国際財務報告基準(IFRS)を適用している在外子会社においては、年金資産の期待運用収益率ではなく、利息純額として年金数理計算上の割引率と同じ指標が用いられている。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、その影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認識される費用及び債務に影響を与える可能性がある。 ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容当社グループの当連結会計年度における経営成績及び財政状態の状況に関する認識及び分析・検討結果は、次のとおりである。(業績)a.売上高連結売上高は前連結会計年度に対し525億円(0.4%)減少し、12兆6,332億円となった。これは主に、為替変動による増益影響はあったものの、販売台数の減少によるものである。b.営業利益連結営業利益は698億円となり、売上高営業利益率は0.6%となった。前連結会計年度の5,687億円の利益に対し4,989億円(87.7%)の減益となった。これは主に、販売台数の減少、販売奨励金の増加及びインフレーションによるものである。c.営業外損益連結営業外損益は1,404億円の利益となり、前連結会計年度の1,334億円の利益に対し、69億円の増益となった。d.特別損益連結特別損益は6,238億円の損失となり、前連結会計年度の1,029億円の損失に対し、5,209億円の悪化となった。これは主に、減損損失及びリストラクチャリング費用の計上によるものである。e.法人税等法人税等は2,465億円となり、968億円(64.7%)の増加となった。f.親会社株主に帰属する当期純利益親会社株主に帰属する当期純損失は6,709億円となり、前連結会計年度に比べ1兆975億円の悪化となった。 (事業セグメント)a.自動車事業当社グループのグローバル小売台数は334万6千台となり、前連結会計年度に比べ9万6千台(2.8%)の減少となった。日本国内では前連結会計年度に比べ4.8%減の46万1千台、メキシコとカナダを含む北米では前連結会計年度に比べ3.3%増の130万3千台、欧州では前連結会計年度に比べ2.9%減の35万1千台、中国では前連結会計年度に比べ12.2%減の69万7千台、その他地域では前連結会計年度に比べ1.2%減の53万5千台となった。自動車事業の売上高(セグメント間の内部売上高を含む)は11兆6,455億円となり、前連結会計年度に比べ1,370億円(1.2%)の減収となった。営業損失は2,680億円となり、前連結会計年度に比べ4,896億円の悪化となった。これは主に、販売台数の減少、販売奨励金の増加及びインフレーションによるものである。なお、当連結会計年度におけるセグメント間の取引消去額を含む自動車事業の営業損失は2,158億円となった。 b.販売金融事業販売金融事業の売上高(セグメント間の内部売上高を含む)は1兆2,621億円となり、前連結会計年度に比べ1,003億円(8.6%)の増収となった。営業利益は2,856億円となり、前連結会計年度に比べ231億円(7.5%)の減益となった。これは主に、為替変動による増益影響はあったものの、クレジットロスの正常化及び金利上昇に伴う資金調達コストの増加によるものである。 (地域セグメント)a.日本日本国内市場の全体需要は前連結会計年度に比べ1.0%増加し458万台となった。当社グループの小売台数は前連結会計年度に比べ4.8%減の46万1千台となり、市場占有率は前連結会計年度に比べ0.6ポイント減の10.1%となった。この結果、日本地域におけるセグメント間の内部売上高を含む売上高は4兆8,581億円と、前連結会計年度に比べ898億円(1.8%)の減収となった。営業利益は1,337億円となり、前連結会計年度に比べ256億円(23.7%)の増益となった。これは主に、国内販売及び輸出台数の減少はあったものの、為替変動の影響によるものである。b.北米メキシコとカナダを含む北米市場の全体需要は前連結会計年度に比べ3.0%増加し1,936万台となり、当社グループの小売台数は前連結会計年度に比べ3.3%増の130万3千台となった。一方で、北米地域におけるセグメント間の内部売上高を含む売上高は7兆1,669億円と、前連結会計年度に比べ1,124億円(1.5%)の減収となった。営業損失は383億円となり、前連結会計年度に比べ3,728億円の悪化となった。これは主に、モノづくりコストの減少はあったものの、販売奨励金の増加及びインフレーションによるものである。米国市場の全体需要は前連結会計年度に比べ2.2%増加し1,602万台となった。当社グループの小売台数は前連結会計年度に比べ2.5%増の93万8千台となり、市場占有率は前年同水準の5.9%となった。c.欧州ロシアを含む欧州市場の全体需要は前連結会計年度に比べ4.7%増加し1,712万台となった。当社グループの小売台数は前連結会計年度に比べ2.9%減の35万1千台となり、市場占有率は前連結会計年度に比べ0.1ポイント減の2.0%となった。この結果、欧州地域におけるセグメント間の内部売上高を含む売上高は1兆7,886億円と、前連結会計年度に比べ819億円(4.4%)の減収となった。営業損失は988億円となり、前連結会計年度に比べ814億円の悪化となった。これは主に、モノづくりコストの減少はあったものの、販売奨励金の増加及びインフレーションによるものである。d.アジアアジア市場の小売台数(中国を除く)は前連結会計年度に比べ16.8%減の9万7千台となった。アジア地域におけるセグメント間の内部売上高を含む売上高は1兆6,475億円と、前連結会計年度に比べ397億円(2.5%)の増収となった。営業利益は573億円となり、前連結会計年度に比べ519億円(47.6%)の減益となった。これは主に、タイの輸出台数の減少及び中国における販売金融事業の収益悪化によるものである。中国市場の全体需要は、前連結会計年度に比べ1.6%増加し2,514万台となった。当社グループの小売台数は前連結会計年度に比べ12.2%減の69万7千台となり、市場占有率は前連結会計年度に比べ0.4ポイント減の2.8%となった。これは主に、価格競争の激化及びICE車から新エネルギー車へのシフトが加速したことによるものである。なお、合弁会社である東風汽車有限公司の業績は、持分法による投資損益として営業外損益に計上している。 e.その他大洋州、中近東、南アフリカ、メキシコを除く中南米等における当社グループの小売台数は、前連結会計年度に比べ3.1%増の43万8千台となった。中南米市場の小売台数は前連結会計年度に比べ0.1%減の16万7千台、中東市場の小売台数は前連結会計年度に比べ11.1%増の16万9千台、南アフリカ等のアフリカ市場の小売台数は前連結会計年度に比べ0.6%減の5万4千台となった。大洋州、中近東、南アフリカ、メキシコを除く中南米等におけるセグメント間の内部売上高を含む売上高は1兆5,447億円と、前連結会計年度に比べ300億円(2.0%)の増収となった。営業利益は25億円となり、前連結会計年度に比べ248億円(91.0%)の減益となった。これは主に、為替変動の影響及び新車の立ち上げ費用によるものである。 (資本の財源及び資金の流動性についての分析)当社グループは、グローバルに展開するグループ会社の資金状況を当社にて一括管理し、グループの資金効率を高めている。当社グループの資金需要としては、自動車事業における研究開発費及び設備投資と、販売金融事業における金融資産の取得原資などがある。これらの必要資金を安定的に確保するため、運転資金効率の改善を含めた自動車事業の営業キャッシュ・フローの向上やグループ内の余剰資金の活用により、内部資金を最大限に利用している。また、外部調達としては、銀行借入やコマーシャル・ペーパー及び社債の発行のほか、販売金融事業ではリースを含む保有金融債権の流動化も行い、各地域での金融市場の特性や状況に応じて調達手法を最適に組み合わせることで、低コストでの資金調達を実現している。なお、研究開発費及び設備投資については、電動化、モビリティ革新、グローバルなエコシステムの構築といった重点分野に集中して投入している。また、販売金融事業における自動車ローンや自動車リースを中心とした金融資産の取得については、常に資産の質を重視して管理している。株主への配当については、収益及びキャッシュ・フロー等の状況を総合的に勘案し決定している。流動性について、当社グループは、継続的な事業運営のための資金調達や満期債務の返済に加えて、地政学的リスクや金融市場の想定外の変化にも対応できるよう、常に十分な流動性の確保を図っている。2025年度の自動車事業における満期債務は合計7,083億円あり、金融市場の状況に応じて適切なリファイナンス手段を検討する。2025年3月末の自動車事業のネットキャッシュは1兆4,984億円と潤沢であるものの、様々なマーケット変化に対応すべく、当社グループは従来から世界の主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、販売金融事業による資産担保コマーシャル・ペーパー発行枠を含む未使用のコミットメントラインとして2025年3月末時点で2兆1,125億円を自動車事業と販売金融事業を合わせたグループ全体で保有している。また、2025年3月末時点での自動車事業における手元資金は2兆1,598億円である。これらにより当社グループの流動性は十分に高い水準にあると考えている。販売金融事業は一貫して利益をあげており、親会社の自動車事業へ配当を分配している。2024年度には、販売金融事業は3,261億円の配当を自動車事業へ分配しており、2020年度から2023年度までの累計配当額は8,067億円となっている。当社グループによる無担保資金調達に係わるコスト及びその発行の可否は、一般に当社グループに関する信用格付及びマーケット環境によっている。ムーディーズ(Moody’s)、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)、フィッチ・レーティングス(Fitch Ratings)及び格付投資情報センター(R&I)による2025年6月6日時点での当社の長期信用無担保格付は以下のとおりである。これら国内外格付機関によって当社の長期信用無担保格付が引き下げられているものの、当社グループは銀行借入や社債等に加えて、長期信用無担保格付の引き下げに左右されにくい資金調達手段であるリースを含む保有金融債権の流動化を通じた資金調達も検討している。なお、これらの格付は当社グループの債券の売買・保有を推奨するものではない。また、当社グループの無担保金融債務やコミットメントラインについて、格付の見直しにより強制的に返済の必要が生じたり新たな借入が制限される条件が付されているものはない。 Moody’sS&PFitch RatingsR&I長期格付Ba2BBBBA- なお、当社グループは、事業の中核と位置付けているサステナビリティの推進に必要となる資金を調達するため、2022年7月にサステナブル・ファイナンス・フレームワークを策定し、フレームワークに基づき2022年度に資金調達を行った。また、本フレームワークは2024年7月に更新されている。本フレームワークを通じて調達した資金は、バッテリーを含む電動車の開発や生産、EVエコシステム・スマートシティの実現に向けた技術開発やインフラ整備、より安全で持続可能なモビリティの開発など、幅広い取り組みに使用されている。 なお、当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前連結会計年度に対するキャッシュ・フローの増減は以下のとおりである。 営業活動営業活動による収入は7,537億円となり、前連結会計年度の9,609億円の収入に比べて2,072億円減少した。これは主として、運転資本の改善があった一方で、自動車事業の収益の減少によるものである。投資活動投資活動による支出は9,712億円となり、前連結会計年度の8,127億円の支出に比べて1,586億円増加した。これは主として、設備投資が増加したことによるものである。財務活動財務活動による収入は2,633億円となり、前連結会計年度の1,316億円の支出に比べて3,948億円の収入の増加となった。これは主として、短期借入金による資金調達が増加したことによるものである。なお、当連結会計年度における自動車事業のフリーキャッシュフローは前連結会計年度に比べ5,658億円悪化し、2,428億円のマイナスとなった。また、当連結会計年度末における自動車事業のネットキャッシュは1兆4,984億円となり、前連結会計年度末から476億円減少した。 セグメント別の内訳は以下のとおりである。前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(百万円) 自動車事業及び消去販売金融事業連結計営業活動によるキャッシュ・フロー698,060262,839960,899投資活動によるキャッシュ・フロー△375,028△437,636△812,664小計:フリーキャッシュフロー323,032△174,797148,235財務活動によるキャッシュ・フロー△298,193166,642△131,551 当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(百万円) 自動車事業及び消去販売金融事業連結計営業活動によるキャッシュ・フロー157,456596,231753,687投資活動によるキャッシュ・フロー△400,272△570,955△971,227小計:フリーキャッシュフロー△242,81625,276△217,540財務活動によるキャッシュ・フロー365,016△101,765263,251 対前年度増減(百万円) 自動車事業及び消去販売金融事業連結計営業活動によるキャッシュ・フロー△540,604333,392△207,212投資活動によるキャッシュ・フロー△25,244△133,319△158,563小計:フリーキャッシュフロー△565,848200,073△365,775財務活動によるキャッシュ・フロー663,209△268,407394,802 |
※本記事は「日産自動車株式会社」の令和7年3月期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

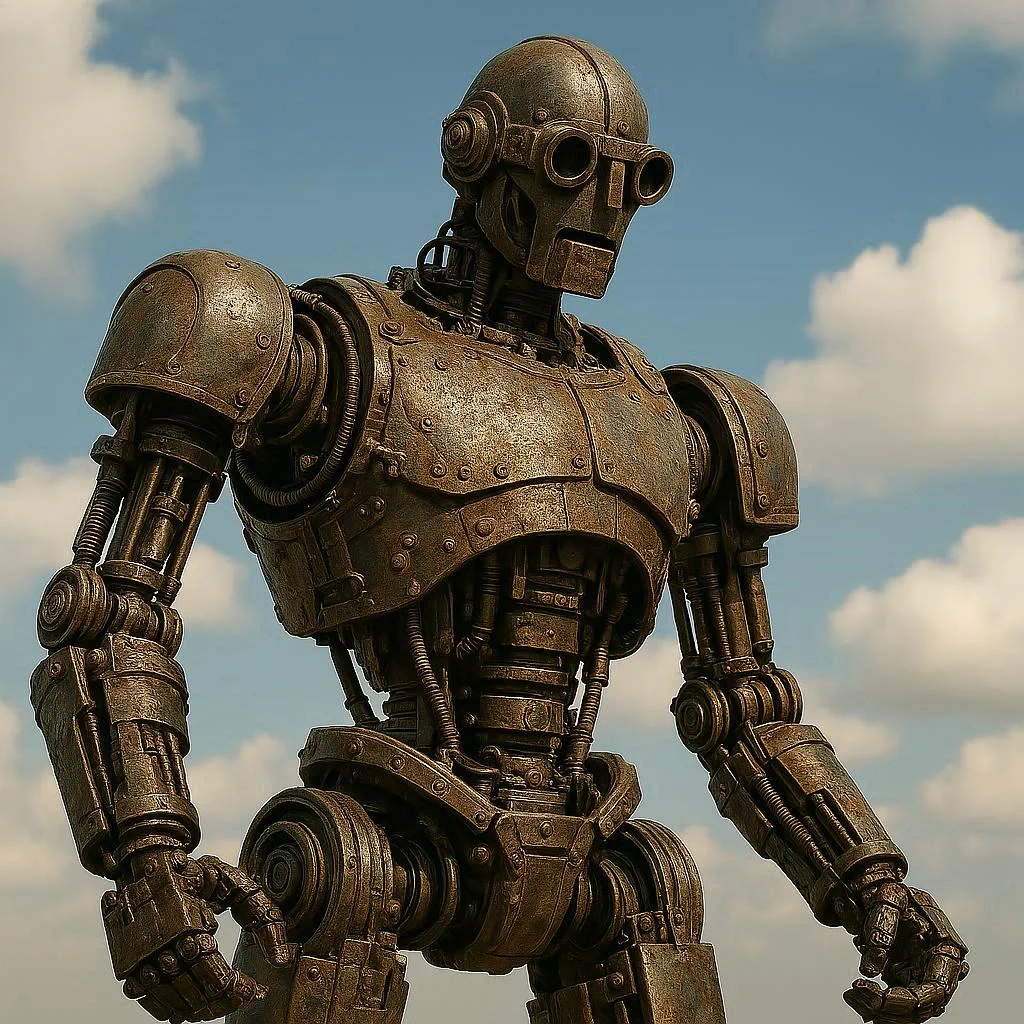


コメント