| 会社名 | 三菱自動車工業株式会社 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 従業員数 | 連28572名 単13570名 |
| 従業員平均年齢 | 42.3歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 15.5年 |
| 平均年収 | 8135000円 |
| 1株当たりの純資産(連結) | 698.28円 |
| 1株当たりの純利益(連結) | 28.7円 |
| 決算時期 | 3月 |
| 配当金 | 15円 |
| 配当性向 | 121.32% |
| 株価収益率(PER) | 14.25倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(連結) | 4.22% |
| 営業活動によるCF | 1747億円 |
| 投資活動によるCF | ▲1147億円 |
| 財務活動によるCF | ▲2747億円 |
| 研究開発費※1 | 1267.48億円 |
| 設備投資額※1 | 1006.27億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 611.1億円 |
| 株主資本比率※2 | 50.5% |
| 有利子負債残高(連結)※3 | 2044.78億円 |
経営方針
| 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 足許の環境変化を踏まえた経営課題の認識と、今後の経営戦略の考え方は次のとおりです。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内包しているため、将来生じうる実際の結果と異なる可能性がありますので、ご留意ください。 自動車業界は、地球温暖化対策としての電動化に加え、AI技術等の進化を取り込み知能化が進むなど、人の移動とモノを運ぶための手段であった自動車の概念が大きく変わり、「100年に一度」の大変革の時代を迎えています。 当社グループは2023年3月に、2023年度から2025年度までの中期経営計画「Challenge 2025」を発表しました。「Challenge 2025」では、これまで行ってきた構造改革による強靭かつ機動的な経営体質を基盤とし、地域や国の独自性に適した事業の拡充を図り、全社的な「手取り改善活動」の継続により、安定的な収益基盤の確立に取り組みました。そのうえで、更なる成長と次の時代へのチャレンジを実現するため、研究開発費や設備投資を安定的に増加させることを計画いたしました。 一方、中期経営計画「Challenge 2025」の発表から2年が経過し、一部に当初想定していた事業環境からの変化が生じ、主要施策の進捗にも差異が出ています。 まず、電動車開発に関しては、昨年来、全世界的に電気自動車(バッテリーEV)の成長が踊り場に差し掛かり、より現実的な環境技術としてプラグインハイブリッド車(PHEV)やハイブリッド車(HEV)が再評価されています。この環境変化を踏まえ、当面、自社製バッテリーEVの開発は見送り、バッテリーEVが必要な市場への対応については、主にパートナーとの協業による商品を活用、当社グループは優位性を持つプラグインハイブリッド車とハイブリッド車の開発に専念することにいたしました。 次に、アセアン地域での新商品連続投入による収益基盤の強化です。アセアン地域は中長期的には成長が期待できる当社グループの重点市場ですが、タイやインドネシアでは景気の冷え込みが継続、想定した市場成長からは大きく乖離した状況となっています。市場が好調なフィリピンや、力強い回復を見せるベトナムでは台数・シェアを大きく伸ばすことができましたが、アセアン全体としては中期経営計画で目論んだ台数・収益目標の達成に遅れが生じています。依然、本格的な景気回復には時間を要する状況と想定されますが、中期経営計画で準備してきた新商品の市場投入が2025年度も続くことから、これら新商品を梃に、アセアン地域の販売伸長を目指していきます。 「三菱自動車らしい」クルマの投入によるブランド力強化に関しては、近年、アセアンなどの新興市場を中心に、中国勢を含む多くの新規ブランドが参入し、競争が激化しています。そのため、従来以上にブランド力の強化が求められています。当社グループは、「三菱自動車らしさ」を具現化したモデルの投入を通じてブランド力を強化してきました。特にホームマーケットである日本では、『デリカミニ』や『トライトン』の投入を契機に、ブランド力が大きく向上し、マーケットシェアも着実に伸ばすことができました。この日本での成功事例を他国にも展開し、グローバルにブランド力を磨いていきます。 今後の商品投入については、クルマの知能化を含めクルマに対する要望が高度化することで、開発工数が増加し、中期経営計画で予定していた新型車の投入に一部遅れが生じましたが、引き続きアセアン戦略車の強化を継続いたします。そして、これら新型車をアセアンだけでなく、中南米・中東やオセアニア、日本へも展開拡大し、これら地域でも収益力向上を図ります。一方、欧米等のグローバルモデルについては、自社開発モデルに加え、様々なパートナーとの協業により、地域に応じたラインナップの強化・拡充を図ります。これにより、経済変動にも柔軟に対応できる強靭なグローバルポートフォリオを築いてまいります。 新事業形態へのチャレンジとしては、フィリピンにおいて新たに販売金融会社「ミツビシ・モーターズ・ファイナンス・フィリピンズ・インク」を設立いたしました。オーストラリアでは、自動車関連金融サービス会社大手の「FLEETPARTNERS GROUP LTD」に出資し、法人向け事業の拡大等、更なる販売台数及び収益拡大を目指します。日本でもスマート充電サービス事業など、新たな取組みを進めています。 資本コストや資本収益性を意識した経営への取組みについては、2024年11月に、資本効率の向上と株主還元の拡充を図ることを目的とし、自己株式の取得及びその一部の消却を実施しております。今後も、資本構造の最適化や株主還元の拡充を図り、企業価値の向上を目指します。 2025年度業績見通しにおいては、中期経営計画で目標とした一部指標を下回る見通しとなっておりますが、環境変化には柔軟に対応しつつも、これらの主要施策を着実に実行し、経営体質の更なる強化と将来に向けた成長の礎を築いてまいります。 今後も、「モビリティの可能性を追求し、活力ある社会をつくります」という当社グループビジョンのもと、お客様や株主様をはじめとしたすべてのステークホルダーの皆様のご期待を超える価値を創造し続けることで、企業価値の向上に取り組んでまいります。 |
経営者による財政状態の説明
| 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。なお、本項において含まれる将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)財政状態及び経営成績の状況① 経営成績当連結会計年度は、タイ・インドネシアの自動車需要回復の遅れや、世界的な車両供給制約が緩和されたことで販売競争が再び激化するなど、当社グループを取り巻く経営環境は厳しさを増しました。そのような環境下において、当社グループは、上期までは、インフレ対応など固定費が増加する中でも、為替の追い風もあり収益を伸ばすことができましたが、下期以降は、当社グループにとってコスト通貨であるタイバーツ独歩高もあり、為替もマイナス影響に転じました。厳しい状況下ではありましたが、新型車を主体とした台数増加を着実に収益に繋げると同時に、費用削減の徹底により、2025年2月に修正した通期業績見通しを上回っての着地となりました。結果、通期販売台数はグローバルで前年度比3%増の84万2千台、通期売上高は前年度比微減の2兆7,882億円となりました。通期営業利益は、1,388億円(前年度比△522億円)となりました。なお、経常利益は986億円(前年度比△1,104億円)、親会社株主に帰属する当期純利益は410億円(前年度比△1,137億円)となりました。 中期経営計画「Challenge 2025」が始まって2年が経過しましたが、この間の自動車業界を取り巻く環境の変化は極めて大きかったと感じております。そのような状況下においても、当社グループの強い領域に徹底的に注力し、自社だけで取り組むことが非効率な領域は、協業パートナー活用を積極的に進めることで、事業基盤の安定性が徐々に高まってきたのではないかと考えております。2025年度の経営環境は、米国の関税措置やこれに伴う各国景気への影響など、自動車業界にとって逆風が強く、不可逆的な変化も予想されます。しかし、引き続き変化に機敏に対応し、現中期経営計画で準備してきた新型車を梃に販売、収益を伸ばすとともに、コスト管理を改めて徹底し、投資においても優先順位を明確につけることで、計画の達成に向けて努めてまいります。なお、2025年度の業績については現段階で全てを見通すことが極めて困難であり、今後の様々な変化に対応するため、適宜見直してまいります。 事業別セグメントの状況は以下のとおりです。 (ⅰ)自動車当連結会計年度における自動車事業に係る売上高は2兆7,578億円(前年度比△138億円)となり、営業利益は1,341億円(前年度比△538億円)となりました。 (ⅱ)金融当連結会計年度における金融事業に係る売上高は466億円(前年度比+86億円)となり、営業利益は42億円(前年度比△2億円)となりました。 ② 財政状態当連結会計年度末の総資産は2兆2,459億円(前期末比△2,086億円)となりました。そのうち現金及び預金は4,525億円(前期末比△2,217億円)となりました。負債合計は1兆2,724億円(前期末比△1,376億円)となり、そのうち有利子負債残高は3,148億円(前期末比△1,776億円)となりました。純資産は9,736億円(前期末比△709億円)となりました。(2)キャッシュ・フローの状況① キャッシュ・フローの基本的な考え方当社は、財務規律を維持しつつ健全で持続可能な成長を図り、企業価値を高めることで、株主の皆様への成果配分を安定的に維持することを基本としており、フリー・キャッシュ・フローをそのための経営管理指標の一つとして設定しております。この考え方に基づき、当社グループにおける自動車の開発・生産・販売等の事業活動における運転資金需要(材料費、人件費、各種経費、金融事業に係る貸付資金等)や、次世代新技術や環境規制対応、生産効率向上に資する設備の維持・更新などの設備投資需要を、毎年当社が新たに生み出すキャッシュ・フローにより賄うことを基本としつつ、必要に応じ過年度までに蓄積した内部資金や金融機関借入等の外部資金を活用しております。 (注)フリー・キャッシュ・フローの算出においては、以下の計算式を使っております。 営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。 ② キャッシュ・フローの状況当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により1,747億円の収入超(前年度比339億円の収入増加)、投資活動により1,148億円の支出超(前年度比241億円の支出減少)、財務活動により2,748億円の支出超(前年度比3,125億円の支出増加)となりました。加えて、現金及び現金同等物に係る為替換算差額による93億円の減少もあり、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末残高に対し2,241億円減少し、4,501億円となりました。なお、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは、599億円の収入超(前年度比580億円の収入増加)となりました。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)営業活動は1,747億円の収入超となりました。この収入超は主として、税金等調整前当期純利益及び減価償却費によるものであります。また、前年度比では、339億円の収入増加となりました。この収入増加は主として、棚卸資産の減少及び仕入債務の増加によるものであります。 (投資活動によるキャッシュ・フロー)投資活動は1,148億円の支出超となりました。この支出超は主として、設備投資の支払によるものであります。また、前年度比では、241億円の支出減少となりました。この支出減少は主として、設備投資の支払減少によるものであります。 (財務活動によるキャッシュ・フロー)財務活動は2,748億円の支出超となりました。この支出超は主として、長期借入金の返済によるものであります。また、前年度比では、3,125億円の支出増加となりました。この支出増加は主として、借入金の返済増加によるものであります。 ③ 資金の流動性及び資金調達当連結会計年度末の連結現預金残高は4,525億円、連結有利子負債残高は3,148億円となりました。また、当社において国内金融機関から2,720億円のコミットメントラインを設定しており、現預金残高にコミットメントラインを加えた流動性は約7,200億円となっております。また、事業環境の悪化による資金需要の増加に備えて、上記の流動性に加え、海外子会社においても資金調達枠を設定し、当社グループの事業の維持拡大、運営に必要な資金の確保に努めております。なお、当社グループは、格付機関である格付投資情報センター及びS&Pから格付を取得しており、本報告書提出時点において、格付投資情報センター:「BBB+」、S&P:「BB+」となっております。 (3)生産、受注及び販売の実績① 生産実績 当連結会計年度における生産実績は次のとおりであります。 当連結会計年度数量(千台)前連結会計年度比(%)国 内47895.8海 外43184.4 アジア41984.2 その他1291.0合計91090.0(注)生産実績は当社及び連結子会社の完成車(国内はKDを含む)の生産台数を示し、他社へのOEM供給及び共同開発車の当社生産分を含んでおります。 ② 受注実績 当社は、大口需要等特別の場合を除き、見込生産を行っております。③ 販売実績 当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。 当連結会計年度前連結会計年度比(%)数量(千台)金額(百万円)数量金額国 内259631,56797.7103.7海 外7022,156,66491.998.9 北米192734,225104.9103.3 欧州31127,06640.459.9 アジア251569,95097.4106.1 オセアニア84321,12294.7100.7 その他143404,29991.2100.8合計9612,788,23293.4100.0 (注)1.販売実績は、外部顧客の所在地別の当社及び連結子会社の完成車及びKDパックの卸売り台数を示しております。 2.国又は地域の区分は、「地理的接近度及び事業活動の相互関連性」によっておりますが、社内管理との整合性を図るため、前連結会計年度まで「欧州」に含めておりましたウクライナ及びカザフスタンを当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。当該変更に伴い、前連結会計年度との比較は、変更後の区分に組み替えた数値で算出しております。 3.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、総販売実績の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。 (4)重要な会計方針及び見積り当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。この連結財務諸表の作成にあたり、連結会計年度末日における資産・負債の計上及び偶発資産・負債の開示、並びに報告期間における収益・費用の計上に影響を与える見積り及び仮定設定を行っております。これらの見積りは、過去の実績や合理的と考えられる方法に基づき行われておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる場合があります。 当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等」の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しておりますが、特に次の重要な会計方針が当社グループの連結財務諸表における重要な判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。なお、市場措置に関する負債、偶発債務(訴訟損失引当金)及び繰延税金資産の回収可能性については、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等」の「重要な会計上の見積り」に記載しております。① 貸倒引当金当社グループは、売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。経済状況の変化等により顧客の財務状態が悪化し、その支払能力が低下した場合には、追加引当が必要となる可能性があります。② 製品保証引当金当社グループは、製品のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、保証書の約款に従い過去の実績を基礎に将来の保証見込みを加味して計上しております。実際の製品不良率又は修理コストが見積りと異なる場合、アフターサービス費用の見積額の修正が必要となる可能性があります。③ 退職給付費用及び債務従業員退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。これらの前提条件には、割引率、将来の報酬水準、退職率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率及び年金資産の長期収益率などが含まれております。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、その影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。④ 投資有価証券の評価当社グループは、価格変動性が高い公開会社の株式と、市場価格のない非公開会社の株式を保有しております。当社グループは、投資有価証券の評価を一定期間ごとに見直し、その評価が取得原価又は減損後の帳簿価額を一定率以上下回った場合、減損処理を実施しております。将来の市況悪化又は投資先の業績不振により、現在の帳簿価額に反映されていない損失又は帳簿価額の回収不能が発生した場合、減損処理の実施が必要となる可能性があります。⑤ 固定資産の減損当社グループは、固定資産の減損会計の適用に際し、生産用資産は主として事業会社単位、販売関連資産は主として事業拠点単位、賃貸用資産及び遊休資産は個々の資産グループとしてそれぞれグルーピングし、各グループの単位で将来キャッシュ・フローを見積もっております。将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回った場合、回収可能価額まで帳簿価額を減額しております。将来この回収可能価額が減少した場合、減損損失が発生し、損益に影響を与えることがあります。 |
※本記事は「三菱自動車工業株式会社」の令和7年3月期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

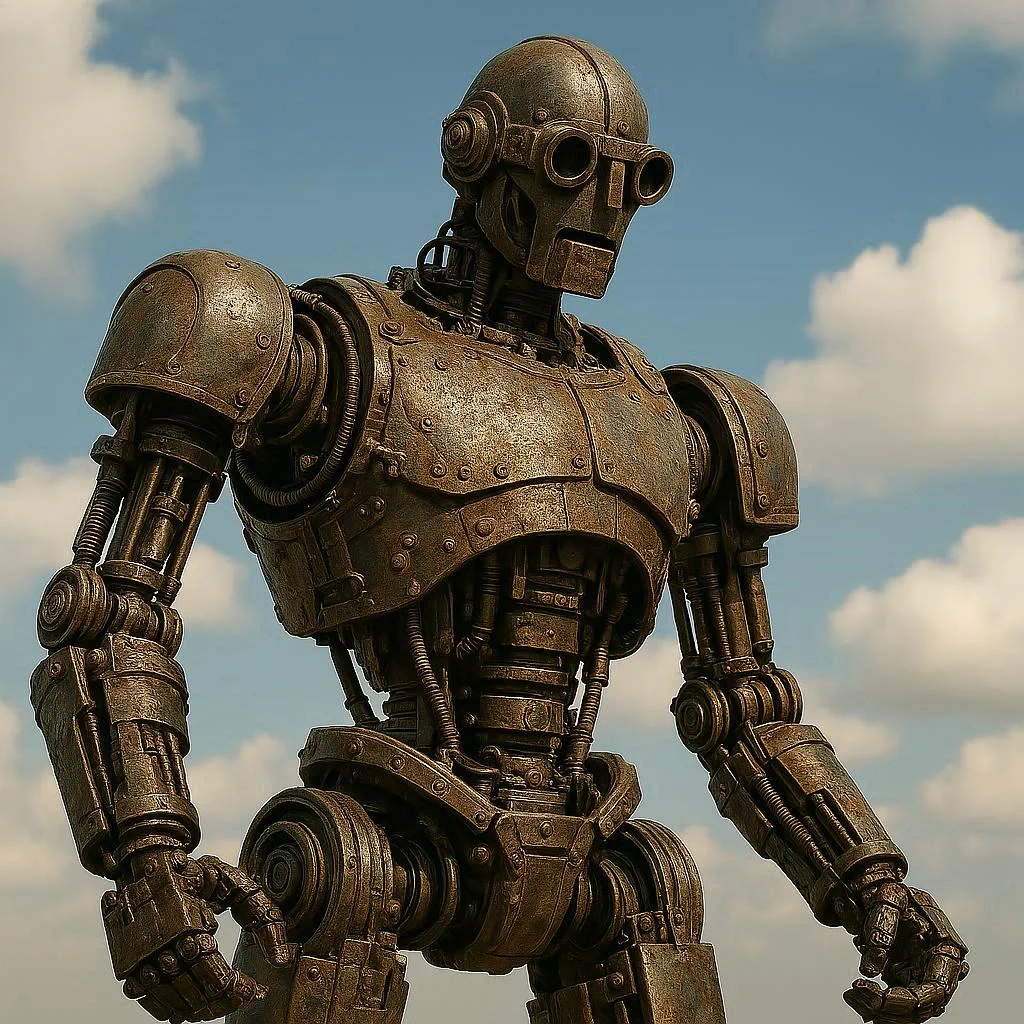

コメント