| 会社名 | 三菱重工業株式会社 |
| 業種 | 機械 |
| 従業員数 | 連77274名 単22347名 |
| 従業員平均年齢 | 42.5歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 18.9年 |
| 平均年収 | 10176595円 |
| 1株当たりの純資産(連結) | 5515.03円 |
| 1株当たりの純利益(連結) | 73.04円 |
| 決算時期 | 3月 |
| 配当金 | 23円 |
| 配当性向 | 64.5% |
| 株価収益率(PER) | 70.82倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(連結) | 6.47% |
| 営業活動によるCF | 5304億円 |
| 投資活動によるCF | ▲1877億円 |
| 財務活動によるCF | ▲1141億円 |
| 研究開発費※1 | 1205.37億円 |
| 設備投資額※1 | 88.26億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 4276.14億円 |
| 株主資本比率※2 | 28.1% |
| 有利子負債残高(連結)※3※4 | 0円 |
経営方針
| 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】以下の記載事項のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものである。 (1)経営方針・経営戦略等①当連結会計年度の経営環境当社グループを取り巻く経営環境は、世界経済は地域により差はあるものの、全体としては底堅い成長を続け、日本経済も、個人消費と設備投資を中心に緩やかに持ち直した。一方、地政学的なリスク、中国経済の低迷に加え、保護主義的な動きの高まりなどで、先行きには不透明感が残る状況となった。かかる経営環境下においても、当社グループは長い歴史の中で培われた技術に最先端の知見を取り入れ、変化する社会課題の解決に挑み、サステナブルで安全・安心・快適な社会と人々の豊かな暮らしの実現に貢献していく。 ②中期経営計画「2024事業計画」2024年4月から開始した中期経営計画「2024事業計画」は、事業成長と収益力の更なる強化の両立に向け、「伸長事業」と「成長領域」を重点領域とし、「ポートフォリオ経営の強化」、「技術・人的基盤の強化」及び「MISSION NET ZEROの推進」に取り組み、その結果、2026年度における「売上収益5.7兆円以上」、「事業利益4,500億円以上(事業利益率8%以上)」、「ROE12%以上」等の目標達成と、安定配当と利益成長に応じた増配による株主還元を進めていく。初年度に当たる当事業年度では、受注、売上、事業利益ともに過去最高となった。特に、「2024事業計画」の目標達成に向けては、伸長事業を中心に旺盛な受注を確保することができた。 ③「MISSION NET ZERO」に向けた取組みサステナブルで安全・安心な社会の実現に向け、MISSION NET ZEROに取り組んでおり、Scope1、2※1のCO2排出量を2030年に2014年比で50%削減するという目標に対して、2024年で47%削減を見込んでいる。これに加え、三原製作所では工場のカーボンニュートラル化を進めており、太陽光発電設備等の既存技術の導入にとどまらず、工場脱炭素化に向けた新たな技術の実証と導入を進めている。また、Scope3※1については当社のバリューチェーン全体からのCO2排出量削減(2019年比で、2030年に50%)が目標であり、この達成に向けて高砂水素パークや長崎カーボンニュートラルパークなどで様々なソリューションの開発・実証を進めている。※1 Scope1は当社のCO2直接排出を、Scope2は主に電気の使用に伴うCO2間接排出を、Scope3はScope1、 Scope2以外の当社バリューチェーン全体でのCO2間接排出を示す。算定基準は温室効果ガス(GHG) 排出量の算定と報告の国際基準であるGHGプロトコルに準じる。 (2)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題当社グループは、当社を取り巻く環境の不確実性に備えつつ、様々な変化に柔軟に対応し、新たな事業機会を着実に捉えていく必要がある。このため、従来の取組みの継続に加え、新たな価値を創造することで社会の進歩に貢献していくことを経営目標に掲げ、これを実現するために、「Innovative Total Optimization」(ITO)という新たな考え方を実践する。具体的には、基盤技術の組合せによって社会や顧客のバリューチェーンを革新する製品・サービスを創出することで事業領域を拡大する。また、縦のバリューチェーンと横の事業部間の連携を強化してシナジー効果を追求することで、全体最適による生産性の向上・収益力強化を実現する。こうした取組みを通じて、「2024事業計画」で掲げた事業成長と収益力の更なる強化の両立に向けた各種施策をより力強く推進していく。 ①伸長事業の着実な遂行エネルギー、原子力、防衛の分野は、旺盛な需要を受け、多くの受注を確保している。計画したQCD(品質・コスト・納期)で顧客に届けるため、人的リソースを拡充し、生産能力強化・生産性向上を図るとともに、サプライチェーンを強化する。また、将来を見据えた研究開発・設備投資も積極的に実施して、大きな成長実現の布石とする。エネルギー分野のガスタービンでは、海外拠点も含めた生産能力増強やサプライチェーンの強靭化、工場の自動化・IT化を推進する。また、発電効率向上のための技術開発に取り組むとともに、水素・アンモニア焚きガスタービンに関しては経済性や燃料供給インフラの状況を考慮し実証を進める。原子力分野では、プラントの新設を見据えた生産設備の更新や高機能化と、革新軽水炉開発等を更に推進する。防衛分野では、組織横断タスクフォースにより生産効率向上、サプライヤー支援及び物流改善等の増産準備を進めるとともに、将来事業の創出に向けた技術開発を加速する。 ②成長領域の事業化推進需要が拡大しているデータセンターでは、当社が強みを持つ電源・冷却・制御に関する幅広い製品とエンジニアリングを統合して最適なソリューションを提供する。これにより、ユーティリティの安定稼働等に貢献していく。また、水素・アンモニア・CCUS※2の分野では、各国の市場・政策動向を踏まえたエナジートランジションへの備えとして、世界最高クラスの経済性を持つ製品を提供するために、案件組成・研究開発を推進していく。CCUSの関係では、関西電力姫路第二発電所内に新設したCO2回収パイロットプラントでの実証を進める。また、現地工事の効率化・省力化や工期短縮を可能とする小型CO2回収装置の市場投入を進める。さらには、ExxonMobil社との次世代CO2回収技術に関する研究開発を加速する。水素・アンモニアの関係では、SAF※3や合成燃料製造にも繋がる高効率な水素製造装置であるSOEC※4の開発を促進する。※2 Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage(二酸化炭素回収・利用・貯留)※3 Sustainable Aviation Fuel(持続可能な航空燃料)※4 Solid Oxide Electrolysis Cell(高温水蒸気電解) ③DXの活用等当社グループでは、デジタル・プラットフォーム「ΣSynX」(シグマシンクス)を活用して事業分野を跨ぐ製品群を「かしこく・つなぐ」ことで、事業競争力強化に取り組んでいる。新しい事業機会開拓のため、更にデジタル技術を活用し、サービスの高度化を図っていく。例えば、画像監視プラットフォーム「ΣSynX Supervision」によるO&M※5の高度化や、発電プラントの配管画像のデータ処理により、プラントの安定運用に貢献する。一方で、デジタルイノベーションを加速するための教育プログラムの充実等による人材育成を進める。また、デジタル技術で可視化した熟練技能を技能伝承に活用するなど、技術・人的基盤の強化も図っていく。※5 Operation & Maintenance(運転・保守) 当社グループは、以上の諸施策を通じ、社会課題の解決によってサステナブルな社会の実現に貢献していく。このように事業を発展し成長させていく上では、従来同様コンプライアンスが大前提であるとの認識の下で各種施策を進めていく。 |
経営者による財政状態の説明
| 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりである。次の記載事項のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものである。なお、当連結会計年度から、セグメントの区分を変更しており、以下の前連結会計年度との比較は、前連結会計年度の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較している。 (1)財政状態の状況の概要及びこれに関する分析・検討内容当連結会計年度における当社グループの資産は、「現金及び現金同等物」及び「棚卸資産」の増加等により、前連結会計年度末から4,026億65百万円増加の6兆6,589億24百万円となった。負債は、「契約負債」の増加等により、前連結会計年度末から2,934億96百万円増加の4兆1,891億1百万円となった。資本は、親会社の所有者に帰属する当期利益の発生等による「利益剰余金」の増加等により、前連結会計年度末から1,091億68百万円増加の2兆4,698億23百万円となった。以上により、当連結会計年度末の親会社所有者帰属持分比率は35.2%(前連結会計年度末の35.9%から△0.7ポイント)となった。 (2)経営成績の状況の概要及びこれに関する分析・検討内容当連結会計年度における当社グループの受注高は、エナジーセグメントをはじめ全てのセグメントで増加し、前連結会計年度を3,872億24百万円(+5.8%)上回る7兆712億59百万円となった。売上収益は、物流・冷熱・ドライブシステムセグメントが減少したものの、航空・防衛・宇宙セグメント、エナジーセグメント及びプラント・インフラセグメントが増加し、前連結会計年度を3,700億29百万円(+7.9%)上回る5兆271億76百万円となった。事業利益は、物流・冷熱・ドライブシステムセグメントが減少したものの、エナジーセグメント、航空・防衛・宇宙セグメント及びプラント・インフラセグメントが増加し、前連結会計年度を1,006億56百万円(+35.6%)上回る3,831億98百万円となり、税引前利益も前連結会計年度を593億43百万円(+18.8%)上回る3,745億31百万円となった。また、親会社の所有者に帰属する当期利益も、前連結会計年度を234億24百万円(+10.6%)上回る2,454億47百万円となった。 セグメントごとの経営成績は、次のとおりである。ア.エナジー電力需要の高まりや低炭素化により、市場が拡大しているGTCCが増加したほか、サービス需要が堅調なスチームパワーや、航空需要が再成長軌道に入った航空機用エンジンが増加したことなどにより、受注高は、前連結会計年度を2,102億80百万円(+8.7%)上回る2兆6,224億66百万円となった。売上収益は、GTCCや航空機用エンジンが増加したことなどにより、前連結会計年度を921億31百万円(+5.3%)上回る1兆8,157億96百万円となった。事業利益は、GTCCや航空機用エンジンが増加したことなどにより、前連結会計年度を554億90百万円(+37.0%)上回る2,053億56百万円となった。 イ.プラント・インフラ脱炭素への動きを背景に欧州で製鉄機械が増加したほか、機械システムや商船が増加したことなどにより、受注高は、前連結会計年度を1,169億93百万円(+13.2%)上回る1兆2億7百万円となった。売上収益は、製鉄機械や商船、機械システムが増加したことなどにより、前連結会計年度を188億97百万円(+2.3%)上回る8,521億12百万円となった。事業利益は、製鉄機械や機械システム、エンジニアリングが増加したことなどにより、前連結会計年度を148億96百万円(+33.3%)上回る596億34百万円となった。 ウ.物流・冷熱・ドライブシステム東南アジア等の需要拡大を背景に冷熱製品が増加したほか、データセンター向けを中心にエンジンが増加したことなどにより、受注高は前連結会計年度を118億77百万円(+0.9%)上回る1兆3,305億25百万円となった。売上収益は、冷熱製品やエンジンが増加したものの、物流機器が減少したことなどにより、前連結会計年度を74億87百万円(△0.6%)下回る1兆3,071億1百万円となった。事業利益は、物流機器やターボチャージャが減少したことなどにより、前連結会計年度を234億97百万円(△32.3%)下回る493億21百万円となった。 エ.航空・防衛・宇宙防衛力整備計画の拡充への対応等により、艦艇や宇宙機器が増加したほか、民間航空機が増加したことなどにより、受注高は、前連結会計年度を314億35百万円(+1.5%)上回る2兆1,001億44百万円となった。売上収益は、飛しょう体や防衛航空機等の防衛関連製品、民間航空機が増加したことなどにより、前連結会計年度を2,390億98百万円(+30.2%)上回る1兆306億46百万円となった。事業利益は、飛しょう体や防衛航空機等の防衛関連製品が増加したことなどにより、前連結会計年度を272億91百万円(+37.5%)上回る999億84百万円となった。 オ.その他受注高は前連結会計年度を466億17百万円(+122.6%)上回る846億28百万円、売上収益は前連結会計年度を413億円(+124.5%)上回る744億74百万円、事業利益は前連結会計年度を141億47百万円(+89.2%)上回る300億2百万円となった。 (3)キャッシュ・フローの状況の概要及びこれに関する分析・検討内容当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,265億29百万円増加し、6,578億16百万円となった。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、5,304億59百万円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べ1,992億72百万円収入が増加した。これは、「税引前利益」が増加したことや受注拡大に伴う「契約負債」の獲得等によるものである。 (投資活動によるキャッシュ・フロー)当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,877億14百万円の資金の減少となり、前連結会計年度に比べ566億66百万円支出が増加した。これは、「有形固定資産及び無形資産の取得による支出」及び「投資(持分法で会計処理される投資を含む)の取得による支出」が増加したことなどによるものである。 (財務活動によるキャッシュ・フロー)当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,141億23百万円の資金の減少となったが、前連結会計年度に比べ447億79百万円支出が減少した。これは、「債権流動化等による収入」の増加及び「債権流動化等の返済による支出」が減少したことなどによるものである。 (4)生産、受注及び販売の状況①生産の実績セグメントの名称当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)金額(百万円)前連結会計年度比(%)エナジー1,888,789+6.2プラント・インフラ793,584△2.2物流・冷熱・ドライブシステム1,294,998△2.4航空・防衛・宇宙1,063,983+33.8その他74,050+87.1全社又は消去10,543―合計5,125,949+7.6(注)1.上記金額は、大型製品については契約金額に工事進捗度を乗じた額、その他の製品については完成数量に販売金額を乗じた額を基に算出計上している。 2.セグメント間の取引については、各セグメントの金額から消去しており、「全社又は消去」の区分は、報告セグメントに含まれない生産高である。 3.上記金額には、消費税等は含まれていない。 ②受注の実績セグメントの名称当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)受注高(百万円)前連結会計年度比(%)受注残高(百万円)前連結会計年度比(%)エナジー2,622,466+8.74,918,439+16.3プラント・インフラ1,000,207+13.21,705,361+5.0物流・冷熱・ドライブシステム1,330,525+0.979,355+36.0航空・防衛・宇宙2,100,144+1.53,514,580+42.0その他84,628+122.618,239+27.6全社又は消去△66,712―320―合計7,071,259+5.810,236,296+21.9(注)1.受注高については、「エナジー」、「プラント・インフラ」、「物流・冷熱・ドライブシステム」、「航空・防衛・宇宙」及び「その他」にはセグメント間の取引を含んでおり、「全社又は消去」でセグメント間の取引を一括して消去している。また、「全社又は消去」の区分は、報告セグメントに含まれない受注高を含んでいる。 2.受注残高については、セグメント間の取引を各セグメントの金額から消去しており、「全社又は消去」の区分は、報告セグメントに含まれない受注残高である。 3.上記金額には、消費税等は含まれていない。 ③販売の実績セグメントの名称当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)金額(百万円)前連結会計年度比(%)エナジー1,815,796+5.3プラント・インフラ852,112+2.3物流・冷熱・ドライブシステム1,307,101△0.6航空・防衛・宇宙1,030,646+30.2その他74,474+124.5全社又は消去△52,954―合計5,027,176+7.9(注)1.「エナジー」、「プラント・インフラ」、「物流・冷熱・ドライブシステム」、「航空・防衛・宇宙」及び「その他」にはセグメント間の取引を含んでおり、「全社又は消去」でセグメント間の取引を一括して消去している。また、「全社又は消去」の区分は、報告セグメントに含まれない販売金額を含んでいる。 2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりである。相手先前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)金額(百万円)割合(%)金額(百万円)割合(%)防衛省489,77810.5704,18114.0 3.上記金額には、消費税等は含まれていない。 (5)資本の財源及び資金の流動性に係る情報ア.資金需要の主な内容当社グループの資金需要は、営業活動については、生産活動に必要な運転資金(材料・外注費及び人件費等)、受注獲得のための引合費用等の販売費、製品競争力強化・ものづくり力強化及び新規事業立上げに資するための研究開発費が主な内容である。投資活動については、事業伸長・生産性向上及び新規事業立上げを目的とした設備投資並びに事業遂行に関連した投資有価証券の取得が主な内容である。今後、成長分野を中心に必要な設備投資や研究開発投資、投資有価証券の取得等を継続していく予定である。 イ.有利子負債の内訳及び使途2025年3月31日現在の有利子負債の内訳は下記のとおりである。(単位:百万円) 合計償還1年以内償還1年超短期借入金62,30762,307―長期借入金305,62135,965269,656社債225,00035,000190,000小計592,928133,272459,656ノンリコース借入金58,45899157,467合計651,387134,263517,123当社グループは比較的工期の長い工事案件が多く、生産設備も大型機械設備を多く所有していることもあり、一定水準の安定的な運転資金及び設備資金を確保しておく必要がある。当連結会計年度においては、当社グループは継続的に資金創出に努め、事業拡大局面においても運転資金を抑制しつつ、期限の到来した借入金を返済してきた結果、当連結会計年度末の有利子負債の構成は、償還期限が1年以内のものが1,342億63百万円、償還期限が1年を超えるものが5,171億23百万円となり、合計で6,513億87百万円となった。これらの有利子負債により調達した資金は、事業活動に必要な運転資金、投資資金に使用しており、具体的には火力発電システム、原子力発電システム、防衛等の伸長事業及び「2024事業計画」で掲げている成長領域が中心である。 ウ.財務政策当社グループは、運転資金、投資資金については、まず営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について有利子負債による調達を実施している。長期借入金、社債等による長期資金の調達については、事業計画に基づく資金需要、金利動向等の調達環境、既存借入金の償還時期等を考慮の上、調達規模、調達手段を適宜判断して実施していくこととしている。一方で、有利子負債を圧縮するため、キャッシュマネジメントシステムにより当社グループ内での余剰資金の有効活用を図っており、また、営業債権、棚卸資産の圧縮や固定資産の稼働率向上等を通じて資産効率の改善にも取り組んでいる。自己株式については、事業計画の推進状況、当社の業績見通し、株価動向、財政状況及び金融市場環境等を総合的に勘案して取得を検討していくこととしている。 (6)経営方針・経営戦略及び経営指標等に照らした経営成績等の分析・検討当社グループは、以前の中期経営計画「2021事業計画」において、「収益力の回復・強化」及び「成長領域の開拓」に優先的に取り組み、長期安定的に企業価値を向上させることを目指して事業を遂行してきた。これにより、足元の収益力の回復が図られ、事業基盤を強化することができた。「2024事業計画」においては、「売上収益5.7兆円以上」、「事業利益4,500億円以上(事業利益率8%以上)」、「ROE12%以上」を2026年度の目標として設定しており、当連結会計年度の実績は「売上収益5兆271億円」、「事業利益3,831億円(事業利益率7.6%)」、「ROE10.7%」となった。エナジーセグメント及び航空・防衛・宇宙セグメントを中心とした大型案件の受注、売上収益の増加、利益率改善等により、受注高、売上収益、事業利益、親会社の所有者に帰属する当期利益のいずれも、過去最高を更新した。また、有利子負債については、成長領域の強化のための投資を実施したが、受注拡大に伴う契約負債の獲得等により、キャッシュ・フローは黒字を確保し、有利子負債残高は6,513億円となった。 (7)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定当社グループの連結財務諸表は、IFRSに準拠して作成されている。この連結財務諸表の作成に当たり、見積りが必要となる事項については、合理的な基準に基づき、会計上の見積りを行っている。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表」の注記「2.作成の基礎(5)見積り及び判断の利用」及び「3.重要性がある会計方針」に記載している。 |
※本記事は「三菱重工業株式会社」の令和7年3月期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
※4. この企業は、連結財務諸表ベースで見ると有利子負債がゼロ。つまり、グループ全体としては外部借入に頼らず資金運営していることがうかがえます。なお、個別財務諸表では親会社に借入が存在しているため、連結上のゼロはグループ内での相殺消去の影響とも考えられます。
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

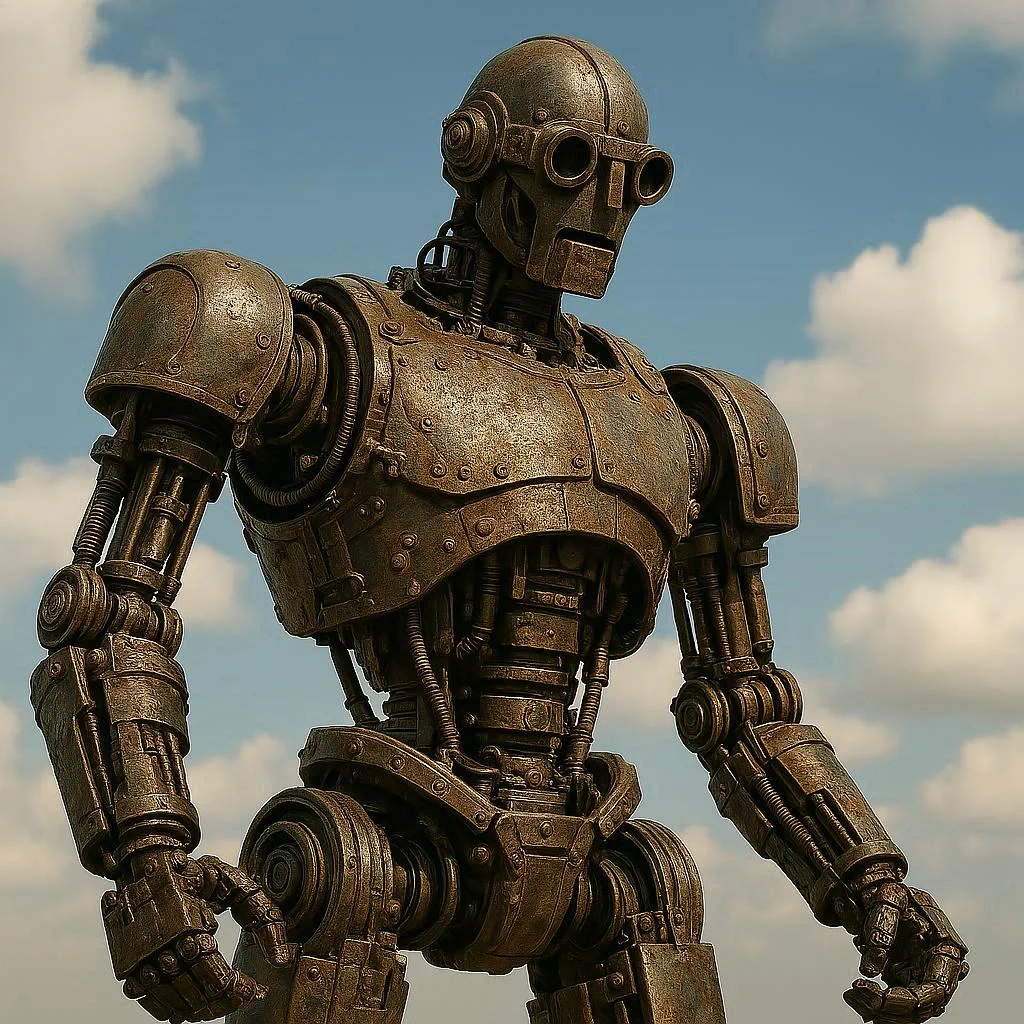

コメント