| 会社名 | マツダ株式会社 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 従業員数 | 連48783名 単23391名 |
| 従業員平均年齢 | 42.5歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 17.4年 |
| 平均年収 | 7145000円 |
| 1株当たりの純資産(連結) | 2843.31円 |
| 1株当たりの純利益(連結) | 181円 |
| 決算時期 | 年3 |
| 配当金 | 55円 |
| 配当性向 | 57.6% |
| 株価収益率(PER) | 5.2倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(連結) | 6.5% |
| 営業活動によるCF | 3056億円 |
| 投資活動によるCF | ▲1999億円 |
| 財務活動によるCF | 900億円 |
| 研究開発費※1 | 9億円 |
| 設備投資額※1 | 19億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 611.1億円 |
| 株主資本比率※2 | 39.2% |
| 有利子負債残高(連結)※3 | 5750.2億円 |
経営方針
| 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】(1) 会社の経営の基本方針当社は、企業理念として、『PURPOSE』『PROMISE』『VALUES』を定めております。また、当社は、未来に向かってステークホルダーの皆さまと共に価値創造を進めていくべく、2030年時点の当社のありたい姿を「2030 VISION」として定めております。 企業理念PURPOSE:前向きに今日を生きる人の輪を広げるPROMISE:いきいきとする体験をお届けする人の頭、身体、心を活性化するコミュニティと共にVALUES :ひと中心 / 飽くなき挑戦 / おもてなしの心 2030 VISION「走る歓び」で移動体験の感動を量産するクルマ好きの会社になる。1. マルチソリューションで温暖化抑制に取り組み、持続可能な地球の未来に貢献する。2. 心と身体を見守る技術で、誰もが安全・安心・自由に移動できる社会に貢献する。3. 日常に動くことへの感動や心のときめきを創造し、一人ひとりの「生きる歓び」に貢献する。 (2) 経営環境及び対処すべき課題① 中期経営計画(2020年3月期~2026年3月期)当社は、企業として存在し続け、持続的な成長を遂げるために「人と共に創るマツダの独自性」を基本方針として中期経営計画を策定し、それに基づいた施策を着実に進めております。 中期経営計画 主要施策■ブランド価値向上への投資 -独自の商品・技術・生産・顧客体験への投資-・効率化と平準化による継続・段階的な新商品/派生車の導入・継続的な商品改良の実行■ブランド価値を低下させる支出の抑制■固定費/原価低減を加速し損益分岐点台数を低減■遅れている領域への投資、新たな領域への投資開始■協業強化(CASE対応(*1)、新たな仲間作り) これまでに築いてきた資産を活用して本格成長を図り、時代の大きな変化に耐えうる強靭な経営体質の実現に向けて取り組みを加速してまいります。また、グローバルでの環境規制の強化・加速などによる経営環境の変化やCASE時代の新しい価値創造競争を踏まえ、技術開発の長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」の実現に向けて2030年を見据えた事業構造の転換に取り組んでおります。 中期経営計画 財務指標売上・約4.5兆円収益性・売上高営業利益率(ROS)5%以上 ・自己資本利益率(ROE)10%以上将来投資・設備投資+開発投資:売上高比7-8%以下 ・電動化・IT・カーボンニュートラル実現に向けた対応財務基盤・ネットキャッシュ維持(*2)株主還元・安定的に配当性向30%以上損益分岐点台数・約100万台(出荷台数) (*1)コネクティビティ技術(connected)/自動運転技術(autonomous)/シェアード・サービス(shared)/電動化技術(electric)といった新技術の総称。(*2)現金及び現金同等物から有利子負債を差し引いた金額がプラスの状態を維持すること。 ② 2030年に向けた経営方針(2030経営方針)現在、当社は2026年3月期までの財務目標達成に向けて中期経営計画の取り組みを推進しておりますが、各国の環境規制動向、社会インフラ整備をはじめ、電源構成の変化、そして消費者の価値観の多様化など、経営を取り巻く環境の不確実性が高まっていることを受け、視点を2030年まで延ばし、世界の潮流を想定した経営方針と主要な取り組みを以下のとおり定めております。 経営基本方針1. 地域特性と環境ニーズに適した電動化戦略で、地球温暖化抑制という社会的課題の解決に貢献すること2. 人を深く知り、人とクルマの関係性を解き明かす研究を進め、安全・安心なクルマ社会の実現に貢献すること3. ブランド価値経営を貫き、マツダらしい独自価値をご提供し、お客様に支持され続けること 未来を拓く主な取り組み1. カーボンニュートラルに向けた取り組み当社が目標とする2050年のカーボンニュートラル(*3)(以下、「CN」)実現に向けては、まず自社のCO2排出について、「2035年にグローバル自社工場のCN実現」と中間目標を定め、省エネ、再エネ、CN燃料活用の3本柱で取り組みを進めてまいります。加えて、サプライチェーン(*4)への対応も必要であり、輸送会社様や購買お取引先様と共にCO2排出量を削減する活動を段階的に進めてまいります。国内においては、サプライチェーンの構造改革に取り組むほか、CN燃料の活用拡大を進めてまいります。 2. 各フェーズにおける電動化の取り組み電動化時代への移行期間には、地域の電源事情に応じて、適材適所で内燃機関、電動化技術、代替燃料など様々な組み合わせとソリューションを提供していく「マルチソリューション」のアプローチが有効と考えております。当社は各国の電動化政策や規制強化の動向を踏まえ、2030年のグローバルでのバッテリーEV比率の想定を25?40%としており、パートナー企業と共に段階的に電動化を進めてまいります。 ■ 第1フェーズ(2022?2024年):蓄積した資産を活用したビジネス基盤強化既存の技術資産であるマルチ電動化技術をフル活用して魅力的な商品を投入し、市場の規制に対応してまいります。ラージ商品群を投入し、プラグインハイブリッド車やディーゼルのマイルドハイブリッド車など、環境と走りを両立する商品で収益力を向上させつつ、バッテリーEV専用車の技術開発を本格化させます。 ■ 第2フェーズ(2025?2027年):電動化へのトランジション電動化への移行期間における燃費向上によるCO2削減を目指し、新しいハイブリッドシステムを導入するなど、これまで培ってきたマルチ電動化技術をさらに磨きます。電動化が先行する中国市場においてバッテリーEV専用車を導入するほか、グローバルにバッテリーEVの導入を開始します。内燃機関における再生可能燃料の利用可能性を踏まえ、熱効率の更なる改善技術の適用等により、内燃機関の性能についても極限まで進化させてまいります。 ■ 第3フェーズ(2028?2030年):バッテリーEV本格導入バッテリーEV専用車の本格導入を進めるとともに、外部環境の変化や財務基盤強化の進捗を踏まえ、電池生産への投資なども視野に入れた本格的電動化に軸足を移してまいります。 3. 人とITの共創による価値創造への取り組み自動車技術の改良を進め、クルマを取り巻く様々な人々や社会の声に耳を傾けつつ、人の幸せを第一に、事故のない安全・安心な社会づくりに貢献していくことは私たちの重要な責務です。安全技術開発に加え、地域や社会と連携し「死亡事故ゼロ」を目指し取り組んでまいります。安全技術開発については、独自の安全思想「MAZDA PROACTIVE SAFETY」のもと、これまで大事にしてきた「ひと」を中心としたものづくりに、デジタル技術を掛け合わせた高度運転支援技術の開発を継続し、運転者も同乗者も周囲の人も安全・安心なクルマづくりを進め、2040年を目途に自動車技術で対策が可能なものについては、自社の新車が原因となる死亡事故ゼロを目指します。 (*3)地球上の炭素(カーボン)の総量に変動をきたさない、二酸化炭素(CO2)の排出と吸収がプラスマイナスゼロになるようなエネルギー利用のあり方やシステム。(*4)商品が消費者の手元に届くまでの、調達、製造、在庫管理、配送、販売、消費といった一連の流れ。 4.原価低減とサプライチェーンの強靭化原価低減は、従来の商品原価や、製造原価だけにとどまらず、その範囲を拡大し、サプライチェーンとバリューチェーン(*5)全体を鳥瞰し、商品ラインアップの見直し等による投資効率・在庫回転率の向上を図るなどムリ・ムラ・ムダを徹底的に取り除く取り組みを通じて原価の作りこみを行うよう変えてまいります。サプライチェーンについては、材料調達からお客様へのデリバリーに至るまでの全ての工程における個々の改善にとどまらず、モノがよどみなく流れ、しかもそのスピードが最大化される「全体最適の工程」を実現するよう取り組みます。また、材料・部品調達の階層を浅くし、種類を産む場所を近場に寄せていくなどの調達構造の変革や、汎用性の高い材料や半導体の活用拡大に取り組み、地政学的リスク、地震といった大規模災害などの外部環境の変化に対する影響も最小限にとどめてまいります。 ③ 企業価値向上に向けた「ライトアセット戦略」電動化を取り巻く環境は、インフレによる投資コストの増加や地域毎の電動化進度の違いなど多くの不確実性を抱えています。当社は2030年までを「電動化の黎明期」と捉え、2030経営方針のもと、多様化するお客様ニーズや環境規制に柔軟に対応すべくマルチソリューションで電動化を進めます。その具現化に向け、本年3月、既存資産の活用度を高めることで、スモールプレーヤーとしての企業価値を向上させる実行戦略として「ライトアセット戦略」(*6)を公表しました。その主な内容は以下のとおりです。■ ものづくり領域では、独自の開発・生産プロセス革新を展開し、開発領域においては、より複雑な開発に対し、既存リソース水準を維持しつつ、生産性を3倍に向上させて対応してまいります。■ 2027年に導入予定のバッテリーEVについては、協業・パートナーシップによって、従来と比較し開発にかかる投資と工数を大幅に低減させる見通しです。■ 電池投資については、当初見込みにインフレ影響を加味した投資総額から半減できる見込みです。■ 生産においては、既存資産を活用してバッテリーEVとエンジン車を混流生産することにより、バッテリーEV専用工場新設と比較し、初期設備投資と量産準備期間を大幅に低減できる見通しです。■ 上記の取り組みを通じて、低投資で高い資産効率を確保の上、競争力ある技術・商品を提供し、資本コストを上回るリターンを創出することで、持続的な成長と企業価値向上を実現してまいります(*7)。 ④ 2030経営方針の進捗当期が最終年度となる第1フェーズでは、成長投資の資金を確保すること及び将来の電動化やカーボンニュートラルなどへの準備を行うことを目標としており、その主な進捗は以下のとおりです。 売上高の成長■ 第1フェーズの3年間で、出荷台数は25%増加し、売上単価の増加と併せて売上高は過去最高を更新しております。■ ラージ商品4車種や販売が好調な北米市場の牽引により、第1フェーズの3年間におけるネットキャッシュは4,000億円余りとなるなど、財務体質の強化も進捗しております。 サプライチェーン・バリューチェーン全体での原価低減推進■ パワートレインの種類数をお客様が選択しやすい仕様に絞り込み、増加傾向にあったサプライチェーンの在庫を改善することなどにより、原価低減活動に取り組んでおります。■ サプライヤーから調達する部品種類数を適正化することでサプライチェーンの構造改革を推進するとともに、マツダの強みである混流生産ラインに無人輸送車を採用した効率性の高い生産設備を導入するなど、部品調達コストや輸送費等の固定費低減に取り組んでおります。■ 原価低減に向けたコスト構造改革活動を加速するため、本年4月より新たに「コスト低減統括役員」及びその実務を担当する原価企画変革室を設置し、コストガバナンス体制の整備と原価企画機能の抜本的な見直しに着手いたしました。■ 経営の適応力・回復力の強化に向けて、サプライチェーン、バリューチェーンの最適化を含めた構造的原価低減で1,000億円、加えて業務の選択と集中、投資効率化、DX活用などによる生産性向上によって固定費1,000億円の削減を目標とし、取り組みを進めております。 (*5)商品の付加価値を創出するための、商品企画、デザイン、開発、生産技術、製造、販売、サービスといった一連の事業活動の流れ。(*6)ライトアセット戦略を説明したマツダ・マルチソリューション説明会2025の様子はこちらをご参照ください。https://www.mazda.com/ja/about/vision/multi-solution-briefing-2025/(*7)企業価値向上に向けた取り組みの全体像については、マツダ統合報告書2024「CFOメッセージ」をご参照ください。https://www.mazda.com/ja/investors/library/integrated-report/ 人への投資■ 今後一層重要となるより高度なソフトウェア技術の開発やイノベーションに対応するため、ソフトウェア技術者の獲得に向け、2025年7月に麻布台ヒルズに「マツダR&Dセンター東京」を新たに開設するとともに、東京本社を移転いたします。■ 従業員一人ひとりが最大限の能力を発揮し、自由にアイデアを出し、活発に意見交換できる風土づくりに注力しており、その一環として2023年11月から全社的に「BLUEPRINT」プログラムを展開しております。本年5月までに全間接・直接従業員が同プログラムに参画し、今後は全従業員への浸透定着ステージに移行し、全社的な取り組みをさらに進めてまいります。 電動化技術・電池の準備■ 2024年9月、パナソニックエナジー株式会社と当社は、バッテリーEV向け電池供給に合意し、本年1月には、車載用円筒形リチウムイオン電池のモジュール・パック工場を山口県岩国市に新設することを公表いたしました。2027年度の工場稼働開始を目指しており、完成した電池パックは、マツダの国内車両工場にて、マツダ初のEV専用プラットフォームを採用するバッテリーEVに搭載予定です。生産能力は年間10GWhを予定しております。■ 次世代電池技術の自社開発を、GI基金(*8)事業として推進しており、社内に試験ラボを開設するなど、研究開発は予定通りに進捗しております。■ 商品に関しては、多様なお客様のニーズに対応すべく、昨年11月には「MAZDA CX-50」にトヨタ自動車株式会社の技術を活用したハイブリッドモデルを追加いたしました。また、第2フェーズに導入予定の次期「MAZDA CX-5」には、電動化時代の主軸エンジンとして開発中のSKYACTIV-Zをマツダ独自のハイブリッドシステムと組み合わせて2027年中に搭載する予定です。■ 電動化の進展が早い中国市場においては、昨年10月よりバッテリーEVとプラグインハイブリッドの2つのモデルを用意した「MAZDA EZ-6」の販売を開始しております。欧州やタイでは「MAZDA6e」として市場導入を予定しており、欧州向けは本年4月に生産を開始いたしました。また、中国では、本年中に「MAZDA EZ-60」を発売予定です。 ⑤ コンプライアンス及びガバナンス強化の取り組み2024年6月3日公表の型式指定申請における不適切事案については、再発防止策の一環として、次の取り組みを行っております。 1. 試験が認証法規に準拠した状態で実施されたかをチェックする仕組み及びガバナンス体制の再整備2. 認証法規に準拠した試験を適正に実施するための手順書の見直し・教育・実践の徹底 3. 認証法規に準拠した試験条件を安定的に満たす設備の整備強化 当社に関係するすべてのステークホルダーの皆様からの信頼回復に向けて、コンプライアンス及びガバナンスの更なる強化を図ってまいります。 (*8)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)によるグリーン・イノベーション基金。 ※文中における将来に関する事項につきましては、本報告書提出時点において当社グループが判断した一定の前提に基づいたものであります。これらの記載は実際の結果とは異なる可能性があり、その達成を保証するものではありません。 |
経営者による財政状態の説明
| 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1) 経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は、次のとおりであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度の当社グループを取り巻く事業環境は、経済環境の緩やかな改善がみられるものの、地政学リスクを背景とした資源価格の高止まり、主要国における高水準の政策金利の継続、急激な為替変動などの影響により、先行き不透明な状況が継続しました。足元では、主要国における政権交代や世界的な貿易摩擦の激化への懸念などにより、地政学的・経済的な不確実性が高い状況が続いております。このような状況の中、当社グループは、主要市場における販売競争の激化、人件費や調達部品価格の上昇等の影響を受けたものの、機動的な販売促進策の強化、新商品の導入等の取り組みにより、過去最高の販売台数となった北米市場を中心に販売台数及び売上高が増加いたしました。また、将来に向けた電動化・価値創造の取り組みや人への投資を推し進めつつ、機種数の削減やお客様価値に沿った部品・装備の見直し、費用対効果の再精査等による原価低減活動、徹底した業務効率化等による固定費低減活動による経営効率の改善にも取り組んでまいりました。商品面では、昨年4月、「MAZDA CX-60」、「MAZDA CX-90」に続くラージ商品群の第三弾となる2列シートクロスオーバーSUV「MAZDA CX-70」の販売を北米にて開始いたしました。また、昨年10月には、同第四弾となる3列シートクロスオーバーSUV「MAZDA CX-80」の販売を欧州及び日本にて開始いたしました。「CX-70」と「CX-80」の両モデルは、プラグインハイブリッドシステムなどの電動化技術の採用によって高い環境性能を備えるとともに、各国で高い安全性評価を獲得しております。急速に電動化が進む中国市場においては、昨年10月、「MAZDA EZ-6」の販売を開始いたしました。「EZ-6」は、マツダと合弁事業のパートナーである重慶長安汽車股?有限公司の協力のもと、当社が出資する現地法人である長安マツダ汽車有限公司が開発・製造を行う新型電動車の第一弾です。また、北米市場においては、昨年11月、米国アラバマ工場で製造する「MAZDA CX-50」にトヨタ自動車株式会社の技術を活用したハイブリッドモデルの販売を開始いたしました。当社は、「ひと中心」の価値観のもと「走る歓び」を進化させ続け、お客様の日常に移動体験の感動を創造し、「生きる歓び」をお届けしていくことを目指してまいります。 [グローバル販売]当連結会計年度のグローバル販売台数は、米国・メキシコ市場の年間販売台数が過去最高を更新するなど、北米市場での販売が好調に推移したことから、前期比5.0%増の1,303千台となりました。市場別の販売台数は、次のとおりであります。<日本>「MAZDA CX-8」の販売終了影響等により、前期比5.2%減の152千台となりました。なお、第4四半期としては、新規導入の「CX-80」や「CX-60」及び「MAZDA CX-5」の商品改良モデルの販売が台数増加に貢献したことから、前年同期比24.8%増の49千台となりました。<北米>米国は、「CX-50」のハイブリッドモデルの導入やラージ商品群が販売を牽引し、前期比15.9%増の435千台と過去最高の販売台数となりました。北米全体でも、カナダやメキシコの好調な販売により、前期比20.0%増の617千台となりました。<欧州>「MAZDA CX-30」や「MAZDA2 Hybrid」の販売は増加したものの、「CX-60」や「CX-5」及び「MAZDA6」等の販売減少により、前期比3.4%減の174千台となりました。<中国>内燃機関車需要の縮小や価格競争激化の影響等により、前期比23.1%減の74千台となりました。なお、昨年10月より、電動専用モデル「EZ-6」の販売を開始しております。<その他の市場>主要市場のオーストラリアでは、新規導入のラージ商品群や「MAZDA CX-3」及び「CX-5」等の販売は増加したものの、「MAZDA CX-9」及び「CX-8」の販売終了の影響等により、前期比1.1%減の97千台となりました。その他の市場全体では、タイやマレーシアなどASEAN市場の販売減少等により、前期比1.4%減の285千台となりました。 [財政状態及び経営成績]a. 経営成績当連結会計年度の当社グループの連結業績は、次のとおりです。 (単位:億円) 前連結会計年度当連結会計年度前期比 通期通期増減額増減率売上高48,27750,189+1,912+4.0%営業利益2,5051,861△644△25.7%経常利益3,2011,890△1,311△41.0%親会社株主に帰属する当期純利益2,0771,141△936△45.1% b. 財政状態当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より2,983億円増加し、4兆901億円となり、負債合計は、前連結会計年度末より2,457億円増加し、2兆2,801億円となりました。純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益1,141億円等により、前連結会計年度末より527億円増加し、1兆8,100億円となりました。自己資本比率は、前連結会計年度末より2.0ポイント減少し、43.8%(劣後特約付ローンの資本性考慮後44.7%)となりました。 c. セグメントごとの財政状態及び経営成績当連結会計年度のセグメント別の連結業績は、次のとおりです。 (単位:億円) 前連結会計年度当連結会計年度前期比 通期通期増減額増減率売上高日本38,68037,328△1,353△3.5%北米29,83232,933+3,101+10.4%欧州9,2677,666△1,601△17.3%その他の地域7,3266,476△850△11.6%営業利益日本1,522485△1,037△68.2%北米876670△207△23.6%欧州203192△11△5.5%その他の地域269231△38△14.2% <日本>売上高は、3兆7,328億円(前期比1,353億円減、3.5%減)、営業利益は485億円(前期比1,037億円減、68.2%減)となりました。これは、主に欧州向け一部車種のモデル切り替えに伴う出荷台数の減少に加え、調達部品価格の上昇影響等によるものです。セグメント資産は、前期比2,252億円増加の3兆1,055億円となりました。<北米>売上高は3兆2,933億円(前期比3,101億円増、10.4%増)、営業利益は670億円(前期比207億円減、23.6%減)となりました。これは、主に米国及びメキシコで過去最高の販売台数を記録したことや為替の円安影響があった一方で、メキシコ工場の製造コストが増加したこと等によるものです。セグメント資産は、前期比572億円増加の8,745億円となりました。<欧州>売上高は7,666億円(前期比1,601億円減、17.3%減)、営業利益は192億円(前期比11億円減、5.5%減)となりました。これは、主要市場のドイツなどにおいて出荷台数が減少したこと等によるものです。セグメント資産は、前期比87億円増加の3,602億円となりました。<その他の地域>売上高は6,476億円(前期比850億円減、11.6%減)、営業利益は231億円(前期比38億円減、14.2%減)となりました。これは、主要市場であるオーストラリアやASEAN市場での販売台数が減少したこと等によるものです。セグメント資産は、前期比18億円増加の3,895億円となりました。 ② キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末において、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1,863億円増加の1兆1,056億円、有利子負債は、前連結会計年度末より1,374億円増加の7,052億円となりました。この結果、4,003億円のネット・キャッシュ・ポジションとなっております。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,558億円に加え、仕入債務の増加等により、3,056億円の増加(前期は4,189億円の増加)となりました。 投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、2,000億円の減少(前期は1,799億円の減少)となりました。 以上により、連結フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は、1,057億円の増加(前期は2,390億円の増加)となりました。 財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フローは、社債及び長期借入金による資金調達に対し、配当金の支払いや長期借入金の返済等により、901億円の増加(前期は847億円の減少)となりました。 ③ 生産、受注及び販売の実績a. 生産実績当連結会計年度における車両生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称台数(千台)前期比(%)日本749△6.3北米32822.1その他の地域131△13.8合計1,207△1.0 b. 受注実績当社グループは、主として販売会社の販売実績及び受注状況等を考慮して生産計画を立て、見込生産を行っております。 c. 販売実績当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称金額(百万円)前期比(%)日本937,886△0.5北米2,775,31418.5欧州731,439△17.6その他の地域574,254△12.3合計5,018,8934.0 (注) 1.セグメント間の取引については、相殺消去しております。2.主要な販売先については、相手先別の販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため、記載を省略しております。 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、本文中の将来に関する事項は、本報告書提出日時点において判断したものであります。 ① 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、次のとおりであります。なお、当社グループの経営に影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク 」に記載しております。 <売上高>当連結会計年度における売上高は、北米での好調な販売等により、過去最高の5兆189億円(前期比1,912億円増、4.0%増)となりました。仕向地別では、国内は、出荷台数の減少により、5,786億円(前期比617億円減、9.6%減)となり、海外は、主として北米での出荷台数の増加に加え、販売単価の改善や為替の円安影響等により、4兆4,403億円(前期比2,529億円増、6.0%増)となりました。製品別では、車両売上高は、出荷台数の増加や為替の円安影響等により、4兆3,624億円(前期比1,723億円増、4.1%増)となり、海外生産用部品売上高は、中国向けの出荷が減少したこと等により、149億円(前期比77億円減、34.1%減)となりました。そのほか、部品売上高は3,762億円(前期比245億円増、7.0%増)、その他売上高は2,654億円(前期比21億円増、0.8%増)となりました。<営業利益>主力市場である北米での好調な販売やラージ商品群の販売台数の増加、及び、ドルやユーロなどの為替の円安影響が増益要因となった一方で、販売費用の増加や調達部品価格の上昇影響等により、営業利益は1,861億円(前期比644億円減、25.7%減)、連結売上高営業利益率は3.7%(前期比1.5ポイント減)となりました。なお、営業利益の主な増減要因は、次のとおりです。 (単位:億円) 通期台数・構成+628販売奨励金△1,249為替+439原材料・物流費等△462コスト改善+250固定費他△250計△644 <経常利益>為替差損229億円(前期は542億円の為替差益)の計上に対し、受取利息等の計上により、1,890億円(前期比1,311億円減、41.0%減)となりました。<親会社株主に帰属する当期純利益>生産終了損失引当金繰入額243億円を特別損失に計上したことや税金費用407億円等により、1,141億円(前期比936億円減、45.1%減)となりました。 当連結会計年度の財政状態の分析、セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況の分析につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。 ② 資本の財源、資金の流動性当社グループは、事業活動に必要な資金を安定的に確保するため、キャッシュ・フローの創出に努めております。また、自動車及び同部品の製造販売事業を行うために必要となる設備投資等に充当することを目的として、銀行借入や社債発行などにより、必要な資金を調達しております。なお、当社は、サステナビリティに関する取り組みを推進するため、資金調達の枠組みとして2024年1月に「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」を策定しました。本フレームワークで調達した資金は、グローバル自社工場のCN、バッテリーEVやプラグインハイブリッド車などの開発・製造、先進安全技術・高度運転支援技術の開発・製造などに活用しております。当社グループの資金の流動性管理にあたっては、資金繰り計画を作成し、適時に更新するなどによりリスク管理を行っているほか、急激な外部環境変化に対応できるよう、一定水準の手元流動性を確保する方針としております。また、当社はグループ全体の資金を一元管理し、グループ内での相互貸借機能を保有することで、流動性リスクに対し機動的に対応できる体制を構築しております。加えて、当社は国内金融機関とのコミットメントライン契約の締結により、十分な流動性を確保する手段を保有しております。当連結会計年度末において、現金及び現金同等物1兆1,056億円に未使用のコミットメントライン2,000億円を加えた流動性は、月商比3.1ヶ月に相当する1兆3,056億円となっております。なお、当社は、国内2社の格付機関から長期発行体格付けを取得しており、当連結会計年度末現在において、日本格付研究所:「A-」、格付投資情報センター:「BBB+」となっております。株主還元につきましては、当期の業績及び経営環境並びに財務状況等を勘案して決定することを方針とし、安定的な配当の実現と着実な向上に努めることとしております。当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載しております。 ③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。連結財務諸表の作成にあたっては、資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす見積り及び仮定を行うことが求められます。当期の連結財務諸表の作成において設定した様々な見積り及び仮定は、当社経営者がその内容について合理的であると判断したものであり、実際の業績は、これらの見積り及び仮定とは異なる場合があります。当社グループが連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。 a. 貸倒引当金売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検証し、回収不能見込額を計上しておりますが、将来、取引先等の財務状況が悪化するなど支払能力が低下した場合は、引当金の追加計上又は貸倒損失が発生する可能性があります。b. 生産終了損失引当金特定の製品について、当初の計画から生産終了時期を早期化したことに伴う取引先への補償などに備えるため、当連結会計年度末における発生見込額を計上しておりますが、将来、損失の発生が増加した場合は、引当金の追加計上が発生する可能性があります。c. 環境規制関連引当金環境規制に対応する費用の発生に備えるため、各国の環境規制を検証し、当連結会計年度末における発生見込額を計上しておりますが、将来、各国での環境規制がより強化された場合は、引当金の追加計上が発生する可能性があります。d. 退職給付関係退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出しておりますが、これらの前提条件が変動した場合、あるいは、運用環境の悪化等により年金資産が減少した場合には、将来期間において認識される費用及び債務に影響を与える可能性があります。e. 固定資産の減損当社グループは固定資産の減損会計の適用に際し、原則として事業会社毎を1つの資産グループとし、遊休資産、賃貸用資産及び売却予定資産は、個々の物件ごとに資産グループとして、各グループの単位で将来キャッシュ・フローを見積っておりますが、経営状況の悪化等により帳簿価額を回収できないと判断された場合には、対象資産の帳簿価額に対する減損損失の計上が必要になる可能性があります。f. 繰延税金資産「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り) 1. 繰延税金資産の回収可能性」に記載しております。g. 製品保証引当金「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り) 2. 製品保証引当金」」に記載しております。 ④ 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等当社グループは、2022年11月に「中期経営計画のアップデートおよび2030年の経営方針について」を公表いたしました。本経営計画に係る経営指標につきましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しております。 |
※本記事は「マツダ株式会社」の令和7年年3期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

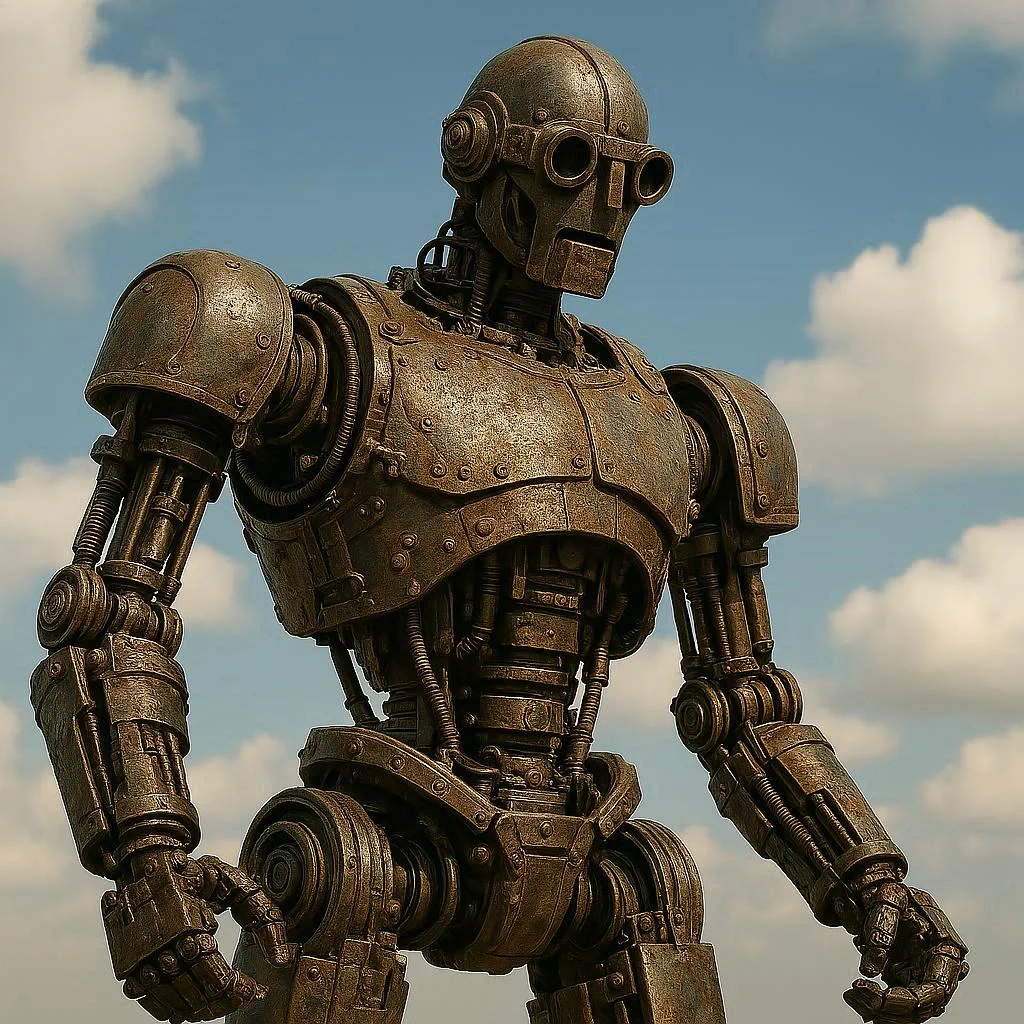

コメント