| 会社名 | 株式会社クボタ |
| 業種 | 機械 |
| 従業員数 | 連52094名 単15472名 |
| 従業員平均年齢 | 39.9歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 13.5年 |
| 平均年収 | 8247922円 |
| 1株当たりの純資産(単体) | 651.67円 |
| 1株当たりの純利益(連結) | 197.61円 |
| 決算時期 | 12月 |
| 配当金 | 50円 |
| 配当性向 | 32.8% |
| 株価収益率(PER) | 12.05倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(単体) | 24.9% |
| 営業活動によるCF | 2820億円 |
| 投資活動によるCF | ▲2088億円 |
| 財務活動によるCF | ▲262億円 |
| 研究開発費※1 | 321億円 |
| 設備投資額※1 | 170.39億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 1276.13億円 |
| 株主資本比率※2 | 40.4% |
| 有利子負債残高(連結)※3※4 | 0円 |
経営方針
| 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりです。なお、文中の将来に関する事項は、当年度末現在において当社が判断したものです。 当社は、「グローバル・メジャー・ブランド(以下「GMB」)」すなわち「最も多くのお客様から信頼されることによって、最も多くの社会貢献をなしうる企業(ブランド)」となることを長期目標としております。この実現を加速するため、2030年を見据えた長期ビジョン「GMB2030」の中で、当社のあるべき姿として「豊かな社会と自然の循環にコミットする“命を支えるプラットフォーマー”」を掲げております。食料の生産性・安全性を高めるソリューション、水資源・廃棄物の循環を促進するソリューション、都市環境・生活環境を向上させるソリューションを通じて持続可能な社会へ最大限の貢献をすることにより、長期にわたる持続的発展をめざすべく、次の内容に取組んでおります。 (1) 経営体制改革事業環境は絶え間なく変化しており、収益改善の取り組みだけでなく、事業環境に適した経営体制が必要となります。直近では当社の売上高に占める機械の海外事業の比率が高まったことにより、機械事業と水・環境事業におけるビジネスモデルの違いがより顕著に表れ、同じ枠組みの中での経営は最適解とは言えない状況となりました。従って、今後は機械事業、水・環境事業がそれぞれの事業特性を十分発揮できる自立運営をめざした体制へ移行を進めてまいります。機械事業では、日本を中心とした組織や体制から脱却し、事業軸・機能軸・地域軸の権限と責任を明確にしたスピーディかつメッシュの細かい効率的な経営ができる体制をめざします。まず第一弾として、コーポレート機能の一部を機械事業本部へ移管しました。2025年一年をかけ、さらなる機能移管及び地域統括体制の権限の見直しを進めてまいります。これにより、機能重複の解消による間接コストの削減と競争に打ち勝てる機敏な意思決定を可能にします。水・環境事業では、既に自立運営が可能な体制ができつつあったため、水環境カンパニーとして2025年からスタートしております。権限委譲により機敏な意思決定ができる体制に移行することで、ソリューションビジネスへの参入を加速させ「インフラソリューションプロバイダー」をめざしてまいります。コーポレート機能は縮小させつつ、より事業に寄り添った再編を行います。当該再編により、外部の動向や要請をいち早く認識し展開できる、プロアクティブな活動を行うことのできる体制を整えます。開発においては地域・製品事業・技術の3軸が一堂に会しての議論をスタートさせ、製品開発ロードマップの見直しを始めております。開発効率の向上では、特に解析等をフル活用し、企画構想から開発・生産まで一貫した工程改革を進め、目標の30%向上に向けた活動を加速させます。海外人財の育成においては、各国の研究開発拠点からグローバル技術研究所(国内研究開発拠点)への人財受け入れを開始し、お互いの技術力向上に向けた取組みを始めております。クボタの成長は、その時々のニーズを掴んだヒット商品に支えられてきました。世の中の技術革新をリードすべく、地域・製品事業・技術の3軸の連動性を高め、ヒット商品の創出に邁進してまいります。 (2) 製品・事業ポートフォリオの見直しによる資本効率の向上資本効率の向上には「売上高利益率」と「投下資本回転率」の改善が不可欠ですが、十分に進んでいないのが現状です。これらの課題に対しては事業ポートフォリオの見直しを通じ、収益性の高い事業への経営シフトを行うことで改善を図ります。水・環境事業では既にいち早く取組みを開始しており、鉄鋼機械市場向けの一部鋳鋼製品の撤退、浴槽製品の製造・販売の終了、サウジアラビアでの生産子会社の撤退などを通じて、営業利益率改善の兆しが見え始めております。事業ポートフォリオについては次期中期経営計画の重要なピースの一つとなるため、引き続き取り組んでまいります。資本効率の改善には現中期経営計画の柱である収益性の高い成長ドライバーの伸長も重要です。需要の変動により機械事業の直近の成長率はやや減速しておりますが、北米建設機械事業ではシェアは順調に増加しており、小型CTL(コンパクトトラックローダ)の導入による参入市場領域の拡大が進んでおります。インド事業においてはトラクタ新製品の導入や自社による小売金融事業の開始など、多少計画より遅れている部分もありますが、施策は着実に進んでおります。水・環境事業ではO&M(オペレーション&メンテナンス)などソリューションの受注が増加しております。機械アフターマーケット事業やASEAN機械事業はさらなる成長に向けて取組みを進めてまいります。通常のコスト改善活動も並行して進めていきます。特に2025年度の市場需要見通しは現中期経営計画期間の中で最も厳しく、固定費の削減など、通常以上に厳格な管理が求められる状況です。現中期経営計画で目標としている営業利益率12%の達成は困難な見込みですが、収益性の改善に最後まで粘り強く取組んでいきます。 (3) 次期中期経営計画への準備2026年度からの次期中期経営計画を策定するプロジェクトチームを立ち上げます。成長ドライバーの推進など成長戦略の加速と経営体制改革を実のあるものとすべく、抜本的な事業体質強化、経営全体の効率化、そして新たな付加価値を創出できる体制への変革をめざし、全社一丸となって取り組んでまいります。 |
経営者による財政状態の説明
| 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】文中の将来に関する事項は、当年度末現在において当社が判断したものです。 (1) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容当年度における、経営者の視点による当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」)の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。 ① 経営成績当年度の売上高は前年度比44億円(0.1%)減少して3兆163億円となりました。国内売上高は機械部門、水・環境部門、その他部門共に減収となり、前年度比107億円(1.7%)減の6,325億円となりました。海外売上高は機械部門及び水・環境部門で増収となり、前年度比62億円(0.3%)増の2兆3,838億円となりました。当年度の海外売上高比率は、前年度比0.3ポイント上昇して79.0%となりました。営業利益は、値上げ効果や為替変動などの増益要因はありましたが、欧州、北米を中心とした機械部門での減販損やインセンティブコストの増加などにより、前年度比132億円(4.0%)減の3,156億円となりました。税引前利益は前年度比70億円(2.0%)減少して3,353億円となりました。法人所得税は807億円の負担、持分法による投資損益は51億円の利益となり、当期利益は前年度比3億円(0.1%)減の2,597億円となりました。親会社の所有者に帰属する当期利益は前年度を80億円(3.4%)下回る2,304億円となりました。 事業別セグメントの外部顧客への売上高及びセグメント利益の状況は次のとおりです。(機械)当事業セグメントでは主として農業機械及び農業関連商品、エンジン、建設機械の製造・販売等を行っております。当事業セグメントの売上高は前年度と同水準の2兆6,369億円となり、売上高全体の87.4%を占めました。国内売上高は前年度比1.2%減の3,119億円となりました。主に農業機械及び建設機械の減少により減収となりました。海外売上高は為替変動の影響もあり前年度比0.2%増の2兆3,250億円となりました。北米では、建設機械の販売は政府のインフラ開発需要を背景に堅調に推移しましたが、トラクタはレジデンシャル市場の低迷及び農作物価格の下落の影響を受け苦戦しました。欧州では、建設機械及びエンジンは経済の減速に伴う市場縮小が続いたことで販売が減少し、トラクタも需要が弱く低迷しました。アジアは、タイでは一部洪水の影響が残るものの、農業機械は稲作向け製品を中心に販売が回復し、建設機械も販売が増加しました。インドでは、第2四半期までは干ばつや総選挙の影響により市場が縮小しましたが、第3四半期以降は十分な降雨と収穫量により回復に転じました。当事業のセグメント利益は、値上げ効果や為替変動などの増益要因はありましたが、主に欧州や北米での減販損やインセンティブコストの増加などにより、前年度比2.4%減少して3,474億円となりました。 (水・環境)当事業セグメントでは主としてパイプシステム(ダクタイル鉄管、合成管等)、産業機材(反応管、スパイラル鋼管、空調機器等)、環境(各種環境プラント、ポンプ等)に係る製品の製造・販売等を行っております。当事業セグメントの売上高は前年度比0.5%減少して3,626億円となり、売上高全体の12.0%を占めました。国内売上高は前年度比1.3%減の3,038億円となりました。産業機材事業の売上は増加しましたが、主にパイプシステム事業での減少により減収となりました。海外売上高は3.9%増の588億円となりました。主に環境事業での売上増加により増収となりました。当事業セグメントのセグメント利益は値上げ効果や原材料価格の改善などの増益要因はありましたが、経費の増加などにより前年度比2.9%減少して297億円となりました。 (その他)当事業セグメントでは主として各種サービスの提供等を行っております。当事業セグメントの売上高は前年度比14.0%減少して168億円となり、売上高全体の0.6%を占めました。当事業セグメントのセグメント利益は前年度比36.1%減少して10億円となりました。 ② 財政状態当年度末の資産合計は前年度末比6,594億円増加して6兆187億円となりました。資産の部では、主に北米で金融債権が増加し、有形固定資産も生産体制強化や災害対策のための投資などにより増加しました。負債の部では、主に北米での社債発行により社債及び借入金が増加しました。親会社の所有者に帰属する持分は、主に為替の変動などに伴うその他の資本の構成要素の改善や利益の積み上がりにより増加しました。親会社所有者帰属持分比率は前年度末比0.6ポイント増加して41.2%となりました。 ③ キャッシュ・フロー当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは2,821億円の収入となりました。主に運転資本の改善により、前年度比2,994億円の収入増となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは2,089億円の支出となりました。主に設備投資に伴う有形固定資産の取得や無形資産の取得に係る支出により、前年度比では354億円の支出増となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは263億円の支出となりました。主に資金調達の減少により、前年度比2,047億円の収入減となりました。これらのキャッシュ・フローに為替変動の影響を加えた結果、当年度末の現金及び現金同等物残高は期首残高から730億円増加して2,951億円となりました。 (2) 資金の源泉及び流動性当社の財務の基本方針は、操業に必要となる資金源を十分に確保すること及びバランスシートの健全性を強化することです。当社は運転資金の効率的な管理を通じて、事業活動における資本効率の最適化を図るとともに、グループ内の資金を親会社や海外の金融子会社に集中させることにより、グループ内の資金管理の効率改善に努めております。当社は営業活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物を内部的な資金の源泉と考えており、資金需要に応じて金融機関からの借入、社債の発行、債権の証券化による資金調達、コマーシャル・ペーパーの発行等を行っております。運転資金及び設備投資のための資金については、主として内部資金により充当することとしており、必要に応じて金融機関からの借入金等を充当しております。当年度の社債及び借入金の使途は、主として販売金融、設備投資及び運転資金への充当となっております。なお、資金調達に係る債務の残高については「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 ※16 社債及び借入金」をご参照ください。現在のところ、当社は健全な財務基盤及び安定したキャッシュ・フロー創出力により、事業運営や投資活動のための資金調達に困難が生じることはないと考えております。 (3) 生産、受注及び販売の実績① 生産実績当年度における事業別セグメントの生産実績は次のとおりです。 事業別セグメントの名称金額(百万円)前年度比(%)機械2,535,695△0.2水・環境371,354△3.5その他16,764△12.0合計2,923,813△0.7(注) 1 セグメント間取引については相殺消去しております。2 金額は販売額をもって計上しております。 ② 受注実績当年度における事業別セグメントの受注実績は次のとおりです。なお、機械では一部を除き受注生産を行っておらず、水・環境及びその他においても一部受注生産を行っていない事業があります。 事業別セグメントの名称受注高(百万円)前年度比(%)受注残高(百万円)前年度末比(%)機械5,568△19.83,144△30.9水・環境257,769△12.8298,860△6.8その他335△81.5366△77.2合計263,672△13.4302,370△7.5(注) セグメント間取引については相殺消去しております。 ③ 販売実績当年度における事業別セグメントの販売実績は次のとおりです。 事業別セグメントの名称金額(百万円)前年度比(%)機械2,636,8740.0水・環境362,631△0.5その他16,776△14.0合計3,016,281△0.1(注) 1 セグメント間取引については相殺消去しております。2 販売額が総販売額の10%以上に及ぶ販売先は前年度、当年度ともにありません。 (4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定当社はIFRS会計基準に準拠して連結財務諸表を作成しており、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を使用しております。実際の業績はこれらの見積り及び仮定とは異なる場合があります。見積り及び仮定は継続して見直され、当該見直しによる影響は会計上の見積りの変更として、見積りを変更した報告期間及び将来の報告期間において認識されます。重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 ※2 作成の基礎 (3) 重要な会計上の判断、見積り及び仮定」及び「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 ※3 重要性がある会計方針」に記載しております。 |
※本記事は「株式会社クボタ」の令和6年12期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
※4. この企業は、連結財務諸表ベースで見ると有利子負債がゼロ。つまり、グループ全体としては外部借入に頼らず資金運営していることがうかがえます。なお、個別財務諸表では親会社に借入が存在しているため、連結上のゼロはグループ内での相殺消去の影響とも考えられます。
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

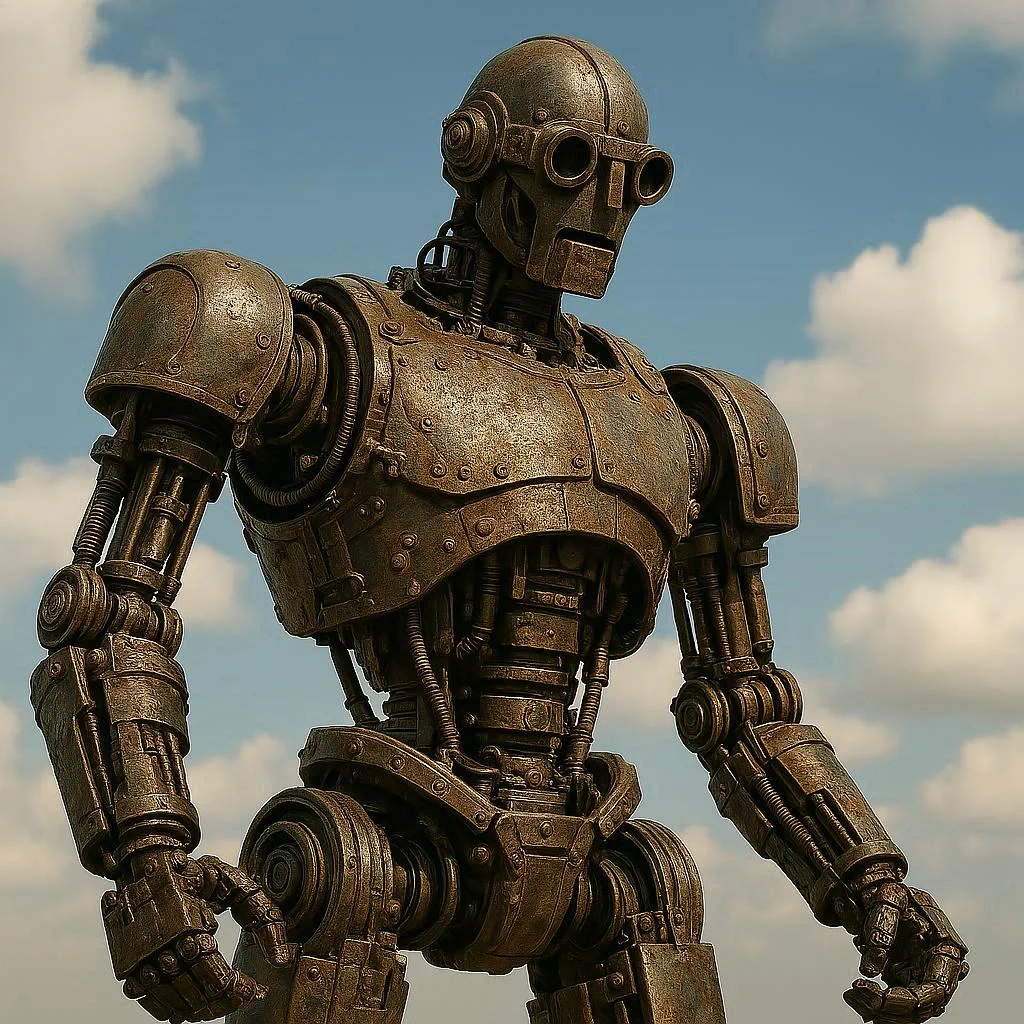

コメント