| 会社名 | JFEホールディングス株式会社 |
| 業種 | 鉄鋼 |
| 従業員数 | 連61296名 単55名 |
| 従業員平均年齢 | 47歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 22.9年 |
| 平均年収 | 12643000円 |
| 1株当たりの純資産(連結) | 3495.2円 |
| 1株当たりの純利益(連結) | 144.43円 |
| 決算時期 | 3月 |
| 配当金 | 100円 |
| 配当性向 | 106.7% |
| 株価収益率(PER) | 19.5倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(連結) | 8.3% |
| 営業活動によるCF | 3789億円 |
| 投資活動によるCF | ▲2831億円 |
| 財務活動によるCF | ▲1574億円 |
| 研究開発費※1 | 40.41億円 |
| 設備投資額※1 | 3184.77億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 4276.14億円 |
| 株主資本比率※2 | 40.1% |
| 有利子負債残高(連結)※3※4 | 0円 |
経営方針
| 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】(1) 会社の経営の基本方針企業理念:JFEグループは、常に世界最高の技術をもって社会に貢献します。行動規範:挑戦。柔軟。誠実。パーパス: ・JFEスチール㈱ ねがう未来に、鉄で応える。 ・JFEエンジニアリング㈱ くらしの礎を 創る・担う・つなぐ ? Just For the Earth ・JFE商事㈱ 世界をつなぐ。鉄でつなぐ。 (2) 企業構造JFEグループは鉄鋼、エンジニアリング、商社の3つの事業を中心とした企業グループです。鉄を中核として、エネルギー技術や資源リサイクル技術等幅広い分野に領域を広げており、世界最高の技術に裏打ちされた3つの事業が生み出し続けるシナジーを、持続可能な社会の構築に向けて更に拡大していきます。 (3) JFEグループの競争力の源泉(鉄鋼事業・商社事業)鉄鋼事業は、世界有数の生産規模と高い技術開発力を有する銑鋼一貫メーカーのJFEスチール㈱を中核としており、お客様や社会の多様なニーズにお応えする鉄鋼製品をグローバルに供給しています。また商社事業は、JFE商事㈱を中核として、鉄鋼製品を中心に、鉄鋼原料・非鉄金属・化学品・資機材・船舶から食品・エレクトロニクスまで幅広く取り扱い、サプライチェーン全体の付加価値を向上させるサービスをグローバルに提供しています。鉄鋼・商社事業の競争優位の源泉は、①お客様のニーズに基づいた最先端の「技術開発力」と、②製造現場で培われてきた「生産」の実力、および③JFEスチール㈱とJFE商事㈱が一体となって長年築いてきた強固なお客様との信頼関係に基づく「販売力」の3つを基礎としています。これらをベースに、お客様のニーズに沿った新たな価値を創造し、最適なソリューションを提供し続けてきました。これらの競争優位性は私たちが長年の努力により積み重ねてきた貴重な財産であり、他社が容易に真似できない持続的成長のドライバーです。 ○新たな価値の創造を可能とする技術開発力(鉄鋼事業)世界各地のお客様の高度なご要望にお応えすることで、業界をリードする技術力を蓄積してきました。幅広い分野での高機能・高品質の商品やサービスの開発と提供を通じて新たな価値を創造し、世界中の産業や社会の発展と人々の生活の進化に貢献しています。また、優れた環境保全・省資源・省エネ技術により、世界で最も低いレベルの環境負荷で鉄鋼製品を生産することができ、その技術を世界各地の環境対策に役立てるとともに、成長の機会として活用しています。 ○製造現場で培われてきた「生産」の実力(鉄鋼事業)JFEスチール㈱の製造現場においては、長年の鉄鋼製品製造で培われてきた質が高く、高い生産性を有する製造技術、知的財産、操業ノウハウ等が無数に蓄積されています。これらに加えて、低CO2での高品質鋼材製造を可能にするGX対応技術、データサイエンス・ロボティクス等のDX技術等が融合した製造実力は、同社固有の競争力の源泉です。なお、内需の減少という事業環境の変化に対応するため、高炉休止による生産効率の維持・向上を実行し、常に国内最適生産体制を構築してまいります。具体的には、現在の粗鋼生産能力2,600万トン(高炉7基体制、仙台製造所電気炉を除く)に対し、2027年度の粗鋼生産能力を2,100万トン程度へスリム化します。また2028年度には西日本製鉄所(倉敷地区)で革新電気炉を稼働させ、高炉5基+電気炉1基体制とします。 ○ニーズへの対応力と安定したお客様基盤(鉄鋼事業・商社事業)長年のお取引による数多くのお客様との双方向のコミュニケーションにより、お客様との信頼関係を構築してきました。お客様との綿密なニーズの摺り合わせや、開発初期段階からの協働等の取り組みを通じて新たな価値を創造し、お客様の課題解決に貢献してきました。結果として、他社が容易に入り込むことができない堅固なお客様基盤を構築しています。 ○JFEグループのグローバル鋼材サプライチェーンマネジメント網(商社事業)JFEスチール㈱と戦略的に連携を取りながら日本、中国、北米、豪州、インド、欧州でグローバル展開する鋼材サプライチェーンマネジメントを構築しています。日本で製造されるJFEスチール材のみならず、鉄鋼事業の海外製造拠点やJFEグループのアライアンス先で製造される鋼材も含めたJFEブランドを、世界各地に製造拠点を展開するお客様へ良質なサービスとともに提供しています。またお客様のニーズに合わせ、スリット等の切断加工製品や、環境規制・省エネを背景に拡大している自動車用モーターコアや高効率変圧器用トランスコア等の鋼材加工部品をグローバルに提供できる体制を整えています。 ○JFEグループの中核商社としての機能(商社事業)変化が激しいグローバル市場においてお客様のニーズを先取りし、中核商社としてJFEグループの全体最適を考えながらトレードビジネスや事業を展開し、お客様への価値貢献を最大化しています。こうした他社にはないグループ全体最適を追求する商社事業モデルを通じ、グローバル市場におけるグループ全体の競争優位性を維持拡大していきます。 (エンジニアリング事業)エンジニアリング事業は、JFEエンジニアリング㈱を中核として、ガス・石油・水道パイプライン、再生可能エネルギー発電設備、都市ごみ焼却炉、水処理システム、橋梁・港湾構造物等、人々が生活する上で不可欠となるインフラの構築等を行っており、それらのEPC(設計・調達・建設)、O&M(運転・維持管理)に加え、リサイクル・発電事業等の事業運営を展開しています。また数多くの国内支店・営業所、海外現地法人・海外支店を有することでグローバルかつきめ細かな販売ネットワークを構築しており、長年にわたり、官公庁や、大手電力会社・ガス会社等様々な民間企業のお客様へ高度な技術・サービスを提供しています。エンジニアリング事業の競争力の源泉は、時代の変化に対応する先進かつ多種多彩な商品・サービスや、高度なプロジェクト遂行能力、ものづくりのノウハウを強みにした事業運営に至るまでの幅広い事業展開を基礎としています。 ○高度な基盤技術、多種多彩な商品技術造船事業がベースの加工・組立技術と鉄鋼事業がベースの素材・燃焼技術を融合・進化させた高度な技術力を強みとして、エネルギー・環境や橋梁等幅広い分野で事業を展開してきました。とりわけ、世界的な課題となっている地球温暖化に対しても、次世代エネルギーの創出や、高効率発電プラントによるCO2排出量の抑制等、課題解決に向けた技術を数多く保有しており、これらの技術に基づいた新たなビジネスモデルの企画・立案・推進に積極的に取り組んでいます。 ○豊富な実績と多様な人材によるプロジェクト遂行能力エネルギー・環境や橋梁等様々な分野で、設計から引き渡しまで、お客様のニーズに即した高機能・高品質な施設を数多く建設してきました。また、国内最大級の鋼構造物製作工場をはじめとする生産拠点を有しており、高品質・低コストでの製品供給を可能としています。更に、アジア諸国を中心とした海外拠点にグローバルエンジニアリング体制を構築し、一段と競争力を強化しています。 ○ものづくりのノウハウを強みにした事業運営環境・上下水等のプラントを中心として、長きに亘りオペレーション・メンテナンスのノウハウを培い、公共サービス分野で数多くの官民連携事業を手掛けています。また、自らが建設したプラントで、リサイクル事業や再生可能エネルギー発電事業を行い、循環型社会、持続可能な社会の構築に取り組んできました。こうした、ものづくりや運営ノウハウを強みにした官民連携事業やエネルギーサービス事業等の運営型事業領域を更に拡大していきます。 (4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題JFEグループを取り巻く事業環境は、国内における需要の減少や中国材の廉価での輸出拡大による海外市場の混乱等足元の厳しい状況が継続することが見込まれ、更に、保護主義の流れが加速する等、これまで以上に環境悪化のリスクが高まることが想定されます。このような厳しい環境において、「JFEグループの目指す姿」に向かっていくために、「JFEビジョン2035」および「第8次中期経営計画」(対象:2025~2027年度)を策定しました。 <JFEビジョン2035・第8次中期経営計画(収益目標)> [第8次中期経営計画](鉄鋼事業)徹底的に強靭化した国内体制において、競争優位性の源泉であるカーボンニュートラルを含めた革新技術や高付加価値品を生み出し、海外成長地域において優位性のある技術・商品・人材を活かして事業を拡大してまいります。○国内:高付加価値品比率の引き上げと国内生産体制の徹底したスリム化による収益力の向上・高付加価値品の比率向上 JFEスチール㈱の技術力を活かした高性能電磁鋼板や自動車用高張力鋼板、着床式洋上風力発電の基礎構造物用大単重厚板、新エネルギー対応用厚板/シームレスパイプ等の商品を拡販し、輸出汎用品から更に置換していくことで、高付加価値品比率を2024年度実績48%から2027年度60%へ引き上げ、製品トン当たり利益の向上を図っていきます。・国内生産体制の再構築および事業の再編 粗鋼生産能力2,600万トン(高炉7基体制(仙台製造所電気炉除く))に対し、高炉休止により2027年度粗鋼生産能力2,100万トン程度へとスリム化を実施します。2028年度には西日本製鉄所(倉敷地区)にて革新電気炉を稼働させ、高炉5基+電気炉1基体制とします。 ○海外:海外成長地域のトップクラスのパートナーとのインサイダー型事業拡大JSWスチール・リミテッド(インド)、ニューコア・コーポレーション(北米)とのパートナーシップはJFEスチール㈱の強みの一つです。グローバルな成長機会を求め、海外トップクラスのパートナーとのインサイダー型事業を推進します。既存事業での利益拡大に加え、引き続き技術優位性がある分野・領域(電磁鋼板/自動車用鋼板・グリーン鉄源等)の事業に注力し、ポートフォリオの最適化を図るとともに、インドにおける電磁鋼板拡販等の前中期投資案件の早期立ち上げに経営資源を集中させていきます。 (エンジニアリング事業)多様な事業によるポートフォリオを強みとして収益基盤を強化しつつ、「サーキュラーエコノミーの実現」を通じて事業を拡大するとともに気候変動問題の解決を図ってまいります。 (商社事業)国内は数量・案件数に拘り存在感を高め、海外では需要が伸張するエリアにおいてM&Aも含めた加工拠点の増強等によりインサイダー化による現地完結型ビジネスを推進します。 (京浜地区の土地活用)「OHGISHIMA2050」の推進にあたり、公共・公益性の高い土地利用転換を図っております。土地事業では、2027年度での累積事業収支は850億円、2035年度に1,000億円を達成します。加えて、京浜地区の立地と当社グループが持つリソースを活用した新規事業の立上げにより企業価値の向上を図り、2035年度に土地事業(賃貸)および事業利用による利益100億円/年を目指します。 (環境的持続性に向けた取り組み)前中期で経営上の極めて重要な経営課題と位置付けてきた「気候変動問題」を中心に、グループ全体で積極的に取り組んでいきます。 (人財戦略等)当社グループでは変革の時代において「人材こそが企業成長の原動力」であると考えています。今回長期ビジョンの策定においては、その経営戦略の実行・実現に向けて「会社の成長」と「社員の成長」を連動させる施策が必要であるとの認識から、長期的な目線での人財戦略を策定しました。 (コーポレートガバナンス)カーボンニュートラルやDX等、当社事業を取り巻く経営環境が、急激かつ大きく変化していくことが想定される中、2025年度より「監査等委員会設置会社」に移行することとしました。前中期で取り組んできた取締役会の実効性向上・監督機能強化に向けた取り組みを更に進展させ、経営の意思決定の迅速化、取締役会における経営方針や戦略に関する議論の充実、および更なる取締役会の監督機能の強化等を目指します。また、役員報酬に関しても、2025年度に、役員報酬に占める業績連動報酬の比率の向上、ESG報酬として新たな算定指標の追加、株式報酬について株価や株主資本コストを意識した算定指標への変更を実施しました。 なお、JFEエンジニアリング㈱は、同社が2017年6月および2020年6月に沖縄県竹富町と契約した海底送水管更新工事に関して、入札談合等関与行為防止法違反および公契約関係競売入札妨害罪により同社元社員が有罪判決を受けたことから、建設業法に基づき、2025年5月に国土交通省より全国における水道施設工事業に関する営業のうち公共工事に係るものについて、営業停止命令を受けました。本事案を厳粛かつ真摯に受け止め、再発防止策を引き続き実行することにより、早期の信頼回復に努めてまいります。 (DX)当社グループでは「長年蓄積された操業データ・ノウハウ」と「広範な事業領域から生み出される技術」が競争優位性の源泉であると捉えています。前中期に引き続きDXによるビジネス変革と生産プロセス・業務プロセス革新により、強靭な収益基盤構築を目指します。 (財務健全性の確保)第8次中期経営計画期間中のキャッシュアロケーション(3ヵ年総額)は以下のとおりになります。なお、第8次中期経営計画の財務目標としては、Debt/EBITDA倍率およびD/Eレシオを、それぞれ3倍程度、60%程度と設定しました。財務健全性を確保しつつ、成長投資・カーボンニュートラル対応投資と安定的な株主還元を両立させるべく、財務目標を意識した経営を実行してまいります。 (株主還元方針)当社は株主の皆様への利益還元を最重要経営課題の一つと考えており、グループ全体として持続性のある企業体質の確立を図りつつ、積極的に配当を実施していく方針としております。第8次中期経営計画においては、引き続き配当性向30%程度といたしますが、安定的に配当を実施する観点から80円/株を下限とする方針といたします。 (企業価値向上に向けた取り組み)当社は、株価を重要な経営指標の一つとして認識しており、現状当社のPBR(株価純資産倍率)が1倍を大きく下回っていることを重要な課題として認識しております。株主資本コストを上回るROE(自己資本利益率)の安定的な実現、市場からの信頼性を向上させていくことで、企業価値を向上させ、資本市場の評価を高めてまいります。また、社会の持続的発展と人々の安全で快適な暮らしに寄り添う「なくてはならない」存在であり続けることを目指してまいります。 (注) 上記の記載には、2025年5月8日の第8次中期経営計画、決算発表時点の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測や目標が含まれております。 |
経営者による財政状態の説明
| 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1) 経営成績等の状況の概要① 財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度における当社グループの経営成績等の状況の概要は、「(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容 a.当連結会計年度の経営成績の分析」に記載しております。 ② キャッシュ・フローの状況当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、「(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容 b.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性についての分析」に記載しております。 ③ 生産、受注及び販売の実績当社グループにおける生産実績については鉄鋼事業の粗鋼生産量を、また受注実績についてはエンジニアリング事業の受注実績・受注残高を記載しております。鉄鋼事業は、特定顧客からの受注については反復循環的に生産しているため、受注実績の記載を省略しております。エンジニアリング事業は、請負工事を中心としているため、生産実績を金額あるいは数量で示すことはしておりません。商社事業は、受注生産形態をとらない製品が多いため、生産実績・受注実績を金額あるいは数量で示すことはしておりません。a.生産実績当連結会計年度における生産実績は、以下のとおりであります。 セグメントの名称粗鋼生産量(千トン)前期比(%)鉄鋼事業(うちJFEスチール㈱)23,196(21,946)△6.5(△6.4) b.受注実績当連結会計年度における受注実績は、以下のとおりであります。 セグメントの名称受注実績(百万円)(※1)前期比(%)(※2)受注残高(百万円)(※1)前期比(%)(※2)エンジニアリング事業579,560△3.2994,468+0.9 (注)1 ※1 自治体等から受託したごみ処理施設等の長期O&M契約について、前連結会計年度以前は単年度の売上収益相当額のみを受注実績に計上しておりましたが、当連結会計年度より、契約時に総額を一括計上する方法へ変更しております。当連結会計年度の受注実績および受注残高を旧計上方法で計算した場合の金額は558,517百万円、603,017百万円であります。2 ※2 前期比は、新計上方法に基づく前連結会計年度の数値および当連結会計年度の数値を比較して算出しております。 c.販売実績当連結会計年度における販売実績は、以下のとおりであります。 セグメントの名称販売実績(百万円)前期比(%)鉄鋼事業3,365,191△9.4エンジニアリング事業569,815+5.5商社事業1,438,559△2.6計5,373,566 調整額△513,919―合計4,859,647△6.1 (注) 主な相手先別の販売実績および総販売実績に対する割合については、各販売先への当該割合が100分の10未満のため、記載を省略しております。 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、特に記載のあるものを除き、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 ① 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定当社グループの連結財務諸表はIFRSに準拠して作成しております。重要性のある会計方針については「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 3.重要性のある会計方針」、重要な見積りについては「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 4.重要な会計上の判断、見積りおよび仮定」に記載しております。 ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容a.当連結会計年度の経営成績の分析当連結会計年度の国内および海外経済は、緩やかに持ち直しつつも、中国経済の停滞継続や人手不足の影響等もあり、一部に足踏みがみられました。加えて、物価上昇や、アメリカの通商政策による影響等により、先行きの不透明感が強まっております。このような状況のもと、JFEグループでは、構造改革の完遂、高付加価値品比率の引き上げ、販売価格体系の見直しにより、収益基盤の強化を進めてまいりましたが、国内需要の低迷、中国による周辺国への廉価での輸出拡大により、事業利益および親会社の所有者に帰属する当期利益ともに前連結会計年度に比べ減益となりました。当連結会計年度のセグメント別の業績は、以下のとおりです。鉄鋼事業は、国内外の需要や海外鋼材市況の低迷等を背景に、当連結会計年度の連結粗鋼生産量は2,320万トンと前連結会計年度と比べ減少しました。売上収益については、販売数量の減少や海外鋼材市況の悪化等を受け、3兆3,651億円と前連結会計年度に比べ3,509億円(9.4%)の減収となりました。セグメント利益については、構造改革の効果発現および継続的な販売価格の改善やコスト削減に取り組んだものの、海外鋼材市況の悪化や販売数量の減少に加え、棚卸資産評価差等の一過性の減益要因等により、前連結会計年度に比べ1,664億円(82.1%)の大幅な減益となる363億円となりました。エンジニアリング事業は、受注済プロジェクトを着実に遂行した結果、売上収益は5,698億円と前連結会計年度に比べ299億円(5.5%)の増収となり過去最高を更新しました。セグメント利益については、洋上風力案件(モノパイル)発注時期遅れ等により、前連結会計年度に比べ50億円(20.5%)の減益となる193億円となりました。商社事業は、2024年5月に買収したスタッドコ・ビルディング・システムズ・US・LLCおよびスタッドコ・コーポレーションからの収益貢献等があったものの、国内建設分野の需要低迷継続等により、売上収益は1兆4,385億円、セグメント利益は479億円となり、前連結会計年度に比べそれぞれ379億円(2.6%)の減収、10億円(2.0%)の減益となりました。以上の結果、当社単体業績等と合わせ、当連結会計年度における連結での売上収益は4兆8,596億円となり、前連結会計年度に比べ3,150億円(6.1%)の減収となりました。事業利益は1,353億円となり、前連結会計年度に比べ1,629億円(54.6%)の減益となりました。税引前利益は1,443億円、親会社の所有者に帰属する当期利益は918億円となり、前連結会計年度に比べそれぞれ1,240億円(46.2%)、1,056億円(53.5%)の減益となりました。 b.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性についての分析当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが3,789億円の収入(前連結会計年度に比べ収入が1,000億円減少)であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として2,831億円の支出(前連結会計年度に比べ支出が421億円減少)であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは957億円の収入(前連結会計年度に比べ収入が580億円減少)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出を中心として、1,574億円の支出(前連結会計年度に比べ支出が1,120億円増加)となりました。この結果、当連結会計年度末の有利子負債残高は前連結会計年度末に比べ638億円減少し、1兆7,664億円となり、現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ702億円減少し、1,728億円となりました。なお、有利子負債は、社債、借入金及びリース負債であります。 当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、次のとおりです。当社グループの運転資金需要のうち主なものは、原材料等の仕入、製造費用、受注建設工事の費用支払および販売費及び一般管理費等の営業費用です。投資資金需要の主なものは、鉄鋼事業における収益向上、GX(グリーントランスフォーメーション)、DX(デジタルトランスフォーメーション)等の戦略投資および製造基盤整備を目的とした設備投資です。運転資金は、主に金融機関からの借入やコマーシャル・ペーパーの発行等により調達しております。投資資金は、自己資金を基本としておりますが、自己資金を上回る資金需要については、金融機関からの長期借入金や社債の発行等で調達しております。当社グループでは、複数の金融機関との間でコミットメントラインを設定することにより、十分な資金の流動性を確保しております。 c.目標とする指標の達成状況当社グループは、2021年5月に公表した第7次中期経営計画(2021~2024年度)の中で、以下の財務・収益目標を掲げ、鉄鋼事業の構造改革の完遂、量から質への転換等の施策を着実に遂行することで、収益基盤の強化を進めてまいりました。しかしながら、想定を大幅に超える鉄鋼の事業環境悪化により、最終年度である2024年度において、主要な財務・収益目標を達成することはできませんでした。一方、インドを中心とした成長マーケットやカーボンニュートラル社会実現に向けたグリーン鋼材等の需要は底堅いとされ、これらの需要を確実に捕捉するため、「第8次中期経営計画」(2025~2027 年度を対象)に基づく取り組みを進めてまいります。(第8次中期経営計画については、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」をご参照ください。) ■第7次中期経営計画 目標(2024年度)実績(2021年度)(2022年度)(2023年度)(2024年度)グループ全体連結事業利益3,200億円4,164億円2,358億円2,982億円1,353億円親会社の所有者に帰属する当期利益2,200億円2,880億円1,626億円1,974億円918億円ROE10%15.7%7.9%8.6%3.7%Debt/EBITDA倍率3倍程度2.8倍3.7倍3.2倍4.5倍D/Eレシオ70%程度80.8%67.8%58.0%54.3%事業会社鉄鋼事業 ・トン当たり利益10千円/トン14千円/トン7千円/トン10千円/トン2千円/トン・セグメント利益2,300億円3,237億円1,468億円2,027億円363億円エンジニアリング事業 ・セグメント利益350億円260億円134億円243億円193億円・売上収益6,500億円5,082億円5,125億円5,399億円5,698億円商社事業 ・セグメント利益400億円559億円651億円489億円479億円 (注)1 D/Eレシオ:格付け評価上の資本性を持つ負債について、格付け機関の評価により資本に算入しております。2 鉄鋼事業のトン当たり利益:(連結セグメント利益÷単体出荷数量) 目標実績(2021年度)(2022年度)(2023年度)(2024年度)株主還元方針(配当性向)30%程度28.0%28.5%30.9%69.2% なお、当連結会計年度の分析につきましては、「② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容 a.当連結会計年度の経営成績の分析」に記載しております。 |
※本記事は「JFEホールディングス株式会社」の令和7年3月期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
※4. この企業は、連結財務諸表ベースで見ると有利子負債がゼロ。つまり、グループ全体としては外部借入に頼らず資金運営していることがうかがえます。なお、個別財務諸表では親会社に借入が存在しているため、連結上のゼロはグループ内での相殺消去の影響とも考えられます。
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

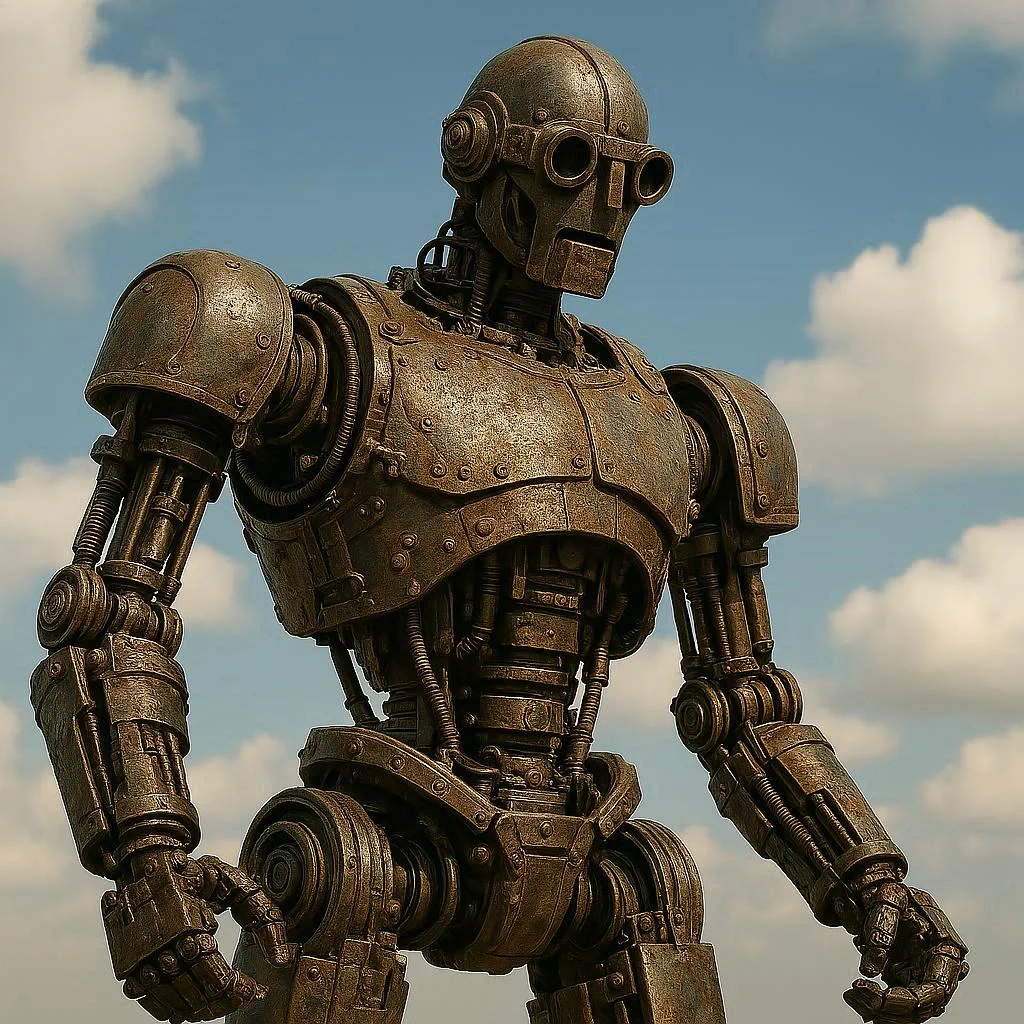

コメント