| 会社名 | 日本製鉄株式会社 |
| 業種 | 鉄鋼 |
| 従業員数 | 連113845名 単28652名 |
| 従業員平均年齢 | 40.5歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 18.2年 |
| 平均年収 | 9051874円 |
| 1株当たりの純資産(連結) | 3563.8円 |
| 1株当たりの純利益(連結) | 350.92円 |
| 決算時期 | 年3 |
| 配当金 | 160円 |
| 配当性向 | 77.8% |
| 株価収益率(PER) | 15.5倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(連結) | 6.4% |
| 営業活動によるCF | 9785億円 |
| 投資活動によるCF | ▲4624億円 |
| 財務活動によるCF | ▲3133億円 |
| 研究開発費※1 | 24億円 |
| 設備投資額※1 | 23.87億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 611.1億円 |
| 株主資本比率※2 | 38% |
| 有利子負債残高(連結)※3※4 | 0円 |
経営方針
| 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】(経営方針)日本製鉄グループは、常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、優れた製品・サービスの提供を通じて、社会の発展に貢献することを企業理念に掲げて事業を行っています。 <日本製鉄グループ企業理念>基本理念日本製鉄グループは、常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、優れた製品・サービスの提供を通じて、社会の発展に貢献します。 経営理念1.信用・信頼を大切にするグループであり続けます。2.社会に役立つ製品・サービスを提供し、お客様とともに発展します。3.常に世界最高の技術とものづくりの力を追求します。4.変化を先取りし、自らの変革に努め、さらなる進歩を目指して挑戦します。5.人を育て活かし、活力溢れるグループを築きます。 (経営環境)中長期的な環境変化については、次のとおり想定しています。世界の鉄鋼需要については、インドも含めたアジア地域を中心に確実な成長が見込まれます。また、カーボンニュートラルに向けた新規ニーズを含め高級鋼の需要は拡大が見込まれます。一方で、国内の鉄鋼需要については、人口減少・高齢化や需要家の海外現地生産拡大等に伴い引き続き減少していくことが想定されます。また、製造業における地産地消・自国産化の傾向が、グローバルに繋がっていた市場の分断を進展させると考えられます。さらに、世界の鉄鋼生産量の5割強を占める中国における需要の頭打ち等により、海外市場における競争が一層激化することが想定されます。世界的に気候変動に関する問題意識が高まるなか、カーボンニュートラルの実現は官民を挙げた総力戦となり、他国に先駆けたカーボンニュートラルスチールの製造技術の確立が、今後の鉄鋼業界における競争力、収益力、ブランド力を決める鍵となると考えています。 2025年度については、世界鉄鋼需要は、中国経済の低迷等を背景に一段と厳しさを増しており、製品・原料価格ともに大幅下落している足元の外部環境は極めて厳しい状況にあります。また、米国関税政策の動向が現時点では見通せないなか、国内外の多方面のお客様に製品・サービスを提供している当社への間接影響が甚大となる可能性があります。 (経営戦略、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題)当社グループは、製鉄事業を中核として、鉄づくりを通じて培った技術をもとに、エンジニアリング、ケミカル&マテリアル、システムソリューションの4つのセグメントで事業を推進しています。製鉄セグメントは、当社グループの連結売上収益の約9割を占めています。当社は、2020年度に断行した抜本的コスト改善による損益分岐点の大幅な引下げに加え、紐付き価格の是正、一貫能力絞込みによる注文選択の効果、海外グループ会社の収益力の向上等により、外部環境に関わらず高水準の事業利益を確保し得る収益構造の構築に取り組んできました。2025年度については、先述した状況下でも、今後、さらなる収益改善施策の実行により利益最大化を図っていきます。2021年3月に策定した「日本製鉄グループ中長期経営計画」の概要と進捗は次のとおりです。 <日本製鉄グループ中長期経営計画(2021年3月5日公表)の概要と進捗>当社は、「総合力世界No.1 の鉄鋼メーカー」を目指し、日本製鉄グループ中長期経営計画を定め、その4つの柱である「国内製鉄事業の再構築とグループ経営の強化」、「海外事業の深化・拡充に向けた、グローバル戦略の推進」、「カーボンニュートラルへの挑戦」及び「デジタルトランスフォーメーション戦略の推進」の実現に向け、諸施策に着実に取り組んでいます。 1.国内製鉄事業の再構築とグループ経営の強化「戦略商品への積極投資による注文構成の高度化」、「技術力を確実に収益に結びつけるための設備新鋭化」、「商品と設備の取捨選択による生産体制のスリム化・効率化」を基本方針として、国内製鉄事業の最適生産体制を構築するとともに、競合他社を凌駕するコスト競争力の再構築と適正マージンの確保による収益基盤の強化を推進しています。ベース操業実力の着実な向上を継続するなかで、生産設備構造対策のロードマップに沿って鹿島第3高炉を含む鉄源1系列等を休止するとともに、注文構成の高度化を推進し、生産能力と固定費規模の適正化を図っています。さらに、本体及びグループを含めた国内製鉄事業のさらなる競争力強化を目的として、当社グループの国内電縫鋼管事業再編、当社による日鉄ステンレス㈱の吸収合併、山陽特殊製鋼㈱の完全子会社化に向けた公開買付けを実施しました。原料事業においては、カーボンニュートラル鉄鋼生産プロセスに必要不可欠な製鉄用原料炭や高品位鉄鉱石の確保、及び原料権益投資を通じた外部環境に左右されにくい連結収益構造の強化を目指しています。この取組みの一環として、豪州Blackwater 炭鉱の権益の20%を取得するとともに、カナダKami 鉄鉱石鉱山の権益の30%取得、新規鉱区の開発・操業を行う合弁会社の設立について関係者と基本合意しました。商社・流通分野では、日鉄物産㈱と当社・グループ会社の連携を強化し、シナジーの追求を図っています。具体的には、カーボンニュートラル原料調達・出資、一貫サプライチェーン強化・最適化、成長分野への拡販等の取組みを推進しています。 2.海外事業の深化・拡充に向けた、グローバル戦略の推進世界の鋼材消費は、2025年さらに2030年に向けて引き続き緩やかな成長が見込まれています。当社は、規模及び成長率が世界的に見ても大きいインド・アジアを中心に事業を展開しており、マーケットの規模や成長を当社の利益成長につなげ得るポジションにあります。このような環境のもと、需要の伸びが確実に期待できる地域において、当社の技術力・商品力を活かせる分野で、需要地での一貫生産体制を拡大し、現地需要を確実に捕捉することで、日本製鉄グループとして、「グローバル粗鋼1億トン体制」を目指しています。なかでも、将来的な市場の拡大及び自国産化のさらなる進展が見込まれるインド市場においては、ArcelorMittal Nippon Steel India Limitedの既存拠点であるハジラ製鉄所にて、現在、能力拡張を進めています。加えて、今後の新たな一貫製鉄所の建設等、さらなる能力拡張に向けた投資も検討しており、こうした取組みを通じて市場におけるプレゼンスの向上を図っていきます。また、最大の高級鋼需要国であり、当社が長年培ってきた技術力・商品力を活かすことができる米国市場においては、当社米国子会社とUnited States Steel Corporation(以下、USスチール)の合併(以下、本合併)に取り組んできました。2024年4月に開催されたUSスチールの臨時株主総会で承認を得て、米国以外の規制当局からの承認も取得しましたが、2025年1月にバイデン前大統領が本合併を阻止する禁止命令を下したため、当社とUS スチールは、同大統領が不適切な政治的理由によりかかる禁止命令を下したとして、当該禁止命令の無効化及びCFIUSの再審査を求めて訴訟を提起するとともに、米政権との協議を続けてきました。その後、同年6月13日に、トランプ現大統領が国家安全保障協定(以下、NSA)の締結を条件に本合併を承認する旨の大統領令を発し、同日、当社とUSスチールは米国政府とNSAを締結したことから、本合併の実行に必要なすべての規制当局からの承認取得が完了し、同年6月18日、本合併が成立しました。これにより、インドとホームマーケットであるASEANに米国を加えた3つの重要拠点を確保することになり、当社のグローバル粗鋼生産能力は8,600万トンに達する見通しです。当社は、グローバル粗鋼1億トン体制の実現を目指し、今後も主要な海外市場における一貫生産体制の拡大を通じた、収益力の向上に取り組んでいきます。 3.カーボンニュートラルへの挑戦脱炭素社会に向けた取組みにおいて欧米・中国・韓国との開発競争に打ち勝ち、引き続き世界の鉄鋼業をリードするべく、「日本製鉄カーボンニュートラルビジョン2050」を掲げ、経営の最重要課題として諸対策を検討・実行しています。東日本製鉄所君津地区における小型試験炉でのSuper COURSE50開発試験において、世界で初めてCO2排出量43%削減を実現し、開発目標を前倒しで達成しました。また、波崎研究開発センター「Hydreams」では小型試験電炉が完成し、2024年12月より大型電炉での高級鋼製造技術開発に向けた試験を開始しました。このように、カーボンニュートラル実現に向けた「高炉水素還元」、「水素による還元鉄製造」及び「大型電炉での高級鋼製造」の3つの革新技術の開発が着実に進展しています。また、当社はカーボンニュートラルの実現を通じて、2つの価値をお客様に提供しています。1つ目は「鉄鋼製造プロセスにおけるCO2排出量を削減したと認定される鉄鋼製品~『NSCarbolexR Neutral』」、2つ目は「社会におけるCO2排出量削減に寄与する高機能製品・ソリューション技術~『NSCarbolexR Solution』」です。これらの価値の提供を通じて、お客様の脱炭素ニーズに応え、国際競争を支えていきます。これらの取組みに対し、脱炭素化における鉄鋼業の役割の重要性が再認識され、グリーンイノベーション基金の鉄鋼業への配分が大幅に拡大されたことを受け、当社としても開発・実機化を加速し、前倒しを行うこととしています。なお、当社のCO2排出量削減目標及び気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の枠組み等に基づく気候変動リスク情報については、統合報告書2024にて開示しています(https://www.nipponsteel.com/ir/library/annual_report.html)。さらに、当社のカーボンニュートラル施策の推進状況やGXスチール市場の形成についてご理解いただくこと等を目的としたGX 説明会と、実際のGX 研究開発設備をご覧いただく見学会を開催しました。説明会・見学会には、機関投資家、金融機関、アナリスト、環境保護団体及びメディアより多くの方々にご参加いただきました(https://www.nipponsteel.com/ir/library/pdf/20250313_100.pdf)。 4.デジタルトランスフォーメーション戦略の推進デジタルトランスフォーメーション戦略に5年間で1,000億円以上を投入し、鉄鋼業におけるデジタル先進企業を目指しています。当期の具体的な取組みの一例として、原料の海上輸送における配船管理において、リアルタイムな運行情報の取得を可能にするシステムを構築し、日々の運行情報を管理できるようになったことに加え、複雑かつ無数にある配船パターンから最適な輸送計画を策定するアルゴリズムを開発・運用し、輸送効率の大幅な向上を実現しました。さらに、東日本製鉄所君津地区で本格運用を開始した、製鋼工程における生産計画を高速立案する出鋼スケジューリングシステムについては、現在、各製鉄所へ順次導入を進め、全社での生産計画の効率化・高度化を推進しています。そのほか、現場に設置した無線IoTセンサのデータを一元管理可能な無線IoTセンサ活用プラットフォーム(NS-IoT)を全社の製銑工程に整備しました。これらのIoT及びAIを活用した操業・設備保全の遠隔管理、予兆監視、自動化並びに実績管理・一貫生産計画の一元化・迅速化等の各DX施策にも引き続き取り組んでいます。 (経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等)「日本製鉄グループ中長期経営計画」の収益・財務体質目標等については、本報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載しています。 (注) 上記(経営環境)と(経営戦略、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題)の記載には、本有価証券報告書提出日時点の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測や目標が含まれている。これらはその発表又は公表の時点において当社が適切と考える情報や分析、一定の前提等に基づき策定したものであり、かかる見積りに固有の限界があることに加え、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性がある。かかる要因については、後記「3 事業等のリスク」を参照されたい。 |
経営者による財政状態の説明
| 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1) 経営成績等の状況の概要① 経営成績の状況当期における当社グループの経営成績の状況の概要は、本報告書「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ①当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容」に記載しています。 ② 当期末の資産、負債、資本及び当期のキャッシュ・フロー当連結会計年度末における資産、負債、資本については、下記のとおりです。 連結総資産は10兆9,424億円と、前連結会計年度に比べて2,278億円増加しました。負債は5兆390億円と、前連結会計年度に比べて3,196億円減少しました。資本は5兆9,033億円と、前連結会計年度に比べて5,475億円増加しました。なお、当期末の親会社の所有者に帰属する持分は5兆3,833億円となり、有利子負債は当期末2兆5,074億円となりました。この結果、親会社の所有者に帰属する持分に対する有利子負債の比率(D/Eレシオ)は0.47倍(劣後ローン・劣後債資本性調整後0.35倍)となりました。 (総資産)現金及び現金同等物は、前期末(4,488億円)から2,236億円増加し、当期末6,725億円となりました。これは、高水準の事業利益による営業活動キャッシュ・フローの収入等によるものです。 営業債権及びその他の債権は、前期末(1兆5,879億円)から1,575億円減少し、当期末1兆4,304億円となりました。これは、売掛金の減少等によるものです。 棚卸資産は、前期末(2兆2,766億円)から775億円減少し、当期末2兆1,990億円となりました。これは、原料価格下落等によるものです。 有形固定資産は、前期末(3兆3,804億円)から2,551億円増加し、当期末3兆6,355億円となりました。これは、名古屋製鉄所への次世代熱延ライン、瀬戸内製鉄所阪神地区(堺)及び九州製鉄所八幡地区への電磁鋼板設備等、戦略商品の能力・品質向上対策への投資を含め競争力優位な設備への選択投資を実行したこと等によるものです。 無形資産は、前期末(1,778億円)から853億円増加し、当期末2,632億円となりました。これは、豪州Blackwater炭鉱の権益の20%を取得したこと等によるものです。 持分法で会計処理されている投資は、前期末(1兆5,379億円)から624億円増加し、当期末1兆6,003億円となりました。これは、持分法による投資利益(1,269億円)等によるものです。 非流動資産のその他の金融資産は、前期末(6,759億円)から2,145億円減少し、当期末4,613億円となりました。これは、政策保有株式の売却を主体とした資産圧縮を実行したこと等によるものです。 (負債)有利子負債は、前期末(2兆7,116億円)から2,042億円減少し、当期末2兆5,074億円となりました。これは、劣後特約付シンジケートローンや公募劣後特約付社債の発行等による増加があった一方で、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使等による減少があったこと等によるものです。 営業債務及びその他の債務は、前期末(1兆8,907億円)から2,193億円減少し、当期末1兆6,713億円となりました。これは、買掛金の減少等によるものです。 その他の非流動債務は、前期末(3,497億円)から712億円増加し、当期末4,209億円となりました。これは、2021年3月5日に公表した中長期経営計画に基づく生産設備構造対策の推進に伴い、東日本製鉄所鹿島地区の鉄源1系列・厚板ライン・大形ライン、並びに関西製鉄所和歌山地区の第4コークス炉等の廃止決定に基づき発生する解体費用等を計上したこと等によるものです。 (資本) 資本金及び資本剰余金は、前期末(8,187億円)から3,292億円増加し、当期末1兆1,479億円となりました。これは、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使等があったことによるものです。 利益剰余金は、前期末(3兆5,255億円)から2,943億円増加し、当期末3兆8,199億円となりました。これは、親会社の所有者に帰属する当期利益(3,502億円)等による増加があった一方で、配当金の支払による減少(1,620億円)があったことによるものです。 その他の資本の構成要素は、前期末(4,915億円)から179億円減少し、当期末4,736億円となりました。これは、為替相場の変動による在外営業活動体の換算差額の増加(981億円)等があった一方で、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の公正価値の純変動による減少(1,236億円)があったことによるものです。 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローについては、下記のとおりです。 営業活動によるキャッシュ・フローは9,785億円の収入となりました(前期は1兆101億円の収入)。投資活動によるキャッシュ・フローは4,624億円の支出となりました(前期は7,106億円の支出)。この結果、フリーキャッシュ・フローは5,161億円の収入となりました(前期は2,995億円の収入)。財務活動によるキャッシュ・フローは3,133億円の支出となりました(前期は5,439億円の支出)。以上により、当期末における現金及び現金同等物は6,725億円(前期は4,488億円)となっています。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)税引前利益5,243億円に、減価償却費及び償却費(3,852億円)の加算、事業再編損(1,352億円)の加算、営業債権及びその他の債権の減少(2,046億円)等の収入がある一方で、持分法による投資損益(1,269億円)の控除の調整に加え、営業債務及びその他の債務の減少(1,045億円)、法人所得税の支払(1,808億円)等による支出がありました。 (投資活動によるキャッシュ・フロー)投資有価証券の売却による収入(2,310億円)等がある一方で、名古屋製鉄所への次世代熱延ライン、瀬戸内製鉄所阪神地区(堺)及び九州製鉄所八幡地区への電磁鋼板設備等、戦略商品の能力・品質向上対策への投資を含め競争力優位な設備への選択投資を実行したこと等による有形固定資産及び無形資産の取得による支出(5,979億円)等がありました。 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 劣後特約付シンジケートローンや公募劣後特約付社債の発行等による資金調達を通じた有利子負債の実質的な増加を伴う収入(717億円)等がある一方で、前期末及び当第2四半期末の配当の支払(1,620億円)、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出(645億円)等による支出がありました。 ③ 生産、受注及び販売の状況a. 生産実績当連結会計年度における生産実績をセグメント毎に示すと、次のとおりです。 セグメントの名称前連結会計年度 金額(百万円)当連結会計年度 金額(百万円)製鉄9,325,8929,255,660エンジニアリング370,240342,927ケミカル&マテリアル234,107241,817システムソリューション314,353345,156合計10,244,59310,185,561 (注) 1 金額は製造原価による。2 上記の金額には、グループ向生産分を含む。 b. 受注状況当連結会計年度における受注状況をセグメント毎に示すと、次のとおりです。 セグメントの名称前連結会計年度受注高(百万円)当連結会計年度受注高(百万円)前連結会計年度受注残高(百万円)当連結会計年度受注残高(百万円)エンジニアリング285,417364,525429,672422,888システムソリューション241,176262,387114,043122,836合計526,594626,913543,715545,725 (注)1 上記の金額には、グループ内受注分を含まない。 2 「製鉄」、「ケミカル&マテリアル」は、多種多様な製品毎に継続的かつ反復的に注文を受けて生産・出荷する形態を主としており、その受注動向は、生産実績や販売実績に概ね連動していく傾向にあり、また、需要動向等についても、本報告書「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ①当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容」において記載していることから、金額又は数量についての記載を省略している。 c. 販売実績当連結会計年度における外部顧客に対する販売実績をセグメント毎に示すと、次のとおりです。 セグメントの名称前連結会計年度 金額(百万円)当連結会計年度 金額(百万円)製鉄8,010,6557,819,748エンジニアリング381,600371,309ケミカル&マテリアル243,327250,873システムソリューション232,513253,594合計8,868,0978,695,526 (注) 1 前連結会計年度及び当連結会計年度における輸出販売高及び輸出割合は、次のとおりである。前連結会計年度当連結会計年度輸出販売高(百万円)輸出割合(%)輸出販売高(百万円)輸出割合(%)3,581,25140.43,580,12241.2 (注) 輸出販売高には、在外子会社の現地販売高を含む。2 主な輸出先及び輸出販売高に対する割合は、次のとおりである。輸出先前連結会計年度(%)当連結会計年度(%)アジア55.657.9中近東5.55.4欧州11.79.6北米13.513.9中南米11.510.9アフリカ1.71.7大洋州0.50.6合計100.0100.0 (注) 輸出販売高には、在外子会社の現地販売高を含む。3 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、各販売先への当該割合が100分の10未満のため、記載を省略している。 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容①当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容(経営成績の分析)当期の世界経済は、インフレ及び金融引締めの長期化等の影響により、下押し圧力が継続しました。日本経済については、持ち直しが期待されたものの、内需は力強さを欠いたまま推移しました。こうした経済状況の下、世界の鉄鋼需給は、未曾有の厳しい経営環境が一段と悪化する危機的な状況が継続しました。需要の低迷に加え、中国経済の減速による需給ギャップの拡大を受けた過剰生産・輸出増加は構造的であり改善の兆しがなく、不透明感が一層増しています。当社は、こうした厳しい経営環境を早くから想定し、2021年3月に策定した「日本製鉄グループ中長期経営計画」において、4つの柱として「国内製鉄事業の再構築とグループ経営の強化」、「海外事業の深化・拡充に向けた、グローバル戦略の推進」、「カーボンニュートラルへの挑戦」及び「デジタルトランスフォーメーション戦略の推進」を掲げ、他社に先んじて収益構造改革を進め、いかなる経営環境にあっても実力ベース連結事業利益(※)6,000億円以上を確保し得る収益構造の構築に向け、諸施策に取り組んできました。2024年度以降、中長期経営計画策定時の想定を上回る規模とスピードで経営環境が悪化しているものの、他社に先駆けて取り組んできた各種の構造対策や収益改善施策が奏功し、世界の同業他社に対し相対的に高水準の収益力を維持しています。(※)事業利益より在庫評価差等を控除し、当社グループとしての実力を表すと認識しているもの。 当期の連結業績については、極めて厳しい事業環境が継続するなかにおいても、従来からの抜本的な収益構造対策等の継続により収益の最大化に取り組むことで、通期の売上収益は8兆6,955億円(前期は8兆8,680億円)、事業利益は6,832億円(前期は8,696億円)、親会社の所有者に帰属する当期利益は3,502億円(前期は5,493億円)となりました。セグメント別の業績は以下のとおりです。当社グループは、製鉄事業を中核として、エンジニアリング、ケミカル&マテリアル、システムソリューションの4つのセグメントで事業を推進しており、製鉄セグメントが連結売上収益の約9割を占めています。 (当期のセグメント別の業績の概況) 製鉄エンジニアリングケミカル&マテリアルシステムソリューション合計調整額連結財務諸表計上額売上収益当期78,7434,0042,6913,39388,833△1,87886,955(億円)前期80,7634,0922,6083,11590,579△1,89888,680セグメント利益当期6,2101461893886,934△1026,832(億円)前期8,210△131533558,707△108,696 <製鉄>製鉄セグメントの売上収益は7兆8,743億円(前期は8兆763億円)、セグメント利益は6,210億円(前期は8,210億円)となりました。製鉄セグメント利益の前期に対する増減△2,000億円の主な要因は次のとおりです。 生産・出荷数量△ 200億円マージン(為替影響含む)△ 300億円コスト改善+ 400億円本体海外事業△ 580億円原料事業+ 230億円鉄グループ会社△ 270億円在庫評価差(グループ会社込み)+ 230億円その他△1,510億円合計△2,000億円 当社は従来からの抜本的な収益構造対策等の継続により収益の最大化に取り組んできましたが、極めて厳しい事業環境が継続するなか、生産・出荷数量(△200億円)やマージン(△300億円)、本体海外事業(△580億円)等の影響が大きく、前期比2,000億円減益のセグメント利益となりました。 <エンジニアリング>日鉄エンジニアリング㈱においては、高い水準の受注残工事を実行しつつ、各事業における成長のための具体的な取組みを着実に進めました。組織・運営面では、セクター制の廃止を柱とする組織改正を実施し、事業遂行面では、昨年度に引き続き収益力強化に向けた取組みを進展させるとともに、ISO9001に則った品質保証体制を強化しました。当期は、廃棄物発電プラント事業や建築工事事業等で大型案件が順調に進捗・完工するとともに、環境O&M事業や電力ビジネス事業等で順調に業績が伸び、売上収益については前年度とほぼ同じレベルを維持しました。事業利益については、売上収益が高水準を維持しているなか、前年度における保有海洋作業船故障のような損失事案等がなく堅調に事業が進捗したことにより増益となりました。エンジニアリングセグメントの売上収益は4,004億円(前期は4,092億円)、セグメント利益は146億円(前期は△13億円)となりました。事業形態別の売上収益(連結調整前)は以下のとおりです。 (当期の事業形態別の売上収益の概況) EPCO&M・サービス部材等販売製鉄プラントその他調整等連結財務諸表計上額売上収益当期2,751999187112△454,004(億円)前期2,824874203217△264,092 EPC分野については、廃棄物発電プラント等の国内建設工事や、タイにおけるガス田開発関連施設等の大型案件を実行したことや、建築工事・建築鉄構事業の大型案件の完工により、前期(2,824億円)とほぼ同規模の2,751億円となりました。O&M・サービス分野については、廃棄物処理O&M、オンサイト、電力取引量の増加により前期(874億円)を上回る999億円を計上しました。部材等販売分野についても堅調で、前期(203億円)とほぼ同水準の187億円となりました。 <ケミカル&マテリアル>日鉄ケミカル&マテリアル㈱においては、世界的な原燃料価格の高騰等により需要低迷が続く厳しい事業環境下、コールケミカル事業部鹿島製造所の休止等の抜本的な収益体質強化等に最大限努め、事業利益は前年比で増益となりました。ケミカル&マテリアルセグメントの売上収益は2,691億円(前期は2,608億円)、セグメント利益は189億円(前期は153億円)となりました。事業別の売上収益(連結調整前)は以下のとおりです。 (当期の事業別の売上収益の概況) コールケミカル化学品機能材料/複合材料その他調整等連結財務諸表計上額売上収益当期6101,0801,00012,691(億円)前期5801,100930△22,608 コールケミカル事業では、主力の黒鉛電極用ニードルコークスの需要低迷が継続し、タイヤ向けカーボンブラックは、自動車検査不正による需要減が下期に回復したものの、前年度並みの販売数量となり、610億円(前期は580億円)となりました。化学品事業では、ベンゼン市況は概ね安定的に推移しましたが、スチレンモノマーは国内誘導品需要の回復遅れによる販売減に加え、中国での新増設継続により市況は低迷し、1,080億円(前期は1,100億円)となりました。機能材料事業では、半導体市場におけるデータセンター向け投資やAI関連需要等ハイエンドゾーンでの成長、スマートフォン・TV・二輪車等の最終製品の需要回復を受け、販売は堅調に推移しました。特に、機能樹脂はAIサーバー・データセンター向け需要が伸長し、原料高騰の影響は受けたものの、円安基調の継続もあり、販売は堅調に推移しました。炭素繊維複合材料の販売は、土木・建築向け補強材料は減少し、産業材料向けは増加しました。炭素繊維については、スポーツ分野向けハイエンド品が堅調に推移し、機能材料と複合材料をあわせて1,000億円(前期は930億円)となりました。 <システムソリューション>日鉄ソリューションズ㈱においては、旺盛なDXニーズを最大限に捕捉し、事業拡大に取り組んでいます。当社に導入した生産管理システムをアセット化した新生産管理パッケージ「PPMP」を他のお客様へ展開するなど、操業現場で得られた長年の業務知見やノウハウを活用した各種ソリューションを提供しています。また、クラウドネイティブ化を包括的に支援する「CloudHarbor」の提供も開始し、お客様のDX推進を強力に牽引しています。事業基盤強化・拡大を目的として、運用・保守に強みを有する㈱OSPソリューションズを完全子会社化するなど、資本業務提携も積極的に進めています。AI技術を有する企業への出資や業務提携を通じ、AI領域の対応力強化にも取り組んでいます。システムソリューションセグメントの売上収益は3,393億円(前期は3,115億円)、セグメント利益は388億円(前期は355億円)となりました。事業別の売上収益(連結調整前)は以下のとおりです。 (当期の事業別の売上収益の概況) ビジネスソリューションコンサルティング&デジタルサービスその他調整等連結財務諸表計上額売上収益当期2,506876113,393(億円)前期2,28182593,115 ビジネスソリューションは、当社及び製造分野向けが好調であったこと並びに金融分野向けのプロダクト販売の増により、2,506億円と前期(2,281億円)に対して増加しました。コンサルティング&デジタルサービスは、クラウドソリューション分野及びオラクルビジネスが好調であったことから、876億円と前期(825億円)に対して増加しました。 (経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等)2021年3月に策定した「日本製鉄グループ中長期経営計画」に掲げた収益・財務体質目標、株主還元とそれに対する当期の状況は以下のとおりです。2024年度の連結業績につきましては、従来からの抜本的な収益構造対策等の継続により収益の最大化に取り組み、通期の売上収益は8兆6,955億円(うち上期4兆3,797億円、下期4兆3,157億円)、事業利益は6,832億円(うち上期3,757億円、下期3,074億円)、ROSは7.9%(うち上期8.6%、下期7.1%)となりました。 2024年度(実績) 2025年度経営計画売上収益事業利益率(ROS)7.9% 10%程度親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)6.9% 10%程度D/Eレシオ(*)0.35倍 0.7倍以下連結配当性向45.6% 30%程度を目安 (*) 劣後ローン・劣後債資本性調整後 ②キャッシュ・フローの状況の分析・検討並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報 キャッシュ・フローの状況の分析については、本報告書「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ②当期末の資産、負債、資本及び当期のキャッシュ・フロー」 に記載しています。 文中の将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものです。 (資本政策) 一定水準の財務健全性が維持されることを前提として、当社グループは投下資本の運用効率を重視し、投資先への資本の投入(資本的支出、R&D、M&A含む)によって企業価値を最大化する資本政策を推進しています。それは、資本コストを超過する収益の創出が期待され、持続的な成長を可能にすると同時に、株主への利益還元によって株主の要求を満たすものです。 当社グループは、上記資本政策の達成に必要な資金を、主として「稼ぐ力」の維持と向上によって生み出される営業キャッシュ・フローから獲得することに加え、必要に応じて銀行借入や社債の発行等、外部からの資金調達も実施しています。 また当社グループは、ROS、ROE及びD/Eレシオを中長期的な収益の成長と財務体質の健全性を達成するうえでの主要な経営管理指標としています。 剰余金の配当等につきましては、本報告書「第4 提出会社の状況 3配当政策」に記載しています。 また、自己株式の取得については、機動性を確保する観点から、定款第33条の規定に基づき取締役会の決議によることとします。取締役会においては、機動的な資本政策等の遂行の必要性、財務体質への影響等を考慮したうえで、総合的に判断することとしています。 (資金需要の動向に関する経営者の認識と資金調達の方法) 1)中長期経営計画の実行状況 2021年3月に公表した「日本製鉄グループ中長期経営計画」では、成長の実現に向けた経営資源投入として、5年間で2兆4,000億円規模の設備投資と6,000億円規模の事業投資に加え、カーボンニュートラル生産の実現に向けた研究開発や設備投資の実行、デジタルトランスフォーメーション戦略への資金投入を計画しています。この中長期経営計画に掲げた投資を実行する前提で、2025年度断面では、D/Eレシオ(※)0.7倍以下を実現することを目標としています。(※)劣後ローン・劣後債資本性調整後 上記方針のもと、設備投資については、強靭な国内生産体制を再構築するための投資や戦略商品の対応力強化に資する投資等を積極的に進めてきました。具体的には、自動車業界において一層高まっていくと想定される車体の軽量化・高強度化ニーズに応えるべく、超ハイテン鋼板等の高級薄板の生産体制を抜本的に強化するため、戦略的な投資として約2,700億円を投入し、自動車鋼板製造の中核拠点である名古屋製鉄所に次世代熱延ラインを新設することを2022年5月に決定しました。また、電磁鋼板についても、カーボンニュートラルに向けた社会的ニーズを踏まえ、既決定投資に加え、新たに約900億円を投入し、瀬戸内製鉄所阪神地区(堺)・九州製鉄所八幡地区においてハイグレード無方向性電磁鋼板の能力対策を実施することを2023年5月に決定しました。 また、事業投資については、将来的なグローバル粗鋼1億トン体制及び外部環境に左右されない厚みを持った事業構造への進化に向けた施策を推進しています。2024年8月に、経営戦略上不可欠な製鉄用原料炭権益確保と、優良な原料権益確保による連結収益の安定化を目的に、高品質製鉄用原料炭サプライヤーである豪州Whitehaven Coal Limitedが保有する豪州クイーンズランド州Blackwater炭鉱の権益20%を約1,080億円で取得することを決定し、2025年3月に取得完了しました。2025年1月には、特殊鋼棒線事業の一体化・最適化を通じた収益機会の拡大、事業戦略の強化、並びにさらなる最適生産体制の追求のため、当社グループ連結子会社の山陽特殊製鋼㈱を705億円で完全子会社化することを決定し、2025年4月に完了しました。また、最大の高級鋼需要国であり、当社が長年培ってきた技術力・商品力を活かすことができる米国市場においては、当社米国子会社とUnited States Steel Corporation(以下「USスチール」という。)を合併すること(以下「本合併」という。)、及びUSスチールとの間で本合併に関する合併契約を締結することを決定し、2025年6月に総額約142億米ドルで本合併が成立しました。 環境面では、カーボンニュートラルの実現に向けて、2021年4月に専任プロジェクトを設置し、3つの超革新技術(高炉水素還元、100%水素直接還元プロセス、大型電炉での高級鋼製造)を他国に先駆けて開発・実機化するための取組みを推進しています。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から公募された「グリーンイノベーション基金事業/製鉄プロセスにおける水素活用プロジェクト」に、当社を含む4社による共同提案を行い、2021年12月に採択されました。2024年3月までには、脱炭素化における鉄鋼業の役割の重要性の認識のもと、同基金の鉄鋼業への配分が大幅に拡大され、支援規模の総額は4,499億円となりました。また、2025年5月には、高炉プロセスから電炉プロセスへの転換投資について、GX推進法に基づく「排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業(事業Ⅰ(鉄鋼))令和7年度~令和11年度事業」に採択され、それを受けて当社は本投資の実行を決定しました(合計投資額8,687億円、政府支援額(上限額)2,514億円)。 2)資金調達 中長期経営計画に関して多額の資金所要が見込まれるなか、調達コストを抑制しながら成長投資資金を確保し財務基盤を強化することを目的として、2021年10月に転換社債型新株予約権付社債3,000億円を発行しました。2023年3月には、脱炭素社会に向けた取組みを推進していくための所要資金を調達する手段として、グリーンボンド(無担保社債)500億円を発行しました。2024年5月には、当社米国子会社とUnited States Steel Corporationの合併に必要な資金の調達等、中長期経営計画に基づく成長投資と財務健全性の両立に資する資金調達手段として、劣後特約付シンジケートローン及び公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)による総額2,500億円の調達を実行しました。 また、フリーキャッシュ・フローの状況に応じて、調達環境、金利条件等を勘案して、最適なタイミングで資金調達面での対応を図ります。 2025年3月末における劣後ローン・劣後債資本性調整後のD/Eレシオは0.35倍となり、中長期経営計画の目標である0.7倍以下を維持しています。当社米国子会社とUnited States Steel Corporationの合併直後のD/Eは一時的に0.8倍程度まで悪化するものの、合併後の最適なパーマネントファイナンスにより早期に0.7倍以下を目指します。 中長期的に機動的かつ確実な成長戦略の遂行を継続するため、財務規律を重視した キャッシュ・マネジメントを引き続き実行していきます。 (流動性管理及び資金調達の方針について) 当社グループの円滑な事業活動に必要な資金を確保するため、手許資金及び外部借入を有効に活用しています。手許資金については、実需に見合った最低限の現預金を保有する方針としており、過去及び将来の資金繰りを勘案し、最適な保有残高を志向しています。外部借入については、安全性・安定性・柔軟性を担保する観点から基本的な調達の枠組みを決定しています。具体的には、不測の事態発生時における、当社の支払余力を確保すべく、適正な長期固定適合比率を維持するとともに、安全性の補完のためにコミットメントライン(当社連結:5,997億円)契約を締結しています。 また、短期資金と長期資金のバランスを踏まえた有利子負債残高の設計により自由度を確保しており、当該枠組みの範囲内で、最適な資金調達の実現を志向しています。 ③会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定当社の連結財務諸表は、国際会計基準に基づき作成されています。重要な会計方針については、本報告書「第一部企業情報 第5 経理の状況」に記載しています。連結財務諸表の作成にあたっては、会計上の見積りを行う必要があり、引当金の計上、非金融資産の減損、繰延税金資産の回収可能性の判断等につきましては、過去の実績や他の合理的な方法により見積りを行っています。ただし、見積り特有の不確実性が存在するため、実際の結果はこれら見積りと異なる場合があります。 当社が特に重要と判断している会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定は以下です。 a.非金融資産の減損当社グループは、資産が減損している可能性を示す兆候のいずれかが存在する場合、資産又は資金生成単位の処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額を回収可能価額として見積り、回収可能価額が資産又は資金生成単位の帳簿価額を下回る場合、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として認識しており、使用価値は見積将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引くことにより算出しています。当該キャッシュ・フローは中長期経営計画及び最新の事業計画を基礎としており、これらの計画には鋼材需給の予測及び製造コスト改善等を主要な仮定として織り込んでいます。鋼材需給及び製造コスト改善の予測には高い不確実性を伴い、これらの経営者による判断が将来キャッシュ・フローに重要な影響を及ぼすと予想されます。なお、当期末における有形固定資産の残高は3兆6,355億円、無形資産の残高は2,632億円となっています。 b.繰延税金資産の回収可能性当社グループは、鋼材需給の予測及び製造コスト削減等の仮定に基づいて算定された将来における課税所得の見積り等の予想等、現状入手可能な全ての将来情報を用いて、繰延税金資産の回収可能性を判断しています。当社グループは、税務上の便益が実現する可能性が高いと判断した範囲内でのみ繰延税金資産を認識していますが、経営環境悪化に伴う中長期経営計画及び事業計画の目標未達等による将来における課税所得の見積りの変更や、法定税率の変更を含む税制改正等により回収可能額が変動する可能性があります。なお、当期末における繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)の残高は3,341億円です。 |
※本記事は「日本製鉄株式会社」の令和7年年3期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
※4. この企業は、連結財務諸表ベースで見ると有利子負債がゼロ。つまり、グループ全体としては外部借入に頼らず資金運営していることがうかがえます。なお、個別財務諸表では親会社に借入が存在しているため、連結上のゼロはグループ内での相殺消去の影響とも考えられます。
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

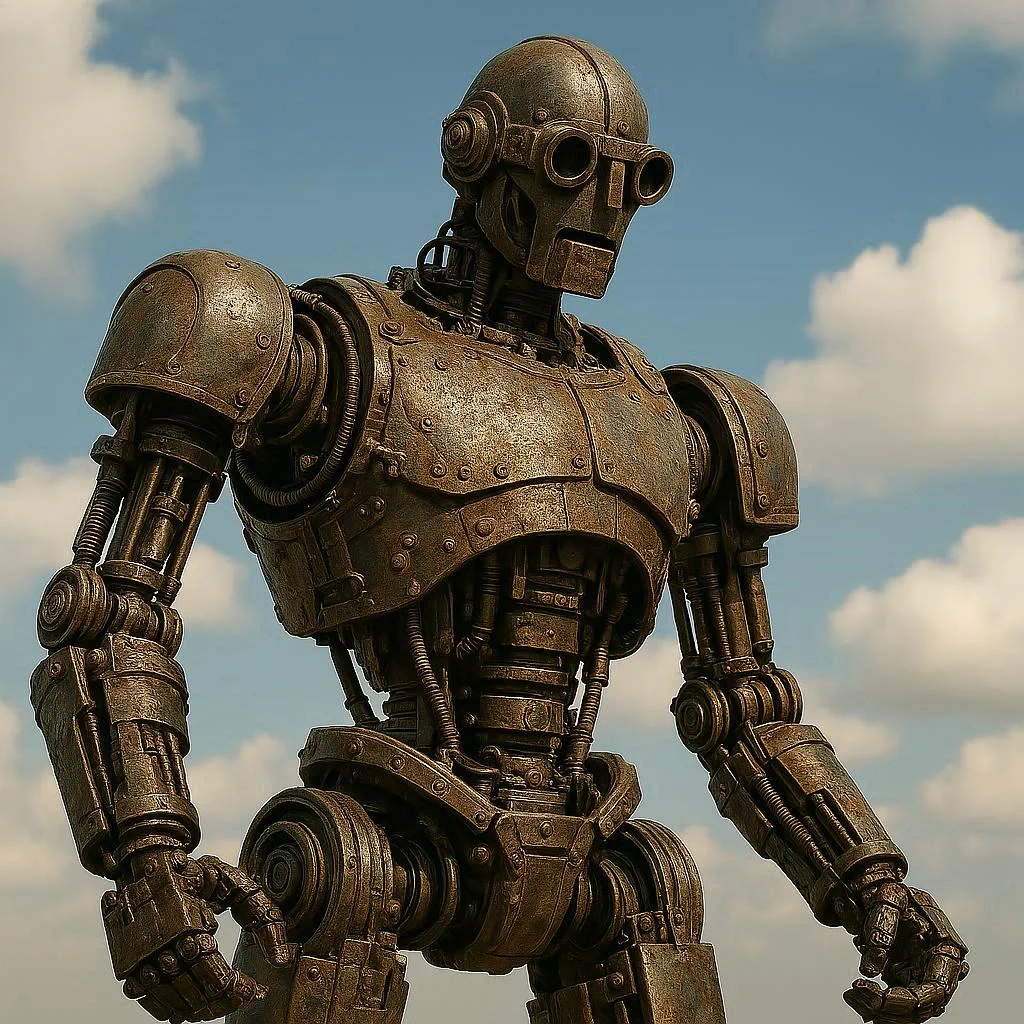


コメント