| 会社名 | 本田技研工業株式会社 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 従業員数 | 連194173名 単32088名 |
| 従業員平均年齢 | 44.5歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 21.3年 |
| 平均年収 | 8955000円 |
| 1株当たりの純資産(単体) | 697.99円 |
| 1株当たりの純利益(連結) | 178.93円 |
| 決算時期 | 3月 |
| 配当金 | 68円 |
| 配当性向 | 34.2% |
| 株価収益率(PER) | 6.7倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(単体) | 29.6% |
| 営業活動によるCF | 2921億円 |
| 投資活動によるCF | ▲9419億円 |
| 財務活動によるCF | 2804億円 |
| 研究開発費※1 | 328億円 |
| 設備投資額※1 | 4457.07億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 793.98億円 |
| 株主資本比率※2 | 67% |
| 有利子負債残高(連結)※3※4 | 0円 |
経営方針
| 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において、当社、連結子会社および持分法適用会社(以下「当社グループ」という。)が判断したものであり、将来生じうる実際の結果と大きく異なる可能性もあります。詳細は「3 事業等のリスク」を参照ください。 (1) 経営方針・経営戦略等当社グループは、「人間尊重」と「三つの喜び」(買う喜び、売る喜び、創る喜び)を基本理念としています。「人間尊重」とは、自立した個性を尊重しあい、平等な関係に立ち、信頼し、持てる力を尽くすことで、共に喜びをわかちあうという理念であり、「三つの喜び」とは、この「人間尊重」に基づき、お客様の喜びを源として、企業活動に関わりをもつすべての人々と、共に喜びを実現していくという信念であります。 こうした基本理念に基づき、「わたしたちは、地球的視野に立ち、世界中の顧客の満足のために、質の高い商品 を適正な価格で供給することに全力を尽くす」という社是を実践し、株主の皆様をはじめとするすべての人々と喜びを分かち合い、企業価値の向上に努めていきます。当社グループは、総合モビリティカンパニーとして、一人ひとりの創造力から生まれる夢のあるモビリティや多様なサービスによって「環境負荷ゼロ社会」「交通事故ゼロ社会」を実現するとともに、2023年にグローバルブランドスローガンである「The Power of Dreams」を再定義して明確に示した「時間や空間といったさまざまな制約から人々を解放し(Transcend)、また人の能力と可能性を拡張する(Augment)」という本質的な提供価値を世界中にお届けすることで、人や社会を前進させるパワーとなることをめざしていきます。めざす姿の実現に向けて、夢を原動力に、独創的な技術とアイデアで、当社グループはこれからも果敢にチャレンジを続けていきます。 (2) 経営環境および対応の方向性当社グループを取り巻く経営環境は、大きな転換期を迎えています。価値観の多様化や、高齢化の進展、都市化 の加速、気候変動の深刻化、さらに電動化、自動運転化、IoTといった技術の進化による産業構造の変化が、グローバルレベルで進んでいます。また、ウクライナ、中東および南シナ海情勢等の国際情勢や各国の通商政策において不透明な状況が続くなど、地政学的リスクも顕在化しています。そのような中、将来の成長に向けては、提供価値の質の向上に継続的に取り組むとともに、企業活動に関わるすべてのステークホルダーと、長期的な社会課題を解決するための、積極的な関係構築が求められます。四輪事業においては、長期的な観点ではカーボンニュートラル実現に向けて、EV(電気自動車)が最も有効なソリューションであると考えています。一方で、四輪車の電動化を取り巻く環境は大きな変化に直面しています。電動化の普及は、地域によって進展の差が大きく、また、黎明期である現在においては、その普及のスピードにも変動があります。当社グループは、電動車の市場動向を見極めながら、リソースの効果的な配分を行うなど、柔軟かつ適応力のある戦略を維持していきます。二輪事業は、若年層人口比率の高い国々を中心に、今後も市場の成長が見込まれます。一方で、世界最大の二輪車市場であるインドでは政策の後押しもあり、電動車の需要も急速に拡大しています。その他の国々でも、電力の安定供給や充電ネットワークの整備といったインフラ面では国ごとに異なる課題があり、政府の販売支援策や産業育成策の実行力にも違いがあるものの、長期的には電動車の拡大トレンドが継続すると考えています。当社グループはこのような状況を踏まえ、ICE(内燃機関)車と電動車の拡大ペースを市場ごとに見極めながら、リソースの効果的な配分を行うとともに、躍進する電動新興メーカーに対して当社グループの強みを活かしながら対応策を展開していきます。 パワープロダクツ事業及びその他の事業においては、建設機械・産業機械業界などにおいても官民一体によるカーボンニュートラルの動きが加速し、環境に配慮された製品のニーズが高まりを見せています。当社グループは、それらの業界の完成機メーカーなど法人顧客向けに電動製品のラインアップを拡充させることで、カーボンニュートラル社会の実現に向けた動きを加速させる役割を担っています。 (3) 優先的に対処すべき課題持続可能性の観点から網羅的に抽出した社会課題を、当社グループがめざす方向性に照らしあわせ、優先的に対処すべき課題を選定しています。従来より経営の重要テーマとして掲げてきた「環境」と「安全」に加え、当社グループの成長の原動力である「人」と「技術」、またすべての企業活動の総和ともいえる「ブランド」の5つの非財務領域を重要テーマとして選定し、財務戦略と連携させることで社会的価値・経済的価値の創出を実現していきます。 <5つの重要テーマ>① 環境負荷ゼロ社会の実現当社グループは、持続可能な企業活動をめざし、それぞれが連鎖している環境負荷を網羅的に低減する取り組みに向けて、全社の重要テーマの一つを「環境負荷ゼロ社会の実現」と設定しています。「環境負荷ゼロ社会の実現」をめざした活動は、「カーボンニュートラル」「クリーンエネルギー」「リソースサーキュレーション」、この3つを1つのコンセプトにまとめた「Triple Action to ZERO」を中心にして取り組んでいます。 1.カーボンニュートラルの取り組み当社グループは、カーボンニュートラルの実現に向けて、乗用車をはじめとする小型モビリティの領域において、長期的視点ではEVが最適解であると考え、その普及に向けて大きく舵を切り、取り組みを進めてきました。一方で、四輪事業を取り巻く環境は日々刻々と変化しています。特に、EV普及の前提となる各地域での環境規制の変化などによるEV市場拡大スピードの鈍化や、通商政策動向の変化など、事業環境の不透明さが増しています。このような環境下で、当初の目標である2030年にグローバルでのEV/FCEV(燃料電池自動車)販売比率30%は見直しておりますが、引き続き「2040年にEV・FCEVの販売比率100%」とする目標に向けて、着実に、強いEVブランドと事業基盤の構築に取り組んでいきます。また、EV普及までの過渡期を担うパワートレーンとしてハイブリッド車の商品群を強化していきます。 二輪事業においては、2040年代に全ての二輪製品でのカーボンニュートラルを実現することをめざし、ICEの進化にも継続的に取り組みながら、環境戦略の主軸として二輪車の電動化を加速させています。 (商品ラインアップの拡充)当社グループは、2030年のグローバルでの電動二輪車の年間販売台数目標を400万台、2030年までにグローバルで30機種の電動モデルを投入することをめざし、戦略的に電動二輪車の市場投入を進めています。この達成に向けて、2024年を電動二輪車のグローバル展開元年と位置付け、電動二輪市場への参入を本格化しており、多様化するお客様のニーズに応える多彩なバリエーション展開により、電動二輪車においてもリーディングカンパニーをめざしていきます。 (充電・利用環境の整備) 電動二輪車の普及に向けては、商品ラインアップの強化だけでなく、利用環境の整備に向けた施策を展開します。日本、インドネシア、タイに引き続きインドでも、交換式バッテリーを搭載する電動二輪車の普及強化に向けて、現地法人ホンダパワーパックエナジーインディアプライベート・リミテッドによるバッテリーシェアリングサービス事業を展開しています。また、インド全土6,000店舗で展開している業界最大(注)の販売ネットワークを活用し、アフターサービス、メンテナンスを強化するほか、今後順次投入していく固定式バッテリー搭載車両の電欠不安に対しても、この幅広いネットワークを生かして充電網を拡充していきます。 (注) 当社調べ(2025年1月時点) パワープロダクツ事業では、パワーユニット領域とガーデン領域を電動化の主要ドメインに位置付け、商品力の向上に向けた取り組みを強化することで、業界における電動化をリードしていきます。また、多様なモビリティを有する当社グループの強みを活かし、電動化に必要なコア部品を二輪事業と共用化することでコストを削減するなど、事業間のシナジーによる開発・コスト競争力の強化を図っていきます。パワーユニット領域では、パワープロダクツの基幹事業である汎用エンジンで培ったBtoBの既存顧客に加えて、電動化が期待される領域へ積極的に「eGX」(Hondaの「GX」シリーズを電動化した汎用エンジン)の搭載を拡大させるため、日本・欧州を中心とするパワーユニット供給先企業との連携を強化します。そしてお客様の要望にきめ細やかに応えていくため、幅広いバリエーションを「eGX」シリーズとして準備していきます。ガーデン領域では、米国市場において、造園業者向け電動製品をフルラインアップ展開し、プロのお客様へも電動製品の拡大を図ります。その実現に向けて、北米の展示会でプロトタイプとして発表した、電動乗用芝刈機や自動芝刈機といった大型モデルについても量産準備のフェーズに移行しました。さらに、手押し芝刈機や、刈払機などの小型の電動製品に関しては、外部協業先を活用し、効率的な開発・生産スキームで電動化を加速するとともに、協業の枠組みを拡大させ、さらなる顧客の獲得をめざしていきます。 2.「クリーンエネルギー」3.「リソースサーキュレーション」の詳細については、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組」を参照ください。 ② 交通事故ゼロ社会の実現 当社グループは、2050年に全世界で、当社グループの二輪車・四輪車が関与する交通事故死者ゼロをめざしま す(注1)。また、そのマイルストーンとして2030年に全世界で当社グループの二輪車・四輪車が関与する交通事 故死者半減(注2)をめざします。これらは、新車だけでなく、登録・届出されたすべての当社グループの二輪 車、四輪車が対象となります。 (注) 1 当社グループの二輪車、四輪車が関与する交通事故:当社グループの二輪車・四輪車に乗車中、および歩行者・自転 車・その他当事者(故意による悪質なルール違反、および故意により飲酒・薬物その他による責任能力のない状態の二 つを除く交通参加者)が関与する交通事故。 2 2020年比で2030年に全世界で当社グループの二輪車・四輪車が関与する1万台当たりの交通事故死者数を半減。 詳細については、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組」を参照ください。 ③ 人的資本経営の進化当社グループの人的資本経営とは、全社の方針である「一人ひとりの夢を原動力に人と社会を前進させる総合モビリティカンパニー」をめざし、事業戦略の到達点からバックキャストした将来必要な人材ポートフォリオを形成していくことです。そしてこれを実現するために中長期・短中期の観点から達成すべき二つの人材マテリアリティ(注)を設定しています。さらに、人材マテリアリティごとに二つ、合計四つの主要テーマを設定しています。 (注) マテリアリティ:持続可能性の観点から網羅的に抽出した社会課題を、当社グループのめざす方向性に照らし優先順位 を付けたうえで選定した「重要テーマ」において、とくに注力していくべき課題。 詳細については、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組」を参照ください。 ④ 独創的な技術の創出めざす提供価値として定めた「Transcend」・「Augment」の実現に向け、「コア技術の創出こそが将来にわたるサステナブルな事業基盤や競争力を生む源泉になる」という考え方に立脚し、イノベーションマネジメントの強化に、継続的に取り組んでいます。将来の「環境負荷ゼロ社会」「交通事故ゼロ社会」の実現に向け、またモビリティフィールドとその概念の拡大をめざし、注力領域を定めた上で、各領域エキスパートがその実現に向け技術開発をリードしています。また、世界中のさまざまな研究機関と共同研究を行うことで、グローバルでの知の探究と結集をはかっています。技術開発は試行錯誤の繰り返しであり、その弛まぬ努力が実際に世の中に上市される商品へと結実するまでには長い時間と莫大なリソースが必要となります。しかし、どのような時代においても「新技術の探究」こそが次代の当社グループをつくり上げるドライビングフォースであるという信念のもと、思い切ったリソース投入を行うことで、高い競争力を持ち続け、サステナブルな事業展開に貢献していくことをめざします。このような技術開発のもと、当社グループは「知能化」の強化およびハイブリッド車の競争力強化に取り組んでいます。「知能化」においては、カーナビで目的地を設定すると、一般道か高速道路かを問わず、目的地までの全経路において、クルマがアクセルやハンドルなどの運転操作を支援する次世代ADAS(先進運転支援システム)の独自開発を進めています。また、ハイブリッド車においては、Honda独自の2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」と、それを搭載するプラットフォームを全方位で進化させ、燃費向上をめざすとともに、Hondaならではの五感に響く上質・爽快な走りをさらに進化させていきます。 ⑤ ブランド価値の向上Hondaのブランドは、創業時から現在に至るまで、お客様とともに歩み続けたあらゆる企業活動の積み重ねによって形づくられてきました。75年の歴史によって紡がれたHondaブランドをさらに輝かせ、将来にわたってその価値を高めていくことは、当社グループにとって極めて重要な課題の一つであると認識しています。ブランドマネジメントにおいては、「企業としての一貫性」と「商品・サービスの多様性・独自性」との間に相乗効果を生み出すことが重要だと考えています。あらゆる企業活動に価値ある一貫性を反映していくことによって、ブランディングを強化し、ブランドの価値を高めていくことをめざします。この一環として、グローバルでブランドに価値ある一貫性をもたらすため、さまざまな発信やブランディングを実践する際の指針として活用する「ブランドアセット」の整備と拡充に取り組んできました。今後はこれらのブランドアセットをさらに拡充するとともにコンテンツを進化させ、グローバルで活用の拡大をはかっていくことで、当社グループで働くすべての仲間の「夢」を原動力とした創造性の発揮を後押しするとともに、ステークホルダーの皆様から共感いただける魅力的なブランドの確立をめざしていきます。 <財務戦略>⑥ 経済的価値の向上企業価値の向上に向けては、財務・非財務資本を活用し、キャッシュ・フローの持続的な成長と資本効率の向上を実現する必要があると認識しています。この実現に向けて、「事業変革フェーズに応じた戦略的な資源配分」「資本コストを意識した経営の強化と環境変化への対応」「積極的な対話による経営の質・透明性の向上」へ取り組んでいきます。 1.事業変革フェーズに応じた戦略的な資源配分(原資創出)2030年に向けては、二輪事業の継続的な事業拡大と、四輪事業での次世代ハイブリッドシステムやプラットフォームの適用に伴うコスト低減効果、ハイブリッド車の販売台数増加により収益性を向上させ、2031年3月期のROIC(投下資本利益率)(注1)目標10%の達成に向けて取り組んでいきます。 (注) 1 (親会社の所有者に帰属する当期利益+支払利息(金融サービス事業を除く事業会社))÷投下資本(注2) 2 親会社の所有者に帰属する持分+有利子負債(金融サービス事業を除く事業会社)、期首期末平均により算出しています。 (資源投入)2024年5月に発表した、電動化戦略の実現に向けた設備投資、出資と研究開発支出など合わせて10兆円の投入資源については、カナダでのEVの包括的バリューチェーン構築の2年程度延期などにより、2031年3月期までの間で合計3兆円を減額し、総額7兆円へ見直しを行いました。この投入資源の減額を踏まえた、2027年3月期からの5年間のキャピタルアロケーションについては、二輪事業での安定的なキャッシュ創出力に加え、ハイブリッド車の販売台数の増加により、R&D調整後営業CF(注)12兆円以上のキャッシュ創出をめざします。また、2031年3月期までの資源配分としては、EV関連への資源投入を3兆円減額した一方、ハイブリッド車への資源投入に関してはミニマムの増加を見込んでいます。 (注) 研究開発費控除後の営業キャッシュ・フロー(金融サービス事業を除く事業会社の営業キャッシュ・フロー + 研究開発 支出 ? 開発資産への振替額) (株主還元)成果の配分については、株主の皆様に対する利益還元を、経営の最重要課題の一つとして位置付けています。市場の変化にリニアに対応した資源配分の見直しにより、将来に向けた仕込みと収益力向上を両立した四輪事業の確立をめざすとともに、二輪事業の強固な収益力も合わせることで、さらなる成長をめざします。また、従来は連結配当性向30%を目安に、安定的・継続的な配当に努めてきましたが、不透明な事業環境下においても、当社グループの強みを活かしたキャッシュ創出力を原資に、今後も継続して事業の成長に応じた株主還元を維持していくという意思表示として、DOE(調整後親会社所有者帰属持分配当率)(注)を導入します。このように、事業体質のさらなる強化による成長と、安定的、継続的な株主還元の両立を図ります。 (注) DOE(調整後親会社所有者帰属持分配当率)のベースとなる「親会社の所有者に帰属する持分」は為替や市場環境の影響に よる変動の大きい「その他の資本の構成要素」を除外した調整後の数値を基にします。 2.資本コストを意識した経営の強化と環境変化への対応環境変化に柔軟かつ適切に対応し企業価値の向上を実現するため、資本コストを意識した経営の浸透をはかるとともに時間軸を踏まえた複数の選択肢を持ち、柔軟な資源配分によるリスクへの対応をはかっていきます。今後の変革期においては、将来に向けた投資が先行しますが、正味現在価値(NPV)を活用し資本コストを踏まえた投資判断を実施するとともに、経営の守るべきラインとして、資本コストを上回る全社ROICの維持をめざします。 3.積極的な対話による経営の質・透明性の向上株主や投資家をはじめとしたステークホルダーの皆様に、経営の方向性が正しく理解され評価いただけるよう、経営陣が主体となり、イベントや個別面談等を通じて、これまで以上に対話を積極的に行っていきます。これらの対話を通じて、経営陣や各領域技術責任者から成長戦略に向けた想いをお伝えするとともに、資本市場が当社グループに求めていることを直接把握し、経営や事業戦略へ活かすことで、PBR1倍超の早期達成と企業価値の継続的な向上へつなげていきます。 以上のような企業活動全体を通した取り組みを行い、株主、投資家、お客様をはじめ、広く社会から「存在を期待される企業」となることをめざしていく所存でございます。 |
経営者による財政状態の説明
| 4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1) 経営成績等の状況の概要 ① 経営成績の状況当連結会計年度の当社、連結子会社および持分法適用会社(以下「当社グループ」という。)を取り巻く経済環境は、ウクライナ、中東および南シナ海情勢等の国際情勢や各国の通商政策など、先行きの不透明な状況が続きましたが、インフレの状況も落ち着きが見られるようになり、景気は持ち直しました。米国では、高い金利水準の継続などに懸念があるものの、個人消費の増加により、景気は拡大しました。欧州では、景気は一部に足踏みがみられたものの、持ち直しの動きがみられました。アジアの景気においては、インドでは成長ペースは減速しつつも拡大、インドネシアでは緩やかに回復しました。タイでは後半にかけて景気が弱含み、中国では持ち直しの動きに足踏みがみられました。日本では、一部に足踏みが残ったものの、雇用・所得環境の改善により、景気は緩やかに回復しました。主な市場のうち、二輪車市場は前連結会計年度にくらべ、ブラジル、インド、ベトナム、インドネシアでは拡大しましたが、タイでは縮小となりました。四輪車市場は前連結会計年度にくらべ、ブラジル、中国、米国、インドでは拡大しましたが、欧州、日本ではおおむね横ばい、インドネシアでは縮小、タイでは大幅に縮小となりました。このような中で、当社グループは、一人ひとりの創造力から生まれる夢のあるモビリティや多様なサービスによって「環境負荷ゼロ社会」「交通事故ゼロ社会」を実現するとともに、「解放と拡張」という本質的な提供価値を世界中にお届けすることで、人や社会を前進させるパワーとなることをめざしており、従来より経営の重要テーマとして掲げてきた「環境」と「安全」に加え、当社グループの成長の原動力である「人」と「技術」、またすべての企業活動の総和ともいえる「ブランド」の5つの非財務領域を重要テーマとして選定し、財務戦略と連携させることで社会的価値・経済的価値の創出に努めてまいりました。研究開発面では、安全・環境技術や商品の魅力向上、モビリティの変革にむけた先進技術開発に、外部とのオープンイノベーションも活用し、積極的に取り組みました。生産面では、生産体質の強化や、グローバルでの需要の変化に対応した生産配置を行いました。販売面では、新価値商品の積極的な投入や、グローバルでの商品の供給などにより、商品ラインアップの充実に取り組みました。当連結会計年度の連結売上収益は、二輪事業における増加や為替換算による増加影響などにより、21兆6,887億円と前連結会計年度にくらべ6.2%の増収となりました。 営業利益は、売価およびコスト影響による利益増などはあったものの、販売影響による利益減や研究開発費の増加および四輪製品保証見積変更影響などにより、1兆2,134億円と前連結会計年度にくらべ12.2%の減益となりました。なお、四輪製品保証見積変更による減益影響は1,276億円となっております。詳細については、連結財務諸表注記の「17 引当金」を参照ください。税引前利益は、アジア地域の持分法による投資損益の減少などにより、1兆3,176億円と前連結会計年度にくらべ19.8%の減益、親会社の所有者に帰属する当期利益は、8,358億円と前連結会計年度にくらべ24.5%の減益となりました。 事業の種類別セグメントの状況(二輪事業) Hondaグループ販売台数 ※連結売上台数 ※ 2024年3月期(千台)2025年3月期(千台)増 減(千台)増減率(%)2024年3月期(千台)2025年3月期(千台)増 減(千台)増減率(%)二輪事業計18,81920,5721,7539.312,21913,6851,46612.0 日 本241224△17△7.1241224△17△7.1 北 米4985485010.04985485010.0 欧 州440475358.0440475358.0 アジア16,01617,4781,4629.19,41610,5911,17512.5 その他1,6241,84722313.71,6241,84722313.7 二輪事業の外部顧客への売上収益は、連結売上台数の増加により、3兆6,266億円と前連結会計年度にくらべ12.6%の増収となりました。営業利益は、為替影響などはあったものの、売価およびコスト影響による利益増などにより、6,634億円と前連結会計年度にくらべ19.3%の増益となりました。 ※Hondaグループ販売台数は、当社および連結子会社、ならびに持分法適用会社の完成車(二輪車・ATV・Side-by-Side)販売台数です。一方、連結売上台数は、外部顧客への売上収益に対応する販売台数であり、当社および連結子会社の完成車販売台数です。 (四輪事業) Hondaグループ販売台数 ※連結売上台数 ※ 2024年3月期(千台)2025年3月期(千台)増 減(千台)増減率(%)2024年3月期(千台)2025年3月期(千台)増 減(千台)増減率(%)四輪事業計4,1093,716△393△9.62,8562,840△16△0.6 日 本595630355.9525539142.7 北 米1,6281,654261.61,6281,654261.6 欧 州10393△10△9.710393△10△9.7 アジア1,6511,182△469△28.4468397△71△15.2 その他1321572518.91321572518.9 四輪事業の外部顧客への売上収益は、為替換算による増加影響などにより、14兆1,692億円と前連結会計年度にくらべ4.4%の増収となりました。営業利益は、売価およびコスト影響による利益増などはあったものの、販売影響による利益減や研究開発費の増加および四輪製品保証見積変更影響などにより、2,438億円と前連結会計年度にくらべ56.5%の減益となりました。 ※Hondaグループ販売台数は、当社および連結子会社、ならびに持分法適用会社の完成車販売台数です。一方、連結売上台数は、外部顧客への売上収益に対応する販売台数であり、当社および連結子会社の完成車販売台数です。また、当社の日本の金融子会社が提供する残価設定型クレジット等が、IFRSにおいてオペレーティング・リースに該当する場合、当該金融サービスを活用して連結子会社を通して提供された四輪車は、四輪事業の外部顧客への売上収益に計上されないため、連結売上台数には含めていませんが、Hondaグループ販売台数には含めています。 (金融サービス事業)金融サービス事業の外部顧客への売上収益は、ローン収益の増加や為替換算による増加影響などにより、3兆5,077億円と前連結会計年度にくらべ8.0%の増収となりました。営業利益は、増収に伴う利益の増加などにより、3,156億円と前連結会計年度にくらべ15.2%の増益となりました。 (パワープロダクツ事業及びその他の事業) Hondaグループ販売台数/連結売上台数 ※ 2024年3月期(千台)2025年3月期(千台)増 減(千台)増減率(%)パワープロダクツ 事業計3,8123,700△112△2.9 日 本302278△24△7.9 北 米1,0831,020△63△5.8 欧 州794651△143△18.0 アジア1,2941,4131199.2 その他339338△1△0.3 パワープロダクツ事業及びその他の事業の外部顧客への売上収益は、連結売上台数の減少などにより、3,851億円と前連結会計年度にくらべ1.8%の減収となりました。営業損失は、売価およびコスト影響による利益増などはあったものの、販売影響による利益減や為替影響などにより、94億円と前連結会計年度にくらべ5億円の悪化となりました。なお、パワープロダクツ事業及びその他の事業に含まれる航空機および航空機エンジンの営業損失は、388億円と前連結会計年度にくらべ59億円の悪化となりました。 ※Hondaグループ販売台数は、当社および連結子会社、ならびに持分法適用会社のパワープロダクツ販売台数です。一方、連結売上台数は、外部顧客への売上収益に対応する販売台数であり、当社および連結子会社のパワープロダクツ販売台数です。なお、当社は、パワープロダクツを販売している持分法適用会社を有しないため、パワープロダクツ事業においては、Hondaグループ販売台数と連結売上台数に差異はありません。 所在地別セグメントの状況前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 日本 北米 欧州 アジア その他の地域 計 消去 連結売上収益5,392,760 12,073,777 966,320 5,009,961 1,081,946 24,524,764 △4,095,962 20,428,802営業利益(△損失)151,070 694,940 60,340 397,804 153,957 1,458,111 △76,134 1,381,977 当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 日本 北米 欧州 アジア その他の地域 計 消去 連結売上収益5,584,504 13,108,269 946,224 4,896,316 1,226,224 25,761,537 △4,072,770 21,688,767営業利益(△損失)191,135 435,215 5,328 408,273 177,885 1,217,836 △4,350 1,213,486 (注) 1 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国(1) 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度によっています。(2) 各区分に属する主な国………………北米:米国、カナダ、メキシコ欧州:英国、ドイツ、ベルギー、イタリア、フランスアジア:タイ、中国、インド、ベトナム、マレーシアその他の地域:ブラジル、オーストラリア2 各セグメントの営業利益(△損失)の算出方法は、連結損益計算書における営業利益の算出方法と一致しており、持分法による投資損益、金融収益及び金融費用および法人所得税費用を含んでいません。3 消去の金額は、セグメント間取引消去によるものです。 (日本) 売上収益は、四輪事業における増加などにより、5兆5,845億円と前連結会計年度にくらべ3.6%の増収となりました。営業利益は、研究開発費の増加などはあったものの、販売影響による利益増や為替影響などにより、1,911億円と前連結会計年度にくらべ26.5%の増益となりました。 (北米) 売上収益は、四輪事業における増加や為替換算による増加影響などにより、13兆1,082億円と前連結会計年度にくらべ8.6%の増収となりました。営業利益は、売価およびコスト影響による利益増はあったものの、販売影響による利益減や四輪製品保証見積変更影響などにより、4,352億円と前連結会計年度にくらべ37.4%の減益となりました。 (欧州) 売上収益は、二輪事業における増加などはあったものの、四輪事業における減少などにより、9,462億円と前連結会計年度にくらべ2.1%の減収となりました。営業利益は、販売影響による利益減や諸経費の増加などにより、53億円と前連結会計年度にくらべ91.2%の減益となりました。 (アジア) 売上収益は、二輪事業における増加などはあったものの、四輪事業における減少などにより、4兆8,963億円と前連結会計年度にくらべ2.3%の減収となりました。営業利益は、販売影響による利益減などはあったものの、売価およびコスト影響による利益増などにより、4,082億円と前連結会計年度にくらべ2.6%の増益となりました。 (その他の地域) 売上収益は、二輪事業や四輪事業における増加などにより、1兆2,262億円と前連結会計年度にくらべ13.3%の増収となりました。営業利益は、為替影響などはあったものの、売価およびコスト影響による利益増などにより、1,778億円と前連結会計年度にくらべ15.5%の増益となりました。 ② キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4兆5,287億円と前連結会計年度末にくらべ4,257億円の減少となりました。当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前連結会計年度に対する各キャッシュ・フローの増減状況は以下のとおりです。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、2,921億円となりました。この営業活動によるキャッシュ・インフローは、顧客からの現金回収の増加などはあったものの、部品や原材料の支払いやオペレーティング・リース資産購入の支払いの増加などにより、前連結会計年度にくらべ4,551億円の減少となりました。 (投資活動によるキャッシュ・フロー)当連結会計年度における投資活動の結果減少した資金は、9,419億円となりました。この投資活動によるキャッシュ・アウトフローは、その他の金融資産の売却及び償還による収入の増加などはあったものの、有形固定資産の取得による支出やその他の金融資産の取得による支出の増加などにより、前連結会計年度にくらべ746億円の増加となりました。 (財務活動によるキャッシュ・フロー)当連結会計年度における財務活動の結果増加した資金は、2,804億円となりました。この財務活動によるキャッシュ・インフローは、自己株式の取得や配当金の支払いの増加などにより、前連結会計年度にくらべ6,381億円の減少となりました。 ③ 生産、受注及び販売の状況(生産実績)セグメントの名称前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)増減台数(千台)台数(千台)台数(千台)増減率(%)二輪事業12,56014,0101,45011.6四輪事業2,9582,875△83△2.8パワープロダクツ事業及びその他の事業2,8563,33347716.7 (注) 1 生産台数は、当社および連結子会社の完成車の生産台数の合計です。 2 二輪事業には二輪車、ATVおよびSide-by-Sideが含まれています。 3 パワープロダクツ事業及びその他の事業にはパワープロダクツの生産台数を記載しています。 (受注実績)見込生産のため、大口需要等の特別仕様のものを除いては、受注生産はしていません。 (販売実績)仕向地別(外部顧客の所在地別)売上収益は、以下のとおりです。セグメントの名称前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(百万円)当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(百万円)増 減(百万円)増 減 率(%) 総 合 計20,428,80221,688,7671,259,9656.2 日 本2,242,2132,477,674235,46110.5 北 米11,713,66812,798,3611,084,6939.3 欧 州961,185938,453△22,732△2.4 アジア4,313,8104,108,992△204,818△4.7 その他1,197,9261,365,287167,36114.0 二輪事業計3,220,1683,626,603406,43512.6 日 本113,746106,632△7,114△6.3 北 米335,558347,50411,9463.6 欧 州351,851379,43227,5817.8 アジア1,793,3272,078,498285,17115.9 その他625,686714,53788,85114.2 四輪事業計13,567,56514,169,240601,6754.4 日 本1,600,6191,807,346206,72712.9 北 米8,510,2429,384,627874,38510.3 欧 州506,755459,756△46,999△9.3 アジア2,449,8021,954,479△495,323△20.2 その他500,147563,03262,88512.6 金融サービス事業計3,248,8083,507,766258,9588.0 日 本440,775474,75333,9787.7 北 米2,729,1082,938,239209,1317.7 欧 州18,12021,4063,28618.1 アジア14,71313,901△812△5.5 その他46,09259,46713,37529.0 パワープロダクツ事業 及びその他の事業計392,261385,158△7,103△1.8 日 本87,07388,9431,8702.1 北 米138,760127,991△10,769△7.8 欧 州84,45977,859△6,600△7.8 アジア55,96862,1146,14611.0 その他26,00128,2512,2508.7 (注) 各事業の主要製品およびサービス、事業形態につきましては、連結財務諸表注記の「4 セグメント情報」を参照ください。 (2) 経営成績等の状況の分析当社グループは2050年に、製品だけでなく企業活動を含めたライフサイクルでの環境負荷ゼロ社会、全世界で当社グループの二輪車・四輪車が関与する交通事故死者ゼロをめざします。詳細については、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」と「2 サステナビリティに関する考え方及び取組」を参照ください。 これらの目標の実現に向けて、適切なタイミングでの戦略的な投資が必要不可欠であると考えています。当社グループは、二輪事業および金融サービス事業に加え、四輪事業のICE/ハイブリッドモデルの安定した事業基盤を活用し、「知能化」領域への資源投入を行うとともに、EVの市場への浸透度を見定めながら、「電動化」へのリソースシフトを進めていきます。 当社グループが展開する事業は厳しい経済・社会環境下に置かれており、その収益性は様々な要因により左右されます。足元では、米国にて新政権発足以降、追加関税をはじめとする様々な政策転換がなされており、当社グループもその動向を注視しています。当社グループが認識している課題、リスク事象の詳細については、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」「2 サステナビリティに関する考え方及び取組」「3 事業等のリスク」を参照ください。それらへの対処の過程、結果により販売台数の増減や追加費用などが生じ、将来の収益性に重要な影響を及ぼす可能性があると考えます。 以降の経営成績等の状況の分析は、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与えた事象や要因を経営者の立場から分析し、説明したものです。なお、この経営成績等の状況の分析に記載した将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであり、リスクと不確実性を内包しているため、将来生じうる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意ください。 ① 経営成績の分析当社グループの業績当連結会計年度の連結売上収益は、二輪事業における増加や為替換算による増加影響などにより、前連結会計年度にくらべ増収となりました。営業利益は、売価およびコスト影響による利益増などはあったものの、販売影響による利益減や研究開発費の増加および四輪製品保証見積変更影響などにより、減益となりました。二輪事業の概要当連結会計年度の連結売上台数は、タイなどで販売が減少したものの、インドやベトナム、フィリピンなどで増加したことにより、1,368万5千台と前連結会計年度にくらべ12.0%の増加となりました。 四輪事業の概要当連結会計年度の連結売上台数は、アジア地域などで販売が減少したことにより、284万台と前連結会計年度にくらべ0.6%の減少となりました。 パワープロダクツ事業及びその他の事業の概要当連結会計年度のパワープロダクツ事業の連結売上台数は、アジア地域で販売が増加したものの、欧州地域などで減少したことにより、370万台と前連結会計年度にくらべ2.9%の減少となりました。 (当連結会計年度の連結業績の概況)売上収益当連結会計年度の連結売上収益は、二輪事業における増加や為替換算による増加影響などにより、21兆6,887億円と前連結会計年度にくらべ1兆2,599億円、6.2%の増収となりました。また、前連結会計年度の為替レートで換算した場合、前連結会計年度にくらべ約6,233億円、約3.1%の増収と試算されます。 営業費用営業費用は、20兆4,752億円と前連結会計年度にくらべ1兆4,284億円、7.5%の増加となりました。売上原価は、二輪事業における連結売上収益の増加に伴う費用の増加や為替影響などにより、17兆247億円と前連結会計年度にくらべ1兆81億円、6.3%の増加となりました。販売費及び一般管理費は、諸経費の増加や四輪製品保証見積変更影響などにより、2兆3,510億円と前連結会計年度にくらべ2,444億円、11.6%の増加となりました。研究開発費は、1兆994億円と前連結会計年度にくらべ1,758億円、19.0%の増加となりました。 営業利益営業利益は、売価およびコスト影響による利益増などはあったものの、販売影響による利益減や研究開発費の増加および四輪製品保証見積変更影響などにより、1兆2,134億円と前連結会計年度にくらべ1,684億円、12.2%の減益となりました。なお、為替影響約936億円の減益要因を除くと、約748億円の減益と試算されます。 ここで記載されている変動要因の各項目については、当社が現在合理的であると判断する分類および分析方法に基づいています。なお、一部の分析項目において、当社および主要な連結子会社を対象に分析しています。・「為替影響」については、海外連結子会社の財務諸表の円換算時に生じる「為替換算差」と外貨建取引から生じる「実質為替影響」について分析しています。「実質為替影響」については、米ドルなどの取引通貨の、対円および各通貨間における為替影響について分析しています。・「売価およびコスト影響」については、販売価格の変動影響、コストダウン効果および原材料価格の変動影響などを対象に分析し、当該項目に影響する「為替影響」は除いています。・「販売影響」については、連結売上台数や機種構成の変化に伴う利益の変動、金融サービス事業の売上収益の変化に伴う利益の変動に加え、その他の売上総利益の変化要因を対象に分析し、当該項目に影響する「為替影響」は除いています。・「諸経費」については、販売費及び一般管理費の前連結会計年度との差から、当該科目に影響する「為替換算差」を除いて表示しています。・「研究開発費」については、研究開発費の前連結会計年度との差から、当該科目に影響する「為替換算差」を除いて表示しています。また、為替影響を除いた試算数値は、当社の連結財務諸表の金額とは異なっており、IFRSに基づくものではなく、IFRSで要求される開示に代わるものではありません。しかしながら、これらの為替影響を除いた試算数値は当社の業績をご理解いただくために有用な追加情報と考えています。 税引前利益税引前利益は、1兆3,176億円と前連結会計年度にくらべ3,247億円、19.8%の減益となりました。営業利益の減少を除く要因は、以下のとおりです。 持分法による投資損益は、アジア地域の持分法適用会社における利益の減少などにより、1,098億円の減益要因となりました。 金融収益及び金融費用は、受取利息の増加などはあったものの、為替差損益の影響などにより、464億円の減益要因となりました。なお、詳細については、連結財務諸表注記の「22 金融収益及び金融費用」を参照ください。 法人所得税費用法人所得税費用は、4,146億円と前連結会計年度にくらべ451億円、9.8%の減少となりました。また、当連結会計年度の平均実際負担税率は、前連結会計年度より3.5ポイント高い31.5%となりました。なお、詳細については、連結財務諸表注記の「23 法人所得税 (1) 法人所得税費用」を参照ください。 当期利益当期利益は、9,030億円と前連結会計年度にくらべ2,795億円、23.6%の減益となりました。 親会社の所有者に帰属する当期利益親会社の所有者に帰属する当期利益は、8,358億円と前連結会計年度にくらべ2,713億円、24.5%の減益となりました。 非支配持分に帰属する当期利益非支配持分に帰属する当期利益は、671億円と前連結会計年度にくらべ82億円、10.9%の減益となりました。 (二輪事業)連結売上台数は、アジア地域で増加したことなどにより、1,368万5千台と前連結会計年度にくらべ12.0%の増加となりました。二輪事業の外部顧客への売上収益は、連結売上台数の増加により、3兆6,266億円と前連結会計年度にくらべ4,064億円、12.6%の増収となりました。なお、販売価格の変動はあったものの、売上収益に与える影響は軽微でした。また、前連結会計年度の為替レートで換算した場合、前連結会計年度にくらべ約4,407億円、約13.7%の増収と試算されます。営業費用は、2兆9,631億円と前連結会計年度にくらべ2,992億円、11.2%の増加となりました。売上原価は、連結売上台数の増加に伴う費用の増加や為替影響などにより、2兆4,930億円と前連結会計年度にくらべ2,672億円、12.0%の増加となりました。販売費及び一般管理費は、諸経費の増加などにより、3,654億円と前連結会計年度にくらべ89億円、2.5%の増加となりました。研究開発費は、1,046億円と前連結会計年度にくらべ229億円、28.1%の増加となりました。営業利益は、為替影響などはあったものの、売価およびコスト影響による利益増などにより、6,634億円と前連結会計年度にくらべ1,072億円、19.3%の増益となりました。 日本2025年3月期二輪車総需要(注)は、約37万台と前連結会計年度にくらべ約6%の減少となりました。当連結会計年度の連結売上台数は、「スーパーカブ50」の増加などはあったものの、「ダックス125」や「CT125・ハンターカブ」の減少などにより、22万4千台と前連結会計年度にくらべ7.1%の減少となりました。 (注) 出典:JAMA(日本自動車工業会) 北米主要市場である米国の2024年(暦年)二輪車・ATV総需要(注)は、約70万台と前年にくらべ約4%の減少となりました。当連結会計年度の北米地域の連結売上台数は、主にメキシコにおいて、「Navi」の増加などにより、54万8千台と前連結会計年度にくらべ10.0%の増加となりました。 (注) 出典:MIC(米国二輪車工業会) 二輪車・ATVの合計であり、Side-by-Side(SxS)は含まない。 欧州欧州地域の2024年(暦年)二輪車総需要(注1)は、約124万台と前年にくらべ約5%の増加となりました。当連結会計年度の連結売上台数は、「PCX」の増加などにより、47万5千台と前連結会計年度にくらべ8.0%の増加となりました。 (注) 1 英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、スイス、ポルトガル、オランダ、ベルギー、オーストリアの10ヵ国の合計、当社調べ(ICE車の合計であり、EV/EM/EB(注2)は含まない。) 2 EM:Electric Moped(電動モペッド)、最高速度25km/h~50km/hのカテゴリー。 EB:Electric Bicycle(電動自転車)、最高速度25km/h以下のカテゴリー。 電動アシスト自転車は含まない。 アジア最大市場のインドの2024年(暦年)二輪車総需要(注1)は、約1,916万台と前年にくらべ約15%の増加となりました。その他アジア地域主要国の2024年(暦年)二輪車総需要(注2)は、インドネシアなどで販売が増加したものの、中国などで減少したことにより、約1,821万台と前年にくらべ約1%の減少となりました。当連結会計年度の連結売上台数は、インドにおける「Activa」シリーズや「SP」シリーズの増加などにより、1,059万1千台と前連結会計年度にくらべ12.5%の増加となりました。なお、持分法適用会社であるインドネシアのピー・ティ・アストラホンダモーターの販売台数は連結売上台数に含まれませんが、当連結会計年度の販売台数は、「Stylo160」や「PCX」の増加などにより、約491万台と前連結会計年度にくらべ約3%の増加となりました。 (注) 1 当社調べ(ICE車の合計であり、EV/EM/EBは含まない。) 2 タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム、パキスタン、中国の7ヵ国の合計、当社調べ(ICE車の合計であり、EV/EM/EBは含まない。) その他の地域主要市場であるブラジルの2024年(暦年)二輪車総需要(注)は、約171万台と前年にくらべ約12%の増加となりました。当連結会計年度の連結売上台数は、ブラジルにおける「Biz」シリーズや「POP 110i ES」の増加などにより、184万7千台と前連結会計年度にくらべ13.7%の増加となりました。 (注) 出典:ABRACICLO(ブラジル二輪車製造者協会) (四輪事業)連結売上台数は、アジア地域で減少したことなどにより、284万台と前連結会計年度にくらべ0.6%の減少となりました。四輪事業の外部顧客への売上収益は、為替換算による増加影響などにより、14兆1,692億円と前連結会計年度にくらべ6,016億円、4.4%の増収となりました。なお、販売価格の変動はあったものの、売上収益に与える影響は軽微でした。また、前連結会計年度の為替レートで換算した場合、前連結会計年度にくらべ約820億円、約0.6%の増収と試算されます。セグメント間取引を含む四輪事業の売上収益は、14兆4,678億円と前連結会計年度にくらべ6,763億円、4.9%の増収となりました。営業費用は、14兆2,240億円と前連結会計年度にくらべ9,931億円、7.5%の増加となりました。売上原価は、為替影響などにより、11兆5,559億円と前連結会計年度にくらべ6,459億円、5.9%の増加となりました。販売費及び一般管理費は、諸経費の増加や四輪製品保証見積変更影響などにより、1兆7,071億円と前連結会計年度にくらべ2,005億円、13.3%の増加となりました。研究開発費は、9,609億円と前連結会計年度にくらべ1,466億円、18.0%の増加となりました。営業利益は、売価およびコスト影響による利益増などはあったものの、販売影響による利益減や研究開発費の増加および四輪製品保証見積変更影響などにより、2,438億円と前連結会計年度にくらべ3,167億円、56.5%の減益となりました。 各カテゴリ別の販売台数構成比は概ね以下のとおりです。(小売販売台数ベース)パッセンジャーカー(セダン・コンパクト等):前連結会計年度39%、当連結会計年度36%ライトトラック(SUV・ミニバン等):前連結会計年度54%、当連結会計年度56%軽自動車:前連結会計年度7%、当連結会計年度8% 四輪事業における主要な製品は以下のとおりです。パッセンジャーカー(セダン・コンパクト等):「ACCORD」 、「CITY」 、「CIVIC」 、「FIT」 、「INTEGRA」、「JAZZ」 ライトトラック(SUV・ミニバン等):「BREEZE」 、「CR-V」 、「ELEVATE」「FREED」 、「HR-V」 、「ODYSSEY」 、「PILOT」 、「VEZEL」 、「WR-V」、「ZR-V」軽自動車:「N-BOX」 カテゴリ別の収益性を決定する要因はさまざまですが、販売価格は重要な要素の一つと考えています。上記カテゴリごとの販売価格については、各モデルによって異なるものの、全体的には、ライトトラックは比較的高く、軽自動車は比較的低い傾向があります。車両の貢献利益も各モデルによって異なりますが、一般的にライトトラックは販売価格が高いことから貢献利益も高く、軽自動車は販売価格が低いことから貢献利益も低い傾向があります。例えば、当社グループの主要な販売地域である日本市場と米国市場における、当連結会計年度のカテゴリ別の貢献利益は、ライトトラックおよびパッセンジャーカーはカテゴリ平均と比較して約10%高く、軽自動車は約70%低いと試算されます。上記の貢献利益は売上収益から販売量に比例して発生すると考えられる材料費を控除した金額の台当たり金額と定義して算定したものです。 日本2025年3月期四輪車総需要(注1)は、約457万台と前連結会計年度にくらべ約1%の増加となりました。当連結会計年度の連結売上台数(注2)は、「WR-V」の増加などにより、53万9千台と前連結会計年度にくらべ2.7%の増加となりました。当連結会計年度の生産台数は、69万3千台と前連結会計年度にくらべ2.0%の減少となりました。 (注) 1 出典:JAMA(日本自動車工業会:登録車+軽自動車)2 当社の日本の金融子会社が提供する残価設定型クレジット等が、IFRSにおいてオペレーティング・リースに該当する場合、当該金融サービスを活用して連結子会社を通して提供された四輪車は、四輪事業の外部顧客への売上収益に計上されないため、連結売上台数には含めていません。 北米主要市場である米国の2024年(暦年)四輪車総需要(注)は、約1,604万台と前年にくらべ約3%の増加となりました。当連結会計年度の北米地域での連結売上台数は、「PROLOGUE」や「CIVIC」が増加したことなどにより、165万4千台と前連結会計年度にくらべ1.6%の増加となりました。当連結会計年度の北米地域での生産台数は、160万8千台と前連結会計年度にくらべ0.6%の増加となりました。 (注) 出典:Autodata 欧州欧州地域の2024年(暦年)四輪車総需要(注)は、約1,296万台と前年にくらべ約1%の増加となりました。当連結会計年度の連結売上台数は、「ZR-V」の減少などにより、9万3千台と前連結会計年度にくらべ9.7%の減少となりました。 (注) 出典:ACEA(欧州自動車工業会)乗用車部門(EU27ヵ国、EFTA3ヵ国、英国) アジアアジア主要市場の2024年(暦年)四輪車総需要(注1)は、タイやインドネシアで減少したものの、インドやフィリピンなどで増加したことにより、約890万台と前年にくらべ約1%の増加となりました。中国の2024年(暦年)四輪車総需要(注2)は、約3,143万台と前年にくらべ約4%の増加となりました。当連結会計年度の連結売上台数の合計は、インドネシアにおける「BR-V」や「WR-V」の減少などにより、39万7千台と前連結会計年度にくらべ15.2%の減少となりました。なお、持分法適用会社である中国の東風本田汽車有限公司および広汽本田汽車有限公司の販売台数は連結売上台数に含まれませんが、当連結会計年度の販売台数は、「CIVIC」の減少などにより、78万6千台と前連結会計年度にくらべ33.7%の大幅な減少となりました。アジア地域の連結子会社の当連結会計年度の生産台数(注3)は、47万6千台と前連結会計年度にくらべ14.8%の減少となりました。なお、持分法適用会社である中国の東風本田汽車有限公司および広汽本田汽車有限公司の当連結会計年度の生産台数は76万8千台と前連結会計年度にくらべ33.9%の大幅な減少となりました。 (注) 1 タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム、インド、パキスタン、台湾の合計、当社調べ2 出典:CAAM(中国汽車工業協会)3 タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、インド、パキスタン、台湾の合計 その他の地域主要市場であるブラジルの2024年(暦年)の四輪車総需要(注)は、約248万台と前年にくらべ約14%の増加となりました。当連結会計年度の連結売上台数は、ブラジルにおける「CITY」の増加などにより、15万7千台と前連結会計年度にくらべ18.9%の増加となりました。当連結会計年度のブラジル工場での生産台数は、9万9千台と前連結会計年度にくらべ27.0%の大幅な増加となりました。 (注) 出典:ANFAVEA(ブラジル自動車製造業者協会:乗用車+軽商用車) (金融サービス事業)当社グループは、製品販売のサポートを主な目的として、日本・米国・カナダ・英国・ドイツ・ブラジル・タイにある金融子会社を通じて、顧客に対する金融サービス(小売金融、オペレーティング・リースおよびファイナンス・リース)および販売店に対する金融サービス(卸売金融)を提供しています。 金融サービスに係る債権およびオペレーティング・リース資産残高の合計は、14兆6,768億円と前連結会計年度末にくらべ1兆2,987億円、9.7%の増加となりました。また、前連結会計年度末の為替レートで換算した場合、前連結会計年度末にくらべ約1兆5,613億円、約11.7%の増加と試算されます。金融サービス事業の外部顧客への売上収益は、ローン収益の増加や為替換算による増加影響などにより、3兆5,077億円と前連結会計年度にくらべ2,589億円、8.0%の増収となりました。また、前連結会計年度の為替レートで換算した場合、前連結会計年度にくらべ約1,159億円、約3.6%の増収と試算されます。セグメント間取引を含む金融サービス事業の売上収益は、3兆5,122億円と前連結会計年度にくらべ2,604億円、8.0%の増収となりました。営業費用は、3兆1,965億円と前連結会計年度にくらべ2,187億円、7.3%の増加となりました。売上原価は、ローン収益の増加に伴う費用の増加や為替影響などにより、2兆9,851億円と前連結会計年度にくらべ1,797億円、6.4%の増加となりました。販売費及び一般管理費は、諸経費の増加などにより、2,114億円と前連結会計年度にくらべ390億円、22.7%の増加となりました。営業利益は、増収に伴う利益の増加などにより、3,156億円と前連結会計年度にくらべ416億円、15.2%の増益となりました。 (パワープロダクツ事業及びその他の事業)パワープロダクツ事業の連結売上台数は、アジア地域で増加したものの、欧州地域で減少したことなどにより、370万台と前連結会計年度にくらべ2.9%の減少となりました。パワープロダクツ事業及びその他の事業の外部顧客への売上収益は、連結売上台数の減少などにより、3,851億円と前連結会計年度にくらべ71億円、1.8%の減収となりました。また、前連結会計年度の為替レートで換算した場合、前連結会計年度にくらべ約152億円、約3.9%の減収と試算されます。セグメント間取引を含むパワープロダクツ事業及びその他の事業の売上収益は、4,146億円と前連結会計年度にくらべ77億円、1.8%の減収となりました。営業費用は、4,240億円と前連結会計年度にくらべ71億円、1.7%の減少となりました。売上原価は、パワープロダクツ事業の連結売上台数の減少に伴う費用の減少などにより、3,232億円と前連結会計年度にくらべ92億円、2.8%の減少となりました。販売費及び一般管理費は、諸経費の減少などにより、669億円と前連結会計年度にくらべ40億円、5.7%の減少となりました。研究開発費は、338億円と前連結会計年度にくらべ61億円、22.4%の増加となりました。営業損失は、売価およびコスト影響による利益増などはあったものの、販売影響による利益減や為替影響などにより、94億円と前連結会計年度にくらべ5億円の悪化となりました。なお、パワープロダクツ事業及びその他の事業に含まれる航空機および航空機エンジンの営業損失は、388億円と前連結会計年度にくらべ59億円の悪化となりました。 日本当連結会計年度の連結売上台数は、発電機が減少したことなどにより、27万8千台と前連結会計年度にくらべ7.9%の減少となりました。 北米当連結会計年度の連結売上台数は、芝刈機が減少したことなどにより、102万台と前連結会計年度にくらべ5.8%の減少となりました。 欧州当連結会計年度の連結売上台数は、OEM向けエンジン(注)が減少したことなどにより、65万1千台と前連結会計年度にくらべ18.0%の減少となりました。(注) 相手先ブランドで販売される商品に搭載されるエンジン(OEM:Original Equipment Manufacturer) アジア当連結会計年度の連結売上台数は、OEM向けエンジンが増加したことなどにより、141万3千台と前連結会計年度にくらべ9.2%の増加となりました。 その他の地域当連結会計年度の連結売上台数は、OEM向けエンジンが減少したことなどにより、33万8千台と前連結会計年度にくらべ0.3%の減少となりました。 ② 重要な会計上の見積り当社および連結子会社は、IFRSに準拠した連結財務諸表を作成するにあたり、会計方針の適用、資産・負債および収益・費用の報告額ならびに偶発資産・偶発債務の開示に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定の設定を行っています。実際の結果は、これらの見積りとは異なる場合があります。なお、これらの見積りや仮定は継続して見直しています。会計上の見積りの変更による影響は、見積りを変更した報告期間およびその影響を受ける将来の報告期間において認識されます。 当社の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の見積りおよび仮定に関する情報は、連結財務諸表注記の「2 作成の基礎 (5) 見積りおよび判断の利用」を参照ください。 ③ 流動性と資金の源泉(資金需要、源泉、使途に関する概要)当社および連結子会社は、事業活動のための適切な資金確保、適切な流動性の維持および健全なバランスシートの維持を財務方針としています。当社および連結子会社は、主に二輪車、四輪車およびパワープロダクツの製造販売を行うとともに、製品の販売をサポートするために、顧客および販売店に対する金融サービスを提供しています。生産販売事業における主な運転資金需要は、製品を生産するために必要となる部品および原材料や完成品の在庫資金のほか、販売店向けの売掛金資金です。また設備投資資金需要のうち主なものは、新機種の投入に伴う投資や、生産設備の拡充、合理化および更新ならびに販売施設や研究開発施設の拡充のための必要資金です。また、当社グループは、総合モビリティカンパニーとして、一人ひとりの創造力から生まれる夢のあるモビリティや多様なサービスによって「環境負荷ゼロ社会」「交通事故ゼロ社会」を実現するとともに、2023年にグローバルブランドスローガンである「The Power of Dreams」を再定義して明確に示した「時間や空間といったさまざまな制約から人々を解放し(Transcend)、また人の能力と可能性を拡張する(Augment)」という本質的な提供価値を世界中にお届けすることで、人や社会を前進させるパワーとなることをめざしていきます。こうした環境・安全の実現に向けて事業変革フェーズに応じた戦略的な資源配分を実施していきます。なお、2024年5月に発表した、電動化戦略の実現に向けた設備投資、出資と研究開発支出など合わせて10兆円の投入資源については、カナダでのEVの包括的バリューチェーン構築の2年程度延期などにより、2031年3月期までの間で合計3兆円を減額し、総額7兆円へ見直しを行いました。上記取り組みに関する資源配分の計画に関しては、「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 ⑥ 経済的価値の向上 1.事業変革フェーズに応じた戦略的な資源配分」を参照ください。 生産販売事業における必要資金については、主に営業活動から得られる資金、銀行借入金および社債の発行などによりまかなっております。なお、当社は、2022年3月期において、環境と安全への取り組みに対する支出の一部を社債発行により調達するためのサステナブル・ファイナンス・フレームワークを設定し、資金使途をそのフレームワークに準じた環境事業に限定する米ドル建てグリーンボンドを、総額27.5億米ドル発行しました。当連結会計年度末の米ドル建てグリーンボンドの債務残高は17.5億米ドルです。これらを踏まえ、現在必要とされる資金水準を十分確保していると考えています。これら生産販売事業の資金調達に伴う当連結会計年度末の債務残高は6,459億円となっています。また、顧客および販売店に対する金融サービスでの必要資金については、主にミディアムタームノート、銀行借入金、金融債権の証券化、オペレーティング・リース資産の証券化、コマーシャルペーパーの発行および社債の発行などによりまかなっています。これら金融子会社の資金調達に伴う当連結会計年度末の債務残高は11兆855億円となっています。当社および連結子会社の借入必要額に、重要な季節的変動はありません。今後も必要資金と手元資金の状況を鑑みながら、必要に応じて資金調達を検討していきます。 (流動性)当社および連結子会社の当連結会計年度末の現金及び現金同等物4兆5,287億円は、主に米ドル建てと円建てを中心としていますが、その他の外貨建てでも保有しています。 当社および連結子会社の当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、売上収益の約2.5ヵ月相当の水準となっており、当社および連結子会社の事業運営上、十分な流動性を確保していると考えています。しかしながら、景気後退による市場の縮小や金融市場・為替市場の混乱などにより、流動性に一部支障をきたす場合も考えられます。このため、特に当連結会計年度末で1兆7,971億円の短期債務を負う金融子会社では、継続的に債務を借り換えしているコマーシャルペーパーについて、代替流動性として合計1兆4,339億円相当の契約信用供与枠(コミットメントライン)を保有しています。さらに、有価証券報告書提出日現在、当社および連結子会社は世界的に有力な銀行と契約に基づかない信用供与限度額を十分に設定しています。 当社および連結子会社の当連結会計年度末の資金調達に係る債務は、主に米ドル建てを中心としていますが、円建てやその他の外貨建てでも保有しています。資金調達に係る債務の追加情報については、連結財務諸表注記の「15 資金調達に係る債務」および「25 金融リスク管理」を参照ください。また、当社および連結子会社が発行する短期および長期債券は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス、スタンダード・アンド・プアーズおよび格付投資情報センターなどから、2025年3月31日現在、以下の信用格付を受けています。 信用格付短期格付長期格付ムーディーズ・インベスターズ・サービスP-2A3スタンダード・アンド・プアーズA-2A-格付投資情報センターa-1+AA なお、これらの信用格付は、当社および連結子会社が格付機関に提供する情報または格付機関が信頼できると考える他の情報に基づいて行われるとともに、当社および連結子会社の発行する特定の債券に係る信用リスクに対する評価に基づいています。各格付機関は当社および連結子会社の信用格付の評価において異なった基準を採用することがあり、かつ各格付機関が独自に評価を行っています。これらの信用格付はいつでも格付機関により改訂または取り消しされることがあります。また、これらの格付は債券の売買・保有を推奨するものではありません。 ④ 簿外取引(貸出コミットメント)当社および連結子会社は、販売店に対する貸出コミットメント契約に基づき、貸付金の未実行残高を有しています。当連結会計年度末において、販売店への保証に対する割引前の将来最大支払額は、1,273億円です。これらの貸出コミットメント契約には、貸出先の信用状態等に関する審査を貸出の条件としているものが含まれているため、必ずしも貸出実行されるものではありません。 (従業員の債務に対する保証)当社および連結子会社は、当連結会計年度末において、従業員のための銀行住宅ローン42億円を保証しています。従業員が債務不履行に陥った場合、当社および連結子会社は、保証を履行することを要求されます。債務不履行が生じた場合に、当社および連結子会社が負う支払義務の割引前の金額は、当連結会計年度末において、上記の金額です。2025年3月31日現在、従業員は予定された返済を行えると考えられるため、当該支払義務により見積られた損失はありません。 ⑤ 契約上の債務当連結会計年度末における契約上の債務は、以下のとおりです。 期間別支払金額(百万円)合計1年以内1~3年3~5年それ以降資金調達に係る債務12,396,0094,819,1784,712,5661,618,6251,245,640その他の金融負債662,395184,839172,18182,323223,052発注残高およびその他契約残高(注1)120,744112,4828,147115-確定給付制度への拠出(注2)45,50445,504---合計13,224,6525,162,0034,892,8941,701,0631,468,692 (注) 1 当社および連結子会社の発注残高は、設備投資に関するものです。 2 2027年3月期以降の拠出額は未確定であるため、確定給付制度への拠出は、次連結会計年度に拠出するもののみ記載しています。 ⑥ 市場リスクに関する定量および定性情報の開示連結財務諸表注記の「25 金融リスク管理 (2) 市場リスク」を参照ください。 |
※本記事は「本田技研工業株式会社」の令和7年3月期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
※4. この企業は、連結財務諸表ベースで見ると有利子負債がゼロ。つまり、グループ全体としては外部借入に頼らず資金運営していることがうかがえます。なお、個別財務諸表では親会社に借入が存在しているため、連結上のゼロはグループ内での相殺消去の影響とも考えられます。
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

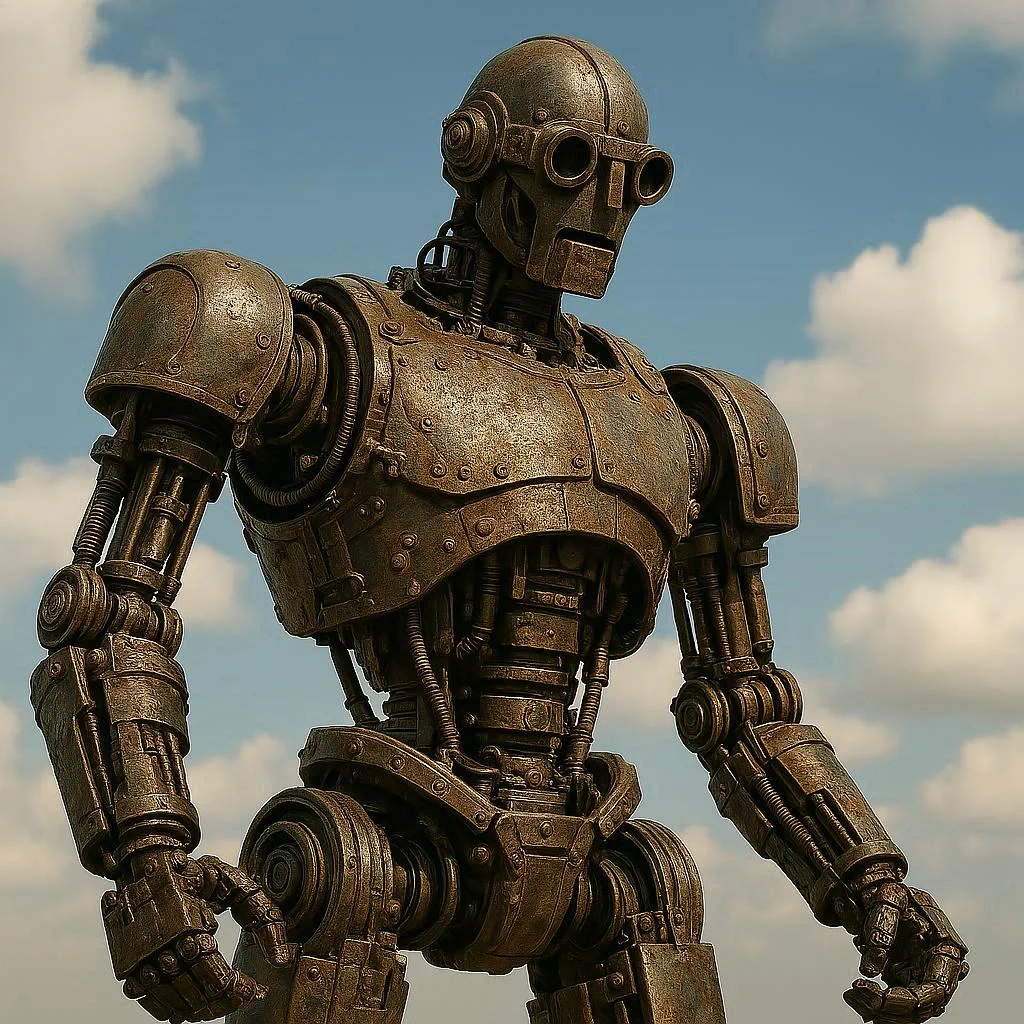

コメント