| 会社名 | 日野自動車株式会社 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 従業員数 | 連33608名 単11950名 |
| 従業員平均年齢 | 41.8歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 19年 |
| 平均年収 | 6554000円 |
| 1株当たりの純資産(連結) | 310.9円 |
| 1株当たりの純利益(単体) | -379.34円 |
| 決算時期 | 3月 |
| 配当金 | 0円 |
| 配当性向 | 0% |
| 株価収益率(PER) | -1.1倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(連結) | -76.3% |
| 営業活動によるCF | 11億円 |
| 投資活動によるCF | ▲46億円 |
| 財務活動によるCF | 297億円 |
| 研究開発費※1 | 13.11億円 |
| 設備投資額※1 | 131.48億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 611.1億円 |
| 株主資本比率※2 | ▲7.1% |
| 有利子負債残高(連結)※3 | 3905.97億円 |
経営方針
| 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社グループは、「人、そして物の移動を支え、豊かで住みよい世界と未来に貢献する」ことを会社の使命とし、人流・物流の課題の解決を通じて、持続可能な社会の実現に貢献します。 会社の使命を果たすため、「HINO基本理念」、「HINOサステナビリティ方針」、「HINO行動規範」から成る企業理念「HINO ウェイ」を定め、以下、3つを共有の価値観として、当社グループは事業活動及び健全な企業風土の醸成に取り組んでおります。「誠実」:コンプライアンスを徹底し、誠実に行動します。「貢献」:安全・環境にこだわり、未来の社会を支えます。「共感」:互いを尊重し、安全安心な職場をつくります。 (2)会社の環境及び対処すべき課題 <会社の環境> 1)エンジン認証不正問題への対応 当社のエンジン認証不正問題については、米国市場におけるエンジンの排出ガス認証試験および性能の問題について米国連邦およびカリフォルニア州当局による調査が継続していましたが、2025年1月16日に米国当局との間で和解に至りました。これは、米国における当社の過去のエンジン認証問題を一括して解決するものとなります。 日本市場においては、国土交通省から型式指定取消の処分を受けたもののうち、大型エンジン「A09C」搭載車の出荷を2023年2月より再開しました。大型エンジン「E13C」は型式指定の再申請に向けて劣化耐久試験を進めており、中型エンジン「A05C(HC-SCR)」については対応に時間を要していることから現行モデルの再申請はせず、エンジンを「A05C(尿素SCR)」の1機種に統合した2026年モデルで対応します。 また、当社に対する訴訟については、2022年8月に提起された米国の集団訴訟、2022年9月および2023年4月に提起された豪州の集団訴訟、2023年10月に提起されたカナダの集団訴訟はすべて和解に至っております。2025年3月に提起されたニュージーランドの集団訴訟については現在係争中です。当社のエンジン認証不正問題の詳細については、「第2 事業の状況 3.事業等のリスク (10) エンジン認証不正問題」をご参照ください。 当社は二度と不正を起こさないため、2022年10月に「3つの改革」を策定しました。すべての礎となる企業理念「HINO ウェイ」に則り、会社の使命を実現して再び社会への責任を果たしていくため、経営層の強い覚悟と率先垂範により経営・企業風土・クルマづくりにおける改革を進めております。国土交通省からの是正命令に対しても、「3つの改革」を含む抜本的な再発防止策に取り組み、進捗を定期的に報告してまいりました。現在は、同省からの是正命令である社内チェック体制の再構築、 コンプライアンスおよびガバナンス強化、開発体制の見直し、組織風土の抜本的改革等、再発防止策を全て実施フェーズに移しています。これらの施策を社内で仕組みとして定着させるべく、従業員への教育の拡充等にも継続的に取り組んでおります。 2024年度の具体的な取り組みとして、品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を2024年4月に取得いたしました。データの適切な管理体制の強化に向けては、認証試験データの自動保存化とアクセス管理を強化した外部新システムを導入しております。また、この問題を 風化させないために、認証不正問題の公表を行った3月4日を新たに「再出発の日」と位置づけ、全社での振り返りを毎年実施しております。 「3つの改革」を更に深化させ、組織風土・業務執行の継続的な改善を実行していくために、経営層と従業員が何度も意見交換をする機会を持ち、これまでの取り組みや成果の振り返り、施策の見直しを行っています。 また、米国当局との和解内容を受け、当局と合意した市場措置および超過排出による環境への影響を相殺するための環境負荷軽減プロジェクトを、確実に実施してまいります。更に、米国環境法等をより意識した「コンプライアンス・プログラム」を策定・実施し、自浄作用を働かせながらコンプライアンスの改善・強化を今後とも継続します。こうした取り組みを自律的なものとして定着させることで、当社の使命である「人、そして物の移動を支え、豊かで住みよい世界と未来に貢献」できるよう、努めてまいります。 2)事業および経営環境の強化に向けて 当連結会計年度における世界経済は、インフレの落ち着き、貿易持ち直し等による実質所得の改善を背景に底堅い成長を維持しています。国内の製造業においても、デジタル化・脱炭素化・サプライチェーン強靱化に向けた取り組みや人手不足対応などを背景に、投資活動の拡大傾向が続きました。一方で、各国の政権交代や紛争などの地政学的な変化と相まって、他社と同様に不確実性が高まっています。 このような状況において、当社がこれからもお客様へ継続的に価値を提供していくには、商品・サービスを軸とした経営を行い、私たちの強みであるクルマのQDR=「商品品質」を、クルマの稼働を支えるサービスとお客様ビジネスの困り事を解決するソリューションの「トータルサポート品質」で最大化し、「2つの品質」が相互に支え合うことで「総合品質」を向上して、お客様からパートナーとして選ばれ続けること、あわせて経営基盤の強化に取り組んでまいります。 商品については、大型トラック「日野プロフィア」、中型トラック「日野レンジャー」、小型トラック「日野デュトロ」、観光・路線バスなどの改良モデル等、まだ出荷再開に至らない型式車両がある中でも、できる限りお客様のニーズにお応えする商品を提供してまいりました。 トータルサポートについては、国内外の販売会社の拠点新設・拡充・更新等を継続的に進め、スピーディーで質の高いサービスを提供し、お客様のビジネスに貢献し続けていくための体制整備に注力しております。また、こうした既存事業の競争力強化に加え、カーボンニュートラルの実現、人流・物流に関する社会課題の解決に向けた取り組みを継続してまいりました。 カーボンニュートラルの実現に向けては、内燃機関車と電動車の両輪で適材適所に対応するマルチパスウェイによるアプローチで取組みを進めています。2022年6月に発売した小型BEVトラック「日野デュトロ Z(ズィー) EV」は、脱炭素社会の実現を目指す全国のお客様に幅広くご愛用されており、2024年度の販売台数は560台を超えるレベルに達しました。燃料電池トラック「日野プロフィア Z FCV」は、水素社会の普及を目指し、お客様に実際に使用していただく走行実証を通じて実用化に向けた取り組みを推進しています。2025年4月から開催中の日本国際博覧会(大阪・関西万博)においては、ENEOS株式会社様と西日本ジェイアールバス様とともに国内初となる合成燃料を使用した駅シャトルバスを運行しております。 人流・物流に関する社会課題の解決に向けては、CASE技術を活用し、業界を越えた様々なパートナーとの実証プログラムを推進しています。2023年7月に提供を開始した公共ライドシェアの運行管理受託サービスは、国土交通省が主導する「『交通空白』解消・官民連携プラットフォーム」に参画したことで自治体への導入やサービス拡充が順調に進んでいます。2024年11月には、国内商用車メーカー3社様ほか官民一体となって、新東名高速道路で自動運転技術を用いた大型トラックによる走行実証を開始しました。2025年1月より、苫小牧港にてコンテナ運搬を行うトレーラーの運行を高度化する実証実験を苫小牧栗林運輸株式会社様、株式会社三井E&S様とともに実施するほか、同2月からは、次世代道路技術の早期実装を目指して、新たに建設された舗装評価走路での自動運転レベル4相当の車両を用いた無人走行試験を大成ロテック株式会社様と開始しました。 また、ステークホルダーの皆さまに持続的に価値を提供していくため、「経営基盤の強化」にも継続して取り組んでおります。身の丈を越えて事業拡大を優先した経営から脱却し、財務基盤と競争力を強化するため、2024年は米国部品事業の撤退や中国事業の縮小等、事業の「選択と集中」を図ってまいりました。あわせて、需給の改善による車両在庫の適正化、車両型式の見直しや部品種類の削減等の取り組みも進めております。 また、経営基盤を強化する上で「人材」を重要な資産と考えており、企業理念の浸透や社内コミュニケーションの活性化、人材育成、職場環境の整備など、従業員が自社に誇りを持ちいきいきと働くための取り組みにも尽力しております。2024年度は、「人の成長」に注力する人事中期計画(2024年度~2026年度)の初年度として、評価・賃金制度の見直しや学びの支援に向けた様々な施策を実施しました。また、毎年実施している従業員意識調査において、2024年度は全ての指標でスコアの改善が見られ、結果を職場にフィードバックし、各組織の対話や改善に活用しています。 <対処すべき課題> 1)収益力回復と営業利益率8%の達成 当社は、2025年1月、北米向けエンジンの認証問題について米国当局と和解し、一連の認証問題に区切りをつけることができました。今後は「日野の目指す姿」実現に向けてスピード感を持って事業を再建し、お客様・社会からの信頼回復に努めるとともに、企業価値の向上と株主還元を実現させていきます。そのためには、「商品・サービスを軸にした経営」への変革が不可欠であり、良品廉価なクルマと高品質な「製品・サービス」でお客様・社会に価値提供し持続的な成長を目指します。 また、当社の持続的成長を実現させるための戦略資産である人的資本の強化についても、「人の成長」を主眼に一層取り組んでいきます。そして、これらの活動の基盤となる、コンプライアンス・ガバナンスの強化については、「「正しい仕事」を仕組み化するための規則・体制整備」と「ルールを守り、主体的に『考動』する行動様式の徹底」を両輪にして、引き続き推進してまいります。 上記を踏まえ、当社グループは、中長期的な成長に向けた方針として、順次利益水準の回復を図り、2030年度には営業利益率8%の実現を目指しています。そのために、事業ポートフォリオ見直し(選択と集中)を念頭に、お客様に貢献できていない事業および商品の再検討、「選択と集中」によって創出したリソースをお客様から高く評価いただいている商品の改良・拡販や、日本、アセアン、オーストラリアなど優位性のある市場での事業拡大に投下し、新たな付加価値の高い商品・サービスの提供につなげて競争力強化を図っていきます。 2)4社協業、2社経営統合について 2023年5月にトヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」という。)、ダイムラートラック社(以下「ダイムラートラック」という。)、三菱ふそうトラック・バス株式会社(以下「三菱ふそう」という。)および当社が基本合意書を締結して以降、当社及び三菱ふそうの統合(以下「本経営統合」という。)に関する協議を進めてまいりましたが、2025年6月10日に経営統合契約を4社で締結いたしました。本経営統合の詳細については、「第2 事業の状況 5.重要な契約等 (4)三菱ふそうトラック・バス株式会社との経営統合に係る経営統合契約の締結」をご参照ください。 なお同日、本経営統合を契機に、羽村工場の競争力の更なる強化を図るべく、当社の羽村工場のトヨタへの移管(以下「本移管」という。)に関する契約を締結しました。本移管の詳細については、「第2 事業の状況 5.重要な契約等 (5)羽村工場のトヨタ株式会社への移管に関する契約締結」をご参照ください。 これら本経営統合と本移管はいずれも2026年4月の新体制発足を目標に準備を進めてまいりますが、その推進にあたっては、あらゆるコンプライアンス面での要求を満たすことを前提に、全てのステークホルダーの皆様への影響を考慮しつつご期待にお応えするべく、誠実にコミュニケーションを図りながら進めてまいります。 |
経営者による財政状態の説明
| 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1)経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要、及び経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 尚、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 ①財政状態及び経営成績の状況及び分析 当連結会計年度における世界経済は、インフレの落ち着き、貿易持ち直し等による実質所得の改善を背景に底堅い成長を維持しています。国内の製造業においても、デジタル化・脱炭素化・サプライチェーン強靱化に向けた取り組みや人手不足対応などを背景に、投資活動の拡大傾向が続きました。 当連結会計年度の国内のトラック市場につきましては、部品供給の改善等に伴う各社生産回復により、大中型トラックおよび小型トラックの総需要は増加となりました。また、国内のバス市場につきましても、供給制約問題の解消や新型コロナ禍以降の買い控えからの回復等によりバスの総需要は増加し、国内トラック・バスの総需要は合計で167.8千台と前期に比べ18.4千台(12.3%)の増加となりました。 当社の国内売上台数につきましては、出荷再開した大型トラックの一部車型の販売が好調なことにより、トラック・バスの合計で42.0千台と、前期に比べ3.4千台(8.9%)の増加となりました。 海外につきましては、主にアセアンを中心とした販売減により、連結売上台数はトラック・バスの合計で85.8千台と前期に比べ6.2千台(△6.8%)減少いたしました。この結果、日野ブランド事業のトラック・バスの総売上台数は127.8千台と前期に比べ2.8千台(△2.1%)減少いたしました。 また、トヨタ向け車両売上台数につきましては、SUVおよび小型トラックともに台数が増加し、152.5千台と前期に比べ48.2千台(46.2%)増加いたしました。 当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。 ⅰ)財政状態(資産合計) 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ138億5百万円増加し、1兆4,781億80百万円となりました。これは、棚卸資産が423億66百万円、投資有価証券が225億67百万円それぞれ減少した一方で、現金及び預金が1,166億48百万円増加したこと等によります。 (負債合計) 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2,262億4百万円増加し、1兆2,271億59百万円となりました。これは、認証関連損失引当金が1,042億67百万円、長期未払金が585億10百万円それぞれ増加したこと等によります。 (純資産合計) 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2,123億99百万円減少し、2,510億20百万円となりました。これは親会社株主に帰属する当期純損失を2,177億53百万円計上したこと等によります。 セグメントごとの財政状態は次のとおりであります。(日本) 当連結会計年度末の売上債権が367億98百万円、棚卸資産が291億21百万円減少した一方で、当連結会計年度末の現預金が1,251億64百万円増加したこと等により、セグメント資産は1兆764億72百万円と前連結会計年度末に比べ、242億74百万円増加しました。 (アジア) 当連結会計年度末の棚卸資産が124億5百万円減少したこと等により、セグメント資産は3,254億59百万円と前連結会計年度末に比べ、129億56百万円減少しました。 (その他) 当連結会計年度末の有形固定資産が56億49百万円、未収入金が28億28百万円減少した一方で、当連結会計年度末の売上債権が122億89百万円増加したこと等により、セグメント資産は1,705億18百万円と前連結会計年度末に比べ、36億34百万円増加しました。 ⅱ)経営成績(売上高) 当連結会計年度の連結売上高は1兆6,972億29百万円となりました。 国内トラック市場につきましては、部品供給の改善等に伴う各社生産回復により、売上高は3,659億49百万円となりました。 海外トラック・バスにつきましては、アセアンを中心とした販売減により、売上台数が減少したものの価格改定の影響により、売上高は増加し5,408億24百万円となりました。 トヨタ向け車両につきましては、SUVおよび小型トラックともに台数が増加し、売上高は1,228億41百万円となりました。 その他の部門の売上高につきましては、トヨタ向けユニットの売上高が増加したこと等により、6,676億13百万円となりました。 (営業利益) 国内売上台数及びトヨタ向け車両台数の増加に加え、為替円安等により、営業利益は574億90百万円と前期に比べ655億94百万円(前期は81億3百万円の営業損失)の増益となりました。 (経常利益) 当連結会計年度は、経常利益は393億10百万円と前期に比べ485億44百万円(前期は92億33百万円の経常損失)の増益となりました。 (税金等調整前当期純利益) 当連結会計年度は、日野工場の一部の土地売却等による固定資産売却益345億53百万円や当社が保有していた政策保有株式の売却等による有価証券売却益180億2百万円を特別利益に計上したものの、北米認証関連損失2,584億13百万円を特別損失に計上したこと等により、税金等調整前当期純損失は1,905億63百万円と前期に比べ2,336億51百万円(前期は430億88百万円の税金等調整前当期純利益)の減益となりました。 (親会社株主に帰属する当期純利益) 当連結会計年度の税金費用(法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計額)は、221億29百万円と前期に比べ42億61百万円の増加となりました。 また、非支配株主に帰属する当期純利益は、50億60百万円と前期に比べ30億71百万円減少しました。 以上により、親会社株主に帰属する当期純損失は2,177億53百万円と前期に比べ2,348億41百万円(前期は170億87百万円の親会社株主に帰属する当期純利益)の減益となりました。 セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。(日本) 日野ブランド事業の国内向けトラック・バスの売上高は、主に大型トラックの売上台数の増加により、増収となりました。海外向けについては、アセアン向けを中心として売上台数が減少したものの、北米向けの売上台数は増加し、全体として増収となりました。また、トヨタ向けについてはSUVやダイナ等で台数増により増収となりました。 以上により、売上高は1兆1,728億51百万円と前年同期に比べ1,463億68百万円(14.3%)の増収となりました。損益面におきましては、セグメント利益(営業利益)は283億53百万円と前年同期に比べ439億94百万円の増益(前年同期は156億40百万円のセグメント損失)となりました。 (アジア) タイを中心としたアジア経済の低迷によって売上台数が減少したこと等により、売上高は4,246億1百万円と前年同期に比べ367億68百万円(△8.0%)の減収となりました。セグメント利益(営業利益)は、246億1百万円と前年同期に比べ73億円(△22.9%)の減益となりました。 (その他) 北米を中心として売上台数が増加したこと等により、売上高は3,346億58百万円と前年同期に比べ550億80百万円(19.7%)の増収となりました。セグメント利益(営業利益)は、64億75百万円と前年同期に比べ327億96百万円の増益(前年同期は263億21百万円のセグメント損失)となりました。 ⅲ)生産、受注及び販売の実績(a)生産実績 当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称区分当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)前年同期比(%)日本トラック・バス(台)84,913△11.2トヨタ向け車両(台)152,423+46.2アジアトラック・バス(台)24,993△17.9トヨタ向け車両(台)65△23.5報告セグメント計トラック・バス(台)109,906△12.8トヨタ向け車両(台)152,488+46.2その他トラック・バス(台)11,312+64.2トヨタ向け車両(台)--合計トラック・バス(台)121,218△8.8トヨタ向け車両(台)152,488+46.2 (b)受注実績 当社グループは国内及び海外の販売実績及び販売見込等の資料を基礎として見込生産を行っております。尚、トヨタ向け車両についてはトヨタ自動車株式会社からの受注に基づき生産しております。 (c)販売実績 当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)前年同期比(%)日本(百万円)1,172,851+14.3アジア(百万円)424,601△8.0報告セグメント計(百万円)1,597,452+7.4その他(百万円)334,65819.7調整額(百万円)△234,880△6.5合計(百万円)1,697,229+11.9 (注)主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。相手先前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)金額(百万円)割合(%)金額(百万円)割合(%)トヨタ自動車㈱93,8596.2153,2189.0 (2)キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報①キャッシュ・フローの状況及び分析 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、入出金が制限された口座への振替による資金の減少があった一方で、売上債権及び棚卸資産の減少や有形固定資産及び投資有価の売却等による資金の増加があったこと等により、前期末に比べ206億87百万円増加(前期は79億50百万円減少)し、884億20百万円となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 当連結会計年度における営業活動による増加は11億28百万円(前期は1,104億10百万円の減少)となりました。これは入出金が制限された口座への振替が973億37百万円あった一方で、棚卸資産の減少が430億22百万円(前期は406億44百万円の増加)、売上債権の減少が330億84百万円(前期は29億13百万円の減少)あったこと等によります。 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は46億円(前期は392億44百万円の増加)となりました。これは有形固定資産の売却による収入が363億66百万円(前期は992億90百万円)あった一方で、生産設備を中心とした有形固定資産の取得による支出が619億87百万円(前期は673億21百万円)あったこと等によります。 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 当連結会計年度における財務活動による資金の増加は297億38百万円(前期は556億38百万円の増加)となりました。これは、短期借入金の純増加額が397億5百万円(前期は630億88百万円の増加)あったこと等によります。 ②資金需要 当社グループの資金需要の主なものは、設備投資、投融資などの長期資金需要と製品製造のための材料及び部品購入のほか、製造費用、販売費及び一般管理費等の運転資金需要であります。 ③契約債務 2025年3月31日現在の契約債務の概要は以下のとおりであります。 年度別要支払額(百万円)契約債務合計1年以内1年超3年以内3年超5年以内5年超短期借入金365,543365,543---1年内返済予定の長期借入金8,5118,511---長期借入金18,351-17,633717-1年内償還社債8,4188,418---社債6,703-6,703-- ④財務政策 当社グループは、事業活動のための適切な資金調達、適切な流動性の維持及び財務構造の安定化を図ることを財務方針としております。設備投資、投融資などの長期資金需要に対しては、内部留保、長期借入債務及び社債の発行により、また、運転資金需要には短期借入債務により対応しております。借入債務については、主にトヨタ自動車株式会社、金融機関からの借入れによって調達しております。 加えて、資金マネジメントについては、当社と子会社の資金管理の一元化を図るなかで、緊密な連携をとることにより、グローバルな資金効率の向上を図っております。 (3)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております。連結財務諸表の作成にあたり、期末時点の状況をもとに、各種の見積りと仮定を行っております。連結財務諸表に与える影響が大きいと考えられる項目は以下のとおりです。 ① 繰延税金資産 当社グループは、繰延税金資産について定期的に回収可能性を検討し、当該資産の回収が不確実と考えられる部分に対して評価性引当額を計上しております。回収可能性の判断においては、将来の課税所得見込額と実行可能なタックス・プランニングを考慮し、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると考えられる範囲で繰延税金資産を計上しております。 将来の課税所得見込額はその時の業績等により変動するため、課税所得の見積に影響を与える要因が発生した場合は、回収懸念額の見直しを行い繰延税金資産の修正を行うため、親会社株主に係る当期純損益額が変動する可能性があります。 ② 退職給付債務及び退職給付費用 退職給付債務及び退職給付費用は、主に数理計算で設定される退職給付債務の割引率、年金資産の長期期待運用収益率等に基づいて計算しております。割引率は、従業員の平均残存勤務期間に対応する期間の安全性の高い長期債利回りを参考に決定し、また、年金資産の長期期待運用収益率は、過去の運用実績及び将来見通し等を基礎として設定しております。割引率及び長期期待運用収益率の変動は、将来の退職給付費用に影響を与える可能性があります。 ③ 製品保証引当金 当社は、製品のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、保証書の約款及び法令等に従い、過去の実績等を基礎にして計上しております。また、北米認証問題を起因とする米国で提起された暫定的な集団訴訟の和解及び米国当局との民事和解並びにカナダで提起された暫定的な集団訴訟の和解において、保証期間の延長を合意した車両の修理費用についても、過去の実績率等により見積もられた台当たりの修理費用、修理の見込み台数等に基づいて計上しております。 引当金の見積り時において想定していなかった製品の不具合による保証義務の発生や、引当の額を超えて保証費用が発生する場合は、当社グループの業績を悪化させる可能性があります。 ④ 認証関連損失引当金 当社は、認証関連課題に関連した損失に備えるため、合理的に見積もることが可能な金額を計上しております。主に北米認証問題を起因とする米国民事制裁金96,993百万円、米国環境負荷軽減費用23,325百万円及び国内顧客への燃費補償費用4,002百万円が含まれています。 引当金の見積り時において想定していなかった認証関連の損失の発生した場合や米国民事制裁金及び米国環境負荷軽減費用、顧客への燃費補償費用の見積り前提が変化した場合には、当社グループの業績を悪化させる可能性があります。 |
※本記事は「日野自動車株式会社」の令和7年3月期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

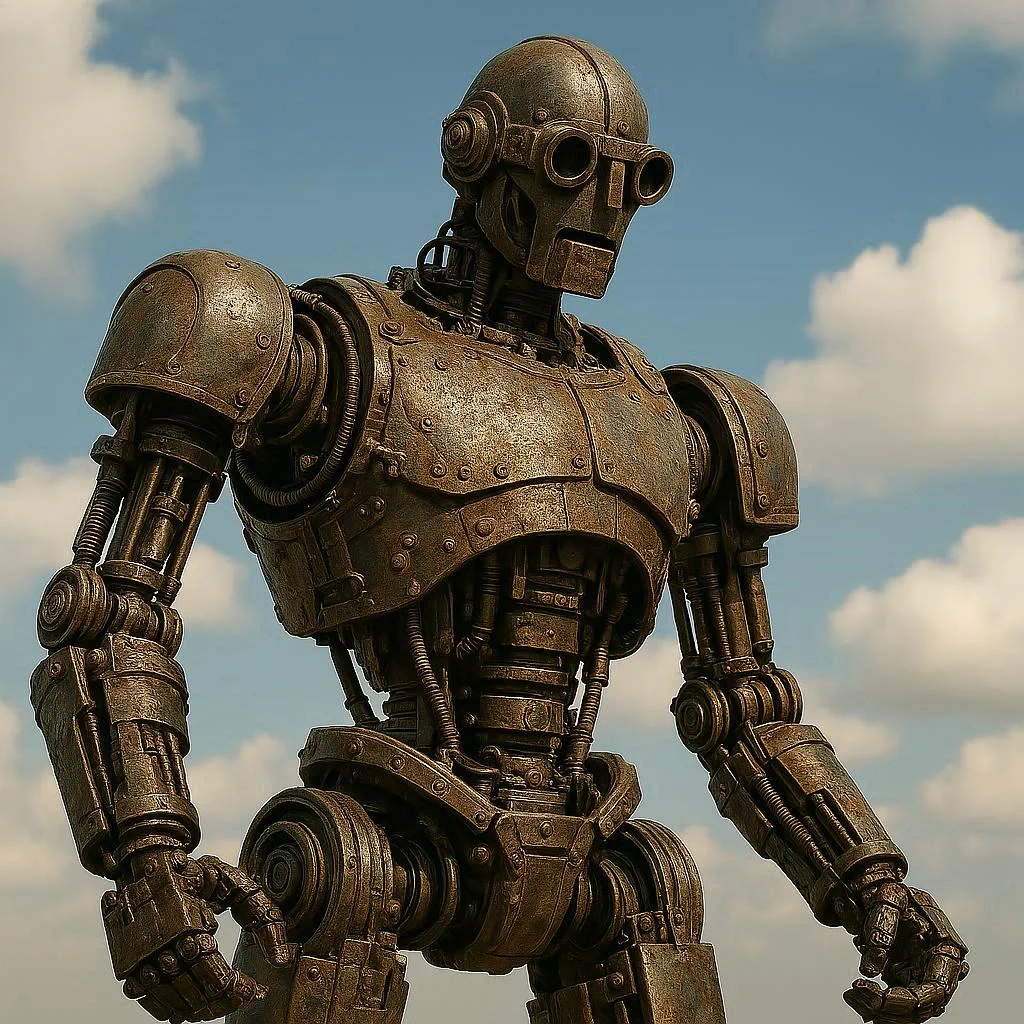

コメント