| 会社名 | エーザイ株式会社 |
| 業種 | 医薬品 |
| 従業員数 | 連10917名 単2998名 |
| 従業員平均年齢 | 44.6歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 18.5年 |
| 平均年収 | 10556563円 |
| 1株当たりの純資産(連結) | 1776.48円 |
| 1株当たりの純利益(連結) | 163.76円 |
| 決算時期 | 3月 |
| 配当金 | 160円 |
| 配当性向 | 109.1% |
| 株価収益率(PER) | 28.25倍 |
| 自己資本利益率(ROE)(連結) | 6.8% |
| 営業活動によるCF | 301億円 |
| 投資活動によるCF | ▲100億円 |
| 財務活動によるCF | ▲578億円 |
| 研究開発費※1 | 65.98億円 |
| 設備投資額※1 | 176.01億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 22033円 |
| 株主資本比率※2 | 52.5% |
| 有利子負債残高(連結)※3※4 | 0円 |
経営方針
| 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 (1)企業理念当社グループは、患者様と生活者の皆様の喜怒哀楽を第一義に考え、そのベネフィット向上に貢献することを企業理念としています。この理念のもとですべての役員および従業員が一丸となり、世界のヘルスケアの多様なニーズを充足し、いかなる医療システム下においても存在意義のあるヒューマン・ヘルスケア(hhc)企業となることをめざしています。当社グループの使命は、患者様と生活者の皆様の満足の増大であり、他産業との連携によるhhcエコシステムを通じて、日常と医療の領域で生活する人々の「生ききるを支える」ことです。その結果として売上や利益がもたらされ、この使命と結果の順序を重要と考えています。当社グループは、このhhc理念の実現に向けて、主要なステークホルダーズである患者様と生活者の皆様、株主の皆様および社員との信頼関係の構築に努めるとともに、コンプライアンス(法令と倫理の遵守)を日々実践し、企業価値の向上に取り組んでいます。本企業理念は、定款に定め、株主の皆様と共有化をはかっています。当社グループは、hhc理念に基づき、人々の「健康憂慮の解消」と「医療較差の是正」という社会善を効率的に実現し、社会的インパクトを創出することで、長期的な企業価値の増大をめざします。 (2)エーザイの未来創造戦略2025年3月、当社グループは、hhc理念に基づき、すべての人が自分らしく生ききる世界をつくるための「エーザイの未来創造戦略」を策定しました。本戦略を経営の根幹に据え、当社グループの医薬品事業等を通じた患者様や生活者の皆様への貢献と、これを支える基盤としてコーポレートガバナンス強化および地球環境保全や社会課題の解決に中長期的に取り組み、企業としての継続的成長と社会の持続的発展への寄与をめざします。当社グループは、本戦略の中長期的な実現に向けて、優先的に取り組む重要な課題とその目標を中期経営計画に定め、取り組みを推進します。 (3)経営環境、経営方針・経営戦略、ならびに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題等当社グループは、中期経営計画「EWAY Future & Beyond」を2021年4月よりスタートしました。 ① 中期経営計画「EWAY Future & Beyond」「EWAY Future & Beyond」では、2021年度からの5年間を「EWAY Future」、2026年度以降を「EWAY Beyond」とし、当社グループが貢献すべき主役を「患者様とそのご家族」から「患者様と生活者の皆様」に拡大しました。患者様と生活者の皆様の「生ききるを支える」という想いとともに、アンメット・メディカルニーズが極めて高く、当社グループが最も強みを持つ認知症を中心とする神経領域とがん領域に立脚したサイエンスとデータに基づくソリューションを創出し、他産業やグループとの連携によるエコシステムの構築を通じて、hhceco(hhc理念+エコシステム)企業へと進化することをめざしています。2023年にhhcエコシステムを通じて社会善を効率的に実現するための新たなマテリアリティを策定しました。認知症領域、がん領域、グローバルヘルス領域における社会善の実現に加え、人財価値の最大化、および財務戦略を重要マテリアリティとして特定し、2030年度に向けた長期目標とKPIおよびリスクを設定・特定しました。これらのマテリアリティを羅針盤とし、社会善の効率的な実現に取り組んでいきます。 ② 中期経営計画「EWAY Future & Beyond」の主な進捗と取り組み疾患を連続体(Disease Continuum)として捉え、複数のバイオマーカーなどのプロファイリングにより疾患病態生理学的に理解することによって社内に蓄積されるヒューマンバイオロジーエビデンスを最大限活用し創薬研究を実践するDeep Human Biology Learning(DHBL)研究開発体制のもと、当社グループが当該領域のヒューマンバイオロジーに最も早く深くアクセスすることが可能なアルツハイマー病(AD)に代表される認知症を中心とした神経領域、難治性がんを中心としたがん領域にフォーカスし、創薬仮説の構築・検証から承認取得までの創薬活動を推進しています。グローバルヘルス領域においても継続的な貢献を果たしていくことをめざしています。また、人々の日常領域から医療領域までのすべてのライフステージを支えるエコシステムを、アカデミア、企業、自治体などのパートナーと連携して構築することで、価値創造をめざします。加えて、これらの価値創造を下支えするべく、効率性の追求と収益性の向上に向けた構造改革も推進しています。グローバル全体のオペレーションを最適化し、単なる費用削減ではなく、組織・プロセスを抜本から見直すことで、全社収益構造の変革をはかります。 (a) 認知症を中心とする神経領域レカネマブ(ブランド名:「レケンビ」)について、早期ADを対象に、米国、日本、中国、欧州、アジア等において44の国と地域で承認を取得し、12カ国で申請中です。ADは、早期の診断と治療が必要な進行性かつ致死性の疾患であり、既に上市を果たしている米国、日本、中国などでは、AD領域におけるパイオニアとして、認知機能検査、APOE4検査、アミロイドβ(Aβ)検査(PET:陽電子放出断層撮影、CSF:脳脊髄液検査)、投薬、ARIA(アミロイド関連画像異常)モニタリングと続く、一連の診断・治療パスウェイを構築するとともに、その改良・軽量化に取り組んでいます。具体的には、2週に1回の初期投与完了後に4週に1回の投与を可能とする点滴静注維持投与、および在宅・在所での投与が可能となる皮下注オートインジェクター製剤(SC-AI)について、先行している米国だけでなく、日本をはじめとする他の国においても申請を進めていきます。また、血液バイオマーカーを用いたAβ蓄積のプレスクリーニングテストの拡大と確定診断の実装に向けた動きも着実に進んでおり、引き続き、複数のパートナー企業との協働により推進をはかります。ADのDisease Continuumに基づく他のプロジェクトの開発も進行中です。レカネマブについては、プレクリニカル(無症状期)ADを対象とするAHEAD 3-45試験(フェーズⅢ試験)が被験者登録を完了し、2028年度中のトップライン取得に向け順調に進行しています。また、抗MTBR(Microtubule binding region: 微小管結合領域)タウ抗体「E2814」については、優性遺伝アルツハイマーネットワーク試験ユニット(DIAN-TU)が優性遺伝ADを対象としたTau NexGen試験(フェーズⅡ/Ⅲ試験)をレカネマブとの併用で実施中です。2024年には孤発性ADを対象としたフェーズⅡ試験も開始しました。さらに、ダメージを受けたコリン作動性神経の機能を回復し、コリン作動性神経の変性を予防することが期待される選択的Tropomyosin receptor kinase A(TrkA)結合シナプス再生剤「E2511」、およびアストロサイト経路を標的としてシナプス機能低下抑制が期待される抗Erythropoietin-producing hepatocellular receptor A4(EphA4)抗体「E2025」については、それぞれフェーズⅠ試験が米国において進行中です。日本においては、慶應義塾大学と共同で設立した産医連携拠点「エーザイ・慶應義塾大学 認知症イノベーションラボ(EKID)」における、脳が本来備えている防御機構、堅牢性の維持・強化に関わる創薬ターゲットの探索研究や創薬研究も進めています。自社創製の脳移行型バイスペシフィック抗体技術である「Evolpath」についても複数のプロジェクトで開発が進行しています。臨床試験データやリアルワールドデータから、病態メカニズムに関わるバイオマーカーを独自に同定・開発することでブレインヘルスパネルを構築し、バイオマーカーとデーターサイエンスに基づく疾患の再定義を進めています。このブレインヘルスパネルは、次世代創薬やプレシジョンメディスンの開発に活用していきます。 (b) 認知症エコシステム認知症エコシステムを通じて、認知症発症前の日常領域における健康状態の維持、疾患啓発、予防から、発症後の医療領域における正確な診断、治療(薬物・非薬物)効果の確認、QOL(Quality of Life)の向上に寄与するソリューションの提供をめざしています。日常領域段階では、子会社であるArteryex株式会社が健康管理サービス(パシャっとカルテ)を提供しています。また、デジタル事業会社Theoria technologies株式会社が、認知症関連情報のポータルサイト「テヲトル」を運営し、高リスクから、発症・治療、予後段階までのステージで役立つ情報を提供するとともに、当事者様・医師・介護者間のコミュニケーション円滑化を支援するアプリ「ササエル」の開発・提供なども行っています。TOBが成立し完全子会社化する予定のエコナビスタ株式会社においても、SaaS型(クラウド型)の高齢者向け見守りシステム「ライフリズムナビ」により、MCIや認知症の早期検知や介護事業者の業務効率化への貢献をめざします。日本においては、保険、金融、自動車、食品などの他産業や自治体と共に、脳の健康度のデジタルツール「のうKNOW」(非医療機器)の活用を中心に、認知症エコシステム拡大に向けた様々な連携を進めています。また中国においては、日常生活から医療までのワンストップオンライン健康プラットフォームである銀髪通(Yin Fa Tong)を通じてオンライン診療を提供し、デジタル技術を活用した医療較差の是正に取り組んでいます。アジア地域では、他産業や非営利団体とのエコシステム構築を拡大し、認知症の疾患認知率向上、早期発見、早期診断に向けた取り組みを進めています。 (c) がん領域抗がん剤「レンビマ」(Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USAと共同開発)については、単剤療法としての甲状腺がん、肝細胞がん、胸腺がん(日本)やペムブロリズマブとの併用療法による腎細胞がん、子宮内膜がん等の既存適応症における価値最大化に引き続き取り組みます。さらに、ペムブロリズマブとの併用療法については、肝動脈化学塞栓療法併用肝細胞がん、食道がんを対象としたLEAP試験に加え、腎細胞がんを対象とした新規併用療法の適応追加に向けた臨床試験が進行中です。次世代オンコロジー製品の開発では、「レンビマ」や「ハラヴェン」で得られたバイオマーカーデータを活用し、薬剤耐性メカニズムの解明を進めています。当社グループが有する先端精密合成技術を基盤として、抗体では作用できない細胞内のUndruggableな治療標的をDruggableへと変え、新たなバックボーン治療薬創出をめざしています。エリブリンをペイロードとした抗体薬物複合体である「MORAb-202」、レンビマ薬剤耐性解除を期待するファーストインクラスの中分子治療薬「E7386」や、当社グループが強みを持つケミストリー力を具現化する創薬プラットフォームからは、スプライシングモジュレーター、標的タンパク質分解誘導剤の創薬を進めています。 (d) グローバルヘルス領域グローバルな医薬品アクセスの課題解決への取り組みを、理念が導く当社グループのビジネスであるとともに、将来への長期的な投資であると考え、政府や国際機関、非営利民間団体等との官民パートナーシップのもと、積極的に推進しています。開発途上国および新興国に蔓延する顧みられない熱帯病(NTDs)の一つであるリンパ系フィラリア症を制圧するため、その治療薬である「DEC(一般名:ジエチルカルバマジン)錠」を当社グループのインド・バイザッグ工場で製造し、本剤を必要とするすべての蔓延国において制圧が達成されるまで、世界保健機関(WHO)に「プライス・ゼロ」で提供することにコミットしています。2025年3月末までに32カ国に25.2億錠を供給し、そのうち8カ国でLF制圧が達成されました。さらに、日本発のグローバルヘルス技術振興基金(GHIT Fund)、NTDsに対する新薬開発の経験豊富な非営利団体/非政府組織、アカデミアとのパートナーシップのもと、マイセトーマ(菌腫)をはじめとするNTDs、結核、マラリアに対する新薬開発を推進しているほか、疾患啓発活動にも取り組んでいます。マイセトーマについては、スーダンにて、抗真菌剤「E1224」(一般名:ホスラブコナゾール)によるフェーズⅡb/Ⅲ試験がDNDiおよびスーダンのハルツーム大学菌腫研究センターにより実施されました。現在、スーダンにおける承認申請に向けた準備を進めています。マラリアについては、米国のブロード研究所と共同で創出した新規薬剤候補「E1018」のフェーズⅠ試験を当社が開始しました。 (e) 人財価値の最大化当社は、定款において社員を主要なステークホルダーの一つと定め、「安定的な雇用の確保」に加え、「人権および多様性の尊重」、「自己実現を支える成長機会の充実」、「働きやすい環境の整備」に努めることを明記しました。また、「統合人事戦略」を策定し、「社員の健康を含めたウェルビーイング」、「多様な働き方」、「社員の成長」、「組織、事業の成長」を柱とした、個と組織が共に成長するための人事施策を実行しています。様々な異なる意見や価値観を尊重して、課題解決に取り組んでいくことは、当社のイノベーション創出の源泉であるとともに、企業理念の実現に向けた重要なアプローチであり、グローバルにおいて多様な価値観を持つ人財が活躍できる風土づくりを継続して進めています。さらにグローバルエンゲージメントサーベイを実施し、人事戦略の検証・強化に活用するなど、中長期的な人財価値の最大化を推進しています。2023年度からは「Human Capital Report」を発行し、人事戦略と連動する人的資本に関する取り組みやKPIを開示しています。開示によって得られる社内外からの様々なフィードバックも踏まえ、企業価値を高める本質的資産への当社人財の転換に向けて人的資本経営に継続的に取り組んでいます。 ③ 各国の関税政策への対応米国の関税措置は関係する国々の関税政策にも影響を与える可能性があり、地政学的ならびに経済的な不確実性の高まりが懸念されます。かかる中、当社は米国および関係諸国の関税政策の動向を常に注視し、当社事業への影響を精査していきます。また、原材料の複数購買体制および複数工場での製品の製造体制を構築するなど、地政学的なリスクを考慮した柔軟なサプライチェーン体制の整備に取り組んでいます。 ④ 目標とする経営指標当社グループは、2021年度からスタートした中期経営計画「EWAY Future & Beyond」においては、売上収益・利益に関しては、社会環境や開発品の承認状況に大きく左右されることから中長期での数値目標は設定していません。その代わりに、年次事業計画を精緻に策定しています。2025年度の業績予想は以下のとおりです。 2025年度業績予想売上収益7,900億円営業利益545億円親会社の所有者に帰属する当期利益415億円ROE*15.0%*1 ROE(親会社所有者帰属持分当期利益率)= 親会社の所有者に帰属する当期利益÷親会社の所有者に帰属する持分 上記に加え、売上収益の拡大と事業活動の効率性を高めることで、2026年度にROE8%レベル、2027年度において営業利益率10%以上を達成することをめざしています。 (4)資本政策の基本的な方針当社グループの資本政策は、財務の健全性を担保した上で、株主価値向上に資する「中長期的なROEマネジメント」、「持続的・安定的な株主還元」、「成長のための投資採択基準」を軸に展開しています。 ① 中長期的なROEマネジメント当社グループは、ROEを持続的な株主価値の創造に関わる重要な指標と捉えています。「中長期的なROEマネジメント」では、売上収益利益率(マージン)、財務レバレッジ、総資産回転率(ターンオーバー)を常に改善し、中長期的に正のエクイティ・スプレッド*1を創出すべく、資本コストを上回るROEをめざしていきます。*1 エクイティ・スプレッド=ROE-株主資本コスト ② 持続的・安定的な株主還元当社グループは、健全なバランスシートのもと、連結業績、DOE*2およびフリー・キャッシュ・フローを総合的に勘案し、シグナリング効果も考慮して、株主の皆様への還元を継続的・安定的に実施します。DOEは、連結純資産に対する配当の比率を示すことから、バランスシートマネジメント、ひいては資本政策を反映する指標の一つとして位置づけています。自己株式の取得については、市場環境、資本効率等に鑑み適宜実施する可能性があります。なお、健全なバランスシートの尺度として、親会社所有者帰属持分比率、負債比率(Net DER)*3を指標に採用しています。*2 DOE(親会社所有者帰属持分配当率)= 配当金総額÷親会社の所有者に帰属する持分*3 負債比率(Net DER)= (有利子負債(借入金)-現金及び現金同等物-3カ月超預金等-親会社保有投資有価証券等)÷親会社の所有者に帰属する持分 ③ 成長のための投資採択基準当社グループは、成長投資による価値創造を担保するために、戦略投資に対する投資採択基準を採用し、リスク調整後ハードルレートを用いた正味現在価値と内部収益率スプレッドにハードルを設定し、投資を厳選しています。 |
経営者による財政状態の説明
| 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 (1)事業の概況○ 当社グループは2021年4月よりスタートした中期経営計画「EWAY Future & Beyond」に基づき、「患者様とそのご家族」から「患者様と生活者の皆様」に視点を拡大し、人々の健康憂慮の解消と医療較差の是正に向けたソリューションをお届けすべく、他産業との協業によるエコシステムの構築をめざしています。また、持続的な企業価値向上のため、人財の価値を最大限に引き出すべく人的資本経営を推進しています。企業理念・経営戦略と連動した統合人事戦略を策定し、国籍・性別・年齢などを問わず多様な価値観を持つ人財が活躍できる風土づくりを進め、イノベーションの創出を目指しています。○ 疾患の根本原因に紐づくゲノム情報、病態生理学に基づいたDeep Human Biology Learning(DHBL)創薬体制のもと、当社グループのみが有するヒューマンバイオロジーの知見や、高質な臨床サンプルから得られるゲノム情報に基づいて、注力分野である神経変性疾患および難治性がんに加えて、顧みられない熱帯病(Neglected Tropical Diseases: NTDs)をはじめとするグローバルヘルス分野における創薬を推進しています。○ 認知症領域では、アルツハイマー病(AD)治療剤「レケンビ」が2024年度末までに40カ国以上で承認を取得しました。2025年度以降、当事者様の利便性向上が期待できる皮下注射製剤の承認を取得する予定です。さらには、プレクリニカル期(無症状期)ADを対象とする臨床試験も進行しています。また、すべての当事者様の健康憂慮の解消と医療較差の是正に貢献すべく、中国における認知症を対象としたワンストップオンライン健康プラットフォームの構築や、日本、アジアにおける他産業や非営利団体との提携といったソリューションを備えたエコシステムの構築を進めています。2025年5月には、エコナビスタ株式会社へのTOB(株式公開買付け)が成立し、認知症プラットフォームをベースとしたさらなるソリューション構築を進めています。○ がん領域では、抗がん剤「レンビマ」について、Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA(以下 米メルク社)の共同販促による既存適応症における価値最大化に取り組んでいます。また、肝動脈化学塞栓療法併用肝細胞がん、食道がんなどの臨床試験(LEAP試験)に加え、腎細胞がんを対象とした新規併用療法(LITESPARK試験)など、複数の適応追加に向けた臨床試験が進行中です。○ 当社事業の持続的成長を目指すと同時に、効率的な事業活動推進による中長期での収益性向上を実現するため、組織体制の再構築やリソース配分の見直しなどを進めています。○ これらの活動の結果、2024年度の売上収益は7,894億円となりました。うち、「レンビマ」は3,285億円、不眠症治療剤「デエビゴ」は538億円、「レケンビ」は443億円となり、前年度から大幅な成長を遂げました。営業利益は、「レケンビ」への患者様アクセス拡大や新たな適応、製剤の開発に対する投資を継続する一方、財務規律に基づいて研究開発費、販売費及び一般管理費の管理を行った結果、544億円となりました。安定した利益およびフリー・キャッシュ・フロー創出により、2024年度末におけるNet DER(負債比率)は-0.12倍、自己資本比率は60.7%と健全な財務ポジションを堅持しており、成長投資と安定配当を両立しています。 (2)経営成績の状況○ 当期(2024年4月1日~2025年3月31日)の連結業績は、次のとおりです。(単位:億円、%) 2023年度2024年度前期比売上収益7,4187,894106.4売上原価1,5531,688108.7売上総利益5,8646,206105.8販売費及び一般管理費3,7444,080109.0研究開発費1,6901,716101.5その他の収益120172143.0営業利益534544101.8税引前当期利益61861198.8当期利益438481109.8親会社の所有者に帰属する当期利益424464109.5当期包括利益1,22843235.2基本的1株当たり当期利益147円86銭163円76銭110.8○ 売上収益は、「レケンビ」、「レンビマ」、および「デエビゴ」が引き続き伸長したことにより、戦略的オプション等による一時金が減少したものの、増収となりました。医薬品事業の売上収益は7,490億円(前期比108.3%)となりました。○ 主要品目の売上収益は、「レンビマ」が3,285億円(前期比110.4%)、「デエビゴ」が538億円(同128.6%)、「レケンビ」が443億円(前期は43億円)、抗てんかん剤「フィコンパ」が298億円(前期比115.3%)となりました。○ 販売費及び一般管理費は、「レケンビ」に係る販売費の増加や「レンビマ」の売上拡大に伴う米メルク社への折半利益の支払いが増加したことに加え、円安の進行の影響により、増加となりました。○ 研究開発費は、パートナーシップモデルの活用により効率性を高めた一方で、「レケンビ」や抗MTBRタウ抗体「E2814」などの重要プロジェクトへの積極的な資源投入および円安の進行の影響などにより、増加となりました。○ その他の収益は、抗体薬物複合体farletuzumab ecteribulinに関するBristol Myers Squibb(米国、以下 BMS社)との戦略的提携契約の終結に伴い、提携契約締結時にBMS社から受領した預り金の取崩益59億円を計上したことにより、増加となりました。○ 以上の結果、営業利益は増益となり、医薬品事業のセグメント利益は3,505億円(前期比108.1%)となりました。 [セグメントの状況](各セグメントの売上収益は外部顧客に対するものです) 当社グループは、セグメントを医薬品事業とその他事業に区分しており、医薬品事業を構成する日本、アメリカス(北米)、中国、EMEA(欧州、中東、アフリカ、ロシア、オセアニア)、イーストアジア・グローバルサウス(韓国、台湾、インド、アセアン、中南米、南アフリカ等)の5つの事業セグメントを報告セグメントとしています。 なお、アジア・ラテンアメリカ医薬品事業の管轄エリアがアジア(日本、中国を除く)、中南米、南アフリカであった状況に鑑み、2024年10月1日より、イーストアジア・グローバルサウス医薬品事業に名称変更しました。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。 また、当連結会計年度より、経営の実態をより適切に表示するため、従来、研究開発費に含めていた各報告セグメントにおけるメディカル活動に伴う費用を各セグメントの利益に反映しています。前連結会計年度のセグメント情報は、当該変更を反映しています。 <日本医薬品事業>○ 売上収益は2,163億円(前期比99.7%)、セグメント利益は717億円(同101.0%)となりました。売上収益の主な内訳は、医療用医薬品が1,938億円(同99.8%)、一般用医薬品等が225億円(同99.1%)でした。○ 品目別売上収益については、ニューロロジー領域で、「デエビゴ」が445億円(前期比125.2%)、「フィコンパ」は77億円(同111.4%)と大幅に伸長しました。2023年12月に新発売した「レケンビ」は127億円(前期は4億円)となりました。オンコロジー領域では、「レンビマ」は139億円(前期比89.4%)、抗がん剤「ハラヴェン」は69億円(同87.3%)となりました。ヤヌスキナーゼ阻害剤「ジセレカ」は148億円(同117.3%)、慢性便秘症治療剤「グーフィス」は78億円(同112.3%)と大幅に伸長しました。なお、2023年6月に、ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体「ヒュミラ」の共同販促契約が満了しました。一般用医薬品等では、チョコラBBグループの売上収益が152億円(同101.7%)と伸長しました。○ 2024年4月、「フィコンパ」について、注射剤を新発売しました。○ 2024年11月、抗がん剤「タスフィゴ」を新発売しました。○ 2024年11月、筋萎縮性側索硬化症用剤「ロゼバラミン」を新発売しました。○ 2025年3月、「チョコラBB ナイトウェル」を新発売しました。 <アメリカス医薬品事業>○ 売上収益は2,783億円(前期比119.7%)、セグメント利益は1,583億円(同114.5%)となりました。○ 品目別売上収益については、ニューロロジー領域で、「レケンビ」が261億円(前期は38億円)、「デエビゴ」が68億円(前期比132.7%)と大幅に伸長しました。オンコロジー領域では、「レンビマ」が2,323億円(同113.8%)と大幅に伸長し、「ハラヴェン」は75億円(同60.5%)となりました。 <中国医薬品事業>○ 売上収益は1,155億円(前期比103.2%)、セグメント利益は572億円(同101.1%)となりました。○ 品目別売上収益については、「レンビマ」が248億円(前期比92.1%)となりました。めまい・平衡障害治療剤「メリスロン」は142億円(同107.2%)と伸長しました。末梢性神経障害治療剤「メチコバール」は115億円(同91.4%)となりました。「レケンビ」は47億円(前期は0.3億円)となりました。○ 2024年6月に中国、同年8月に香港、2025年2月にマカオにおいて、「レケンビ」を新発売しました。 <EMEA医薬品事業>○ 売上収益は794億円(前期比104.5%)、セグメント利益は359億円(同100.9%)となりました。○ 品目別売上収益については、ニューロロジー領域で、「フィコンパ」が157億円(前期比122.2%)と大幅に伸長しました。オンコロジー領域では、「レンビマ/Kisplyx」が419億円(同109.8%)と伸長し、「ハラヴェン」は87億円(同74.2%)となりました。○ 2024年7月にイスラエル、同年9月にアラブ首長国連邦、同年10月に英国において、「レケンビ」を新発売しました。 <イーストアジア・グローバルサウス医薬品事業>○ 売上収益は596億円(前期比109.8%)、セグメント利益は274億円(同120.2%)となりました。○ 品目別売上収益については、「レンビマ」が156億円(前期比120.6%)と大幅に伸長しました。アルツハイマー型認知症治療剤「アリセプト」は142億円(同105.4%)と伸長しました。○ 2024年5月、マレーシアにおいて、パーキンソン病治療剤「エクフィナ」を新発売しました。○ 2024年7月、南アフリカにおいて、「デエビゴ」を新発売しました。○ 2024年11月、韓国において、「レケンビ」を新発売しました。○ 2024年11月、シンガポールにおいて、「ジセレカ」を新発売しました。 (3)財政状態の状況○ 資産合計は、1兆3,865億円(前期末より73億円減)となりました。「レケンビ」等の生産を進めたことにより棚卸資産が増加した一方で、為替の影響により海外連結子会社の資産が減少したことに加え、現金及び現金同等物が減少しました。○ 負債合計は、5,206億円(前期末より258億円増)となりました。預り金の減少に伴いその他の金融負債が減少した一方で、短期借入金が増加しました。○ 資本合計は、8,660億円(前期末より330億円減)となりました。為替の影響により在外営業活動体の換算差額が減少したことに加え、配当金の支払いおよび取得した自己株式の消却に伴い利益剰余金が減少しました。○ 以上の結果、親会社所有者帰属持分比率は60.7%(前期末より2.1ポイント減)となりました。 (4)キャッシュ・フローの状況○ 営業活動によるキャッシュ・フローは、301億円の収入(前期より259億円の収入減)となりました。運転資本は、「レケンビ」等の棚卸資産が増加したことに加え、預り金の減少などにより増加となりました。○ 投資活動によるキャッシュ・フローは、101億円の支出(前期より152億円の支出減)となりました。販売権を譲渡したことによる一時金を受領した一方で、製造設備の増強を進めたことに加え、無形資産の取得による支出が発生しました。○ 財務活動によるキャッシュ・フローは、578億円の支出(前期より351億円の支出増)となりました。主に自己株式の取得および配当金の支払いによるものです。○ 以上の結果、現金及び現金同等物の残高は2,656億円(前期末より391億円減)、営業活動によるキャッシュ・フローから資本的支出等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは199億円の収入となりました。 (5)生産、受注および販売の実績① 生産実績(a) 生産実績当期における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。セグメントの名称金額(百万円)前期比(%)日本医薬品事業219,38897.8アメリカス医薬品事業392,20071.2中国医薬品事業108,365119.8EMEA医薬品事業124,032110.9イーストアジア・グローバルサウス医薬品事業71,011113.9報告セグメント計914,99688.0その他事業3,48076.9合計918,47687.9(注1) 金額は販売見込価格により算出し、セグメント間の取引については相殺消去しています。 (b) 商品仕入実績当期における商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。セグメントの名称金額(百万円)前期比(%)日本医薬品事業18,48369.8アメリカス医薬品事業39968.2中国医薬品事業5,985113.4イーストアジア・グローバルサウス医薬品事業2,198155.7報告セグメント計26,70680.5その他事業724108.4合計27,43081.0(注1) 金額は仕入価格により算出し、セグメント間の取引については相殺消去しています。(注2) 当期においてEMEA医薬品事業の商品仕入実績はありませんでした。 ② 受注実績当社グループは販売計画に基づいた生産を行っているため、該当事項はありません。 ③ 販売実績当期における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。セグメントの名称金額(百万円)前期比(%)日本医薬品事業216,28199.7アメリカス医薬品事業278,259119.7中国医薬品事業115,539103.2EMEA医薬品事業79,397104.5イーストアジア・グローバルサウス医薬品事業59,555109.8報告セグメント計749,031108.3その他事業40,36980.3合計789,400106.4(注1) セグメント間の取引については相殺消去しています。(注2) 主な相手先別の販売実績については、前期・当期とも総販売実績に対する割合が100分の10以上の相手先がないため、記載を省略しています。 (6)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容① 重要な会計方針及び見積り連結財務諸表作成にあたり、必要と思われる見積りは合理的な基準に基づいて実施しています。重要な会計方針及び見積りの詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 3. 重要性のある会計方針、 4. 重要な会計上の見積り及び判断」に記載のとおりです。 ② 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)事業の概況、(2)経営成績の状況、 (3)財政状態の状況、(4)キャッシュ・フローの状況」に記載しています。 ③ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報当社グループは、資金調達手段について、「手元現金」、次に「負債による資金調達(デット)」、最後に「株式の新規発行による資金調達(エクイティ)」とするペッキング・オーダー理論にもとづく優先順位付けをしています。原則として、手元現金の活用および負債が優先であり、既存株主の価値を毀損する可能性があるエクイティによる資金調達は最終手段として考えています。そのため、キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)管理による運転資本のコントロール、投資有価証券を含む資産売却などによるバランスシートマネジメントを継続的かつグローバルに推進することで資産効率を高め、最適資本構成にもとづく最適配当政策と積極的な成長投資の両立を可能としています。2024年度において、株主還元については、健全なバランスシートを維持していることから、1株当たり年間配当金を前年と同額の160円としました。成長投資については、将来の成長のための川島工園・筑波研究所の設備・施設への投資継続などを積極的に実施しました。2025年度においても積極的な成長投資を継続する計画で、資本的支出は365億円を見込み、手元資金を充当する予定です。資金の流動性については、現時点では概ね月商の3倍を適正な運転資金の水準と考えています。2024年度末における現金及び現金同等物残高は2,656億円であり、十分な流動性を確保しています。さらに、当座借越・コミットメントラインなどの流動性補完により、流動性を一層強化しています。また、手元資金の効率的な活用を企図して、日本国内・EMEA域内におけるキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)に加え、グローバル・キャッシュ・マネジメント・システム(GCMS)を導入しています。2024年度末時点での実質的なキャッシュ残高である有利子負債控除後のネットキャッシュは1,006億円と、実質無借金を維持しています。引き続き、「ネットキャッシュの維持」を主要な財務規律として重視するとともに、Net DERを±0.3レベルにコントロールすることで財務の健全性を維持します。 ④ 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等当社グループは、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(3)経営環境、経営方針・経営戦略、ならびに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題等 ④目標とする経営指標」に記載のとおり、中長期での数値目標は設定していません。その代わり、年次事業計画を精緻に策定しています。これに加え、売上収益の拡大と事業活動の効率性を高めることで、2026年度にROE8%レベル、2027年度において営業利益率10%以上を達成することをめざしています。2024年度業績予想(売上収益:7,540億円 営業利益:535億円 親会社の所有者に帰属する当期利益:430億円ROE:5.2%、2023年度有価証券報告書提出日時点)との比較では、売上収益は7,894億円(業績予想対比104.7%)、営業利益は544億円(同101.6%)、親会社の所有者に帰属する当期利益は464億円(同108.0%)、ROE5.4%(業績予想差0.2ポイント増)となりました。売上収益は、グローバルブランドである「レンビマ」、「デエビゴ」、「レケンビ」が伸長したことにより業績予想を上回りました。営業利益は、「レケンビ」へ継続して資源投入を行ったことに加え、「レンビマ」の売上拡大に伴う米メルク社への折半利益の支払いが増加した一方、パートナーシップモデルの活用、開発テーマの優先度を踏まえた研究開発費の効率的な投入など、財務規律に基づいた費用管理を行った結果等により、業績予想を上回りました。 |
※本記事は「エーザイ株式会社」の令和7年3月期の有価証券報告書を参考に作成しています。(データが欠損した場合は最新の有価証券報告書より以前に提出された前年度等の有価証券報告書の値を使用することがあります)
※1.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分(販管費・原価など)に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式:株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式:有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務(流動+固定) + コマーシャル・ペーパー
※4. この企業は、連結財務諸表ベースで見ると有利子負債がゼロ。つまり、グループ全体としては外部借入に頼らず資金運営していることがうかがえます。なお、個別財務諸表では親会社に借入が存在しているため、連結上のゼロはグループ内での相殺消去の影響とも考えられます。
連結財務指標と単体財務指標の違いについて
連結財務指標とは
連結財務指標は、親会社とその子会社・関連会社を含めた企業グループ全体の経営成績や財務状況を示すものです。グループ内の取引は相殺され、外部との取引のみが反映されます。
単体財務指標とは
単体財務指標は、親会社単独の経営成績や財務状況を示すものです。子会社との取引も含まれるため、企業グループ全体の実態とは異なる場合があります。
本記事での扱い
本ブログでは、可能な限り連結財務指標を掲載しています。これは企業グループ全体の実力をより正確に反映するためです。ただし、企業によっては連結情報が開示されていない場合もあるため、その際は単体財務指標を代替として使用しています。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら:EDINET(金融庁)

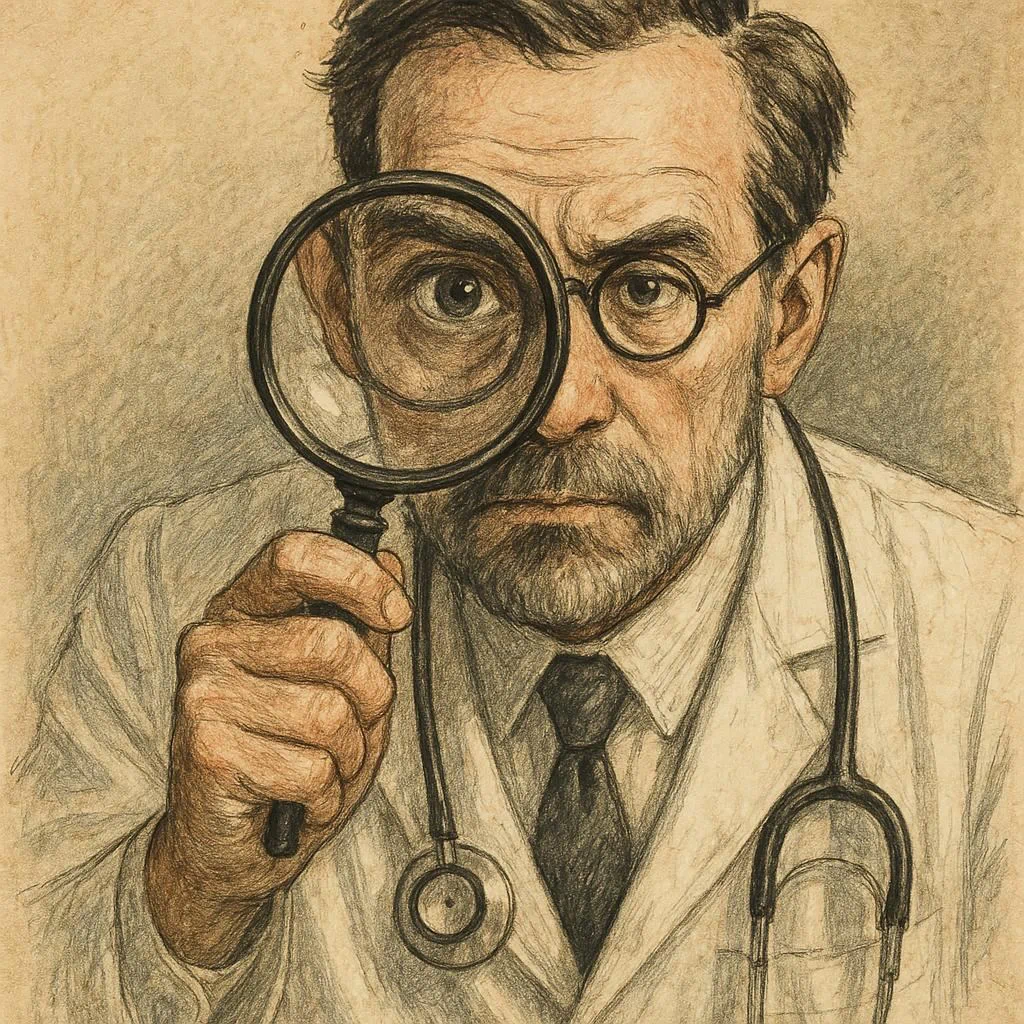


コメント